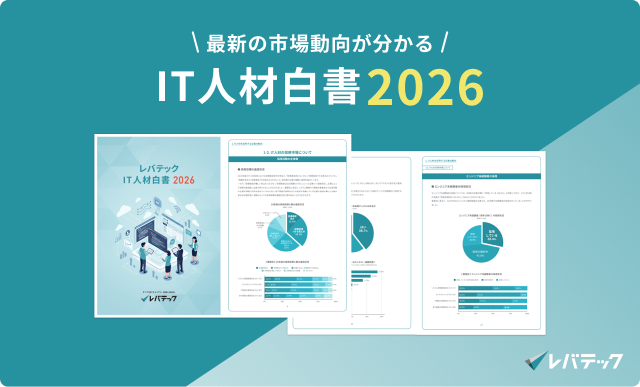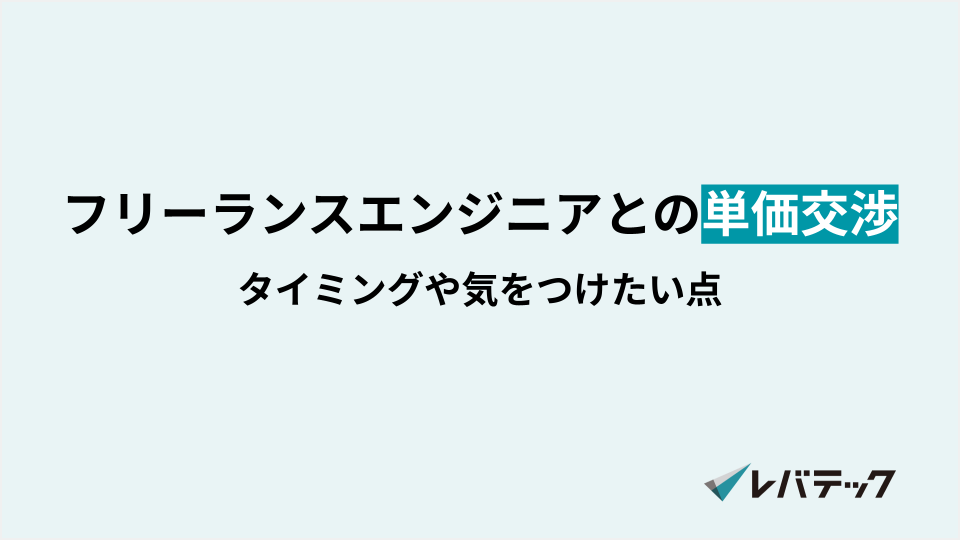採用ノウハウ - レバテック|エンジニア&クリエイターの採用情報サイト
エンジニア派遣業界とは?利用のメリット・デメリット、派遣会社の選び方
無料IT人材の採用に関わるすべての方へ

派遣会社から専門分野のエンジニアを派遣してもらう「エンジニア派遣」は、ピンポイントでニーズに合ったスキルを持つ人材を獲得でき、企業にとって効率的な採用手法です。
この記事では、エンジニア派遣業界の特徴やエンジニア派遣のメリットを紹介します。派遣会社の選び方も解説するので、エンジニアの獲得で困っている企業の方は、ぜひご一読ください。
【最新版】IT人材白書2026 を公開!
激化するIT人材の獲得競争を勝ち抜くための「最新データ」がここに。
IT人材白書2026は、貴社の採用戦略をデータで裏付け加速させるためのレポートです。IT人材採用のリアルな課題と、成功への具体的なヒントを数字で示します。
・IT系企業は順調、非IT系企業は苦戦傾向。業態で差が出る採用進捗のリアル
・採用手法は「待ち」から「攻め」へ。スカウト媒体や外部サービスの活用が活発に
・求人票やスカウト文の作成などにおいて生成AIの活用が広がる
・20代の正社員IT人材の約半数が「静かな退職」状態にある
最新のIT人材採用市場について詳しく知りたい方は以下より無料でダウンロードし、採用活動にお役立てください。
「レバテック」は業界歴20年のIT人材専門エージェントです。中途採用、フリーランス(業務委託)、派遣、新卒採用など、採用ニーズに合わせて70万人を超える登録者の中から最適な人材をご紹介します。
レバテックについて詳しく知りたい方は、こちらからサービス資料をダウンロードしてください。
目次
エンジニア派遣業界の特徴
エンジニア派遣会社と他の派遣会社との違いを挙げるとすれば、エンジニア派遣会社には、即戦力としてのITスキルを持つ人材が登録していることがあります。エンジニア派遣会社には、ある程度の知識やスキルを持った人材が揃っており、多くの企業がIT人材を求めてエンジニア派遣を利用しています。
ITの需要増によって人手不足が深刻になる中、IT技術者の派遣を行うエンジニア派遣業界は年々成長傾向にあります。厚生労働省のデータによると、令和6年1日時点で「情報処理・通信技術者」の派遣労働者数は18万3,983人で、派遣全体の9.6%を占めています。全業種の中では3番目に割合が高く、エンジニア派遣が活発であることが分かるでしょう
エンジニア派遣業界の市場規模や派遣エンジニア数の推移を知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
技術者派遣の市場規模は?現状や今後の展望をわかりやすく解説
技術者派遣業界の動向や市場規模は?人材派遣利用のメリットや注意点も解説
エンジニアの人材獲得を検討している場合は、IT人材採用に関わるデータをまとめた以下の資料もおすすめです。
最新のIT人材の採用市場動向を知りたい方へ
IT人材白書2025は他社の採用人数や予算の動き、エンジニア未経験者の採用、生成AIの活用状況などIT人材採用に関わる方が知りたい情報を一つにまとめた資料です。
⇒「IT人材白書2025」を無料でダウンロードする
エンジニア派遣業界と企業のこれから
ITの急速な発展に伴い目まぐるしくトレンドが変わる近年、その時々のニーズに合った人材を確保できるエンジニア派遣は、IT人材獲得の手段として認められはじめています。
最近は、クラウドソーシングサービスや、フリーランス専門エージェントといった、案件単位でのマッチングを行えるサービスが充実してきたこともあり、フリーランス化するエンジニアも出始めてきました。こうした動きからは、エンジニアの働き方およびIT人材の獲得方法が多様化していることが伺えます。
状況が移り変わる中で自社ニーズに合ったIT人材を確保したい企業に必要なことは、「人材要件」を明確にすることです。
人材要件を明確にするうえでは、採用現場における「エンジニアへの理解」が必要不可欠といえます。人事側にエンジニアへの理解がなければ、自社に必要なスキルとエンジニアの資質を判断できません。自社に合う候補者を見極めるためにも、採用担当者は基本的なIT知識やエンジニア側の転職の動機を理解しておきましょう。

派遣で活用できるエンジニアの職種
エンジニアを探す際は、派遣で活用できるエンジニアの種類を把握しておく必要があります。ここでは、主な派遣エンジニアの職種を紹介するので参考にしてください。
| 職種名 | 役割 |
| システムエンジニア(SE) | システムやソフトウェアの設計や開発を行う |
| ネットワークエンジニア | ネットワークの設計や構築、保守・運用を行う |
| サーバーエンジニア | サーバーの設計や構築、保守・運用を行う |
| サポート・ヘルプデスク | 社内からのIT関連の問い合せに対応する (顧客からの問い合わせに対応する場合もあり) |
| テストエンジニア | 製品やシステムが仕様通りに動くかテストを行う |
エンジニア・クリエイターの採用にお困りではありませんか?
業界最大級のIT人材特化型データベースなら求めていた人材がきっと見つかる!
⇒「3分でわかるレバテック」のダウンロードはこちらから
エンジニア派遣の費用相場
エンジニア派遣の費用は、派遣会社や人材のレベルによって異なります。ここでは、人材のレベル別にひと月あたりの費用の目安を紹介します。
- 初級SE(実務経験1~3年):60万円〜80万円
- 中級SE(実務経験3~10年):80万円〜100万円
- 上級SE(実務経験10年以上):100万円~150万円
エンジニアは専門職であるため、事務職といった派遣人材と比較して派遣料金が高い傾向にあります。上記から分かるように、同じエンジニア職であっても、どの程度のレベルの人材を活用するかでコストが大きく変わる点にも注意が必要です。
派遣のエンジニアに業務を依頼するメリット
ここでは、企業がエンジニア派遣を利用するメリットを確認していきます。
ピンポイントで必要なエンジニアを確保できる
派遣エンジニアを利用すれば、トレンドや時代の流れに応じて、自社に必要なエンジニアをピンポイントで確保できる可能性が上がります
現在はIT需要の高まりに伴い、ITスキルの需要も変化し続け、エンジニアに求められる能力は多様化しています。しかし、需要が変化していくたびにエンジニアを育成するのは難しく、時間や費用コストも大幅にかかってしまいます。
派遣であれば社内での育成コストを抑えつつ、その時々のニーズに合った人材を確保できるでしょう。
コストの削減ができる
派遣エンジニアを利用することで、採用コストの無駄を解消できるでしょう。
新卒や中途採用でエンジニアを雇う場合、募集から採用まで、選考の過程で長い時間とコストがかかります。 それだけ手間暇をかけて採用した社員でも、社風や業務内容が合わずにすぐに辞めてしまう可能性もあるでしょう。その場合、採用にかけたコストのほとんどが無駄になってしまいます。
その点、派遣エンジニアの場合は派遣会社と企業間で期間を定めた契約を結ぶため、選考の手間がかからず、契約期間内に派遣エンジニアが辞めてしまうリスクも少ないです。
比較的早くエンジニアを採用できる
派遣エンジニアであれば、派遣会社の紹介により契約を結べるため、急に自社で人手が必要になった場合でも、すぐにエンジニアを確保できる可能性が高いです。そのため、急ぎでIT人材を確保したい場合、派遣エンジニアの活用が一つの選択肢として挙げられます。
エンジニアに直接指示を行える
派遣契約においては、派遣先の企業が派遣スタッフに直接指示を行えます。
派遣と似たサービスに、エンジニアが客先の企業に常駐して業務を行う「SES(システムエンジニアリングサービス)」では、顧客企業はエンジニアに業務内容に関する細かい指示はできません。
そのため、その場で直接業務の指示を行いたい場合は派遣サービスがおすすめです。
エンジニア派遣とSESの詳しい違いについては、以下の記事を参考にしてください。
【企業向け】エンジニア派遣とは?メリットやSESとの違い、相場を解説

派遣のエンジニアに業務を依頼するデメリット
エンジニア派遣にはデメリットも存在します。派遣利用時にどのような問題が起こりやすいのか確認していきましょう。
帰属意識が希薄になる
派遣社員は自社で雇用する社員ではないため、どうしても帰属意識が薄くなります。帰属意識がないと「仕事のモチベーションがなくなる」「職場に愛着を持てず辞めてしまう」といった問題が起きるので注意が必要です。
派遣社員の帰属意識を高めるには、派遣社員と自社社員の間で不必要な差を設けない工夫をしましょう。
たとえば、派遣社員だけが利用できない施設(食堂や保健室など)があると帰属意識の低下を招くため、社内の設備は誰もが使用できるようにします。業務時間外のイベントも、自社社員と派遣社員の区別なく参加できるようにすると良いでしょう。
成果物への保障がない
仕事の完成を約束する「請負契約」と違い、派遣契約においては成果物に対する保障はありません。
請負契約は仕事の完成を目的とし、仕事の結果(成果物)に対して報酬が発生するものです。一方、派遣契約は業務の遂行自体を目的とし、業務が適切に遂行されれば成果物の有無に関わらず報酬が発生します。
そのため、確実に成果物を納品して欲しい場合は、派遣サービスでは目的を達成できない可能性があります。依頼したい業務の目的によって、派遣サービスを使うか、フリーランスと請負契約を結んで作業を行ってもらうのが良いか検討しましょう。
契約期間に制限がある
派遣には、通称「3年ルール」と呼ばれる契約期間の上限があり、気に入った人材がいても3年以上受け入れることができません(登録型派遣の場合)。一定の条件を満たせばさらに3年の受け入れが認められますが、その際も同じ人材を同じ組織単位(課など)で継続して就業させることはできないので注意が必要です。
プロジェクトの途中でも期限がきたら派遣エンジニアが離脱することになるため、引き継ぎの体制を整えたり、プロジェクトの中核メンバーを正社員で固めたりする対策が必要です。
以下の記事では、エンジニア派遣のメリットとデメリットを詳しく解説しています。派遣の利用を迷う場合は、ぜひこちらも参考にしてください。
エンジニア派遣のメリットとデメリットは?単価相場や企業の選び方も解説
エンジニア派遣の種類
エンジニア派遣には、以下の3種類があります。派遣の種類によって利用のルールが異なるので確認しておきましょう。
登録型派遣
登録型派遣は、派遣会社が自社で雇用する人材を派遣する形態です。派遣社員は派遣先での就業期間中のみ派遣会社と期間を定めた雇用契約を結ぶため、「有期雇用派遣」と呼ばれることもあります。
先述したように登録型派遣には3年ルールが適用されるため、同じ組織単位で就業させられる期間は3年が上限です。
派遣エンジニアの中には、フリーランスとして独立することを前提に、あえて登録型派遣を選択している人もいます。そういった方は、スキルアップのためにさまざまな現場を渡り歩いていることが多く、新しい技術に興味を持っている可能性が高いです。
常用型派遣
常用型派遣とは、派遣会社が正社員・契約社員として自社で常時雇用する社員を顧客企業へ派遣する形態です。派遣されるエンジニアは、1つの企業で契約が終了しても、派遣会社での雇用が継続されます。この点が、登録型派とは違う特徴といえるでしょう。
一概にはいえませんが、高いスキルや知識を保有するエンジニアは常用型派遣に多い傾向があり、常用型派遣は登録型派遣より派遣料金が高くなります。
紹介予定派遣
紹介予定派遣は、派遣先が派遣社員を直接雇用することを前提に、一定期間(最長6ヶ月)派遣として受け入れる働き方です。派遣期間の終了後、派遣社員と派遣先が合意したうえで、派遣先が派遣社員を自社の社員として直接雇用します。
企業にとっては雇用前に人材のスキルを見極められ、人材にとってはあらかじめ職場の雰囲気を知ることができるため、双方にとってメリットがある制度といえるでしょう。
紹介予定派遣を利用していない場合も、派遣エンジニアを引き抜くことは可能です。以下の記事では、詳しい手順や注意点を紹介しているので、気になる方は参考にしてください。
派遣社員の引き抜きに紹介料はかかる?相場や引き抜きの違法性も解説

エンジニア派遣会社を選ぶポイント
自社ニーズに合ったエンジニアを派遣してもらうためには、派遣会社の選定にも慎重にならないといけません。以下、エンジニア派遣会社を選ぶ際のポイントをまとめました。
大手企業を選ぶ
派遣会社を選ぶ際は、大手企業を選ぶことが無難です。一概にはいえませんが、大手と呼ばれる派遣会社では社内教育が行き届いている場合が多く、優秀な営業が集まりやすい傾向にあります。
営業担当のスキルが高いと、質の高いマッチングが期待でき、自社のニーズに合ったエンジニアを効率的に確保できます。何か問題が発生した際も的確な対応を期待できるでしょう。
さらに、大手企業は優良派遣事業者認定を受けている場合が多く、安心してサービスを利用できます。優良派遣事業者認定とは、労働者保護や法令遵守などの観点から、一定の基準を満たした派遣会社を厚生労働省が審査・認定する制度です。
認定を受けた派遣会社は派遣法をはじめとする法律に違反している可能性が低く、派遣先企業にとってはコンプライアンス上のトラブルを未然に防げるメリットがあります。
IT分野を得意としているか確かめる
IT分野を得意としている派遣会社かどうかを確かめることも大切です。派遣会社によって、「事務に強い」「医療や介護に特化してる」など、得意分野は異なります。
エンジニアを活用したい場合は、IT領域やエンジニア職に特化した派遣会社を選ぶことで、高度なスキルを持った人材に出会える可能性が高まります。派遣会社のWebサイトを閲覧し、扱っている職種や対応している技術領域を比較しましょう。
レバテックフリーランスでは、エンジニアの派遣サービスを提供しています。幅広い登録者の中からご希望に合う人材をご提案するので、エンジニアをお探しの際はぜひご相談ください。
レバテックフリーランスのサービス内容や登録している人材の種類については、以下のページからダウンロードできる資料で詳細を説明しています。
エンジニアの採用にお困りですか? レバテックフリーランスなら即戦力エンジニアが最短1週間でチームに参画!
⇒レバテックフリーランスの資料を見てみたい
質問に対し明確な返答が返ってくるか確認する
派遣エンジニアの経歴やスキルなど、具体的な情報を聞いた際、曖昧な返答で質問にはっきりと答えない派遣会社は要注意です。
紹介を増やすために、不都合な情報をあえて答えないようにしている可能性があります。その場合、いざエンジニアを採用しても現場とミスマッチを起こしてしまい、大きなコスト負担になってしまいます。 そのため、質問に明確に答えてくれる派遣会社を選びましょう。
フォローが充実しているか見極める
派遣スタッフに対する定期的なフォローがあるかもチェックしましょう。派遣会社による適切なサポートがあると、派遣スタッフが安心して就業でき定着率が上がります。
フォローのやり方は派遣会社によりますが、営業担当が派遣先を訪問したり、メールや電話で派遣スタッフに連絡をとったりすることが多いです。訪問や連絡の頻度は派遣会社によるので、事前に確認しておきましょう。
このほかに派遣会社を選ぶ際のポイントとして、予算に合った料金かを確かめることも必要です。以下の記事ではエンジニア派遣の詳しい単価相場やSESとの比較を紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
【最新】エンジニア派遣の単価相場は?SESの料金やそのほかの採用手法も解説
派遣エンジニアを上手に活用する3つのコツ
派遣エンジニアに力を発揮してもらうには、自社社員と差別しない、事前に依頼内容を明確にする、などのコツがあります。派遣エンジニアを受け入れる前に、以下のコツを確認しましょう。
1.社内のエンジニアと同等に扱う
派遣エンジニアを活用する際は、正社員との区別なく同等に扱うことが大切です。情報共有の場に招いたり、意見を聞いたりすることで、チームの一員としての意識が高まります。
派遣だからといって必要な情報を制限すると、業務の理解が不十分となり生産性が下がってしまうおそれがあります。会社の方針やプロジェクトの背景も含めて共有することで、仕事の質を高められるでしょう。
2.社内の研修会に参加してもらう
派遣エンジニアにも社内で行われる技術研修や勉強会への参加を促すと良いでしょう。勉強会や研修会への参加は、技術力向上だけでなく、社内文化への理解を深めるためにも役立ちます。
さらに、研修を通じて社内エンジニアと交流することで、コミュニケーションがとりやすい環境が生まれます。その結果、チームワークが向上すれば、プロジェクトの進行もスムーズになるでしょう。
3.依頼内容を明確にしておく
派遣エンジニアに業務を依頼する際は、タスクの内容を明確にし関係者で共有しましょう。派遣社員には、契約外の業務を依頼することはできません。派遣社員と一緒に働く現場社員に業務内容を伝えておくことで、不適切な指示を行うリスクを減らせます。
派遣においては、契約書に記載のない部署での業務も禁止されているので注意が必要です。派遣契約における禁止事項の詳細を知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
派遣契約の禁止事項とは?企業が理解すべき10の注意点を解説
派遣会社以外でエンジニアを確保する方法
幅広い選択肢の中からエンジニア人材を探すためにも、派遣以外に人材を確保する方法を知っておきましょう。フリーランス専門エージェントとクラウドソーシングについて、それぞれのサービス内容とメリット・デメリットを紹介します。
フリーランス専門エージェント
フリーランス専門エージェントを利用すれば、希望の条件に合ったフリーランス人材の紹介を受けられます。エンジニアを探すなら、IT系人材に特化したエージェントを活用するのがおすすめです。
メリット
エージェントには多くのフリーランスが登録しているため、自社で一から調達活動をするより早く人材を確保できます。自社に調達ノウハウがなくても、担当者のサポートを受けながら要件に合った人材を効率的に見つけられるでしょう。
デメリット
フリーランスを募集する際は、あらかじめ業務内容や報酬、勤務地、プロジェクトの期間などを提示することになります。
そのため、正社員を雇用したときのように、仕事の進め方に合わせて柔軟に業務内容を変更することはできません。相性が良いフリーランスがいても、契約完了後に取引を継続できる保障がない点にも注意が必要です。
以下の記事では、フリーランスエンジニアと正社員エンジニアの違いを解説しています。フリーランスの特徴を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
フリーランスエンジニアの活用方法は?正社員との違いや実際の導入事例を紹介
フリーランスの詳しいメリットや懸念を解消する方法については、以下の資料もご覧ください。
もうエンジニア不足は怖くない。採用難を乗り越え、事業成長を加速させるには?
⇒「ITエンジニア採用難の突破口!フリーランス活用で事業成長を加速」をダウンロードする
クラウドソーシング
クラウドソーシングとは、企業がインターネット上で不特定多数の人に業務を依頼する形態を指しています。
使い方としては、クラウドソーシングサイトに案件を掲載し、応募者のスキルや実績を確認したうえで依頼する人材を決定します。納品物の受け取りや入金といったやりとりは、すべてサイト上で完結するのが特徴です。
メリット
「コンペ式」の形式で案件を掲載すれば、募集内容に対して制作物を提案してもらうことができます。コンペ式のほかには、「タスク式」「プロジェクト式」といった依頼形式があり、業務に合わせて依頼の仕方を選べます。
デメリット
クラウドソーシングでは、候補者と事前に面談することはありません。顔の見えない状態で取引することになるので、途中で音信不通になったり、納期を過ぎても成果物が納品されなかったりするトラブルも考えられます。
トラブルを防ぐには、事前に候補者のプロフィールや評価を確認し、信頼できる人物か見極める作業が必要です。
エンジニア派遣業界に関するよくある質問
派遣の動向や利用時のコツなど、エンジニア派遣業界に関する質問に答えます。エンジニア派遣を利用する前に疑問を解消しておきましょう。
Q.エンジニア派遣業界の動向は?
技術者派遣数(情報処理・通信技術者)は年々増加傾向にあり、厚生労働省の資料によると以下のように推移しています。
- 2022年6月1日時点:17万2,445人
- 2023年6月1日時点:18万2,701人
- 2024年6月1日時点:18万3,983人
IT需要が高まりエンジニアが人手不足となる中、派遣は技術者確保の手段の一つとして定着しつつあるといえるでしょう。
参考:
労働者派遣事業の令和4年6月1日現在の状況(速報)|厚生労働省
労働者派遣事業の令和5年6月1日現在の状況(速報)|厚生労働省
労働者派遣事業の令和6年6月1日現在の状況(速報)|厚生労働省
Q.エンジニア派遣で欲しい人材を確保するコツは?
派遣会社に募集背景や詳しい業務内容を伝えましょう。派遣社員が就業する部署の人員構成や派遣社員に期待する役割など、細かな情報を伝えることで、マッチする人材を紹介してもらえる可能性が高まります。ただ、あまりにも求める要件が多いと該当する人材が見つからなくなってしまいます。どのようなスキルや要素が必須なのかは、あらかじめ社内で整理しておきましょう。
Q.エンジニア派遣とSESの違いは?
エンジニア派遣では、顧客企業が派遣社員に対して仕事の進め方を指示できます。一方、SESのエンジニアは所属しているSES企業から指示を受けることになっており、顧客企業が直接指示を行うことはできません。