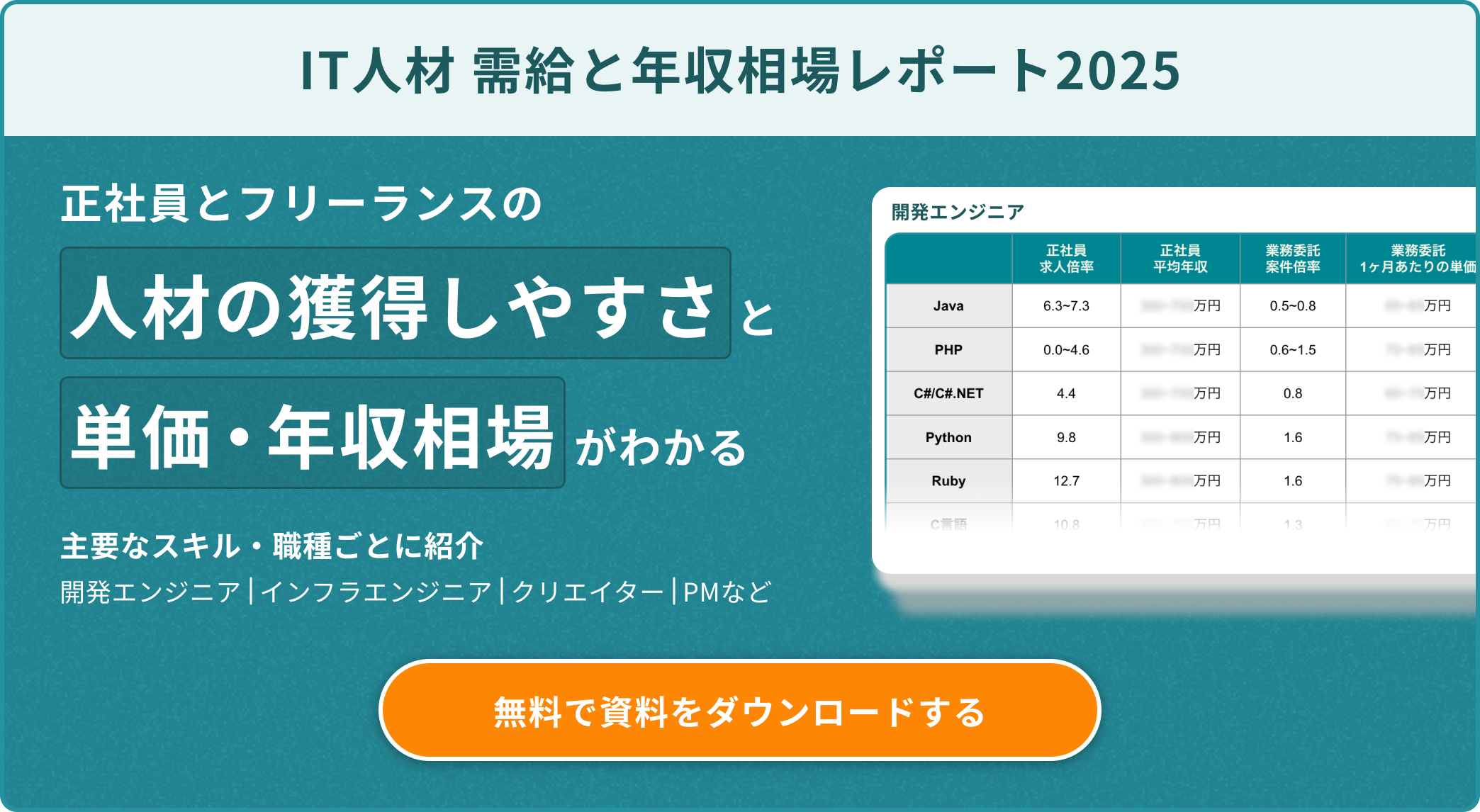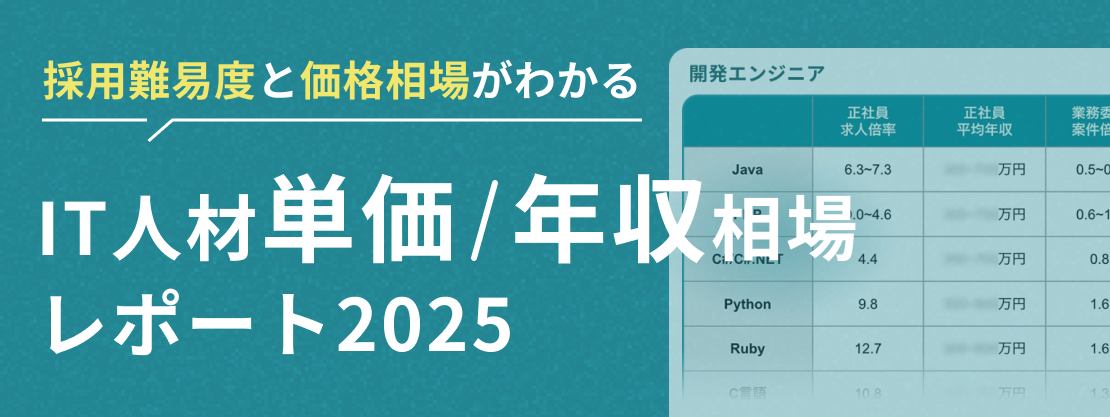採用ノウハウ - レバテック|エンジニア&クリエイターの採用情報サイト
SESで直接コミュニケーションをとると指揮命令?注意すべきケースを解説
無料IT人材の採用に関わるすべての方へ

「SES契約において、指揮命令となるのが怖くてコミュニケーションが取れない」
このような悩みを持つ担当者も多いのではないでしょうか?
この記事では、SES契約(準委任契約)の趣旨にそぐわない指揮命令とはどのようなものなのか、フリーランス活用の中で、「独立性」を妨げないとはどういうことなのかを企業の目線で解説します。
「レバテック」は業界歴20年のIT人材専門エージェントです。中途採用、フリーランス(業務委託)、派遣、新卒採用など、採用ニーズに合わせて70万人を超える登録者の中から最適な人材をご紹介します。
レバテックについて詳しく知りたい方は、こちらからサービス資料をダウンロードしてください。
目次
SES契約とは
SES(System Engineering Service)契約とは、SES企業がクライアントに対してエンジニアの技術力を提供することを目的とする契約を指します。
一般的なSESは準委任契約
SES契約にも種類がありますが、締結される業務委託契約は一般に「準委任契約」とされています。準委任契約とは、受託事業者のスキルや経験を活かして一定の業務を遂行することを目的とする契約です。
エンジニア・クリエイターの採用にお困りではありませんか?
業界最大級のIT人材特化型データベースなら求めていた人材がきっと見つかる!
⇒「3分でわかるレバテック」のダウンロードはこちらから
SES契約と請負契約、労働者派遣契約の違い
外部のエンジニアを活用する契約には、準委任契約のほかに請負契約や労働者派遣契約もあります。ここでは、それぞれの契約の違いを簡単に紹介します。
請負契約との違い
準委任契約と請負契約の大きく異なる点は、成果物(仕事)の完成義務の有無といえます。
請負契約では、納期までに完成、納品等することが求められ、原則として契約どおりに完成してはじめて報酬が発生するのに対して、準委任契約では、受託者が適切に業務を進捗(期間、時間、工数等が目安)させることに応じて発生するというように、契約の目的や報酬という点では異なりますが、契約関係でいえば、業務の受委託という意味では共通していて、次に紹介する派遣契約とは大きく異なるといえます。
労働者派遣契約との違い
労働者派遣契約は、派遣元企業が雇用する人材を相手方企業に派遣する契約ですが、労働者は派遣先企業との間にも雇用関係が生じるという点が大きなポイントになります。
雇用関係により、労働者は派遣先企業に対しても「誠実労働義務」を負い、派遣先企業(クライアント側)の業務上の指示や業務命令に従って労働することになるのです。逆にいえば、準委任契約に基づき役務を提供するエンジニアは、クライアント側との雇用関係がないため、「指揮命令をうけない」ともいえます。もちろん、契約の範囲での履行請求に法的に従わなければ「債務不履行」の責任を追及することになりますが、雇用労働者のように指導したり懲戒等の処分をすることはできないということになります。
関連記事:【最新】SESの単価相場一覧|スキル別の相場やSES利用の流れを解説
エンジニアの採用にお困りですか? レバテックフリーランスなら即戦力エンジニアが最短1週間でチームに参画!
⇒レバテックフリーランスの資料を見てみたい
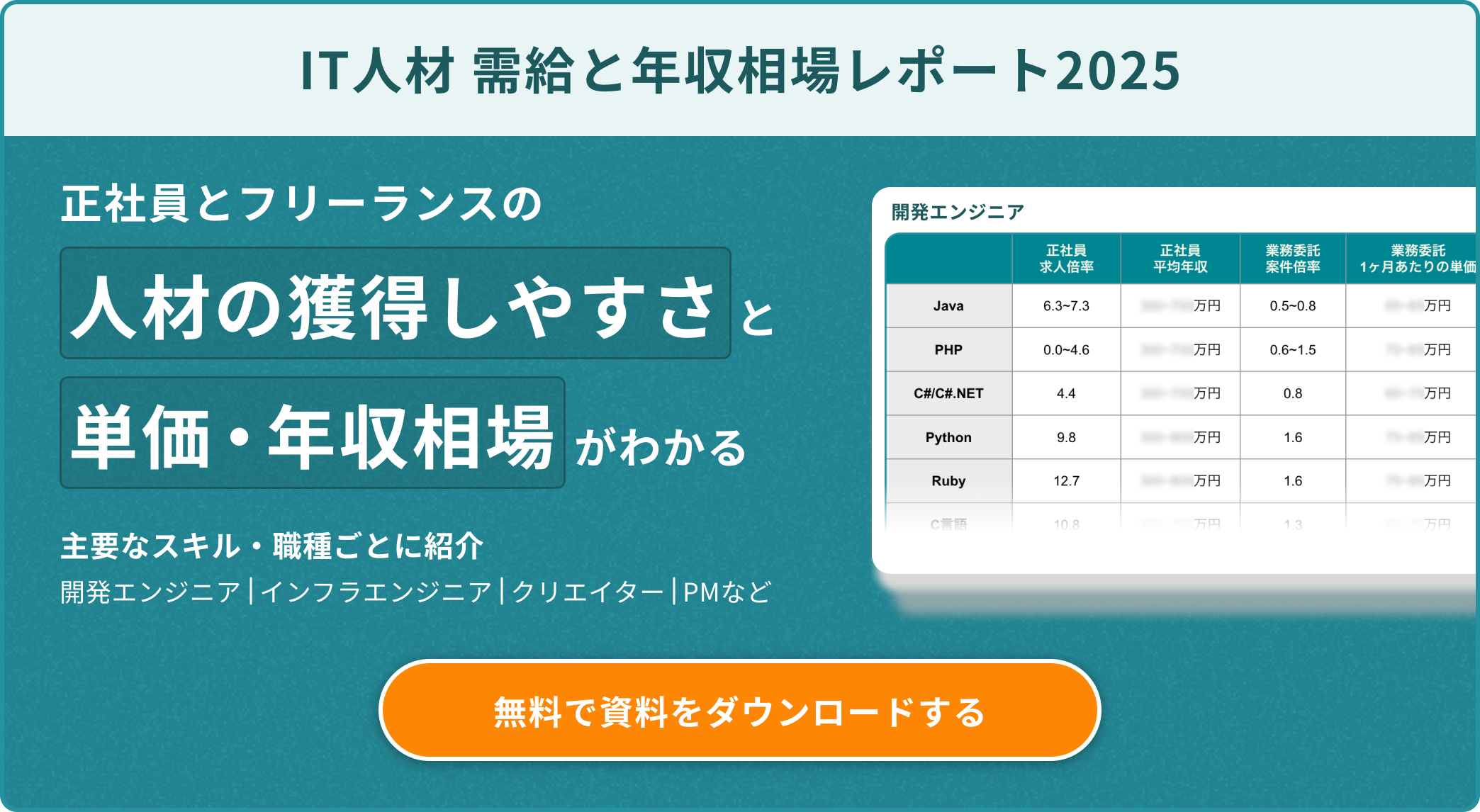
SESで問題となる「偽装請負(偽装フリーランス)」とは
これまでご紹介したとおり、SESのエンジニアは雇用労働者と異なって指揮命令に従う義務がないにもかかわらず、この準委任契約の性質に反して指示や命令に従うことを強制すれば、事業者としての「独立性」が妨げられることになります。
こうした状態が常態化する等して「独立性」が認められないような場合には、本来、社会保険等の制度でも保護される「労働者」として扱われるべきであるのに、見せかけ上雇用関係にないだけの状態にもみられ、「偽装請負(偽装フリーランス)」として指摘を受けてしまうということにもなりかねません。
適切な外部人材の活用のためには、エンジニアがクライアントから独立した事業主体であることに十分留意する必要があります。ここで重要になるのが、「誰が指揮命令権を持つのか」を正しく理解することです。これはSESの契約形態によって異なります。
常駐型業務委託(SES企業の正社員を常駐させる)の場合
SES企業が自社の正社員エンジニアを常駐させる場合、雇用契約に基づく指揮命令、労務管理その他一切の雇用主としての責任はSES企業が負います。
しかし、クライアントがエンジニアに直接指揮命令を行うなど、SES企業が雇用主としての役割を果たしていない状態になると、契約形態は業務委託であるものの実態は労働者派遣に該当する労働者派遣法上の「偽装請負」とされるリスクが生じます。多くの場合、SES企業が現場に作業員の指揮命令、労務管理等を行う責任者(常駐または非常駐)を配置しますが形骸化していると同様の懸念が生じます。クライアントは、その責任者に対して契約に基づく依頼を行い、責任者からエンジニアへ業務指示を出す、という体制を構築することが重要です。
フリーランスを活用する場合
フリーランスは独立した事業主であり、クライアントもSES企業も当該事業主の独立性を損なうような指揮命令や労務管理を行う立場にはありません。そのため、契約上の必要性なくフリーランスに指揮命令を行ったりすると実態としては雇用関係にあるのではないかという「偽装請負(偽装フリーランス)」と指摘される可能性があります。
このケースでは、「クライアントとSES企業」「SES企業とフリーランス」の間でそれぞれ業務委託契約が結ばれており、クライアントとフリーランスの間に直接の契約関係はありません。業務に関する要望や協議は、契約の直接の当事者間で行われることになります。
独立性を妨げる指揮命令に該当すると考えられるケース
では、どういった取引が独立性を妨げてしまうと考えられるのでしょうか。ここで多くの担当者が悩むのが、「業務の性質上必要なコミュニケーションまで躊躇してしまう」という点です。
まず理解すべきは、直接行うコミュニケーションのすべてが独立性を妨げたり不当な指揮命令にあたったりするわけではない、という点です。業務の性質上、必要な協議や調整は問題ありません。例えば、システム開発において事業の目的に照らして仕様の変更を協議したり、関連部署との連携のためにスケジュールを調整したりすることは、正当な業務連携の範囲内と示されています。
一方で、「独立性」を妨げる指揮命令と考えられるおそれがあるのは、以下のような「雇用労働者」と混同した管理・指示といえます。
不当な業務プロセスの指定、やり直し等
あらかじめ業務仕様書やマニュアル等のとおりに遂行することを目的としたり、品質管理や他の工程との調整、事業の合理的な遂行などの業務の性質上の必要からの指定であったりということでもなく、契約上正当な理由のない業務の遂行方法の指定ややり直しは、「業務の遂行」よりも「指示したとおりに労働すること」を求めているといえ、独立性を妨げる指揮命令とされるおそれがあります。
なお、業務の遂行の結果を受けて、事業や製品の必要等から、新たに調整、修正を加えることを求めること自体は不当な「やり直し」ではありません。契約に含まれない事象について事後的に否定する姿勢に問題があり、特に、受領拒否、支払い拒否等をすることは不当な受領拒否、やり直しともされ得るものであることに注意が必要です。
事業者それぞれに、契約上の責任に基づき、自分の裁量で方法を決定して遂行することに期待されるのです。
作業時間、作業場所の一方的な指示、変更
業務の遂行方法だけでなく、作業時間や場所についても、あらかじめ契約で合意している業務内容に前提となる提供時間や提供場所が含まれ、それが契約の目的となっている場合や業務の性質上の必要に応じた場合でもなく、契約上正当な理由なく、一方的に時間や場所を指定して従わせるケースも、独立性を妨げているといえるでしょう。
あらかじめ業務の提供方法や場所については、双方の認識にずれが生じないよう契約書に明記する等の方法が望ましいといえます。
契約範囲外の業務の強制
契約内容に含まれない業務を強制したときは、もちろん事業者の独立性を妨げてしまっているといえます。このような行為が行われてしまうのは、そもそも広く会社の業務命令や上司の指示に従うべき誠実労働義務を負う雇用労働者と混同してしまっているともいえるかもしれません。
業務遂行上不要な朝礼や掃除等は、誠実労働義務に基づく職場秩序の維持を期待するものでもありますので、会社と個人の間に、強い従属関係があるとされ、雇用関係であるはずだとの指摘をうけるおそれは特に大きいケースといえます。
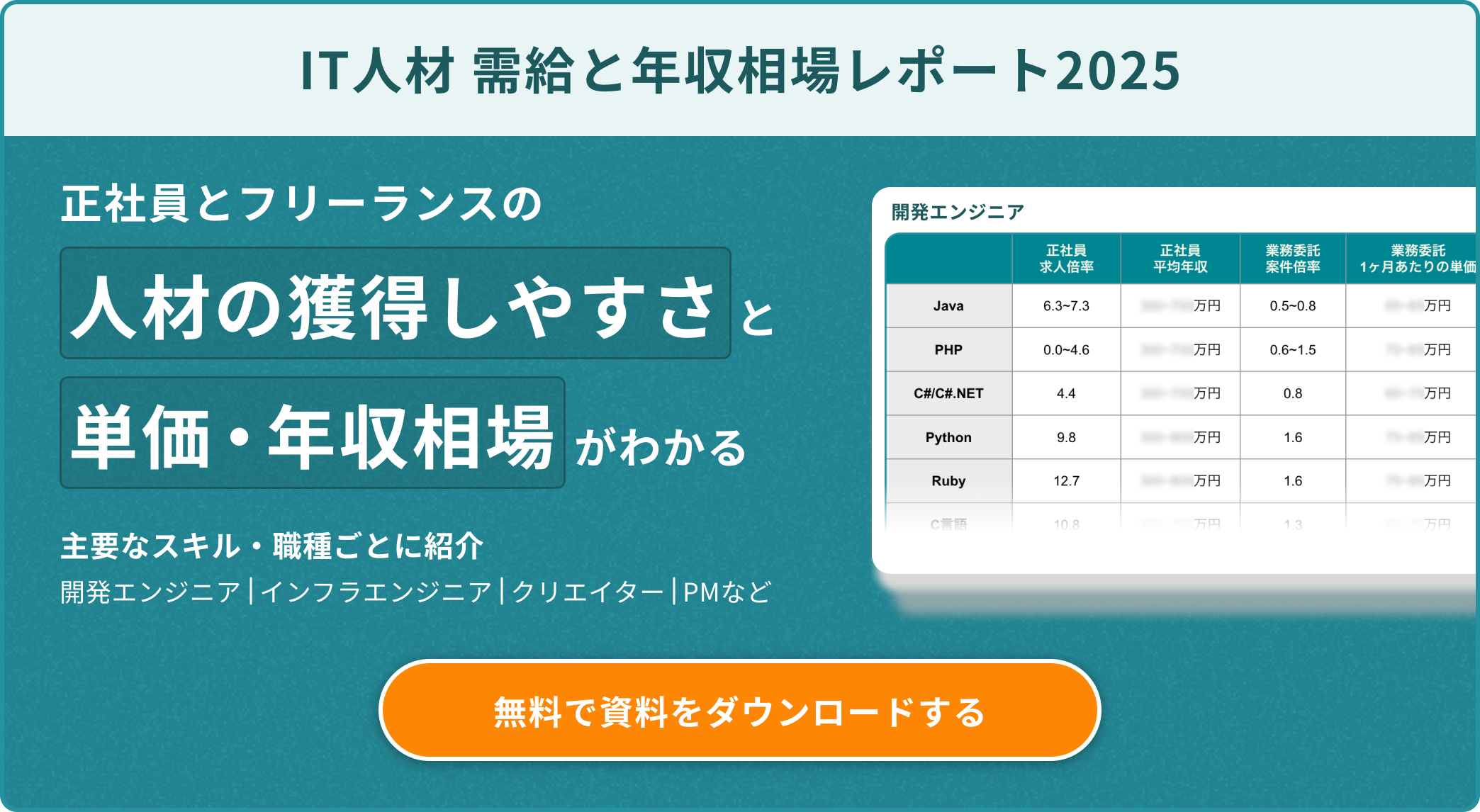
SES企業の意義
これまでいくつかのケースをご紹介しましたが、一番気づいていただきたい重要なポイントは、いずれもクライアント企業の思いや要望をエンジニアに直接ぶつけてしまったことが原因ともいえることです。
SES企業は、クライアントとの契約当事者であり、かつエンジニアの雇用主、または契約当事者でもある特別な立場にあります。クライアントの要望を踏まえ、適切な契約内容に反映させていく役割を担うSES企業は、プロジェクトを円滑に推進するパートナーとして、契約の当事者として大きな意義を持っているといえます。現場でのやり取りに迷われた際や、業務範囲の調整、契約内容の変更などが必要になった場合には、まずSES企業に相談しましょう。
まとめ
エンジニアのスキルや経験を活かすためには、契約の相手方やフリーランス人材としての独立性を妨げないよう、対等な立場で信頼関係を構築することが重要です。
フリーランス人材の活用や外部事業者への委託等の経験があまりない場合、雇用労働者である部下との違いがわからず、意図せず指摘の原因を生じてしまうこともあるかもしれません。
適正かつ効果的な事業の推進、拡大には、社員だけではなく、フリーランスや協力事業者等の活躍が大切です。そのためにも、それぞれの立場や契約関係を十分理解し、対等な契約当事者として尊重していく関わり方を進めていくことが必要です。その関係当事者のひとつとしてSES企業を選定いただいたときには、自社、フリーランス、SES企業それぞれの役割を踏まえて協力することで、適した事業環境を構築していけるはずです。
SES契約に関するよくある質問
Q.SES契約とは?
A.SES契約とは、クライアントの求めるシステム開発や保守、運用などの業務を受託する契約で、SES企業のエンジニアの技術を提供することを目的としています。一般的には準委任契約とされ、SES企業は、自社の社員や業務委託契約を締結するフリーランスをクライアントに常駐させるなどして業務を提供します。
Q.偽装請負(偽装フリーランス)とは?
A.業務委託(請負)の形態をとりながら実態は労働者派遣や労働者供給となってしまっている状態を労働者派遣法に抵触する「偽装請負」といいますが、実態は雇用労働者であるのにかかわらず、業務委託(請負)の形態がとられていることで労働基準法上の保護を受けられない状態も広く含んで使われることがあります。また、フリーランス人材が実態として雇用労働者であるような状態になってしまうケースは「偽装フリーランス」とされることもあります。
Q.SES契約のエンジニアに残業を命じられる?
A.契約上、業務を提供する時間帯を限定しているようなケースはもちろん、クライアントの事業上の理由から当日中の業務の遂行を求めるような場面では、原則として契約の範囲外となるため、エンジニア本人の個別の合意が必要となります。フリーランス人材による業務提供のときには、SES企業と協議し、SES企業の調整によりフリーランス人材の合意の上で業務が提供されている必要があります。
Q.SES契約と派遣契約の違いは?
A.どちらも外部の人材が業務を提供するサービスですが、契約の種類に違いがあります。SES契約では業務委託契約を結び、業務の受委託が契約の目的となりますが、派遣で結ぶ派遣契約は雇用関係に基づく誠実な労働提供が目的となります。SES契約では独立して業務が遂行されますが、派遣契約では誠実労働義務に基づきクライアントの指示、業務命令に基づく労働が提供されます。