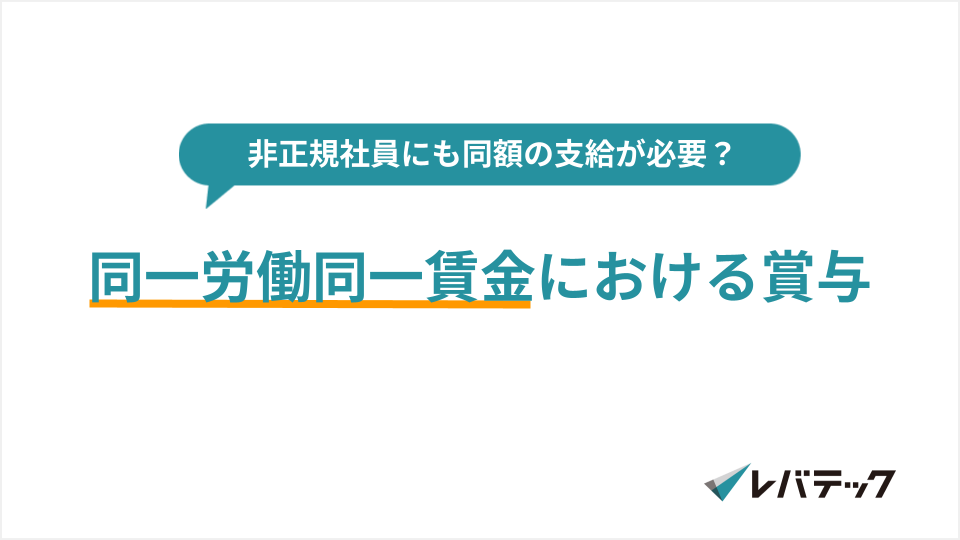採用ノウハウ - レバテック|エンジニア&クリエイターの採用情報サイト
-
人材をお探しの企業様はこちら
-
お役立ちコンテンツ
- 運営会社
- 求職者の方
- 採用支援サービスお問い合わせ
- 採用ノウハウ・サービス資料ダウンロード
同一労働同一賃金の影響で業務委託が増える?企業に求められる対応とは
IT人材の採用に関わるすべての方へ
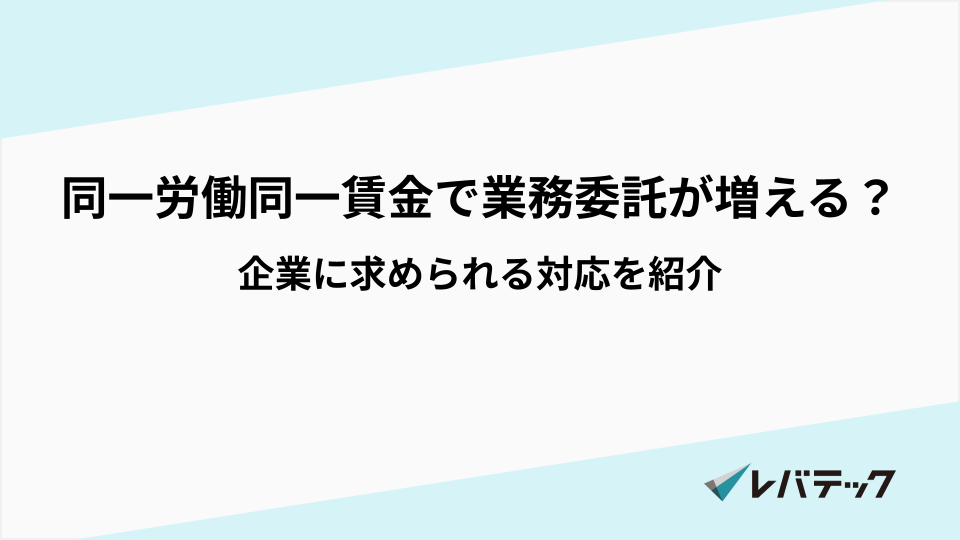
2020年4月よりスタートした同一労働同一賃金は、正社員と非正規社員の不合理な待遇差を解消することが目的で、派遣社員も対象になります。派遣元企業は派遣社員の待遇改善を図る必要があり、不合理な待遇差がある場合、その是正をしなければなりません。
この影響から、派遣契約から請負契約に転換する派遣先企業が増える可能性もあると考えられます。この記事では、同一労働同一賃金が派遣事業に与える影響と、同一労働同一賃金導入にあたって派遣先企業が果たすべき義務を説明します。
エンジニア・クリエイターの採用にお困りではありませんか?
レバテックなら業界最大級!登録者40万人のデータベースでエンジニア・クリエイターの採用成功を実現
⇒レバテックについて詳細を知りたい

目次
同一労働同一賃金で請負契約が増える?
国は2020年4月1日より同一労働同一賃金を導入しました。この影響から、派遣契約が減少し、請負契約が増える可能性があると考えられます。
派遣元企業の義務
同一労働同一賃金は、派遣社員にも適用されるルールです。派遣元企業には、改正労働者派遣法にもとづき、正社員と派遣社員を含む非正規社員との不合理な待遇差を解消することが求められます。
具体的な待遇の決め方としては、「派遣先均等・均衡方式」もしくは「労使協定方式」のいずれかを用いることが義務化されました。
派遣先企業への影響
改正労働者派遣法は派遣先企業に対して、「派遣元企業が派遣社員の待遇差を解消できるように、派遣料金について配慮する」ことを規定しています。実際に、大手人材派遣会社では、同一労働同一賃金導入後に派遣料金を引き上げる動きがありました。
派遣契約から請負契約へ
派遣料金の引き上げを受けて、派遣社員を活用していた企業の一部が請負契約に転換する動きが予想されます。
請負契約を含む業務委託には労働基準法は適用されず、同一労働同一賃金の対象にもなりません。そのため、コスト削減を目的にフリーランスなどに委託し請負契約を結ぶ企業が増えると考えられます。
同一労働同一賃金と請負契約についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
同一労働同一賃金の適用と請負契約
DX人材の確保を実現する「フリーランス活用」とは?
フリーランスとDXを進めるための具体的なステップを紹介!
⇒DX先進企業のフリーランス活用事例集を無料でダウンロードする
請負と派遣の違い
請負と派遣の違いは、「労働者と注文者の間に指揮命令関係があるか」という点にあります。労働者派遣においては、派遣先は派遣社員に仕事の指示を行えます。一方、請負では、注文者は請負契約の実施者に指揮命令を行うことはできません。
また、派遣は人材の補充を目的としますが、請負は成果物の納品を目的とする契約です。そのため、派遣契約においては業務が完了するか否かに関わらず料金が発生します。一方、請負契約の場合は、依頼した仕事が完了しない限り費用が発生しない仕組みとなっています。
【最新版】IT人材の採用市場動向がこれ一つでわかる。
他社の採用人数や予算のトレンド、どんな採用チャネルを利用しているかを知れる資料です。
⇒「IT人材白書 2024」を無料でダウンロードする

請負以外の業務委託の種類
請負契約以外にも、業務委託には「準委任契約」「委任契約」という形態があります。外部の企業やフリーランスに業務を委託する際は、この2つの契約について覚えておきましょう。
準委任契約は、法律行為以外の業務の遂行を目的とする契約です。決まった成果物を想定しない業務を委託する際は、請負契約ではなく準委任契約を結ぶのが一般的です。
たとえば、ITエンジニアに業務を委託する際は、準委任契約を結びます。SES(システムエンジニアリングサービス)を使って技術力の提供を受ける場合も、準委任契約を結ぶのが一般的です。
派遣とSESの違いについては、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。
エンジニアの「派遣」「SES」の違いとは
委任契約は、法律行為を伴う業務を依頼する際に結ぶ契約です。準委任契約と同様に業務の遂行を目的とし、弁護士や司法書士に業務を依頼する際などに締結します。

同一労働同一賃金について
ここからは、同一労働同一賃金ついて詳しく紹介します。同一労働同一賃金の目的や対象となる待遇について確認していきましょう。
同一労働同一賃金導入の目的
国は同一労働同一賃金を導入して正規社員と非正規社員の不合理な待遇差を解消することで、「どのような雇用形態を選んでも納得して働ける社会」を実現したいと考えています。同一労働同一賃金ルールが徹底されれば、労働者はより多様で柔軟な働き方を選べるようになるでしょう。
同一労働同一賃金が規定された法律
同一労働同一賃金については、2020年4月1日に施行されたパートタイム・有期雇用労働法と労働者派遣法に詳しい規定があります。
また、国は同一労働同一賃金ガイドラインを策定し、どのような待遇差が不合理なのか、あるいは不合理でないのかを、具体例を挙げて示しています。
参考:
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律|e-Gov
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律|e-Gov
同一労働同一賃金ガイドライン|厚生労働省
同一労働同一賃金の対象となる待遇差の範囲
同一労働同一賃金で解消が求められる不合理な待遇差は、基本給やボーナスなどの賃金にとどまりません。ガイドラインでは、教育訓練や福利厚生についても言及しています。
また、ガイドラインに具体的な記載がない退職手当や住宅手当などの各種手当についても、不合理な待遇差の解消が求められています。
同一労働同一賃金の対象となる待遇の詳細については、以下の記事を確認してください。
同一労働同一賃金とは?企業が行うべき対応をわかりやすく解説
同一労働同一賃金において派遣先企業に求められること
先ほどお伝えしたとおり、派遣先企業は派遣料金に配慮することが求められます。
加えて、改正労働者派遣法では、派遣先企業が「比較対象労働者」の待遇に関する情報を提供することが義務化されました。
比較対象労働者とは、職務内容や配置などが派遣労働者と同一である派遣先の社員のことです。比較対象労働者に関する情報は、派遣元企業が派遣労働者の均等・均衡待遇を図る際の参考になります。
また、同一労働同一賃金で改善が求められる待遇差には、福利厚生施設や教育訓練も含まれます。そのため、派遣先企業は、派遣社員に食堂・休憩室・更衣室の利用機会を提供しなければいけません。診療所や保育所、娯楽室といったその他の施設についても、利用できるよう配慮することが求められます。
さらに、教育訓練に関しても、派遣元企業の要請に応じて実施する必要があります。
フリーランスを活用するIT企業が急増中?
フリーランスの活用を検討している方や、他社の活用状況を知りたい方はこちらから資料をダウンロードしてください。
⇒「IT企業のフリーランス活用実態調査」をダウンロードする
同一労働同一賃金に関するよくある質問
同一労働同一賃金に関するよくある疑問を解消します。同一労働同一賃金を守らなかった場合のリスクや、派遣・業務委託におけるルールを解説するので確認しましょう。
Q.同一労働同一賃金は義務?
A..同一労働同一賃金への対応は義務ではありますが、違反した場合の罰則はありません。ただし、同一労働同一賃金に違反した場合、従業員から訴訟を起こされる可能性はあり、その際は企業イメージが低下したり、人材が流出したりするリスクが考えられます。
Q.同一労働同一賃金は派遣も対象になる?
A.派遣社員も対象になります。派遣元企業は、派遣先均等・均衡方式もしくは労使協定方式にもとづき、適切な報酬を支払う必要があります。派遣先企業にとっては、派遣料金の引き上げといった影響が考えられるでしょう。
Q.同一労働同一賃金は業務委託も対象になる?
A.業務委託は同一労働同一賃金の対象にはなりません。そのため、同一労働同一賃金の施行後は、派遣料金の値上がりによるコスト増を抑えるため、業務委託に切り替えて人材を確保する企業が増えると考えられます。