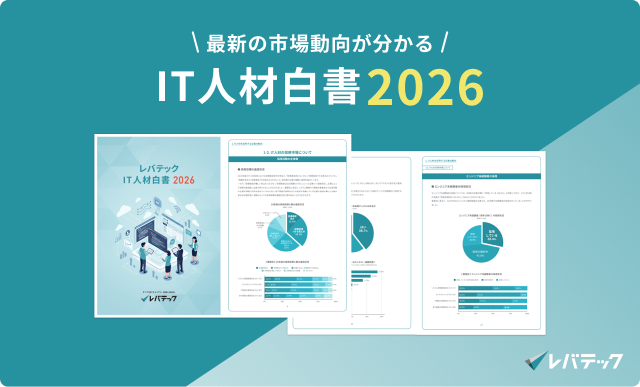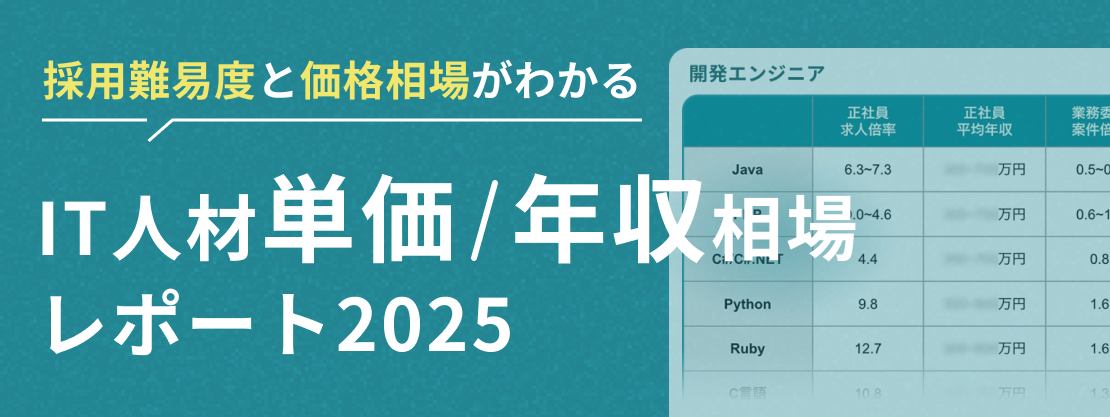採用ノウハウ - レバテック|エンジニア&クリエイターの採用情報サイト
システム導入の流れを解説!成功のポイントや失敗例と回避策も紹介
無料IT人材の採用に関わるすべての方へ
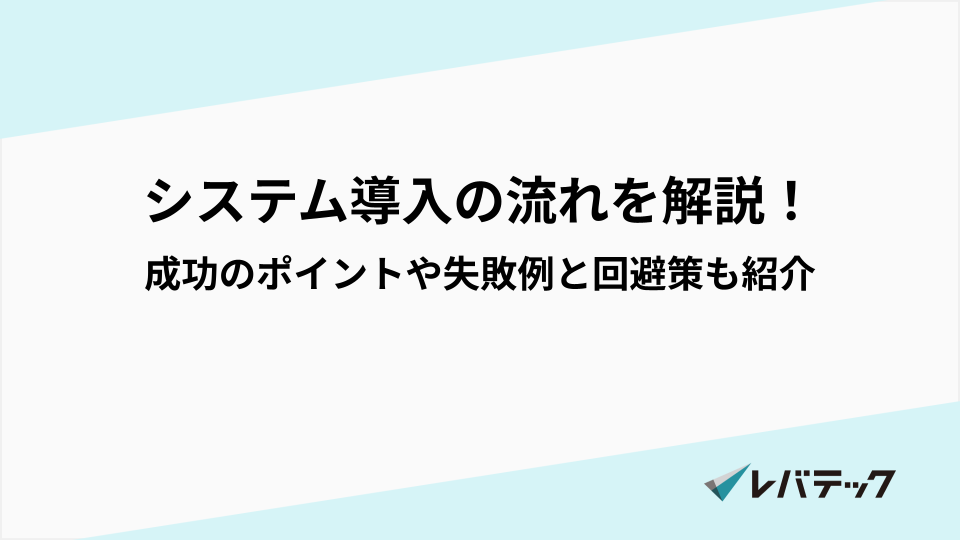
「業務効率化のためにシステムを導入したいけど、どう進めれば良い?」と悩んでいませんか?システムを導入するには、目的設定から運用開始まで多くの工程を必要とします。
この記事では、システム導入の流れを9つのステップで詳しく解説するとともに、導入を成功に導くための重要ポイントや、失敗事例とその回避策も紹介します。これからシステム導入を検討している企業の方は、ぜひ参考にしてください。
【最新版】IT人材白書2026 を公開!
激化するIT人材の獲得競争を勝ち抜くための「最新データ」がここに。
IT人材白書2026は、貴社の採用戦略をデータで裏付け加速させるためのレポートです。IT人材採用のリアルな課題と、成功への具体的なヒントを数字で示します。
・IT系企業は順調、非IT系企業は苦戦傾向。業態で差が出る採用進捗のリアル
・採用手法は「待ち」から「攻め」へ。スカウト媒体や外部サービスの活用が活発に
・求人票やスカウト文の作成などにおいて生成AIの活用が広がる
・20代の正社員IT人材の約半数が「静かな退職」状態にある
最新のIT人材採用市場について詳しく知りたい方は以下より無料でダウンロードし、採用活動にお役立てください。
「レバテック」は業界歴20年のIT人材専門エージェントです。中途採用、フリーランス(業務委託)、派遣、新卒採用など、採用ニーズに合わせて70万人を超える登録者の中から最適な人材をご紹介します。
レバテックについて詳しく知りたい方は、こちらからサービス資料をダウンロードしてください。
目次
システム導入の流れを9ステップで解説
まずは、システム導入を進めるための流れを9つのステップに分けて解説します。ただし、企業の状況やシステムの規模などによって進め方が異なる場合があるので、参考例の1つとしてご活用ください。ここでは外部ベンダーに依頼する場合の流れを説明します。
1. 導入目的の明確化
まずは、なぜシステムを導入するのかという目的を明確にすることが大切です。目的を明確にしないと、後の工程である要件定義やベンダーの選定基準が定まらない原因となります。
具体的には、「業務効率化を図りたい」や「コストを削減したい」といった漠然とした目標ではなく、明確な目標を設定すると良いでしょう。たとえば、「営業部門の事務作業を20%削減する」「顧客対応の処理時間を半減させる」といったような目標です。これにより、どのようなシステムを導入すれば良いか、どんな機能が必要かなどを検討しやすくなります。
2. 現状課題の洗い出し
次に、導入目的に関連する業務の現状と課題を洗い出します。現状と課題を具体化することで、必要なシステムの輪郭がはっきり見えてくるためです。
具体的には、現場スタッフへヒアリングを行い、現状の課題と要望を確認します。この際、実際の業務フローを作成し、それぞれの作業工数を計測しておくと良いでしょう。そのうえで、「どの業務プロセスに問題があるのか」「どのような機能があれば解決できるのか」を明確にすることが大切です。
3. システムの要件定義
洗い出した課題に基づいて、導入するシステムに必要な機能や性能などの要件を定義します。ここで定める要件は、限られた予算や時間の中で最適なシステムを構築するための重要な要素となります。
要件を曖昧にしたまま導入を進めると、開発途中での仕様変更につながり、コスト増加や納期遅延のリスクが高まるためです。
要件定義においては、「絶対に必要な機能」「あれば便利な機能」「将来的に必要になる機能」などに分類し、優先順位をつけると良いでしょう。また、技術的な制約条件(既存システムとの連携、セキュリティ要件、運用環境など)も明確にしておく必要があります。
なお、ここで定めるシステム要件は、現場の理解も得ておくことが大切です。事前に洗い出した課題を解決できる要件となっているか、要件に抜け漏れがないかなどを確認したうえで次の段階に進みましょう。
4. ベンダーの選定・ヒアリング
3で定義した要件を満たせるベンダーを選定するためのフェーズです。ベンダーによって品質や費用が変わってくるため、ベンダーの選定は慎重に行う必要があります。自社に最適なベンダーを選ぶため、複数のベンダーへ問い合わせを行いましょう。
問い合わせ後は、ベンダーによるヒアリングが実施されます。1~3で明確にしたシステム導入の目的や自社の課題、要件を詳細に伝えましょう。予算やスケジュールもこの時点で伝えておくことが大切です。
また、ヒアリングでは、自社からベンダーに質問することもできるため、選定の判断材料を集められます。類似案件の実績や品質の管理体制、サポート体制の充実度などを確認し、相手の技術力や提案内容の質を評価しましょう。
さらに、コミュニケーションの質もベンダーの選定に必要な要素です。自社の要望に応えられるだけでなく、新たな提案や指摘をしてくれるベンダーが望ましいでしょう。自社では気がつかない部分にも気がつき、より質の高いシステムを提案してくれる可能性があるのです。
5. 見積もり依頼・契約締結
各ベンダーに見積もりを依頼し、ベンダーを選定したら契約締結を行います。提案内容や費用対効果、契約条件などを比較したうえで、自社に最適と判断したベンダーと契約を結びましょう。
提案内容は、自社が提示した要件が網羅されているか、自社の課題を解決できるシステムとなっているかどうかを確認します。費用についても、予算に見合っているかどうかをチェックしましょう。
契約締結時には、納期や支払い条件、瑕疵担保の責任、知的財産権の帰属など、契約内容を細部まで確認することが大切です。後々のトラブル防止のため、契約書はできるだけ具体的に明記しましょう。
なお、契約前にトライアル利用(デモンストレーション)が可能な場合があります。事前にシステムに触れることで、操作性や自社の業務との適合性を確認できるため、積極的な試用がおすすめです。
また、システム導入には多額の費用がかかるため、契約前に自社の上長から承認を得るための稟議書が必要です。ベンダー選定と並行して手続きを進めましょう。
下記の記事では、システム開発にかかる外注費用の相場を紹介しています。外注先を検討する際の参考にしてください。
システム開発の外注費用を解説!相場や内訳、費用を抑えるコツを紹介
6. システムの設計・開発
契約締結後、ベンダーにより、要件定義に基づいた詳細設計と開発が始まります。ここで大切なのは、すべてをベンダーに任せきりにするのではなく、定期的な進捗確認やミーティングを通じて、自社も積極的に関わっていくことです。
これにより、契約で定めた要件どおりの仕様になっているかやスケジュールどおりに開発が進んでいるかどうかを適宜確認でき、システム導入をスムーズに進めやすくなります。
開発途中での仕様変更は、コストアップや納期遅延の原因となるため、最小限に抑えるようにしましょう。どうしても変更が必要な場合は、影響範囲や追加コストを加味したうえで、慎重に判断することが重要です。
7. テスト運用の実施
システムが完成したら、本運用前に必ずテスト運用を行います。実際の業務の中でシステムを利用した際、正常に利用できるかどうかを確認するためです。ただし、テスト段階のため、先行運用として一部の部署で行うことをおすすめします。
テストでは、当初の目的や定義した要件に沿ったものになっているかどうか、操作性やパフォーマンスに問題がないか、エラーが発生していないかなどを確認しましょう。
もし、要件に合致しない箇所や不具合が見つかったら、ベンダーに修正を依頼できます。ただし、要件で定めていない内容は、修正対応ができなかったり、追加コストや納期の遅延が発生したりする可能性があります。
なお、テスト運用に合わせて、マニュアルの作成も並行して進めておくと、本運用を効率的に進められます。システムの操作マニュアルについては、ベンダーに作成を依頼することも可能です。その場合は、要件の提案時に「システムマニュアル」を成果物として盛り込んでおきましょう。
8. データの移行
本運用開始前に、既存のデータを新システムへ移行します。移行前には既存データのバックアップを行い、移行後はデータの整合性をチェックしましょう。万が一、データ移行時にデータの欠損や不整合が生じると、後の業務に大きな支障をきたすからです。
なお、大規模なデータ移行の場合は、より多くの時間を費やします。そのため、夜間や休日など業務への影響が少ない時間帯での実施を検討してみると良いでしょう。
9. 本運用の開始
すべての準備が整ったら、新システムの本運用を開始します。本運用を開始したら、効果測定のため、システムの使用感や業務改善の効果などを利用者からフィードバックしてもらいましょう。せっかくシステムを導入しても、利用率が低かったり、本来の目的である業務効率が改善されなかったりした場合は、導入した意味がなくなってしまうからです。
また、この結果をもとに、必要に応じた改善を行っていくことで、システム導入の効果を最大化できるのです。
この項目ではベンダーに依頼する場合の流れを解説しましたが、下記の記事ではSlerとベンダーに関する解説を行っています。ベンダーへシステム導入の依頼を検討している場合は、あわせてご活用ください。
SIerとベンダーは何が違う?依頼先を選ぶときのポイントと

業務効率化を実現するシステムの種類
ここでは、業務効率化に役立つ代表的なシステムを5つ紹介します。それぞれの特徴を把握して、自社にとって最適なシステムを決めるときの参考にしてください。
顧客管理システム(CRM)
顧客管理システム(CRM)は、顧客の情報を一元管理するシステムです。顧客の基本情報や問い合わせ履歴、購入履歴などを管理できるだけでなく、これらのデータを社内で共有することが可能で、自社の営業やマーケティングに活用できます。
具体的には、営業部門で顧客との関係を構築しやすくしたり、マーケティング部門で購入者のニーズを分析し、マーケティング戦略の策定に役立てたりといったことができます。
営業管理システム(SFA)
営業管理システム(SFA)は、営業に関する一連のプロセスを管理するシステムです。案件の進捗や商談内容、受注・売上状況の管理や、レポート作成などをサポートしてくれるため、営業活動をより効率的に進めやすくなります。
たとえば、可視化された各データに基づき、現状の営業プロセスの見直しや、売上予測の精度を高められます。これにより、営業活動の効率化だけでなく、営業成果の向上も図れるのです。
生産管理システム
生産管理システムは、製造業における生産プロセスを最適化し、生産性を向上させるためのシステムです。生産計画や在庫管理、品質管理など、生産から出荷までの一連の流れを一元管理できるため、適正な在庫維持や品質の担保、生産コストの削減といった効果が期待できます。
たとえば、生産状況をリアルタイムで把握できるため、過剰在庫や資材の欠品防止につなげられます。また、製造スケジュールの調整や現状の生産プロセスの最適化にも役立つでしょう。
販売管理システム
販売管理システムは、自社の商品販売に関する一連の業務を管理するシステムです。商品の受発注や在庫を管理できるだけでなく、見積もりや請求書作成のサポートも可能なため、販売に関する業務負担を削減できます。
たとえば、見積・請求書を自動で作成する機能により、人的なミスや漏れを減らすことができます。また、販売実績のデータを分析することで、売れ筋商品の把握や需要の予測も容易になるでしょう。
ERPシステム
ERPシステムは、企業の基幹となる業務を統合的に管理するシステムです。人事、会計、生産、販売など、従来は各部門ごとに管理していたさまざまな業務をシステム上で連携させることができます。
ERPの主な特徴は、各業務間でのデータ連携がリアルタイムに行われることです。たとえば、営業部門で入力した受注データが、そのまま生産計画や会計処理に反映されるため、部門間のデータの不整合や二重入力を防げます。そのため、部門や事業所を多く持つ企業にとって、大幅な業務効率化を実現できるシステムといえるでしょう。
上記のようなシステムの導入は、企業における社内DXの推進にもつながります。下記の記事では、社内DXについても解説していますので、さまざまなデジタル技術を活用して社内業務を効率化させたいと考えている場合は、ぜひ参考にしてください。
社内DXとは?具体例や推進に向けた4ステップ
システム導入を成功に導く5つの重要ポイント
ここでは、システム導入を成功させるための重要なポイントを5つ紹介します。導入前の参考にしてください。
導入前に社内の理解を得ておく
システム導入を成功させるには、事前に社内の理解と協力を得ておく必要があります。いくら優れたシステムを導入したとしても、現場の社員が適切に利用しなければ、導入の効果が限定的となってしまいます。
特に、新しいシステムの導入は業務の変化を伴うため、現場からの抵抗を招きがちです。そのため、計画段階からシステム導入の目的を説明し、現場の意見を取り入れたうえで導入を進めましょう。現場部門とのヒアリングや社内アンケートを実施することで、社員からのフィードバックを得やすくなります。
費用対効果を踏まえて導入を検討する
システム導入においては、かかるコストと得られる効果のバランスを見極めることが重要です。単に「最新のシステムだから」「競合他社が導入しているから」という理由で導入するのではなく、自社の目的や予算に応じて導入を検討しましょう。
費用面では、初期導入費用だけでなく、運用コストや将来的なアップグレードコスト、利用社員への教育費用なども含めた総コストを考慮します。効果面では、業務効率化による工数削減やヒューマンエラーの減少、売上の増加など、定量的・定性的な効果を予測しましょう。
また、システムの選定においては、必要な機能だけを絞り込むことが大切です。過剰な機能は導入・運用コストを増やすだけでなく、システムの複雑化を招き、かえって効率を下げる場合もあるからです。自社の本当のニーズに合致したシステムを選ぶことが、費用対効果を最大化するカギとなるのでしょう。
導入フローを事前に把握しておく
システム導入をスムーズに進めるには、計画から本稼働までのフローを事前に把握しておくことが大切です。もし導入フローが曖昧な状態で導入を進めてしまうと、スケジュールどおりに導入が進まなかったり、要件定義がうまくいかず、システムの品質が低下したりするおそれがあります。
あらかじめ導入フローを明確にし、余裕を持ったスケジュールを設定して導入を進めましょう。フローの各段階において、プロジェクトの責任者と現場の関係者を明確にし、タスクの進捗管理を徹底することも大切です。定期的な進捗会議を開催し、問題点を早期に発見・解決する体制を整えておくと良いでしょう。
クラウド化も検討する
システムの利用形態については、従来のようなオンプレミス型だけでなく、クラウド化も選択肢の1つとして検討すると良いでしょう。ただし、オンプレミスとクラウドにはそれぞれ特徴があるため、自社に最適な方法を選ぶことが大切です。以下、利用形態やメリット・デメリットを表で比較します。

上記のように、オンプレミスは、導入から運用・保守まですべて自社で対応するため、コストや手間がかかりますが、カスタマイズ性やセキュリティ性が高い点が魅力です。
一方で、クラウドの場合は、外部のサービスを利用するため、オンプレミスよりも導入や運用が容易といえます。ただし、オンプレミスのように自社独自の高度なカスタマイズができないため、サービスによっては導入したいシステムと連携ができないケースもあります。
オンプレミスかクラウドのどちらを選ぶかは、自社の状況(IT人材の有無、予算、セキュリティ要件など)や導入するシステムの性質に応じて選択しましょう。
下記の記事では、サーバー構築や保守・運用にかかるコストについて解説しています。クラウド化と比較したい場合の参考にしてください。
サーバー構築・保守・運用の相場は?コストを削減する方法を解説
導入後の運用体制を整備しておく
システム導入を成功させるためには、導入後の運用体制を本格稼働までに整備しておくことが重要です。運用開始後に後付けで運用体制を考えてしまうと、運用開始時に混乱が起きるおそれや、システムの効果を最大限に発揮できない可能性があるためです。
運用開始後のサポートについては、利用者からの問い合わせに迅速に対応できるよう、運用開始前の段階から体制を整備しておきましょう。特に、初期段階は問題が発生しやすいため、マニュアルやヘルプデスクの問い合わせ先をしっかり社内に周知しておくことが大切です。システムの操作方法に関する研修会を運用開始前後に開催することも有効です。
また、導入後もシステムのメンテナンスや、セキュリティアップデートを定期的に行う必要があります。メンテナンスやアップデート作業をどのような周期でどう実施するかについても、事前に決めておくと良いでしょう。
システム導入をスムーズに進めたいのに、社内にIT人材が不足しているといったお悩みはありませんか?
業界最大級のIT人材特化型データベースなら求めていた人材がきっと見つかる!
⇒「3分でわかるレバテック」のダウンロードはこちらから
システム導入でよくある失敗事例と回避策
ここでは、システム導入でよくある失敗事例とその回避策を解説します。導入を失敗してしまわないよう、ぜひ業務の参考にしてください。
導入のプロセスやコストを把握できていない
システム導入の失敗でよくあるのが、導入プロセスやコストを正確に把握していないまま計画を進めてしまうケースです。初期の見積もりよりも大幅に時間や費用がかかってしまい、結果として費用対効果が得られないという事態に陥ることがあります。
この問題を回避するためには、適切なスケジュール管理や予算設定を行うことが大切です。導入の各フェーズにおける工数やコストを詳細に見積もったり、予期せぬ事態に備えて、余裕を持ったスケジュールを設定したりしましょう。
また、予算設定の際はシステム自体の費用だけではなく、導入にかかる人件費や運用コストなどの「見えないコスト」も考慮して設定することが重要です。これにより、予算の抜け漏れを減らすことができるでしょう。
システムの導入自体が目的化してしまう
業務改善や課題解決を目的とするシステム導入ですが、導入のプロセスが進むにつれて、システムの導入自体が最優先となり、当初の目的が見失われてしまうことがあります。「なぜこのシステムを導入するのか」という根本的な目的が置き去りにされてしまうと、本来の目的である業務改善の効果が得られなくなってしまうおそれがあるのです。
この問題を解決するためには、システム導入はあくまでも手段であり、目的ではないという原点に常に立ち返るための工夫が必要となります。具体的には、導入の目的を明文化し、プロジェクト全体で共有することが大切です。そして、定期的に「このシステムで何を解決したいのか」を確認する機会を設けると良いでしょう。
また、導入計画の時点で、システム導入後の効果を測定する具体的な指標(KPI)を設定することも有効です。これらの工夫により、要件定義やテストなどの各段階で、「このシステムは当初の課題解決につながっているか」を問い続けることができるのです。
現場の業務実態に合わず形骸化する
導入したシステムが現場の業務実態に合わず、形骸化してしまうケースもよくある失敗例の1つです。現場の業務フローやニーズを十分に把握せずに導入を進めると、結果的に「使いづらい」「業務に合わない」などの不満が出て、システムの利用率が低下する可能性があります。
このような事態に陥らないためには、事前に利用者の現場の課題を把握し、どんな効果を望んでいるかをしっかりと把握しておきましょう。特に、現状の業務フローを可視化させ、システム導入後はどの部分を自動化させるべきか、どの程度工数を削減するかなどを具体的に定めることが大切です。
また、システム選定時のデモンストレーションや導入前のテスト運用において、現場から実際に使用してみた感想や意見を求めることも重要です。これらの対策により、システム導入後のイメージを描きやすくなるでしょう。

システム導入をスムーズに行うためのスキル
ここまで説明したとおり、システム導入にかかるプロセスは、膨大な業務量となります。ここでは、システム導入をよりスムーズに進めるために必要なスキルを3つ解説します。
プロジェクト全体を管理・把握できる
システム導入を効率的に進めるためには、プロジェクト全体を俯瞰して適切に管理・把握できるスキルがあると良いでしょう。これにより全体の進捗を把握でき、リソースの適切な配分や、問題の早期発見と対応が可能になります。
たとえば、システム導入を進める中で、一部のプロセスが当初の予定より工数がかかってしまうケースも少なくありません。しかし、全体をマネジメントできる能力があれば、タスクの優先順位付けや、影響範囲を分析したうえでスケジュール調整を行うなど、状況に応じて柔軟な対応ができるのです。
ベンダーと対等に交渉できる
システム導入をベンダーに依頼する場合、ベンダーと対等に交渉できるスキルが成功の鍵を握ります。ベンダーとの交渉が上手く進まないと、進捗の遅れや自社の目的に沿ったシステムが導入されないおそれがあるためです。
ベンダーと対等に交渉するためには、システムで使用される技術の基礎的な知識に加え、コミュニケーションをスムーズに進める力や相互理解が必要になります。これにより、現場の要望を適切にベンダーへ伝えるとともに、ベンダーの提案を適切に評価するといったことが可能となります。
また、ベンダー側の制約や事情にも配慮しつつ、自社に最適な交渉を行うことができるでしょう。自社に最適なシステムを導入するためには、ベンダーに任せきりにするのではなく、相手と対等なパートナーシップを築きながら、協力して導入を進めることが大切なのです。
現場の状況や要望を理解できる
システム導入を成功させるには、現場の状況や要望を深く理解することが大切です。いくら高機能なシステムを導入したとしても、現場のニーズに合っていなければ本来の導入目的が達成されないためです。
具体的には、現場の要望を正確に理解し、システム要件に落とし込む能力が求められます。そのためには、現状の業務フローを詳細に把握し、問題点や改善点を見出すことが大切です。たとえば、「なぜ自動化させる必要があるのか」「システム導入によりどんなことが改善されるのか」を整理しましょう。業務フロー図を作成して、現状の業務を視覚的に把握することも有効です。
また、システム導入により業務フローが変わるため、現場からは「今までのやり方を変えたくない」「新しいシステムの操作が不安」といった声が挙がることがあります。このような状況でも計画をスムーズに進めるためには、現場とこまめなコミュニケーションを図り、相手の意見を尊重する姿勢が求められるでしょう。
なお、システム導入をスムーズに進めたくても、上記のようなスキルを持つ人材が社内にいないといったケースもあるでしょう。そんなときは、レバテックの活用がおすすめです。
レバテックは、ITに特化した人材を専門としたエージェントサービスを提供しています。IT人材の中でもさまざまなスキルを持つ人材が豊富に登録されていますので、導入したいシステムの要件に合致した人材を紹介することが可能です。レバテックの詳細については、下記のリンクから資料をダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
エンジニア・クリエイターの採用にお困りではありませんか?
業界最大級のIT人材特化型データベースなら求めていた人材がきっと見つかる!
⇒「3分でわかるレバテック」のダウンロードはこちらから
システムの導入の流れに関してよくある質問と回答
ここでは、システム導入に関するよくある質問とその回答をご紹介します。
Q. システム導入する際のフローを教えてください
システム導入のフローは、主に以下のようなステップで進行します。ただし、これはシステム導入をベンダーに依頼する場合の一例です。企業の状況やプロジェクトの規模によって適切な流れが異なるため、あくまでも参考例の1つとしてください。
- 1.導入目的の明確化
- 2.現状課題の洗い出し
- 3.システムの要件定義
- 4.ベンダーの選定・ヒアリング
- 5.見積もり依頼・契約締結
- 6.システムの設計・開発
- 7.テスト運用の実施
- 8.データの移行
- 9.本運用の開始
また、上記フローはステップごとに厳密に区切られるわけではなく、プロジェクトによっては同時並行で進めたり、何度か前のステップに戻ったりすることもあります。状況に応じて、最適な対応方法を柔軟に判断していくことが大切です。
Q. 導入システムは自社開発することも可能ですか?
自社のリソース状況やシステムの規模などにもよりますが、自社にIT部門があれば、システムを自社開発することは可能です。
システムを自社開発すれば、導入するシステムのノウハウを社内に蓄積できたり、セキュリティ対策も強化できたりといったメリットがあります。また、仕様の変更が必要となった場合は、自社で完結できるため、迅速な対応がしやすくなるでしょう。
しかし、自社開発を行うには社内の人材が足りないというケースが少なくありません。そのような場合は、IT特化の人材紹介サービスやフリーランスを活用するという方法があります。
レバテックでは、即戦力となるさまざまな分野のIT人材を、スピーディーに提案します。自社でシステム開発を行いたいのに人材が不足しているといった場合は、ぜひレバテックの活用を検討してみてください。