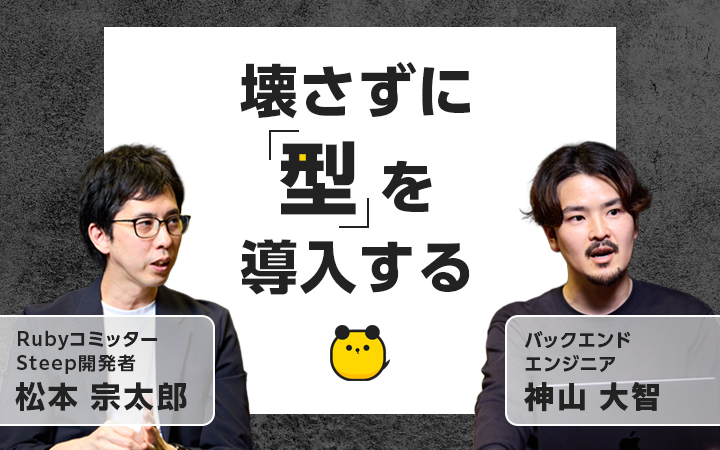ゲーム開発→事業会社へ。大ヒットゲームを開発した僕らが、「裏方的エンジニアライフ」を楽しむワケ
2021年4月15日
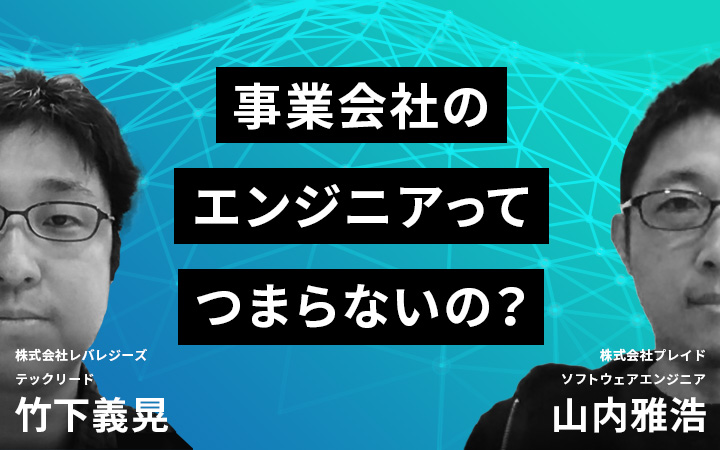

株式会社プレイド ソフトウェアエンジニア
山内雅浩
東京大学大学院理学系研究科修了。博士課程中退後、ゲーム開発を手掛ける企業に入社し、在職中に2007年II期未踏本体に採択。その後、ファッション系アプリ開発会社の技術チーム立ち上げを経て、2016年に株式会社プレイドに入社。

株式会社レバレジーズ テックリード
竹下義晃
東京大学農学生命科学研究科修了。ゲーム開発を手掛ける企業に入社後、米国のApple Storeで1位を獲得したゲーム開発に貢献。在職中はマーケティング、採用、法務など幅広い業務を担当。2020年にレバレジーズ株式会社に入社。一般社団法人Japan Scala Associationにて理事を務める。
「1000万ダウンロード突破!」、「アクティブユーザー数500万人!」、目を引く数字が飛び交うゲーム業界。そんな世界で話題のゲームを数々開発した後、新たな挑戦に事業ベンチャーのテックリードとしてのキャリアを選んだ2人のエンジニアがいる。
華やかに見えるゲーム開発者としてのキャリアから、縁の下の力持ちとして事業を支えるエンジニアに転じた理由はなんなのか。それを紐解くと、お2人ならではの「裏方的エンジニアライフ」を楽しむ極意が見えてきた。
- ARパッケージ製品から大ヒットソシャゲまで。開発に没頭した日々
- 組織づくりや事業開発にチャレンジしたい。事業会社へ転じた理由とは
- マイクロサービス化に奮闘。大きい組織に身を置くメリデメとは
- 「裏方的エンジニア」として事業をスケールさせるために大事なこと
ARパッケージ製品から大ヒットソシャゲまで。開発に没頭した日々
──お2人は、新卒でゲーム開発を手掛ける企業に入社しましたが、当時はどんなソフトを開発していたんですか?
竹下:新卒といったら、かれこれ15年以上前ですよね。はじめはゲームだけじゃなく、いろいろやっていましたね。
山内:そうそう、なんか当時13万円くらいするホビー向けの二足歩行ロボットが流行っていて(笑)。その制御ソフトウェアもつくっていましたね。
竹下:プログラムを書きはじめて間もない頃だったのに、いきなりC#で3Dのプログラムをバリバリ書くという、すごくチャレンジングな仕事で。
山内:もうメインのプログラムを書くこととは関係なく、パッケージングとか、箱詰めとかユーザーサポートまで全部自分たちでやりましたよね(笑)。
竹下:あとは、2008年頃にARを使ったエンタメソフトウェアもつくりましたね。特殊な二次元コードの書かれた四角いキューブをWebカメラで撮ると、パソコンの画面でバーチャルフィギュアが登場するPC用アプリで、当時はテレビの取材もきていましたね。
──2008年にARを利用したアプリは、かなり先進的ですね。
山内:ええ。最初スマホでリリースしようとしたんですが、当時はiPhoneもまだ3Gが出たばっかりの頃で、スペックが足りなくてPC版でリリースしたんですよ。
──それはすごいですね。あの時代といったらソーシャルゲームが盛り上がっていたと思うのですが、お2人はソシャゲの開発も手掛けていたのですか?
竹下:やっていましたね。 mixiやGREEなどでもリリースされていて、最盛期はアクティブユーザー数百万超えのゲームの開発も担当していたことがあります。
山内:一時は、電車の中で隣に座っている人が自分の開発したゲームをやっている、みたいなことも実際にあって、おもしろかったですね。
竹下:ヒットした!と実感した瞬間でしたね。
組織づくりや事業開発にチャレンジしたい。事業会社へ転じた理由とは
──まさにゲームエンジニアの醍醐味ですね! これだけワクワクするゲーム開発の世界を、お2人が飛び出したのはなぜですか?
山内:僕の場合、10年間同じ会社で同じ仕事を続けてきたこともあって、ちょっと違うことがやりたくなったという部分が大きいですね。前職の頃から、開発チームをゼロから立ち上げたり、採用にも関わっていたりしたので、もっとそのスキルが活かせる仕事をしたいと思って。もともとゲーム開発に強いこだわりがあったわけではとくになかったですし。
ちょうどそのタイミングで知り合いからファッション関係のアプリを立ち上げると聞いて転職を決めました。
でもその後、そのファッション系の会社が丸ごとなくなってしまったので、知り合いに紹介してもらったプレイドにジョインすることになりました。
竹下:僕は会社の方向性が変わったのが大きかったですね。僕はサーバサイドエンジニアなんですが、前職の会社が力を入れていたハイパーカジュアルゲームって、そもそもサーバがいらないんですよ(苦笑)。
だけど、ずっと現場でエンジニアリングをしていたかったし、組織づくりや事業開発もやってみたくて。それで、ちょうどサービス開発部ができたばかりのレバレジーズを受けてみたら、「やりたいことを全部やっていい」と言ってもらえたので、バイト時代含めて16年間いた前職を辞めて、2020年に転職することにしました。
実は当時大手の外資IT企業も受けていましたが、オファーされたのがざっくりソフトウェアエンジニアというポジションで、日本チームの場合ローカライズに携わることが多いかなと思って。
世界的なプロダクトに関われるのはエンジニアとしておもしろいかもしれないけど、僕はどちらかというと、エンジニアリング以外の組織づくりの部分に携わりたいという気持ちが強かったですね。
──お2人とも現職に入社するまでは、一般のエンドユーザー向けサービスをつくっていたわけですが、to B向けサービスの開発に興味を持つようになったのはなぜですか?
竹下:ゲームにこだわらなくても、何かサービスをつくること自体が好きなんですよね。単純に世の中の人が喜んでくれたり、楽しんでくれたりするものを考えてつくっていきたかったので。そこはto Bもto Cもそんなに大きな違いはなかったですね。
山内:僕の場合は、プレイドの経営陣と直接話せたことが大きかったですね。みんな強いビジョンを持っていて、トップダウンのワンマン経営ではないところにも惹かれました。目標と達成するための手段は臨機応変に変えていこうという柔軟さがあるというか、そこがおもしろいと感じたんです。
あとは当時CTOだった柴山(直樹氏、現CPO)と不思議と経歴が似ているのもあって(笑)。開発したプロダクトがともに未踏本体(IPA未踏スーパークリエータ)に採択されていたし、同じく東大の博士課程をドロップアウトして事業会社に参画している。プレイドで働く彼の姿に共感した部分もありましたね。
プレイドは「KARTE(カルテ)」というSaaSのto B向けマーケティングツールを開発していますが、to B向けといいつつも、実際にインターフェイスを触ったり、データを入力したりしているのは、その企業で働く個人なんですね。
「解析ユーザー累計68億」(2020年時点)というto Bならではの規模感の大きさもチャレンジングだし、ずっと思っていた「人々にサービスを使ってもらいたい」という部分も変わらなかった。そういうところに興味を持ちました。
マイクロサービス化に奮闘。大きい組織に身を置くメリデメとは
──実際入社してみて、いまの仕事のどういうところにおもしろさを感じていますか?
竹下:やはりエンジニアとして技術的チャレンジができていることがすごくおもしろいところですね。僕は現在人材系サービス「レバテック」の基幹システムのマイクロサービス化を進めている途中で。まだ動き出しの段階ですが、事業を拡大するために基盤を整えている実感があって、まずそれが楽しい。
それに、基盤が整備できたあとは、もっと楽しい次のプランが待っている、というワクワク感もありますね。
山内:うちも似ていますね。フェーズこそ違うけど、自分が携わっているKARTEも、モノリスからマイクロサービスへ移行させているところで。
これまでどんどん機能を増やしてきましたが、その過程でパフォーマンスが悪化したり、コードがぐちゃぐちゃになってしまったりと、いわゆる技術的負債がいっぱいたまってきたんですね。それを解消するために、新しい技術を駆使しながら細かいところから改善に本格的に取り組めることが、一番のおもしろさですね。
竹下:ゲームをつくっていた頃はなかなかそういう細かい改善ができなかったんですよね。
山内:そうだね。規模の大きいプロダクトだと、モノリスで開発して、どんどん新しい機能を追加していくことでジェンガみたいに繊細なバランスになってしまうんですよ。それが将来的に崩れないために、システムを複数個のサービスに分割して歪みを少しずつ調整していけるのは、僕的にはパズルみたいで楽しいですね。
竹下:あとは、マイクロサービス化をやることで、プロダクトがどんどんスケールしていくことが見えてくるところに期待を抱いてしまうんですよね。一度「電車で隣に座っている人が自分のつくったプロダクトを楽しんでいる」という感動を経験すると、そういうプロダクトをもう一度つくりたいと欲張ってしまうんです。僕が開発の最前線に居続けたいと思うのは、根源的にはそこが理由だと思います。
──逆に、大変だと思うことはありますか?
竹下:会社の規模感が一気に大きくなったところですかね。前職のときは20人もいなかったので。今はエンジニア組織だけで7、80人いますね。エンジニアだけではなくて、セールスやマーケターなど他職種の方とも連携を取りながら仕事を進めていくことになるので、最初のころはそこに文化的な違いを感じました。
山内:僕も似たような感じですね。今プレイドには200人ぐらいの社員がいますが、そもそも定員100人以上の組織で働いたことがなかったので、エンジニアリング組織のあり方自体を新しく考えてつくっていかなければいけないところがチャレンジングでしたね。
あと僕の場合、社員40人の時期に入社したので、組織が急激に拡大した中で、新しいメンバーとの接し方や仕事の教え方についてもいっぱい考えました。
竹下:そうですね、メンバーとのコミュケーションに時間をかけました。昔は「やるぞ!」と決めたらひたすら自力で突き進めていましたが、今は関係者も増えたし、エンジニアリングへの理解も不揃いだったりするので、説明に手間をかけることを学んだように思います。
山内:「社内にも説明が必要なんだ!」と身に沁みてわかりましたよね。

「裏方的エンジニア」として事業をスケールさせるために大事なこと
──お2人は、ゲームエンジニアという比較的華やかなプロダクトをつくっていた時代を経て、今は人材・マーケティングといったそれぞれの事業を支えるエンジニアとして活躍していますよね。敢えてこのような裏方的な働き方を選んだのでしょうか?
山内:僕はエンジニアリングの本質とは「不確実性を減らすこと」にあるとずっと思ってきたので、どうしたらその不確実性を「確実なもの」にしていくかという今の仕事のプロセスが興味深いし、そこがエンジニアの仕事の醍醐味だと思うんですね。
そういう意味で、「裏方的」なキャリアだからおもしろいとか、つまらないというわけではなく、自分のやりたいことに従ってキャリアを選んだらこうなったという感じです。
どちらかというと、華やかなプロダクトをつくって目立ちたいというよりは、後から結果がついてきて「実はあの凄いサービスをつくったんだって」みたいな存在になることの方に憧れがありますね。
竹下:僕も結構似ていますね。まあ、目立つ成果を出していくほうがキャリア的にプラスになるなら、積極的に表に出れば良いと思うんですけど。有名なプロダクトを開発したり、エンジニアとして目立ったりできれば採用広報にも役立ちますし。
ただ、今はGitHubのレコードや技術ブログなどもありますから、地に足つけて開発をしていたら、正当に評価される時代になったと思います。表立って華やかな世界で開発を続けていくとか、裏方的エンジニアであるとかいうことにこだわらず、自分の特性に合ったキャリアを選べたら良いんじゃないかと思います。
──ちなみに、「地に足のついたエンジニア」というのは、具体的にはどういうエンジニアのことを指しますか?
竹下:定義するのは難しいのですが、自分のイメージだと、一時期言われていた「T型人材」に近いエンジニアですかね。常に広く好奇心を持って、プロダクト全体のことに目を配りながらも、特に精通している言語があるなど、得意な武器をいくつも持っているエンジニアは強い。そういうエンジニアは安定した技術力が身についているでしょうし、事業を支えることができるのではないかと思いますね。
──そのような技術力を身につけるためにどうすればいいのでしょうか?
山内:そうですね……例えば1つのプロダクトを完成させるまでつくりきってみるというのは良い方法かもしれないですね。1本のゲームをゼロからリリースできるまで開発するとか。途中で挫折することもあるかもしれませんが、そういう試行錯誤を繰り返すことで、技術力が自然に身についていくはずです。
例えば僕はJuliaという言語を触ったり、量子コンピュータを使ってもさらに解読できない暗号の理論を勉強したりしています。
竹下:僕は、最近はマイクロサービス化やっているのでもっぱらその周辺ですね。サービスメッシュだったり、gRPCだったり。また、マイクロサービスには直接関係しませんが、言語ではRustを勉強したりしています。
──多様なキャリアを描いてきたお2人ですが、あらためて事業をスケールさせるエンジニアになるために大切なことは何だと思いますか?
竹下:言われたままただ手を動かすだけじゃなく、この事業をより良くするためには何が一番重要なのかセールスやBizDevも含めて様々な人に話を聞き、絶えず考え続けることだと思います。そして事業をスケールさせるために技術力という「武器」をしっかり磨き、正しく使っていくことだと思います。
山内:僕も能動的に動けることだと思いますね。人に言われたからこの機能を開発した、という人は多いですが、それだけではダメ。組織やチームの隙間に落ちたタスクを自律的に拾い、よりユーザーのためになることは何なのか真摯に向き合うことで、事業は円滑に進むと思いますから。
取材・編集:石川香苗子
企画・執筆:王雨舟
関連記事

爆速で成長する若手エンジニアの共通点とは? 1000万ダウンロードのビッグタイトルに携わる新卒4年目コンビに聞く「チャンスの掴み方」
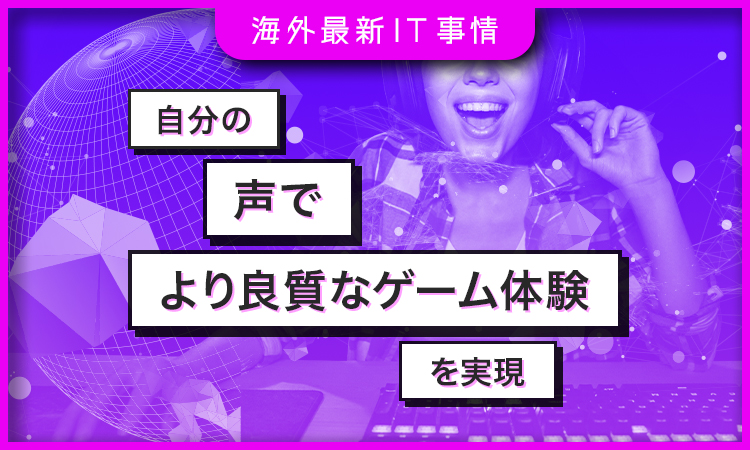
ゲームの「主人公の声」を「自分の声」にしたらどうなる? 米研究チームは声の類似性がユーザーに与える影響を実験【研究紹介】

「欲しいけど難しい」IPづくり。群雄集うクリエイティブ集団「SSS by applibot」が実践する、IPを生み出すスクラップアンドビルドに密着
人気記事