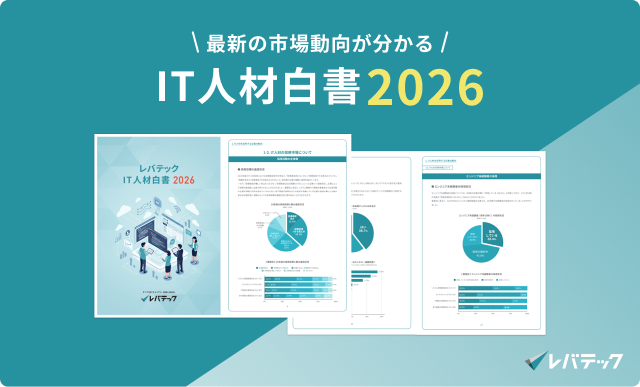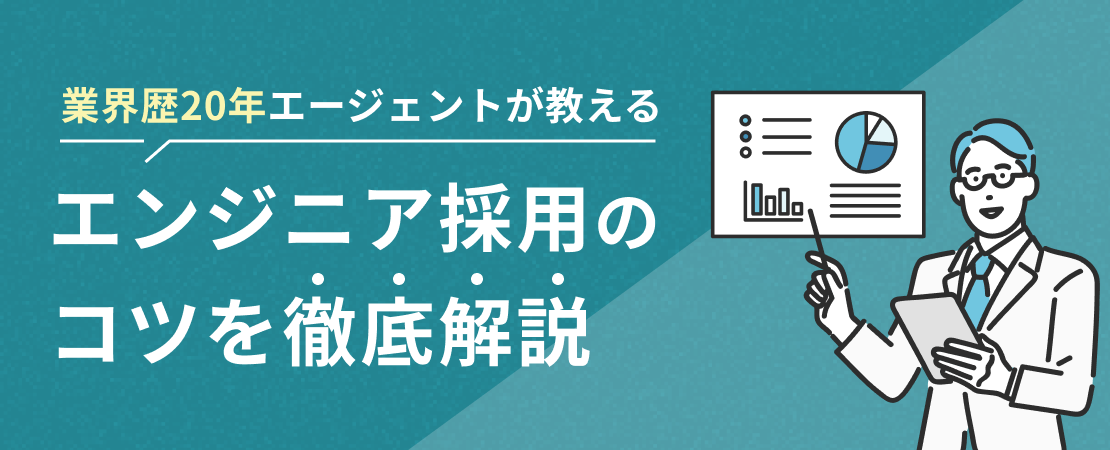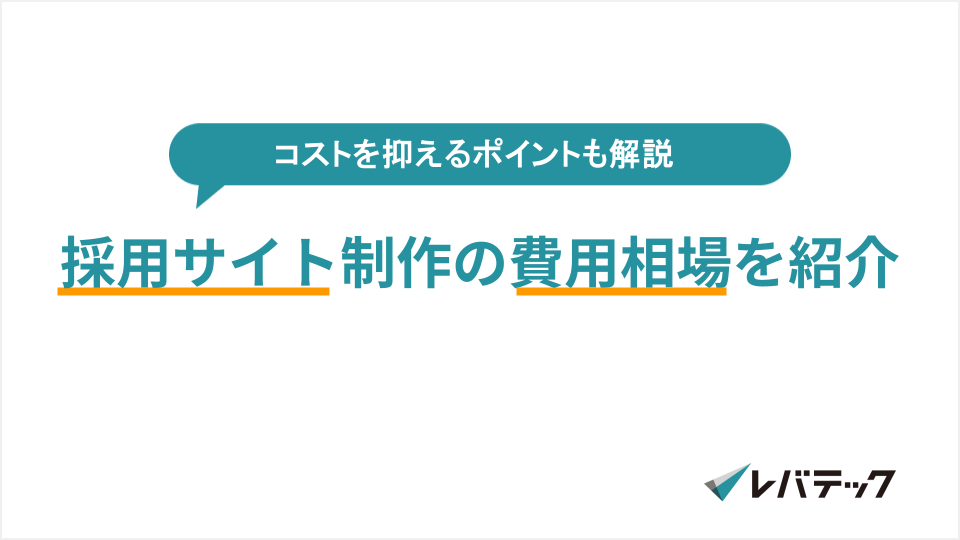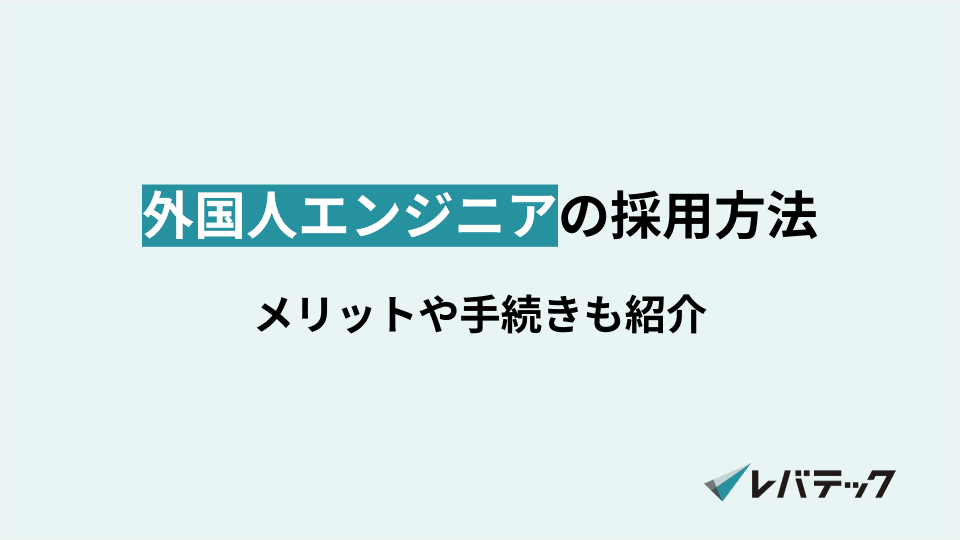採用ノウハウ - レバテック|エンジニア&クリエイターの採用情報サイト
採用KPIの設定手順を解説!メリットから設定・運用のポイントまで網羅
無料IT人材の採用に関わるすべての方へ

「応募が少ない」「選考がうまくいかない」と思っているものの、改善をしないまま採用活動を進めていませんか?このような状況を改善するために注目されているのが「採用KPI」です。
本記事では、採用KPIの説明やメリット、設定手順、運用のポイントなどを解説します。採用KPIにより進捗や成果を客観的に把握し、戦略的に人材を確保したい方は、ぜひ参考にしてください。
【最新版】IT人材白書2026 を公開!
激化するIT人材の獲得競争を勝ち抜くための「最新データ」がここに。
IT人材白書2026は、貴社の採用戦略をデータで裏付け加速させるためのレポートです。IT人材採用のリアルな課題と、成功への具体的なヒントを数字で示します。
・IT系企業は順調、非IT系企業は苦戦傾向。業態で差が出る採用進捗のリアル
・採用手法は「待ち」から「攻め」へ。スカウト媒体や外部サービスの活用が活発に
・求人票やスカウト文の作成などにおいて生成AIの活用が広がる
・20代の正社員IT人材の約半数が「静かな退職」状態にある
最新のIT人材採用市場について詳しく知りたい方は以下より無料でダウンロードし、採用活動にお役立てください。
「レバテック」は業界歴20年のIT人材専門エージェントです。中途採用、フリーランス(業務委託)、派遣、新卒採用など、採用ニーズに合わせて70万人を超える登録者の中から最適な人材をご紹介します。
レバテックについて詳しく知りたい方は、こちらからサービス資料をダウンロードしてください。
目次
採用KPIとは?
採用KPIとは、企業の採用活動における、成果や効率といった目標の達成度合いを測定するための指標です。KPIは、「Key Performance Indicator(重要業績評価指標)」の略です。
採用KPIの例としては、以下のような項目が挙げられます。
- 応募者数
- 選考通過人数・率
- 内定数・率
- 内定辞退数・率
- 入社後の定着率(離職率)
- 採用チャネルごとの費用対効果
- 採用コスト
- 採用単価
- 入社配属後の評価
採用KPIには、決められた項目や指標がありません。このため、自社の採用目標や課題に合わせて、項目と指標を設定します。
採用KPIとKGIとの違い
採用KPIを設定する際、よく間違えられやすい用語として「KGI」があります。KGIは「Key Goal Indicator(重要目標達成指標)」の略で、組織や事業が最終的に達成すべき目標を数値化したものです。採用活動における最終目標としては、「今年度はエンジニアを20名採用する」といった具体的な採用人数が該当します。
つまり、採用KPIは、KGI(最終目標)を達成するための中間指標と言えます。KGIが目的地だとすれば、KPIは目的地に至るまでの道程で確認すべきチェックポイントのようなものでしょう。「応募者数」「一次選考通過率」「内定承諾率」などは、採用プロセスの各段階における達成度を測る指標となるのです。
採用活動にKPIを設定する3つのメリット
採用活動においてKPIを設定すると、以下のような3つのメリットが得られます。
1. 採用フローごとの進捗状況を確認できる
KPIを設定することで、採用フローの各段階における進捗状況を確認できます。数値により状況を可視化できるため、計画通りに進んでいるのか、遅れが生じているのかを早期に気づくことが可能です。
たとえば、「6月末までに応募者を30名集める」というKPIを設定し、5月末時点で応募者数が目標値を大きく下回っている場合、目標達成が難しいと予測できます。数値を確認後、すぐに対策を講じることで、軌道修正が可能となるのです。
2. 採用活動における課題を把握できる
KPIの達成状況により、採用活動のどこに問題が生じているかを把握できます。採用フローの各段階(応募、書類選考、一次面接など)ごとに数値で達成状況を確認できるため、感覚や印象によるものではない客観的な課題把握が可能となるのです。
たとえば、応募者数が目標値を大幅に下回っている場合、採用チャネルの選択が適切でない、求人内容から魅力が伝わっていないなどの可能性が考えられます。また、内定承諾率が低い場合は、自社よりも待遇の良い企業からの内定や、選考中に自社と合わないと感じる要素があったなど、自社への満足度に問題があるかもしれません。
このように、採用フローごとに状況を把握できるため、早期に適切な改善策を立てることが可能になるのです。
3. 目標を共有することで組織の連携を強化できる
採用KPIを社内で共有することにより、組織の連携が強化できることもメリットです。採用活動は、採用担当者だけでなく、各事業部や経営層も含めた社員全員が一体となって取り組む必要があります。採用KPIは採用フローごとに設定するため、KPIを社内に共有することで、各部門の役割が明確になり、協力体制を構築しやすくなるのです。
たとえば、面接官の増員やスキル強化、社員紹介による採用強化といった対策を講じる際に、KPIの状況を共有することで、各部門や社員の理解と協力を得やすくなります。また、社内会議で採用活動の進捗や成果を報告する際、数値データに基づいた報告ができるため、社内の採用活動への理解と支援を促進する効果も期待できるでしょう。
エンジニア採用、なぜうまくいかない?激化する市場で”求める人材を確保するコツ”を紹介。
⇒「求める人材を確保するコツ」をダウンロードする
【4STEP】採用KPIの具体的な設定手順
次に、採用KPIを設定する手順について、4つのステップに沿って解説します。
STEP1:最終目標となるKGIを設定する
まずは、最終的な目標(KGI)を明確に設定しましょう。最初にKGIを設定することで、最終目標の達成に向けた中間目標(KPI)を設定することが可能になります。
KGIは「最終的な採用人数」を設定するのが一般的ですが、「人材の質」も含めて考えることが重要です。たとえば、新規事業の立ち上げに必要な人材数や、既存事業の拡大に伴う増員計画、プロジェクトに必要なスキルなども踏まえて採用人数を設定しましょう。
経営陣や事業部門のリーダーとも密に連携しながら、組織のニーズを正確に把握したうえで決めることが大切です。
STEP2:採用チャネルごとの採用フローを作成する
KGIが決まったら、次は利用する採用チャネルを決め、各チャネルごとに具体的な採用フローを作成します。採用チャネルとは、求人広告や人材紹介会社、ダイレクトリクルーティング、リファラル採用など、人材を集める方法のことです。
採用フローは、以下の流れに沿って作成します。
1.利用する採用チャネルを決める
採用チャネルにはそれぞれ特徴があるため、KGIを達成するためにはどの採用チャネルが適しているのかを見極めましょう。たとえば、中途採用で即戦力人材を採用したい場合は、人材紹介会社から採用要件に合う人材を紹介してもらうのがおすすめです。リファラル採用で社員から優秀な知人を紹介してもらうのも選択肢として挙げられます。
2.採用チャネル別の採用フローを作成する
次に、採用チャネルごとの採用フローを作成します。採用チャネルによって、候補者の集め方や内定までのフローが異なるため、それぞれのチャネルに適したフローを作成することが大切です。
たとえば、求人広告を利用する場合は、応募から書類選考、面接、内定、内定承諾までのフローを設定します。

また、採用ターゲットに適したフローを設定することも大切です。たとえば、求める採用要件に必須スキルがある場合は、スキルテストを実施したり実務経験を重視した選考を行ったりするなど、必要に応じて適切なフローを設定しましょう。
採用チャネルの種類やそれぞれのメリットなどについて詳しく知りたい方は、ぜひこちらの記事も参考にしてください。
採用チャネルを徹底解説!種類やメリット・デメリット、選び方を紹介
STEP3:採用フローごとに歩留まり率の目安を設定する
採用フローを作成したら、各フローごとの歩留まり率の目安を設定します。歩留まり率とは、ある選考段階から次の段階に進む人数の割合(通過率)のことです。
歩留まり率を確認することで、採用活動の成功率を各フローごとに把握できるため、KPIを設定する上で重要な指標となります。採用活動においては、「書類選考通過率」「面接通過率」「内定率」「内定承諾率」などの項目があり、KPIの項目と一部同一であるともいえるでしょう。
歩留まり率は、「通過数÷対象数×100」の計算式で求められます。自社における過去の採用データをもとに設定しましょう。たとえば、応募者数20名のうち、10名が書類選考を通過した場合は、歩留まり率は50%となります。もし過去の採用データがない場合は、業界の平均値などを参考にすると良いでしょう。
また、実際の採用活動では、これらの歩留まり率を定期的に測定し、目標値との乖離があればすぐに対応策を検討することが大切です。一例として、書類選考通過率が設定値より大幅に低い場合、募集要項と応募者のミスマッチが考えられるため、募集内容や掲載媒体の見直しが必要かもしれません。
歩留まり率については、下記記事でも詳しく解説しています。歩留まり率について知りたい方は、ぜひこちらもご活用ください。
採用の歩留まりとは?低下する原因や改善策を解説
STEP4:各採用フローにKPIツリーを設定する
最後のステップでは、各採用フローにKPIツリーを設定します。KPIツリーは、KGI(最終目標)を達成するためのKPI(中間目標)を採用チャネルごとに整理したものです。設定した採用KPIツリーに沿った採用業務を進めていくことで、目標達成に向けた効率的な採用活動が可能となります。
以下、KPIツリーの設定方法を解説します。
1.採用チャネルごとの採用人数比率を決める
KPIツリーは、STEP1で設定したKGIから逆算して設定します。まずは、KGIで設定した総採用人数に対し、採用チャネルごとの採用人数比率を決めましょう。
たとえば、KGIを「今年度はWebエンジニアを10名採用する」とし、求人広告からは10%の人数を採用することに決めたとします。この場合、求人広告におけるKPIは「採用人数1名=内定承諾者数1名」となります。
2.各採用フローに歩留まり率を当てはめる
続いて、STEP2とSTEP3で設定した採用チャネルごとの採用フローと歩留まり率を当てはめます。すると、以下のようなKPIツリーが作成できます。

KPIツリーを作成することで、各段階での目標と成果が明確になり、進捗管理がしやすくなるでしょう。また、どの段階でボトルネックが生じているかも把握しやすくなるため、迅速な改善策の実施が可能となるのです。

採用KPIを設定・運用する際のポイント
次に、採用KPIを設定・運用する際の重要なポイントを5つ解説します。
達成すべき期限を明確に定める
KPIを設定する際は、「何を」「どれだけ」という数値目標だけでなく、「いつまでに」達成するのかという期限を定めることが大切です。期限を設けることで、進捗状況の評価がしやすくなり、「このペースでは間に合わない」といった問題を早期に発見できます。これにより、迅速な軌道修正や追加施策の検討が可能となり、計画的な採用活動を実現できるのです。
年間目標だけでなく、四半期、月次、週次といった短いスパンでの期限を設定しましょう。たとえば、「〇月までに応募者300名」「〇月中に最終面接を10件実施」といった具体的な期限付きのKPIを定めることで、チーム全体の行動が促進されます。期限を設定する際は、過去の採用実績や市場環境を参考にして、現実的な目標を立てることが大切です。
KPIの進捗をリアルタイムで管理・共有する
設定したKPIの進捗状況はリアルタイムで管理し、関係者間で共有することが大切です。最新の状態に更新し、いつでも関係者が確認できる環境にしておきましょう。数値の更新や進捗の共有が遅れると、問題発見が遅れ、対策が後手に回るおそれがあります。
また、進捗情報は人事部門だけでなく、採用に関わる全ての部門と共有しましょう。これにより組織全体で目標への現状認識が統一され、必要な協力も得やすくなります。
リアルタイムでの管理・共有は、問題の早期発見だけでなく、チームの一体感を醸成し、全員が当事者意識を持って採用活動に取り組むための基盤となるのです。
進捗率が悪いKPIは原因を特定して対策を考える
進捗率が悪いKPIがあったら、すぐに原因の分析を行い、対策を考えましょう。KPIを設定する目的は、数値によるデータで計画と実績の差を客観的に把握し、状況に応じて対策をとれるようにすることです。このため、進捗の遅れを発見した時点で原因特定を行い、具体的な対策を講じることが重要です。
たとえば、特定の採用チャネルによる応募者数の進捗が悪ければ、媒体の見直しや掲載内容の修正を検討する必要があるでしょう。
このように、常にKPIの進捗を把握し、すぐに原因特定と対策を行うことで、採用における最終目標の達成につなげることができるのです。そして、対策実施後も継続的に効果測定を行い、PDCAサイクルを回しましょう。
KPIの数値を追うこと自体が目的にならないようにする
KPIはあくまでも目標を達成するための手段であり、数値を追うこと自体が目的になってはいけません。数値達成のために質を犠牲にするような行動は避けましょう。
よくある失敗例として、「応募者数」というKPIを達成するために、求める人材像と合わない層にまで募集を広げてしまうケースがあります。この結果、自社にマッチしない人材からの応募が増えてしまい、かえって採用効率が悪化してしまいます。
このような事態を避けるためには、常に「このKPIは何のために設定したのか?」という本来の目標(KGI)に立ち返ることが重要です。採用におけるKGIは、単なる人数の確保ではなく、「自社に貢献できる優秀な人材を採用すること」であるはずです。採用者数だけでなく、「採用後の定着率」や「入社後の活躍」といったKPIもバランス良く見ることで、本質を見失わない採用活動が可能になります。
必要に応じてKPIを見直す
設定したKPIが現状に合わなくなった場合は、柔軟に見直すことも大切です。ビジネス環境や採用市場の変化により、当初設定したKPIが適切でなくなることもあるためです。KPIは、半年や四半期ごとなど定期的に妥当性を検証し、必要に応じて目標値や測定項目を調整しましょう。
たとえば、採用市場が急速に厳しくなった場合は、応募者数の目標を現実的な数値に修正します。事業戦略の変更に伴い求める人材像が変わった場合は、KPI全体の見直しをする必要があります。
市場や自社の状況が変わったにもかかわらず、古いKPIに固執していては、現実的でない目標を追い続けることになります。この結果、目標が高すぎることによるモチベーションの低下や目標の未達成につながるかもしれません。定期的にKPIの妥当性を評価し、必要であればKGIや採用戦略そのものから見直すなど、柔軟に対応しましょう。
エンジニア採用、なぜうまくいかない?激化する市場で”求める人材を確保するコツ”を紹介。
⇒「求める人材を確保するコツ」をダウンロードする
採用KPIの設定に関するよくある質問
最後に、採用KPIに関してよく寄せられる質問と回答を紹介します。
Q.採用KPIはどんな項目を設定すべきですか?
KPIには決まった項目が存在しません。まずは自社が抱える採用課題を明確にし、その上で課題解決に直結する項目をKPIとして設定することが大切です。
以下、一般的に設定されることが多いKPIを観点別に紹介します。自社の目的はどのプロセスにあるのかを考えながら、適切な項目を選んでみてください。

Q.採用KPIの計算方法を教えてください
KPIにはさまざまな項目があるため、項目によって計算方法も異なります。このため、多くの企業で設定されている指標の一部について、計算方法を紹介します。
選考通過率
各選考フェーズで、どれだけの候補者が次のステップに進んだかを示す指標です。たとえば、書類選考の通過率が極端に低い場合、母集団の質と求人要件が合っていない可能性があります。
- 計算式: 選考通過率(%)=当該選考の通過者数÷当該選考の参加者数×100
- 例: 100名の応募があり、書類選考を通過したのが20名だった場合
→20÷100×100=20%
内定承諾率
内定を出した候補者のうち、どれだけの人が入社を承諾してくれたかを示す指標です。この数値が低い場合、選考体験や待遇、企業の魅力などに課題がある可能性が考えられます。
- 計算式: 内定承諾率(%)=内定承諾者数÷内定者数×100
- 例: 内定者10名に対し7名が承諾した場合
→7÷10×100=70%
採用単価
1人を採用するために、どれだけの費用がかかったかを示す指標です。コスト効率を測る上で重要になります。
- 計算式: 採用単価=採用活動にかかった総コスト÷採用決定人数
- 例: 求人広告費や人材紹介手数料などの総コストが300万円で、5名採用した場合
→300万円÷5人=60万円
採用コストや採用単価について知りたい方は、ぜひこちらの記事も参考にしてください。削減のためのポイントなども解説しています。
採用コストの計算方法とは?平均コストや削減のポイントも紹介