最新記事公開時にプッシュ通知します
なぜ「プレイヤーの自分」と決別できたのか。「技術に詳しい経営者」が、本当にやるべきこととは|カミナシCTO原トリ
2025年4月22日
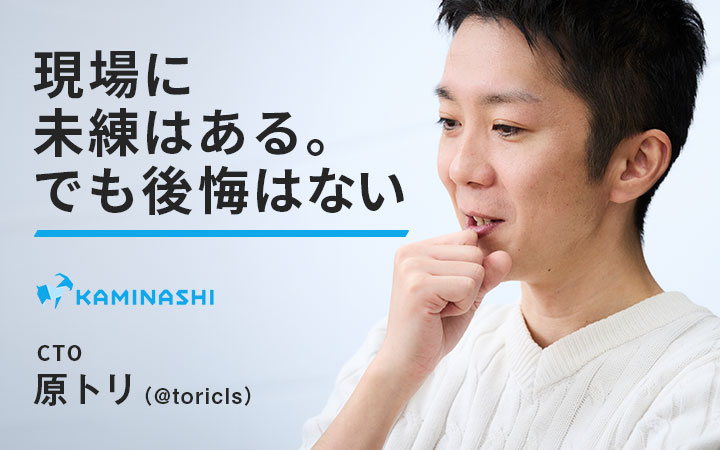

株式会社カミナシ 取締役CTO
原トリ
大学を卒業後、ERPパッケージベンダーのR&Dチームにてソフトウェアエンジニアとして設計・開発に従事。クラウドを前提としたSI+MSP企業で設計・開発・運用業務を経験し、2018年Amazon Web Services入社。AWSコンテナサービスを中心とした技術領域における顧客への技術支援や普及活動をリードし、プロダクトチームの一員としてサービスの改良に務めた。2022年4月カミナシ入社、2022年7月よりCTOに就任。
X(Twitter)
ノンデスクワーカーのDXプラットフォームSaaSを開発・提供するカミナシ。2024年8月~2025年2月の間に3つの新規プロダクトをリリースし、2025年1月には元DMM社のpospomeさんがVPoEになるなど、明るいニュースが続いています。
CTOの原トリさんは2024年1月の取材で、「現場から完全には離れられなくて、長期的な課題にじっくり取り組む時間を確保できない」と話していました。権限委譲がうまく進まなかったこともあり、「離れなくては」とわかっていても、行動に移すのは難しかったそう。
しかし今は現場から徐々に離れ、「技術に詳しい経営者」としてのCTOになってきていると語ります。
プロダクト開発の現場が大好きで、カミナシに入社するまでは、マネジメントラインに進まず「プレイヤー」としてキャリアを重ねてきた原トリさん。なぜ「現場」に未練を残しながらも、離れることができたのか。「CTOの役割」と向き合い続けてきた道のりを、詳しく聞きました。
権限委譲と、「経営者」としての成長
——CTO就任から2年半が経ちました。最近は、どんな変化がありましたか?
原トリ:そうですね。僕自身の変化として真っ先に思いつくのは、開発チームやプロダクトの状況について漏れなく情報を取りにいくのをやめたことです。「諦めた」といったほうが適切かもしれません。

——「諦めた」といいますと‥?
原トリ:以前は、メンバーがSlackで会話している内容にくまなく目を通して、チームやメンバーの状況を把握していました。
ただ、カミナシのエンジニアは、この1年半でほぼ倍の人数になっています。今後、例えばエンジニアだけで100名を越えるような組織や事業規模になってくると、自分1人で完全にフォローするのは不可能でしょう。前回の取材で「未来のことを考える時間が足りない」とお話したと思いますが、時間が足りない原因の一つは、現場に意識が向き過ぎていたせいだったようです。
それに、現場を任せられる優秀なエンジニアリングマネージャーが社内から生まれてきたり、外部から採用したりということもできました。2025年の1月には、元DMMのpospomeさんがVPoEに就任しました。マネジメントに挑戦したいと考えるメンバーも、これまで以上に増えています。だからこそ、「彼らとの会話やレポーティングから得られる情報をもとに、正しい意思決定をするにはどうすればいいか」というマインドに切り替えられたんだと思います。
マネージャー層が固まりはじめてまだ日が浅いので万全とまでは言えませんが、近い将来、僕が持っているボールや権限の多くを現場に委譲できるでしょう。
——権限委譲のめどが立って、現場から離れられるようになってきたのですね。ほかにはどんな変化がありましたか?
原トリ:経営という観点でいうと、24年4月に現CFOの吉田(純平)が入社してくれたのは、カミナシの経営陣全員に大きな変化をもたらしてくれたように思います。
僕を含め、CEOの諸岡(裕人)、COOの河内(佑介)も、他社での経営経験がなくカミナシではじめて経営に携わりました。一方吉田は、証券アナリストとして10年以上の深い経験を持つだけでなく、数々のIPOの支援をしてきて、前職ではスタートアップのCFOも務めた人物です。手探りで経営に取り組んできた我々よりも、経営の経験値を持っています。
経営会議などでの彼の言動から、経営的な視点や動きを学ばせてもらっています。おそらく諸岡も河内も、吉田との関わりを通して、経営者としての視座を引き上げてもらっていると感じているのではないでしょうか。
——経営陣には具体的に、どんな変化があったのでしょうか。
原トリ:分かりやすい話でいうと、たとえば経営レベルの重要な課題が発見されたとき「誰がそのボールに責任を持ち、いつまでに対処するか」を、これまで以上にシステマティックに管理していけるようになりました。
我々はスタートアップなので、取締役といえども執行役として務めが多分にあります。以前は、足もとの業務に追われてしまった結果、誰がボールを持っているのか曖昧なまま、忙しさにかまけて課題を放置してしまったり、対処が後手に回ってしまったりすることがありました。でも吉田が経営陣に加わってからは、アクションプランやプロセス管理が仕組み化され、会社として重要なことの取りこぼしが格段に減ったのです。そのおかげで、経営会議での議論も深まった気がします。
——ミドルマネジメント層が厚くなったのに加え、経営経験のある吉田さんが経営陣に加わった結果、原さんと現場の距離感が変化した訳ですね。
原トリ:そうですね。このふたつの変化をきっかけとして、視座が高まり、視野が広がって「経営者としての自分の務めは何か」という重要な問いに気づけるようになりました。
だから現場の状況をつぶさに把握することを、諦められたんだと思います。
現場への未練はある。でも「大きな賭け」を成功させたい
——「諦める」という言葉選びが印象的です。やはり現場と距離ができることに、ためらいや未練があるのでしょうか?
原トリ:それはありますよ(笑)。長年エンジニアとして、仲間たちとワイワイいいながら技術について議論したり、手を動かしていたりしていたわけですから。こうした時間がなくなるとなれば、ちょっと残念な気持ちにもなりますし、未練がないといったらウソになります。プロダクトに一番近い場所で仕事するのは、やっぱり楽しいですからね。
——エンジニアとしての本音とCTOとしての職務。どう折り合いをつけますか?
原トリ:CTOになってほぼ3年が経ち、プロダクトはカミナシのビジョンやミッションを実現するための大切な手段のひとつだと、以前に増して思えるようになりました。エンジニア時代から「技術はお客様に価値を届けるための手段」だと思っていたので、意識が大きく変わったわけではないのですが、特にこの1年でより広い視野から経営というものを捉え、焦点がはっきりした感覚があります。
僕はテックリードではなく、あくまでもCTOです。SaaS企業の経営陣の一角を担う以上、経営判断にテクノロジーとエンジニアリングの視点を採り入れ、その時点での最良の意思決定に到達できるようにすることが、僕の務めです。そして、CTOが現場に下りていかなくても、よりよいプロダクトを継続的に生み出せる状態を築くのも、大事な役割のひとつです。
このように明確に考えるようになったから、メンバーや仕事へのアプローチが変わったんだと思います。立場が人をつくるといいますが、CTOどころかマネジメント経験すらなかった僕にとって、大きな変化でした。
というか…カミナシはよく僕にCTOを任せたなあと思うんですよね。

——どういうことですか?
原トリ:僕はカミナシに入社するまで、プレイヤーの経験のみで、マネジメントは全くしたことがない。なんなら、「マネージャーって何のためにいるんだろう」って本気で思っていた。そんな僕がCTO、経営者になるわけですから。
よく考えてみれば僕の入社において、カミナシには「CTOというラベルのついたテックリードとして採用する」という選択肢もあったはずです。でも、僕みたいなマネジメント経験のない人間に、立場を与えて無理やり視座をぐっと上げさせるみたいなアプローチも、業界全体を見れば本当は必要なんだと思います。いい人材を捕まえることが難しいのはどこも一緒ですから。
僕は、SaaSなどソフトウェアテクノロジーで商売をしていて、スケールのために正しい意思決定をしたいなら、技術のことがわかる人が経営メンバーに絶対必要だと考えています。会社のお金が何にどういう割合で投資されているかの全体感が視野に入りにくい、テックリードとしてのCTOと、そこまで視界を持つ経営者としてのCTOは、意思決定の仕方も役割も全く違います。そうした人の必要性を認知できていない会社も多々あるはずで、だからこそ技術バックグラウンドの経営者が増えていかないんだろうと思うんです。
といっても当時のカミナシにそういう意図があったのかも、カミナシが僕に賭けてくれて成功しているのかもわかりません。賭けの勝敗については、僕はまだ判断がつかないし、僕だけで判断できることではないと思っています。
システムも組織も、密結合にはさせない
——いま一番苦労しているのは、どんなことですか?
原トリ:自分の考えを言語化して、関係者に伝えるのには未だに苦戦しています。誰もが納得できる言葉でまとめるのは、やっぱり難しい。
いちプレイヤーなら仮に言語化レベルが不足していたとしても、モックアップひとつ見せれば伝わることもあるので、さして問題にはならない場合もあるでしょう。しかし、CTOとして求められるレベルの抽象度で経営や組織を動かすとなれば、そうもいっていられません。意思が伝わらなければ状況を変えられませんし、誤った伝わり方をすれば組織をミスリードしかねないからです。
実は今朝も、今後の重要な方針についてSlackでメンバーに共有しました。うまく伝わっているといいんですが…。

——差し支えなければ教えてください。どんな内容だったんでしょうか?
原トリ:マルチプロダクト化するまでのカミナシは、1プロダクト1チーム体制で開発を進めてきました。しかし今後は、複数プロダクト・複数チーム体制となり、たとえば機能連携などチームをまたいで協働する機会も増えていきます。
このような状況で各プロダクトがソフトウェアシステムとして連携しようとするとき、その具体的な実現方法が重要になります。なぜなら、その方法はプロダクト自体だけでなく、未来の組織改編の容易性にも大きな影響を与えるからです。組織の形がシステムの形に影響することは広く知られていますが、逆にシステムの形も組織の形に影響を与えます。今後カミナシが成長し、プロダクトや組織がスケールする中でも組織の柔軟性を保てるよう、「組織を疎結合に保つための技術的方針」を策定し、開発組織に共有したのです。
今のカミナシでは、「1つのプロダクトに1つのチーム」を基本原則として、各チームが自律的に開発を進めています。複数のプロダクトがリリースされ、それらのシナジーが見えてきた今後は、チームをまたがった技術的な意思決定が行われるようになっていくでしょう。しかし、チーム間の意思決定まで各々が自律分散的に行ってしまうと、局所最適化されたシステムが生まれがちです。その結果、全体感の欠如を招き、システムや組織が継続的に改善していく可能性を失う恐れがあります。
「システムと組織が密結合な状態になって、変えられない」というのは、アジリティが最も重要な特性の一つであるスタートアップにとっては致命傷です。そうならないように、「複数プロダクト間で、一定のレベルを超えた複雑性を持つ技術的連携を考えている場合は、(全体感を持って組織やシステムを見ている)CTOやVPoEを必ず巻き込んでほしい、それ以外は相談しなくていい」と、取り急ぎ伝えたのです。自律性高くスピードを出して開発するために、相談しなくていいラインをまずはクリアにしたかったんですよね。
同じ踊り場でも、1年前より上の階にいたい
——視座が上がったと話していましたが、見る距離感も焦点距離も伸びて、すごく遠くまでピントが合いはじめてるような印象です。
原トリ:以前と比較すれば、そうなっているんでしょうね。現場のメンバーには、「なんか以前とスタンスが違うな」って思われてるかもしれません(苦笑)。
たぶん、カミナシに今いるマネージャー陣もメンバーも、まだまだマネージャーとしての今の僕に満足はしていないだろうなと思うんですよ。CTOになって初めて取り組んだピープルマネジメントですが、自分なりに理論も学びながら考え抜いて実践しているものの、きっと足りていない部分、もっとうまくやれる部分がまだまだたくさんある。僕のマネージャー経験の足りなさは、随所に滲み出ちゃっているだろうなと思います。
ただ経営メンバーを含めたみんなが、僕が足りないところにフィードバックをくれています。フィードバックをもらえるから、僕の成長に期待してくれているんじゃないかなと思える。きっとこれも、いわゆる心理的安全性のひとつの形なのかなと思っています。

——前回の取材では、CTOとして「成長の踊り場」にいると話していました。この感覚は解消されましたか?
原トリ:どうでしょうか。長く同じ仕事をしていると、ちょっと手を抜いても60点ぐらい楽に出せるようになることがありますが、カミナシに入社してから今まで、一度もそういった感覚になったことがありません。
できないことを「捨てる」とか「やらなくていいようにする」のではなくて、できないなりに努力して考えて実践する。結果的には、常にチャレンジできる環境にいるってことなんだと思います。それをみんなが、割と生暖かく見守ってくれているのは、本当にありがたいことだと感じます。
——カミナシのこれからについては、どう見ていますか?
原トリ:将来に向けて、理想的なプロダクト、理想的なエンジニア組織を描き、そこから逆算していま何をしなければならないか、さらにどんなファンクションが必要かまでイメージして形にしていかなければと思っています。
具体的には、誰かが片手間でやっていたり、ムリしてやっていたりすることを洗い出して組織のなかにきちんと位置づけて機能させたり、採用や評価、組織体制や権限委譲の指針についてももっと適切な言葉でまとめなければと思っています。
目の前の課題にリアクティブに反応し続けるだけでは、おそらく出せるインパクトは最小のサイズ。インパクトを最大化するためにも常に何年も先の青写真を持ち続けられるくらいの状態を継続していかなければと思っています。
——すでに新しい展望が見えているのでは?
原トリ:いえ、全然(笑)。「これをやれたら強くなるんじゃないか?」っていう感じかな。本当に強くなるかはやってみないとわかんないですよ。でも、いけそうだと思える。
これからも、僕らを取り巻く環境も、僕ら自身も刻々と変化し続けるはずですから、多分この先もずっと模索し続けるんじゃないかと思います。潮目が変わったときすぐ対応できるよう、1年前よりひとつでも上の階の踊り場にいられたらいいですね。何が起こってもいいように、常に準備だけは整えておきたいと思っています。

取材・執筆:武田 敏則(グレタケ)
編集:光松 瞳
撮影:赤松 洋太
関連記事

【カミナシ原トリ×AlphaDrive赤澤】「CTOになる」という選択がエンジニアとしてのキャリアにもたらしたもの

【カミナシ原トリ×AlphaDrive赤澤】フェアなエンジニアリング組織をつくるために「短期的な非合理を取っていく」CTOの度量

「初めてぶつかる課題ばかりで正直悩んでます」CTO2年生の原トリが語る、成長の踊り場
人気記事





