最新記事公開時にプッシュ通知します
スマートグラス普及のカギは“大スター”の登場? 日本市場で注目・XREAL社の現状分析
2025年11月10日
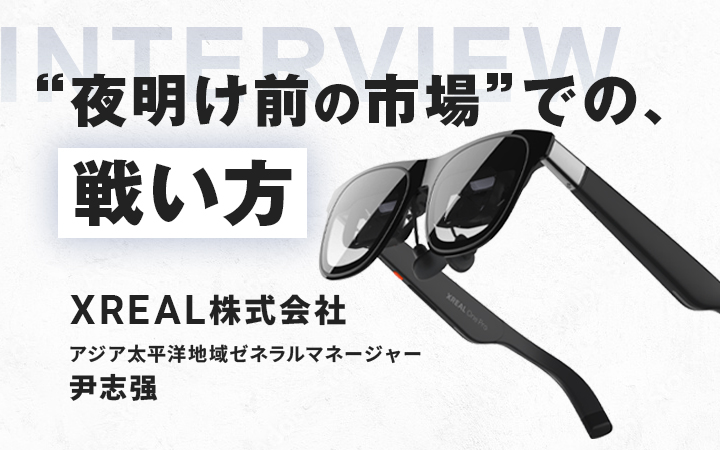

XREAL株式会社 アジア太平洋地域ゼネラルマネージャー
尹志強(イン・ズーチャン)
Huaweiにて約7年間、ドイツ・ロシア・トルコをはじめとする複数の国・地域において、マーケティングマネージャーとして現地市場戦略の立案およびブランド構築を担当。各地域での事業拡大に貢献。その後、新エネルギー車メーカーLi Autoにて、グローバル戦略部門に所属し、約2年間にわたり新興市場における事業戦略の企画・実行に携わる。2022年よりXREALに参画。現在は海外マーケティングディレクター、日本法人ゼネラルマネージャー、ならびにアジア太平洋地域統括責任者(GM)として、ARグラス事業の国際展開および地域戦略の策定・実行を主導。
公式サイト
サングラスのようにかけ、視界にスマートフォンの通知表示や映画鑑賞ができたり、場合によっては空間コンピューティングもできたりする「スマートグラス」。未来的なデバイスとして多くの人の関心を集める一方で、現状ではまだ、スマートフォンやスマートウォッチのように誰もが使うデバイスには至ってはいません。一体、なぜなのでしょうか?
「この業界はまだまだ初期段階です。現状、中心ユーザーはテクノロジー愛好家、いわゆるギークユーザーにとどまります」
素朴な疑問に対しこう話すのは、「AR(拡張現実)グラス」で世界でも高いシェアを誇る中国XREAL社・尹志強さん(アジア太平洋地域ゼネラルマネージャー)。市場を牽引する同社の目には、スマートグラス普及の「壁」と、その先の未来はどう映っているのでしょうか?
スマートグラスが完全普及を遂げるために、まだ足りないものとは何か。率直な分析を行う尹さんの口から語られたのは、巨大プレイヤーが存在しない市場で戦うスタートアップの、極めて力強い「生存戦略」でした。
スマートグラス市場に「iPhoneタイム」をもたらすために
――まず現状のスマートグラスの普及状況を、どのように見ていますか。
尹:まずお伝えをしておきたいのは、「スマートグラス」市場は、まだ本当に初期の段階にあるということです。
そもそも「スマートグラス」というワードの定義すらもまだ定まっていません。各社が、異なるアプローチで手探りのように開発を行っているためです。私たちが主に開発してきた、視界に映像を投影する「ARグラス」製品を含む広い概念としてスマートグラスという言葉が使われることもあれば、AIアシスタント機能などが搭載されたものを「AIグラス」や「スマートグラス」と呼ぶこともあります。
ただ将来的には、これらは現在のスマートフォンのように、仮想空間へのインターフェースとなるひとつの製品カテゴリーに収束していくと考えています。

――概念自体がまだ過渡期にあるのですね。その上で、あえて現在の市場規模を数字で示すとすれば、どの程度になるのでしょうか。
尹:調査会社「Wellsenn XR」のデータを見ながら分析する限りでは、ARグラスの世界市場は、ビジネス向けと消費者向けを合わせても、現状おそらく年間50万台です。純粋に消費者向けに限れば、40万台。我々XREALは、その中で半分以上のシェアを有しています。
日本市場に限ると、ARグラスの年間の市場規模は約4万台強のようです。XREALのシェアは、そのうち80%を超えています。
AIグラスでも、各国の競合各社が力を入れています。
ただ私自身の見立てでは、消費者が実際に購入した分に限ると、世界中のARやAIグラスも含めた広義の「スマートグラス」市場全体の売上はまだ年間200万台ほどではないかと考えています。本当の意味で商業的に成功した事例はまだない、というのが私の認識です。
――多くの企業が参入している中で、なぜまだ「商業的な成功」と呼べる段階にまで至っていないのでしょうか?
尹:どんな新しいテクノロジー製品だろうと、最初は「市場への普及と教育」という壁に直面するからです。つまり、製品の価値が十分に伝わっておらず、市場の理解も得られない。かつてのスマートフォンも、最初期はそうでした。普及のためには、技術はもちろんとして、サプライチェーンや具体的なユースケースが十分に成熟する必要があります。
そうした製品を最初に受け入れてくれるのは、やはり情報感度が高いテクノロジー愛好家、「ギーク」層になります。彼らは製品に関する情報にいち早く触れ、体験や機能における不完全さも受け入れてくれる傾向があります。そのため、普及初期は必ずこの層のユーザーに向けて市場への情報発信や販売活動を展開することになります。
しかし、市場規模の拡大とともに、徐々に一般ユーザー向けの製品教育やコミュニケーション、情報発信も展開していかなければなりません。ですので、現在のスマートグラス業界は、ギークユーザーから一般大衆ユーザーへと、この製品をどうにか広めようとしている段階にあります。
――世界的に見ても、まだ本格的な普及には至っておらず、各社が実験を繰り返している段階なのですね。しかし、スマートフォンでいうと、こちらは登場して間もなく爆発的な普及を見せた印象があります。スマートグラス市場の場合、なぜまだギーク層にとどまっているのでしょうか?
尹:それは、市場に「iPhoneタイム」が到来していないからでしょう。
――iPhoneタイム、ですか?
尹:ええ。iPhoneタイムは、中国国内のビジネス関係者の間でよく使われる言葉です。「新しいガジェット」という極めてニッチなマーケットの範囲を、一気にマス市場へと変える、決定的な製品やプレイヤーが登場する瞬間を指します。スマートフォンの場合、iPhoneのリリースがまさにそうでした。
スマートウォッチも同様でした。2015年に「Apple Watch」が登場する前、世界のスマートウォッチ市場は年間100万台にも満たない小さなものだった。しかし、初代Apple Watchが発売されると、市場は一気に2000万台規模へと拡大し、そのうちの半分以上をApple一社が占めました。Apple社というスタープレイヤーが、その高い製品力で市場を創造した典型的な例です。
――確かに、近年はApple社が、新しいガジェットの歴史を紡いできた側面もありますね。
尹:しかし、スマートグラスの市場では、「iPhoneタイム」はまだ起きていない。
市場は私たちのようなスタートアップが中心となっていますが、いずれも製品力においてブレークスルーを実現できておらず、市場全体を牽引するほどのパワフルなプレイヤーが存在しません。これが、現在スマートグラスの普及がギーク層にとどまっている最大の理由だと考えています。
XREALが日本市場で存在感を示す背景と「ユニークな市場特性」
――スタープレイヤーが不在で、いわば群雄割拠の状況にある中、XREAL社はなぜ日本市場で大きなシェアを獲得できたのでしょうか?
尹:各国の市場特性の違いを理解した上で、日本市場にマッチした戦略をとれたことが大きいと考えています。特に日本の市場は、中国やアメリカとは全く異なる、非常にユニークな構造をしています。
まず中国ではTikTokや小紅書(RED)といった新しいソーシャルメディアが非常に発達しており、無数のインフルエンサーが情報を発信しています。情報伝達の形はいわば「分散的」であり、商品販促を行う際は、「特定のメディアを押さえればよい」わけではありません。マーケティング戦略としては、多様なユーザー層や利用シーンに合わせた大量のコンテンツを制作し、AIのアルゴリズムを通じて最適なターゲットに届ける、というアプローチが主流になります。
次にアメリカは、宗教、人種、民族、所得階層が非常に多様です。人々が見るメディアも、バラバラといえます。特定の政治思想を持つ人々が好む伝統的なTVニュースチャンネルもあれば、新興国からの移民が用いるSNSも混在しているため、マーケティングを行うにはターゲットごとに最適なチャネルを選び、複雑なアプローチを組み合わせる必要があります。
――では、日本市場はどのように違うのでしょうか?
尹:我々にとって、日本における情報発信の主戦場は、小紅書やTikTok、BiliBili動画のようなオンラインメディアではありません。
日本はテレビや新聞、雑誌、ラジオといった伝統的なメディアの影響力が依然として強く、また家電量販店のようなオフラインの実店舗での販売が非常に重要な、「集中的」な市場だと捉えています。
――それは、中国国内で蓄積された「分散的」な情報発信のノウハウが通用しにくい、ということですよね。その意味では、商品販促が難しい市場なのでは?
尹:いいえ、逆です。このような状況は、私たちにとって非常に都合がよいのです。なぜならば、アプローチすべき対象が明確だからです。
中国で数百万人のインフルエンサーにリーチするのは大変な労力がかかりますが、日本では影響力のある主要なメディアや販売チャネルの数は限られています。彼らとしっかり関係を築き、製品の価値を伝えれば、情報は効率的に社会へ拡散していきます。拡散における費用対効果は、中国国内で小規模な影響力を持つブロガーを何名も探すよりも、はるかに高い。
私たちはこの日本市場の特性を分析し「伝統的なメディアと連携し、徹底的にローカライズするべきだ」との結論に至りました。そして「完全にローカライズされたチーム」を日本国内で結成しました。このチームは、単なる「日本における販売拠点」ではありません。PR、ソーシャルメディア、イベント企画、デザイナー、さらには物流、製品管理、総務、人事といった全ての機能を持つチームを日本に置いています。こうした試みは、スマートグラス業界ではほとんど行われません。
このローカライズされたチームをもとに、私たちは日本のメディアや販売チャネルと関係を築き、ユーザーの声を直接聞き、製品やサービスに反映させることに注力してきました。回り道したこともありましたが、こうした戦略が、日本で高いシェアを獲得することができた大きな理由だと捉えています。
「生き続けるしかない」という言葉の真意
――日本市場の特性を見極め、徹底したローカライズ戦略で攻略した、と。それでもなお、市場全体としてはまだ「夜明け前」の状況です。今後どのようにこの停滞状況を突破していくのでしょうか?
尹:「とにかく生き続けること」が第一だと考えています。
――生き続ける、ですか。
尹:はい。スマートグラスは全く新しいカテゴリーの製品であり、誰も正解の道筋を知りません。しかし明らかに、現状は市場の爆発期ではありません。そして市場が今後どうなるかは誰にも予測できず、変数が多すぎます。
しかし、会社が市場に適応し、進化し続ける道を模索できなければ、少なくとも、花が咲く「春」の到来を待てないのは確かです。
ですから私たちは、市場が成熟するその日まで、地道にユーザーと対話を重ねて製品を改善し、その価値を伝え続ける必要があります。まずは何よりも、生き続けること。そして静かに花が開くのを待つ。これが私たちの考え方です。
――非常に現実的ながら、力強いお言葉ですね。では、その「生き残り戦略」について具体的に教えていただけますか?
尹:私たちはふたつの製品ラインを同時に進めることで、不確実な市場に対応しようとしています。ひとつは現在のため、もうひとつは未来のためです。
ひとつ目の製品ラインは「Spatial Display」と呼ばれるものです。これは、映画鑑賞やゲーム、オフィスワークといった、既存のユースケースの体験を向上させることに特化しています。例えば、冬の寒い夜に布団から手を出さずに映画を見たり、新幹線や飛行機の中で自分だけの大画面でゲームを楽しんだり。こうした、一般ユーザーの既存のライフスタイルをアップグレードすることで、着実に収益を確保し、会社が「生き残る」ための基盤を作る製品ラインです。
ふたつ目の製品ラインが「Spatial Computing」です。これは未来への投資です。現在、Google社と共同で開発している「Project Aura」などがこれにあたります。AIとの連携や高度なアルゴリズム、ソフトウェアインタラクションといった、次世代のスマートグラスに必要となる技術をここで蓄積していきます。

尹:そして「Spatial Display」で得た収益を、「Spatial Computing」の研究開発に投資していきます。現在を見据えた製品で足場を固めながら、未来に向けた準備も行い、いずれやってくる「春」に備えたいのです。
――そうして最終的に目指すゴールについて教えてください。
尹:我々も含め各社スタートの仕方は違いますが、例えば、映画の『フリー・ガイ』や『レディ・プレイヤー1』のような現実と仮想空間が融合した世界を、この業界にいる誰もが目指しているはずです。その夢は非常に壮大ですが、そこに至る道筋は長く険しい。
そのゴールにたどり着くために、私たちはふたつの短期的・長期的課題に取り組んでいます。まずは、短期的な商業化の課題。つまり、現在の技術や市場環境の中で、ユーザーに最も受け入れられる製品は何かを探り続けることです。そして次に、長期的な「技術蓄積」です。5年後、10年後も会社が競争力を持ち続けるために、どのような能力を今のうちから蓄えておくべきかを見極める。
私個人の役割は、主に前者の「現在」の製品を商業的に成功させることです。しかし会社全体としては、現在と未来のふたつの視点を持ち、着実に一歩ずつ進んでいく方針です。それが、新しい市場を切り拓き、壮大な未来にたどり着くための唯一の方法だと信じています。
取材・執筆:田村 今人
取材協力:王 雨舟
関連記事

分割キーボードの「肩こり改善」効果、医学的に見てどう? “デスクワーク痛”対策の現実解を求めて【フォーカス】

メタバースは今の時代に早すぎるのか? VR法人COOが語る、大「仮想空間」時代到来の条件【フォーカス】

AIに「ゲームの面白さ」を任せるのはまだ早い。それでもスクウェア・エニックスがAI研究を推し進める理由
人気記事





