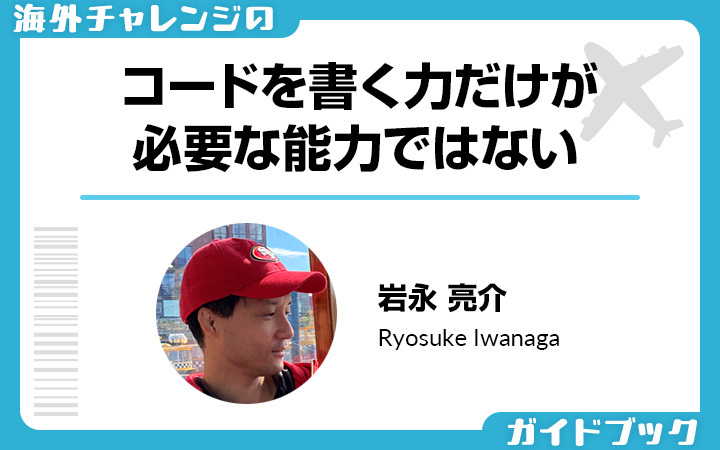最新記事公開時にプッシュ通知します
最初から完ぺきを求める必要はない。10年かけて、英語で生活できるようになった話
2024年6月6日


OpsBR Software Technology Inc. 代表
ソフトウェア業界で15年以上、物理的なデータセンター運用から、世界最大規模の分散システムの運用、多数の業界のお客様のシステム設計支援、フロントエンドからバックエンド、データベース管理者、DevOps やテスト設計・実装、アーキテクチャレビュー、などを経験。特に、運用に関する改善や設計は得意で、OpsBR Software Technology Inc. を立ち上げた。カナダのバンクーバー在住。経歴は、Autify で Staff Software Engineer、Sr. Technical Support Engineer、Amazon で Sr. Systems Development Engineer、Solutions Architect など。
ソフトウェアエンジニアとして海外、特に北米を目指すのであれば、英語で仕事ができるようになることは必須になります。ただ、新卒の頃の僕の英語力は、とても仕事ができるレベルにはなかったです。
第2回では、そこから10年かけて英語を使えるようになった僕の道のりをご紹介しつつ、自分の中で下手なりに上手くいった TIPS も併せて紹介したいと思います。
- 大学受験英語止まりの英語力
- 初めてのアメリカ、絶望を味わう
- 英語のトレーニング
- 丸腰でのアメリカ駐在経験
- Amazon に入って、日本にいながら英語を飛躍的に伸ばせた
- 新卒から7年でとりあえず使える英語になった
- サバイバル TIPS
- 次回に向けて
大学受験英語止まりの英語力
僕は英語とは縁遠い人生を歩んできました。日本語しか使わない環境でずっと育ち、日本の公立中学校に入って初めての英語の授業が始まると、意味の分からない単語や構文をひたすら暗記させられるだけで、非常に嫌いでした。特に5文型を教えられなかったので、文の構成が理解できず例文をただただ暗記するような感覚でした。不規則動詞も意味不明で、全然頭に入りませんでした。
中学がそんな状態だったので、公立高校に入る時にはすっかり英語嫌いになってしまって、なるべく英語の授業が少ないコースを選んでいました。そこの授業で分厚い文法書を渡され5文型を習って、初めて英語を言語として捉えることができるようになりました。夏休みの宿題か何かで、薄い英語の小説を全文和訳するというのをやった記憶があって、あれは結構今でも生きていると思います。気づけば、大学受験では英語は得意科目のひとつになりました。英単語を覚えれば覚えるだけ点があがるので単語帳が手垢で黒くなるまで繰り返し、リスニングはNHKラジオを毎日聴いていくことで聴けるようになってきました。それでも相変わらずテストのための勉強であり、日常で使うことなど考えてはいませんでした。
大学では、また一転して英語の講義は苦痛で全く何も身に着けることができませんでした。他の講義は結局日本語だし、教科書も日本語、後に研究室に入ってからの研究も卒業論文も全部日本語(これは僕が不良学生で英語の文献に手を出せなかったというだけではありますが)という状況において、英語をやる意味が全然わかりませんでした。なので、大学受験時点をピークに英語のスキルは落ちる一方でしたし、もちろん日常で使う機会も全くありませんでした。
そんな状況だったのに、新卒で働き始める頃には日本を出てアメリカに行ってみたいと思ってしまったのです。まず真っ先に英語を何とかしなければいけない、という考えには至りましたが、仕事でもやはり英語を使う機会はなかったのでした。英語で働くためには英語で働いた経験が必要、というデッドロックがそこにはありました。
初めてのアメリカ、絶望を味わう
どうにかそうした状況を変えられないかと、社内の制度を利用してアメリカで開催される技術カンファレンスに参加させてもらうことにしました。当時僕は MySQL のサーバーをたくさん扱う部署にいたので、MySQL Conference という世界で一番の MySQL 情報が集まるカンファレンスに行くことにしました。しかも、カンファレンスの場所はあの有名なシリコンバレー。人生で初めてのアメリカ、そして初めての一人旅に、期待に夢膨らませて参加してきました。
結果は散々なものでした。1週間の滞在の中で、自分の口から英語を発したのはyes/noとかを含めてもおそらく合計3分にも満たない程度。カンファレンス中の食事では隣の人とお喋りする、なんてできるはずもなく、コンビニでジュース1本買うときですら何を言われているのか分からないので、無言でお金出すだけでした。一人で食べる夜のご飯はメニューの数字を言えば出てくるファストフードのみ。カンファレンスのセッション発表はどうにか最低限は聴くことはできたものの、本当に何も喋らずに帰りました。
この体験を経て、ひとまず現状ではまるでダメということが分かったので、今の時点を一旦計測しようと思い TOEIC を受けてみると、595点という結果でした。これが現実でした。とにかく何かできることをしようと思い、まずは iPhone と MacBook の言語設定を英語にしてみました。
英語のトレーニング
英語の基礎力をつけるために、書籍(『英語上達完全マップ』)等を参考にしながら、2つのトレーニングを始めました。ひとつ目は、瞬間英作文というトレーニングです。これは、文法としては初歩(中学レベル)の文章を、瞬時で大量に英作文するというものになります。大学受験時にはかなり高度なところまでやってきた自信があったので、さすがにこれは楽勝だろうと思ったら、is/are を普通に間違えるレベルで、もう全然ダメでした。トレーニング用の本を使って、電車移動などの時間もぶつぶつと続けていったことで、基礎的な瞬発力が鍛えられました。
もうひとつは、音読パッケージというトレーニングで、こちらは英語のスクリプトと音声を使って、効率よく音読を繰り返すというものです。僕は、TED Talks の中で気に入ったものを使って、その英語スクリプトを一語一語調べて文法を理解しながら和訳(これは高校の時の小説和訳と全く同じやり方でした)、音声を聴いてリピーティング、それから音読、さらにシャドーイング、等、これらを手順通りのサイクルとして繰り返しました。とにかく回数をこなす必要があったのですが、興味のある題材を使ったことでモチベーションを維持できました。
それ以外にも、とにかく耳から英語の音に慣れようと思い、仕事の最中でも英語のラジオを流しておいて、意味は分からなくとも英語の音に慣れるようにしました。定番ですが、ドラマの「 Friends」 も字幕付きでみました。それから、僕はスティーブ・ジョブズの “Stay hangry, stay foolish” というスタンフォード大学でのスピーチが本当に大好きで、100回以上は聴きました(今でも時々聴いています)。そのせいで、自分の発音やイントネーションがあのスピーチのジョブズに引きずられてしまった部分があります。あとは、 NFL というアメリカのフットボールリーグの試合を観るのが好きなので、その放送も英語で聴き続けました。
これらのおかげか、TOEIC のスコアは2年間で595->690->750->785 点と上がりました。他に週1くらいでの英会話もやっていましたが、そうこうしているうちに前回のお話にも出たアメリカへの駐在の機会を得ることができました。ずっと勉強してきたとはいえ、これまで英語で仕事をする機会は結局ありませんでした。なので、渡航前に1週間フィリピンの語学学校に行って、英語を特訓してくる予定でした。しかし、ビザ取得のためにパスポートをアメリカ大使館に提出したらしばらく返ってこず、残念ながら特訓はなくなって丸腰でアメリカに渡航することになったのでした。
* 渡航直前に YAPC::Asia 2012 で人生初めて英語でプレゼンをしてみた動画が残っています。当時の英語力はこんなレベルでした。 りーお@DeNA – Perl初心者が作ったサーバ運用ツール
丸腰でのアメリカ駐在経験
サンフランシスコオフィスには、日本からの駐在の人が既に何人かいたのですが、僕が入ったチームは完全に現地メンバーのみで構成されていたので、もちろん仕事の全てがいきなり英語になりました。当然、そんなすぐにコミュニケーションが上手くいくわけもなく、早口で何言っているのかは全然わからないし、自分のこともうまく喋れない。それでも、徐々に英語のリズムがつかめてきて、少なくとも何を話していて肯定的なのか否定的なのか、くらいは分かってくるようになり、そうすれば自分の意見を述べ、ダメなら聞き返してもらうことでコミュニケーションが徐々に成立するようになってきました。ここでの TIPS というか経験の詳細は、記事の後半にてご紹介します。
結局アメリカには 1年ちょっとしかいなかったので、語彙が劇的に増えたわけでも流暢に喋れるようになったわけでもなかったのです。その後日本に帰ってから1年程は全く英語を使う機会はなく過ごしていました。とはいえ、アメリカでの生活経験から、少なくとも「何とかなる」という自信はつきました。
Amazon に入って、日本にいながら英語を飛躍的に伸ばせた
次の大きな転機は Amazon に入社したことでした。入社早々に社内のグローバルカンファレンスがあってアメリカに出張したのですが、たった1年でまるでダメになっていました。日本での仕事はやっぱり日本語ばかりなので、これではダメだなと思い、自分から英語での仕事の機会を取りに行くことにしました。幸いグローバルに展開している会社なので、社内で何かしようと思えば自然と英語を使うことになります。海外のメンバーと関わる機会には積極的に手を挙げていき、また AWS が英語で発信する情報を日本のお客さんにタイムリーに届けるために、かなりの量とスピードで和訳も担当しました。社内のカンファレンスでは今度こそちゃんと英語で人と喋って、何なら発表も結構な回数やりました。
中でも、ある程度英語に自信がついたところから、レベルを飛躍的に引き上げてくれたと思っているのが、逐次通訳の経験でした。AWS のサービス開発チームが来日した時に、日本側のお客さんと双方向で言語が通じないことが多かったです。であれば、技術的に詳しい人間が通訳してしまった方が早いということで、ミーティングや講演で逐次通訳を何度も行いました。こういう状況での逐次通訳の最大のメリットは、話す内容自体の理解にほぼ頭を使う必要がなく、その分の脳みそを言語の変換にまわすことができることです。サービスチームが話す内容は既に知っているし、お客さんから出てくる要望や課題も普段から接しているので大体把握しています。なので、会話の内容自体は予測可能だったり容易に理解できるので、自分は双方向の言語の翻訳に徹することができました。瞬発力を鍛えるのにはうってつけだと思います。
これが入って1年くらいの成果で、自分でもびっくりでした。2年目以降は、特に技術的に詳しくない領域の通訳もやったり、海外カンファレンスに参加したついでに本社に寄って短いミーティングで必要な情報のやり取りをしてきたりしていました。また、英語のブログも書いたり、英語の発表も社内外でやったり、英語のテレカンもやったり、と拠点は日本でしたがグングンと英語スキルを伸ばすことができました。
新卒から7年でとりあえず使える英語になった
ここまでを振り返ると、まず大学受験勉強で身に着けた基礎力は大いに役立ったと思います。特に基本的な文法、ある程度の語彙力があったおかげで、トレーニングでは瞬発力と耳を慣らすことにリソースを割くことができました。そうして最低限は聴けるようになったことで、最初のカンファレンスでは絶望しつつも最低限は聴くことはできましたし、アメリカ駐在中も聴くことはできるので何とか次につなげることができました。そこから飛躍的に伸ばせたのは通訳含めた仕事での実体験が非常に大きくて、瞬発力を一気に引き上げることができました。
前回書いたように並行してインターナルトランスファーの面接を受け続けていましたが、それももちろん英語でやるので、英語ができるようになってくることでやりやすくなっていきました(結局落ちまくりましたが、それは技術力の問題でした)。最終的にカナダのチームとの面接を終えオファーをもらった後は、英語に関して何か言われるということは全くありませんでした。そうして完全に英語で仕事をする環境に改めて身を置いて、はや5年が過ぎました。どっぷりと英語のみの環境で過ごすことで、もちろん更に英語のスキルは上げられて、会議の進行役からドキュメントを書きまくって重要な提案を粘り強く交渉して通したりと、仕事する上で特に英語で困ることはなくなりました。今ではむしろ日本語の方がまどろっこしく感じることもあります。
なお参考までに、新卒から10年経過してカナダの永住権を取る際に受けた英語の試験結果は、IELTS という試験で Overall 7.0 (Listening 8.0、Reading 7.5、Writing 6.0、Speaking 7.0)でした。
サバイバル TIPS
最後に、自分が英語で(特にアメリカ駐在時に)サバイバルをやっていた時に感じたTIPS を紹介します。あくまでも僕の体験に基づくものなので、一般的に通用するものかは分かりませんが、何かの参考になれば幸いです。
まずは何より音に慣れることです。これは標準的な発音を聴ける(&発音できる)ようになるのはもちろんなんですが、周りにいる人の音の癖に慣れていくことも大事です。英語は世界中の人が使うので、文化特有の発音やその人自身の音の癖やスピード、リズムがあります。たくさん聴いていくことで、一人ひとりの音に慣れていけば、より聴けるようになりました。
また、英語のやり取りのリズムとして僕の周りでよく見られたのが、「雑談の後に本題が来る」というものでした。ミーティングでされる雑談的な話は、ブロークンだし速いし、そもそも文化的に知らない話(例えば僕は映画を見ない)なので、全然何を言っているのかわかりませんでした。最初はそれらも頑張って聴こうと思っていたのですが、実はそうした雑談がひと段落して(もしくはそれを遮って)始まる話にこそ本題が含まれているという経験を何度もしました。なので、サンフランシスコで生き残りをかけていた時には、雑談が始まったら中身には一切耳を貸さず、話題が切り替わるタイミングまで耳と脳を休憩させておきました。トーンが変わったら一気に集中して何を話しているのかを聴くと、重要な本題の話を聞き逃さずに済みました。
最後に、別に流暢にできなくても大丈夫、ということです。話す方は通じてなければ何度でも繰り返し分かるまで話せばいいだけだし、聴く方も同じです。何なら、英語ネイティブの人であっても「ごめん、速すぎて何を言っているか分からないからもっとゆっくり喋って」と普通に言うわけです。英語はあくまで手段であり、本当にやりたいのはコミュニケーション、情報を伝え合うことなのですから、伝わったならそれが正解です。効率を上げるという意味で、英語が上手だともちろん良いのですが、最初から完ぺきなど求める必要はありませんでした。
次回に向けて
次回は、ソフトウェアエンジニアが海外に出ていくというときに多くの人が思い描く、世界で通用するエンジニアとして働くために必要なものとは何か、について僕がどのように考えていて、成長してきたかを共有させて頂ければと思います。
関連記事

【エンジニアの海外挑戦記】岩永氏が語る、10年かけた移住計画。狭いチャンスを自分の道につなげられたわけ

「初めてぶつかる課題ばかりで正直悩んでます」CTO2年生の原トリが語る、成長の踊り場
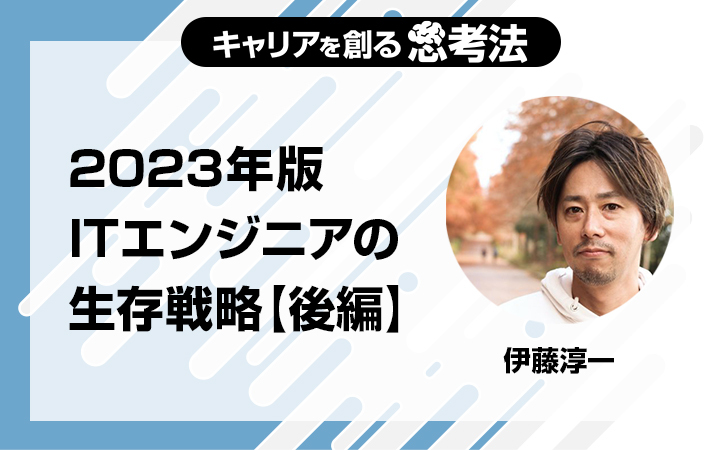
伊藤淳一氏が「一番下手くそエンジニア」から脱出した4つの方法。2023年版ITエンジニアの生存戦略【後編】
人気記事