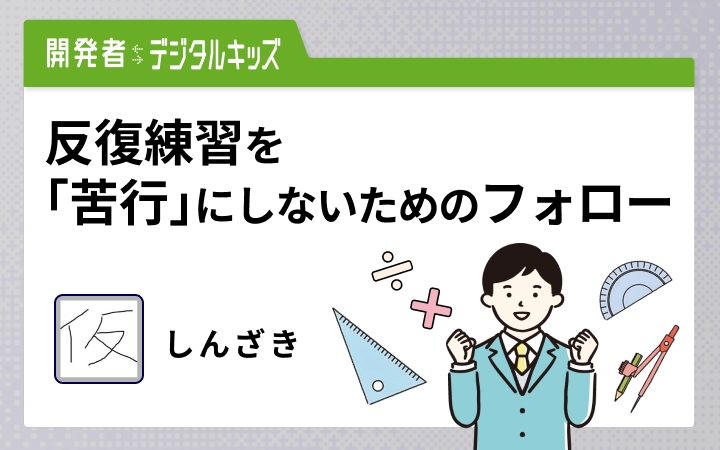最新記事公開時にプッシュ通知します
「国産ヒューマノイドは巻き返せる。だが、いまが最後のチャンス」。日本のロボット開発の厳しい現実と、起死回生の道筋
2026年1月26日


株式会社テムザック 代表取締役議長
髙本 陽一
モビリティや災害救助、介護、医療など幅広い分野で実用ロボットを手がける、日本のサービスロボット開発のパイオニア企業の創業者。神奈川大学法学部卒業後、産業機械メーカーを経て、1993年よりロボット開発に着手。2000年に株式会社テムザック 代表取締役に就任。ロボット黎明期から独自の遠隔操作システムを開発し、「ワークロイド」という人と共存して現場で働くロボットの開発をミッションに、実証実験に終わらせない産業としての構築に尽力している。

SREホールディングス株式会社
佐々木 啓文
新規事業/事業改革×AI・Roboticsを中心に事業を展開。製造業をはじめ、農業や医療、まちづくりなど、医・食・住、暮らしにかかわる領域で活躍される方と“その「夢」を形にする”をミッションに、実現していくことを力を入れいている。
かつて日本は「ロボット大国」と呼ばれ、ASIMOをはじめとするヒューマノイド開発で世界の最先端を走っていました。あれから20年以上が経ったいま、世界中でヒューマノイド開発の動きが起こり、SFの世界の存在だった人型ロボットがいよいよ現実味を帯びてきています。
しかし、現在その開発の中心にいるのは米中であり、日本ではありません。かつて技術的に先行していたにもかかわらず、国内の開発者数は減少し、日本の存在感は薄れてしまっているのが現状です。
そんななか、 2025年、早稲田大学や村田製作所など十数団体が連携し、「純国産ヒューマノイドの開発」「国内のサプライチェーン構築」を目指す団体「京都ヒューマノイドアソシエーション」(以下、KyoHA)が発足しました。
開発するヒューマノイドの技術的な全体構想を担う株式会社テムザック代表・髙本陽一氏、KyoHA事務局を運営するSREホールディングス株式会社・佐々木啓文氏にお話を伺うと、「日本のヒューマノイド開発は巻き返せる。だが、いまが最後のチャンス」だと危機感をにじませます。
四半世紀前、技術的に先行していた日本は、なぜヒューマノイド開発の表舞台から姿を消してしまったのでしょうか。そして、KyoHAは日本のものづくりの起死回生に向けて、どのような勝ち筋を描いているのでしょうか――。
なぜ日本は、ヒューマノイド開発の最前線から消えたのか
――かつて日本はASIMOなどのヒューマノイド開発を行っていました。なぜその後、実用化に至らなかったのでしょうか?
髙本:日本が「新しい技術で、新しい市場を生みだす」という発想が弱い国だから、だと思います。
約25年前、私が代表取締役を務めるテムザックやホンダ、早稲田大学などは世界に先駆けてヒューマノイドをつくっていました。
当時、ロボットを二足歩行させるには、ZMP(Zero Moment Point)等の理論に基づいて重心位置を計算する必要がありました。ひとつひとつのパーツの重心位置を計算し、さらにそれが動いた時の移動予測まで立てなければなりません。
※ZMP(Zero Moment Point)理論:二足歩行ロボットが転倒せずに動くための安定判定手法。床との接地点において回転モーメントがゼロになる点(ZMP)が、足裏で形成される支持領域内に収まるよう重心軌道を設計・制御する。
それでも我々は開発に成功し、二足歩行を実現しました。しかし、投資家などからは「それをどこに売るの?」と言われ、事業として続けられなくなってしまったのです。

――なぜ「売れない」と思われたのでしょうか?
髙本:自動車開発の黎明期、ドイツのダイムラー社がつくりはじめたころには、「自動車は馬に勝てない」と言われていました。実際、初期の自動車は100メートル走れば壊れるような代物だったそうです。しかしそれでも、自動車という新しい技術は広まり、新しい文明や市場が生まれました。
日本はこういった歴史的な経験値を持っていないんですね。
国内の産業史を振り返ると、欧米から新しい技術、例えば鉄道や製鉄などの“すでに産業として成立しているもの”を取り入れることで発展してきました。そのような領域では、「欧米で売れている」という前例から「日本でもつくれば売れる」と投資判断を立てられます。
ところが、ヒューマノイドに関しては、日本が技術的に先行してしまいました。まだ世界で誰もつくっていないわけですから、当然、市場もなかったのです。
――現在は米中を中心にヒューマノイド実用化に向けた動きがあり、いよいよ市場が生まれそうです。日本には開発できる人材はいるのでしょうか?
髙本:2000年ごろは、トップレベルのヒューマノイド技術者が国内に100人程度いたと思います。ですが、その“生き残り”は、10人いるかどうかでしょう。また、その多くは私と同じ世代、もう70歳近い人たちです。
佐々木:日本には「ヒューマノイドの全体システムを統合して設計できる人」はほとんど残っていないんです。
髙本:私は、冗談半分で「ジェダイの残党」と言ったりしていますね。
――日本は世界に先駆けてヒューマノイド開発に成功したものの、技術継承には失敗してしまった、と。
髙本:部品に関しても深刻です。モーターもバッテリーも、今や中国製のほうがレベルが上です。ヒューマノイドロボットの部品において「日本がトップ」と言えるものは、残念ながら1つもありません。
――“1つも”ですか?
髙本:ないと思います。ここも「市場の論理」です。
日本には、ヒューマノイド用の部品をつくれるだけの技術力があります。しかし、まだ市場がないので、つくる理由を見出せないのです。
世界各国が「国産ヒューマノイド開発」に取り組む理由
――いま、米中を中心にヒューマノイド開発が再び盛り上がりを見せています。なぜこのタイミングなのでしょうか。
髙本:当時と決定的に違うのは、AIの発展です。以前は論理を積み重ねて「どうすれば転ばないか」を計算し、プログラミングする必要がありました。しかし、現在はシミュレーション空間でAIに何万回も学習させれば、とりあえず歩けるようになります。
もちろん、そのためのデータを集めるには相当な労力がかかります。とはいえ、高度な知識がなくても開発が可能になったことで、参入のハードルが劇的に下がりました。
また、AIの進化にとってもヒューマノイドが必要不可欠になっています。言語モデルの進化はピークに達しつつあり、ここからさらに賢くなるには、現実世界のフィジカルデータを取り込む必要があります。そのための身体として、ヒューマノイドが求められているのです。
佐々木:他国製のヒューマノイドを導入して研究を進めることも可能です。しかし、そこで得られたフィジカルデータは、そのロボットの製造国に吸い上げられてしまうおそれがあります。
だから、「自国でヒューマノイドをつくろう」という動きは日本に限らず、世界各国で現れています。

――ところで「日本は産業用ロボットが強い国だ」と言われますが、その技術やデータはヒューマノイド開発に転用できないのでしょうか?
髙本:そもそもの設計思想が異なります。
産業用ロボットは、工場などの「環境が整備された場所」で、プログラム通りに正確かつ高速に動くことに特化しています。地面に固定され、安全柵の中で動くことが前提です。
対してヒューマノイドは、人間が活動するカオスな環境に出ていくためのロボットです。足元は悪く、予測不能な事態も起きる。そこに自ら動いていって作業をするには、産業用ロボットとは全く異なるアプローチが必要なのです。
佐々木:どちらも「ロボット」と呼ばれますが、このお話の文脈ではまったくの別物だと考えてください。日本は産業用ロボットの分野では優れていても、ヒューマノイドの分野では大きく遅れを取っているのが現状です。
KyoHAが狙う、起死回生の「ラストチャンス」
――「KyoHA」はどのような経緯から設立したのでしょうか?
髙本:私が、周囲に声をかけていったのが発端です。
私は、今となっては数少ない“ヒューマノイド開発者の生き残り”のひとりです。災害現場や足元の悪い現場で動くロボットをつくりつづけてきましたが、昨今の情勢を見て「このまま何もしなければ、日本のヒューマノイド開発は終わる」と危機感を覚えました。

髙本:モーター、バッテリーといった部品調達ひとつとっても私だけではできませんから、村田製作所などに「日本でもう一度、ヒューマノイドをつくりませんか」と声をかけました。それがKyoHAのはじまりです。
佐々木:雰囲気としては「もう一度、日本のモノづくりでワクワクしたい人、集まりませんか?」という感じでしたよね。
最初に集まったのはテムザック、早稲田大学、村田製作所、SREホールディングスの4団体でしたが、2025年6月に設立発表をすると、多くの企業から問い合わせが殺到し、現在は十数団体まで増えています。
――「つくりませんか」「ワクワク」というノリの軽さで、それほど多くの企業が集まったんですか?
髙本:私は本当に、声をかけただけですね(笑)。
KyoHAに参画している企業の多くは、自動車産業のサプライチェーンを担っているのですが、「自動車の次にくる産業はロボットだ」という共通認識があるのだと思います。
佐々木:自動車産業は日本の屋台骨ですが、もし次世代の主力となるヒューマノイドが輸入頼みになれば、日本のサプライチェーンは崩壊し、産業が空洞化してしまいます。
「誰かがヒューマノイドをつくろうと言いだすのを、みんな待っていた」ような側面があるのかもしれません。現在、KyoHAの会員には「自費だとしてもやります」「みんなで成功させよう」と、日本のものづくりに対して強い気持ちを持った企業や団体が集まっています。
――KyoHAでは、どのような体制で開発を進めているのでしょうか?
佐々木:テムザックと早稲田大学が技術的な旗振り役としてヒューマノイドの全体設計を担い、KyoHA会員になっている各社が、それぞれの得意分野に応じて技術力を発揮し、部品提供などを行います。
受発注のような関係ではなく「こうするのはどうか」「うちの技術なら、こういうものがつくれる」とお互いにアイデアを出し合えるかたちを取っています。
髙本:開発するヒューマノイドは、災害現場などでの利用を想定しています。社会課題の解決に直結する分野ですし、災害現場の環境は多種多様なので、さまざまなフィジカルデータが得られるはずです。
――現代のヒューマノイドの進化は目を見張るものがあります。勝算はありますか?
髙本:我々は25年前にヒューマノイドをつくったことがあり、基本的なプログラムはそろっています。それを最新のハードウェアにアップデートし、シミュレーションを回せばいい。
KyoHAでは2026年3月に初期プロトタイプを、そこからギャップ分析を行って、ある程度実用的なレベルまで引き上げた2つめのプロトタイプを同年末までに公開する予定です。
初期プロトタイプは「今ある日本の技術をかき集めて、とりあえず形にする」というベンチマーク機。性能はそれなりだと思いますが、最終的には、海外のヒューマノイドを追い抜く自信があります。
佐々木:ですが、「日本がヒューマノイドをつくれる国になるかどうか」の最後のチャンスになるのではないか、とも考えています。だからこそ、いまのタイミングを逃すわけにいかないのです。

取材・執筆:川島 昌樹
撮影:芝山 健太
関連記事

活発化する人型ロボットの開発競争。中国ロボット業界の2024年を振り返る

AIは「お金と脆弱性を交換できる」世界をもたらす。米内氏に聞く“「つくる」を守るためのセキュリティ”

AI時代に差がつく、低レイヤの基礎を学ぶ。「Linux標準教科書」著者・宮原徹氏が選ぶ「最初の6冊」
人気記事