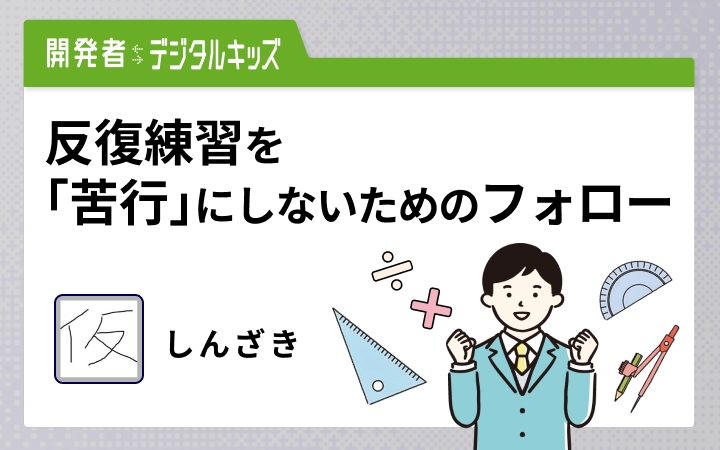最新記事公開時にプッシュ通知します
プロダクトの「世界観」はどうして壊れる? 「解釈違い」な機能を避ける仮説検証の進め方
2025年12月10日


プロダクトマネージャー
飯沼 亜紀
大学で人間工学を学び、ソニーグループのソフトウェア企業に新卒入社。ユニクロおよびファーストリテイリングでは新規事業立ち上げ、EC・デジタルコマース領域で国内外のプロダクトマネジメントを推進した。日本マクドナルドではモバイルオーダー立ち上げをはじめとするデジタル施策全般を統括し、店舗オペレーションと融合した新しい体験を構築。キャディではプロダクトマネジメントに加え、プログラムマネジメントやプロダクトデザイン組織もリードし、プロダクトと組織づくりの双方に取り組んだ。現在はスタートアップから大企業まで幅広い企業のプロダクト開発や新規事業開発を支援している。著書に『Noを伝える技術』。
note:https://note.com/ak_iii
X:@LoveIdahoBurger
新しくリリースした企画や機能が、「このプロダクトらしくない」と嘆かれ、既存ユーザーが離れてしまう――。プロダクト開発に携わる方は、一度はこうした事例を見聞きしたことがあるのではないでしょうか。
ユーザーが愛着を抱くプロダクトの根幹には、一貫した「世界観」が存在します。しかしこの世界観は、事業成長の過程で生じるさまざまな要因によって、ふとした瞬間に損なわれてしまう脆さも孕んでいます。では、その捉えどころのない「世界観」とは一体何なのでしょうか。そして、つくり手はそれをいかにして守り、育てていけばよいのでしょうか。
今回お話を伺ったのは、著名プロダクトマネージャーである飯沼亜紀さん。これまでご自身の執筆した「note」の記事で、世界観の意義について鋭い問題提起をされてきました。今回は飯沼さんの考えを、具体的な事例と共に語っていただきました。
つくり手とユーザーの目線がずれたとき、プロダクトの「世界観」が壊れる
――飯沼さんは過去に、「note」の記事で「プロダクトの世界観」について情報発信をされてきました。その内容を踏まえてお伺いしますが、そもそも世界観とは、どのような概念だと捉えていらっしゃいますか?
飯沼:この話をするには、まず「プロダクトビジョンとプロダクトの世界観は何が違うのか」を考える必要があります。プロダクトマネージャーは開発の指針としてプロダクトビジョンを定めますが、これはつくり手の視点です。一方で、プロダクトの世界観とは「ユーザーがプロダクトから受け取る情報の総体」だと捉えています。
私が過去に「note」の記事で「Voicy」「Slack」「Microsoft Teams」などを解説する際に世界観という言葉を使ったのは、私自身が一人のユーザーとしてそれらのプロダクトに触れていたからです。このように、ビジョンと世界観は関連しているものの、異なる概念だと考えています。
多くのプロダクトマネジメントの書籍では「プロダクトビジョンを定めましょう」と説かれていますが、「プロダクトの世界観をつくりましょう」と書かれているものは多くありません。それは、世界観が意図的にコントロールできるものではない側面があるからだと思います。つくり手がプロダクトに手を加えることで世界観は形成されますが、同時にユーザーの行動によって意図せず醸成されていく部分も大きいです。
――ユーザーの行動によってつくり上げられる世界観というと、たとえばどのようなプロダクトが挙げられますか?
飯沼:「Facebook」はその好例かもしれません。もともとは、大学生が学内の友人と繋がるためのツールでしたよね。それが次第にあらゆる人々と繋がれるSNSへと変化し、今では「Facebookでログイン」のように、共通認証基盤としての役割も担っています。
――多くの企業は、プロダクトの世界観や既存ユーザーを大切にしたいと考えているはずです。にもかかわらず、なぜ世界観が損なわれてしまうことがあるのでしょうか?
飯沼:プロダクトの成長過程で、つくり手がもともと想定していなかった「外圧」や「異変」が起きることが、大きな原因だと考えられます。たとえば、「早急にマネタイズしなければならない」などのケースです。そうなると、必ずしもプロダクトビジョンに沿わないとか、プロダクトの価値向上に繋がらない機能開発に陥ります。それが、ユーザーに「世界観が壊れた」と感じさせてしまう原因になります。

定性・定量調査でユーザーが感じる「価値」をつかむ
――とはいえ、事業フェーズによっては早急にマネタイズしなければならない場面もありますよね。どうすれば、プロダクトの世界観を壊さず事業の成果も出せるのでしょうか?
飯沼:「プロダクトの世界観に沿ったマネタイズ手法になっているか」が重要だと思います。仮に、あるコンテンツプラットフォームで、ユーザーがコンテンツ単位でお金を支払っているとします。この場合、課金できるコンテンツの幅を広げていく方法が考えられます。
たとえば「note」は、コンテンツを1本単位で購入できるだけでなく、複数の記事をまとめたマガジンや、月額課金制のメンバーシップといった多様な選択肢を用意しています。既存ユーザーが「価値が損なわれた」と感じることなく、「良いプロダクトやコンテンツだから、もっとお金を出したい」と思える仕組みを構築することは可能なはずです。
――そのためには、既存ユーザーがプロダクトのどこにコアバリューを感じているのかを、プロダクトマネージャーは丁寧に把握し続ける必要がありそうです。
飯沼:そうですね。つくり手側には「ユーザーにどう使ってほしいか」「どのような価値を感じてほしいか」といった意図、つまりプロダクトビジョンがあります。確認すべきは、この「つくり手が届けたい価値」と「ユーザーが感じている価値」がすり合っているか、という点です。ユーザーが何に価値を感じているかは、ユーザーインタビューや定量調査によって把握できます。
――飯沼さんが過去に経験されたプロジェクトで、ユーザーインタビューや定量調査を行った事例をお話しいただけますか?
飯沼:「マクドナルド公式アプリ」のモバイルオーダー機能についてお話しします。このアプリは店舗とお客様という、2種類のユーザーが存在します。そして、店舗向けとお客様向けの、2つのビジョンがありました。店舗向けは「行列のできない繁盛店」、お客様向けは「自分の手に専用レジ」という内容です。
これらは同じ状態の裏表なのですが、立場によって捉え方が異なるため、あえてお客様・店舗スタッフそれぞれの視点からビジョンを立てていました。そして、アプリを利用する方々が、実際にこれらの価値を感じてくれているかを検証していきました。
まず店舗向けですが、店舗側への提供価値を測るには「店舗オペレーションが円滑に回るか」を見る必要があります。マクドナルドにはそのような検証に利用できる施設があるのですが、そこで大量の注文を擬似的に発生させ、どれくらいの注文数をさばけるのかという負荷テストを徹底的に行いました。そのうえで「この比率までなら対応可能」という明確な基準を持ってサービスを開始しています。
それに加えて、導入後も現場の運用状況や困っている点について、店舗にかなり細かくヒアリングしていました。特に、サービス開始当初は沖縄県限定で導入したため、1店舗ごとの動向を詳細に追うことができました。現場を見ている店長やフランチャイズのオーナーの方々にヒアリングを重ね、私たち開発側が見えている世界とのすり合わせを密に行っていました。
――お客様側には、どのようなアプローチをされたのでしょうか?
飯沼:お客様に対しても、高い頻度でユーザーインタビューを実施しました。沖縄でサービスを開始した当初も、ユーザーを募集し、定性的なフィードバックを集めていました。また、「マクドナルド公式アプリ」内にあるアンケート機能「KODO」に寄せられる、モバイルオーダー関連のコメントはすべてチェックしていましたね。

――お客様向けの定量調査は、どのように実施しましたか?
飯沼:基本的な考え方としては、「私たちが届けたい価値がユーザーに伝わったならば、ユーザーの行動にはこのような変化が現れるはずだ」という仮説を立て、データで検証するというアプローチを取ります。この事例では「モバイルオーダーをきっかけに、お客様はこれまで以上に多様なシーンで店舗を利用してくれるようになるのではないか」という仮説を立てていました。
モバイルオーダーによって、行列に並ばず手軽に商品を受け取れるようになれば、マクドナルドがより親しみやすく、すきま時間にサッと寄れる場所として認識されるはずだと考えたからです。そうなれば、来店頻度の向上はもちろん、利用シーンそのものが多様化していくのではないかと考え、それに関連するデータを取得していました。
ビジョンは「浸透」が命。言葉が一人歩きするまで語り続ける
――ここまで、「世界観の定義」や「つくり手のビジョンとユーザー価値のすり合わせ」などを伺ってきましたが、次に社内に向けたビジョンの共有方法について伺います。プロダクトのビジョンをエンジニアやデザイナー、マーケターなどのステークホルダーに伝える際、工夫されていることはありますか?
飯沼:重要なのは、チームのメンバーがビジョンステートメントをただ暗唱できるだけでなく、「そのビジョンが実現した世界で、ユーザーはどのような状態になるのか」といった“ありたい姿”を、各メンバーが自分の言葉で語れる状態になっているかどうかです。社内に対しては、まずそこを目指すべきだと考えています。
そのため、ビジョンを策定する際にはプロダクトの目指す目標を「なるべくシャープに、つまり具体的かつ明確に示せる」ようにします。抽象的なフレーズを使ってしまうと、どうしても人によって解釈にブレが生じるためです。「シャープかつ具体的」であることで、その解釈のブレ幅を最小限に抑えられます。そして「明瞭」であることは、そのビジョンが実現した世界を、誰もがクリアにイメージできるかどうかにつながります。
――そうして決めたビジョンは、どのような場で、どれくらいの頻度で共有するのでしょうか?
飯沼:基本的には、プロダクトの立ち上げ時に「このプロダクトは、こういう目的で開発します」という形で最初に共有します。その後はプロダクトや会社の文化にもよりますが、私自身は、ある程度浸透するまで、あらゆる機会を捉えて発信し続けるようにしています。
たとえば、スプリントプランニングの際に開発メンバーから「なぜこの機能をつくるのですか?」と問われれば、「それは、私たちのビジョンである『これ』につながるからです」と必ずひも付けて説明するといった具合です。社内の役員など数カ月に一度くらいしか会えない人に対しても、会うたびにビジョンの話をするなどして印象付けていきます。
マクドナルドの例では、最初にチームへビジョンを提示したところ、非常に気に入ってもらえました。その後は、そのビジョンが書かれたスライドが自然と一人歩きするようになったんです。
導入地域を拡大する際に開催する店舗向けの説明会で必ずそのスライドが使われるようになり、それを見て気に入った店舗の方々が休憩室にビジョンを貼り出してくれたこともありました。さらには、全社のキックオフミーティングのスクリーンに大きく映し出されることもありました。
ビジョンを発信し続けることで、やがては自然発生的にチームや会社全体へ広がっていく状態が理想ですね。
――最後に、この記事の読者である現職のプロダクトマネージャーの方々へメッセージをお願いします。特に、プロダクトビジョンの策定・運用や、その先にある世界観の醸成に悩んでいる方に向けて、アドバイスをいただけますか?
飯沼:プロダクトビジョンについて、多くの方が難しく考えすぎているように感じます。ビジョンは、一度決めたら変えられないものでは決してありません。策定してみて浸透しなかったら変えてもいいですし、浸透した後に違和感を覚えたら変えても構いません。
そして、ビジョンは策定すること自体が目的ではありません。その本質的な価値は、「日々の意思決定のよりどころになる」「チームを同じ方向に向かわせる」といった機能にあります。ただ設定するだけでは意味がありません。
最も重要なのは、そのビジョンを使って「どれだけ関係者を巻き込めるか」です。たとえ洗練された言葉でなくても、プロダクトに込めた想いがチームに伝わり、全員が同じ目標に向かえる環境を築けているのであれば大丈夫です。そして、結果としてユーザーに愛される世界観が生まれるのであれば、それが何より素晴らしいことだと思います。

取材:中薗昴、池田恵実
執筆:中薗昴
編集:池田恵実
撮影:山辺恵美子
関連記事
![“作る”だけでは価値は生まれない。ソフトウェアエンジニアが学ぶべきプロダクトマネジメント[レバテックLAB]](https://levtech.jp/media/wp-content/uploads/2025/10/251028_lab_342-.jpg)
“作る”だけでは価値は生まれない。ソフトウェアエンジニアが学ぶべきプロダクトマネジメント

ロードマップは決めきるべきじゃない。「売れない」から脱出するために、PdMがやるべきこと【エムスリー山崎聡】
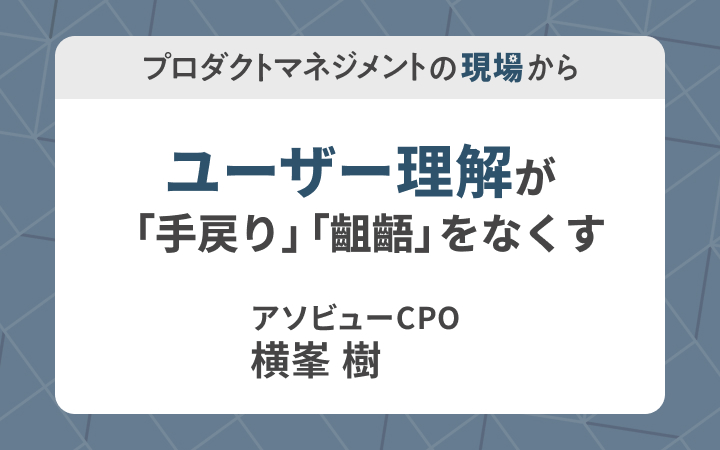
ステークホルダーの「インサイト」を掴むと、合意形成がラクになる。プロダクト思考で組織を動かす方法
人気記事