最新記事公開時にプッシュ通知します
ロジックだけでは通用しない「人」の問題を解き続ける。マネージャーの孤独と無力感を受容するための8冊
2025年8月6日


READYFOR株式会社 VPoE/EM
熊谷 遼平
学生時代の起業を皮切りに、ウェブ・ネイティブアプリケーション開発、インフラ設計構築、全文検索エンジンの導入など、テクノロジー領域での開発経験を積む。プロダクトマネージャーやプロダクトオーナーとしてのチームマネジメント経験の他、事業開発やインサイドセールスチームの立ち上げにも携わる。現在はREADYFORのVPoE/EMとして、エンジニアリングを軸に事業と組織の成長を推進すべく、日々奮闘中。
エンジニアがマネジメントに踏み出すとき、今まで向き合ってきた「技術やシステム」と、マネージャーとして向き合うべき「組織や人」の特性の違いに戸惑う人も少なくありません。
この連載では、業界で活躍する多くのマネージャーたちに、今までどんな困難にぶつかってきたのか、また、そのときどんな本が助けになったのかを紹介していただきます。
今回ご登場いただくのは、READYFOR株式会社でVPoE・EMを務める熊谷遼平さん。高い技術力と問題解決力で卓越した成果を出してきた彼もまた、多くのマネージャーと同じ苦しみを感じていました。感情や価値観といった「正解のない問い」と向き合う中で、良かれと思った言葉がすれ違うこともあるし、経営と現場の板挟みの中で孤独に苛まれることもあるといいます。
理想論だけでは解決できない“組織の生々しい現実”と、彼はどう向き合ったのか。ロジックだけでは正解を出せない領域に飛び込んでから、「マネージャー」の仕事におもしろさと尊さを見出せるようになるまでの軌跡を、支えとなった書籍と共に辿ります。
※本取材は前・後編でお届けいたします。前編はこちら
「人」に向き合う苦しさと、「組織の力学」
――プレイヤーからマネージャ-になると、向き合う相手は「技術」から「人」に変わります。熊谷さんはこの変化に、どんな難しさや戸惑いを感じていますか。
熊谷:ロジックで正解を導き出せたエンジニアリングの世界から、感情や価値観といった正解のない「人」の問題に向き合うことへの難しさは、正直なところ今でも感じています。
事業やプロダクトには、単純な利害関係だけでなく、関わる人それぞれの業務に対する強い想いが乗っています。だからこそ時には対立も生まれます。「人と問題を分離する」や「共通の利益を設計する」といったことも日々意識はしていますが、現実はそう綺麗に割り切れない。どちらかが痛みを伴う妥協をしなければならなかったり、せっかくの設計が日々の運用の中で形骸化してしまったりもします。
もっと根源的なコミュニケーションのすれ違いに頭を抱えることもあります。丁寧に説明したつもりでも、相手には全く伝わっていなかったと後で気づいて愕然としたり、メンバーが何かを理解できないまま頷いていることに気づけず、意図と全く違う方向に物事が進んでしまったり。良かれと思って伝えた言葉が、かえって相手を萎縮させているのではないかと、自分の振る舞いを省みる夜も一度や二度ではありません。
もちろん、マネジメント手法やコーチングのスキルを学ぶことで得られる気づきや、日々の実践で役に立つことはたくさんあります。でも教科書通りに「こういう時は、こう問いかければいい」「このフレームワークに当てはめればいい」と試みても、大抵はうまくいかないものですよね。
――教科書通りに対応したからこそ「親身になってくれなかった」と感じさせてしまう……という場合もありますよね。こうした困難には、どのように向き合ってきたのでしょうか。
熊谷:理想論では解決できない組織の生々しい現実と、そこで起きるコミュニケーションのすれ違い。その両方と向き合うために、大きな組織の力学を理解することと、目の前のチームの土台作りに立ち返ること、その両方が必要だと感じました。
その両輪を前に進めるための大きな示唆を得たのが、2冊の書籍でした。
1冊目は『企業文化をデザインする』(冨田憲二)。
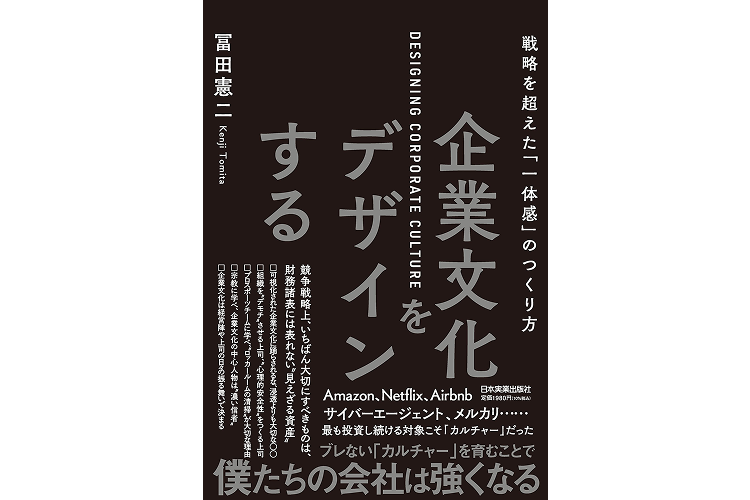
熊谷:良かれと思って導入した仕組みが形骸化してしまったり、想いがすれ違って対立が生まれたり。そうした数々の「うまくいかない」ことの背景には、目に見えない組織の力学があるのだと、この本に教わりました。
本書では、企業のカルチャーは「組織の全員が『各自が信じるもの』に基づいて行った無数の判断/行動の集積」であると解説されています。この言葉がすごく好きで。物事がうまくいかないのは、ルールや制度といった「ハード」な部分だけでなく、人々の価値観や行動様式という「ソフト」な力学が働いているから。こうした「組織の見えざる力学」を理解できたことで、より人の根源的な部分も含めながら打ち手を考えられるようになりました。
2冊目は『心理的安全性 最強の教科書』(ピョートル・フェリクス・グジバチ)。
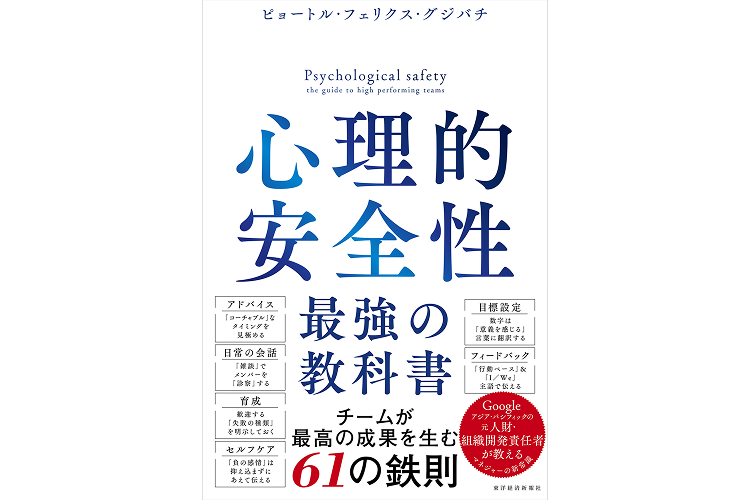
熊谷:組織の力学を理解した上で、自分のチームで具体的に何をすべきか。実践的な「How」を示してくれたのがこの1冊です。
本書で紹介されている数々の“鉄則”の土台には、ある重要な考え方があるといいます。それは「マネージャー自身が自分の価値観、信念、期待感を言語化すること」。この一節に、自分の盲点を指摘されたようでハッとしました。自分の価値観を正直に開示することこそが、メンバーの心理的安全性を高めることに繋がる。この本質的な考え方や、それを支える具体的な「61の鉄則」は、マネージャーとしてチームの土台をつくるうえで多くの示唆を与えてくれました。
経営と現場の板挟み 「孤独」をほぐしてくれた本
――マネージャーになると、これまで同じ立場だった同僚が「部下」に変わります。経営層と現場の板挟みになることに、孤独を感じたことはありましたか。
熊本:もちろん、何度もあります。昨日までフラットに言い合っていた仲間が、評価やフィードバックの対象となる「部下」に変わる。どうしても一定の距離が生まれますし、本音で相談しにくくなることもあると思います。
同時に、経営陣が描く大きなビジョンを現場の言葉に翻訳し、逆に現場のリアルな課題を経営層が理解できる言葉で伝える役割もまた、非常に難しいものです。例えば経営戦略の大きな転換によって、積み上げてきた計画が白紙に戻ったとき。マネージャーは矢面に立ってその調整や説明に奔走することになります。自分は組織全体のことを考えて動いているはずなのに、経営と現場のどちらからも理解されていないように感じ、まるで一人で荒野に立っているような心細さを覚えることもありました。
――想像するだけで苦しくなります。どんな書籍を読み、どのように乗り越えたのですか。
熊谷:自分がどんなに苦しくとも、事業や組織に変化はつきものですし、危機的な状況はいつかは訪れます。であれば重要なのは、その変化の波を乗りこなし、ピンチをチャンスへと変えることだ、と考えました。その変革の瞬間にこそ、マネージャーのリーダーシップのあり方が問われるのだと、私は思います。
組織に変化が起こるときに求められるリーダーシップとは何か。その本質を学ぶ上で、2冊の書籍から、大きな示唆を得ました。
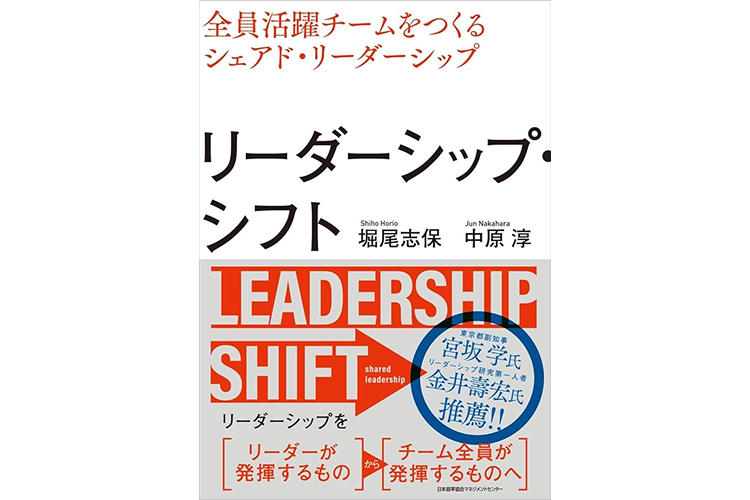
熊谷:この本は、リーダーシップを「マネージャーひとりが発揮するもの」から「チーム全員が発揮するもの」へと捉え直す、「シェアド・リーダーシップ」という考え方を教えてくれます。
「責任を1人で背負い板挟みになることこそがマネージャーの宿命だ」と考えている方もいるかと思います。しかしこの本を読み、マネージャーの役割は「孤独を感じながらも、ひとりでチームを率いること」ではなく、「メンバーが持つリーダーシップを信じ、それを引き出すために環境を整えること」なのだと、視点を転換できました。
そして、その考えをさらに深めてくれるのは、2冊目の『最難関のリーダーシップ――変革をやり遂げる意志とスキル』(ロナルド・A・ハイフェッツ)です。
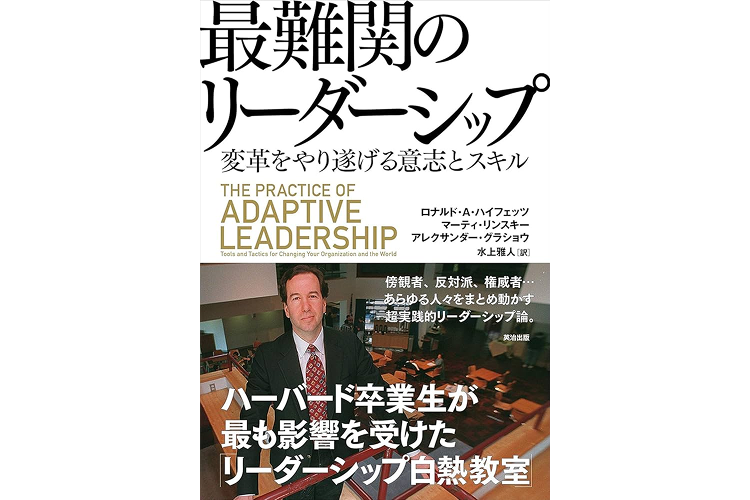
熊谷:こちらの書籍でも、「リーダーシップ」と「リーダー(役職者)」は全く別のものとして明確に切り分けられており、リーダーシップは「本人が選択さえすれば誰でも使うことができるもの」という前提で語られています。その上で、周りの人たちの持つ力を引き出しながら、自らもリスクをとって課題を前進させる「アダプティブ・リーダーシップ」というアプローチを説いています。
この2冊を通じて、リーダーシップとは一部の特別な人のものではなく、誰もが自己成長や自己実現のために使える、普遍的なスキルなのだと気づかせてもらいました。
リーダーシップの担い手や在り方についての学びをさらに深める上で、より内面的なアプローチを示してくれるのが、3冊目の『チームが自然に生まれ変わる 「らしさ」を極めるリーダーシップ』(麻野 祥一郎)です。
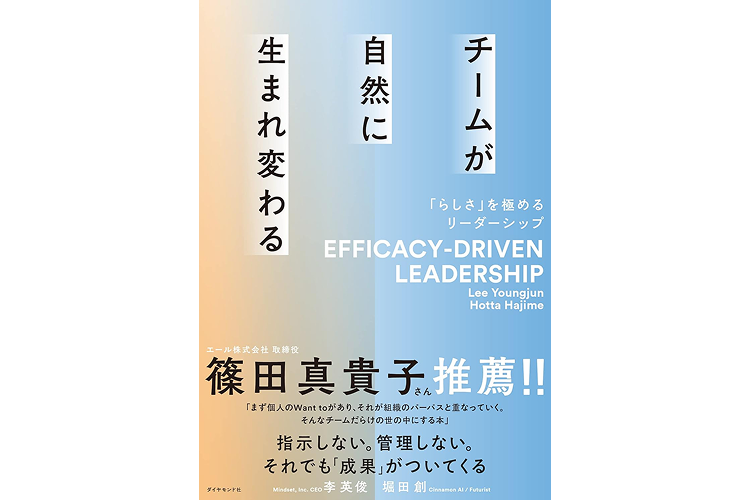
熊谷:日々マネジメントに取り組む中で、私たちはどうしても具体的な「行動」に目を向けがちです。それに対し本書は、あらゆる行動の手前には必ず個人の「認知」が存在すると指摘し、その認知に働きかけるアプローチの重要性を、認知科学の視点から教えてくれます。
特にエンジニアからマネージャーになると、業務の抽象度が急に高まり、「本当に意味があるのか」といった疑問や違和感を抱くこともあるのではないでしょうか。そうした状況において、この「認知」に着目する視点は大きな示唆を与えてくれます。本書で紹介されているアプローチは、そうした違和感を乗り越え、リーダーシップやマネジメントを内面的な深さからも捉え直すための、新たな視点を与えてくれる一冊です。
つらさの根源は「確実性の高い世界を失ったこと」だった
――今回のお話を通じて、プレイヤーからマネージャーになる際に感じた「喪失感」、またマネージャーの仕事にある面白さとは、総括してどんなものだと捉えていらっしゃいますか。
熊谷:つまるところ、エンジニアからマネージャーになる際の「喪失感」とは、「自分の手で直接コントロールできる、確実性の高い世界」を失うことなのではないでしょうか。
コードを書き、それが正しく動くことで得られる短期的な達成感。ロジックで答えを導き出せる明快さ。これらは全て、手触り感のあるコントロールと確実性に支えられています。その世界を得るために、必死に学び、一つひとつ出来ることを積み上げていく過程にも、純粋な喜びがありました。そうして自分が生み出したものが、誰かの役に立ち喜ばれる実感は、何物にも代えがたい、エンジニアとしての誇りの源泉でした。
そうして「誰かの役に立ち、喜ばれる」ことを突き詰めていくと、次第に自分の世界の中だけでは越えられない壁、外側にある多くの課題の存在に気づきます。マネージャーの役割は、この内と外をつなぎ合わせて、大きな価値を生みだすこと。つまり「自分の手でコントロールできる、確実性の高い世界」の外に出なくてはならないのです。
最初は、内と外の世界は断絶していると感じるものです。しかし「マネージャーの役割」にまっすぐ向き合い続けていれば、きっと「内と外は地続きなのだ」とわかります。地続きであれば、それぞれの領域で磨かれた専門性という「核」をうまく紡ぎ、重ね合わせられる。それができれば、大きな価値を生み出せるはず。マネージャーという役割の面白さはまさに、そうした異なる専門性を紡いでチームの力を引き出し、価値を生み出すことにあります。多様なメンバーの意思を粘り強く紡ぎあげていく、難しくも尊い営みに触れられること自体に、大きな価値があるのだと考えています。
――そのように思考を転換できたのはなぜでしょうか。
熊谷:特定の出来事がきっかけになった、というよりは、様々な課題と向き合う中で読んだ書籍の言葉が、私の思考や行動の「土台」や「道標」となってくれています。
まず思い浮かぶのは『Team Geek』(Brian W. Fitzpatrick,Ben Collins-Sussman)です。
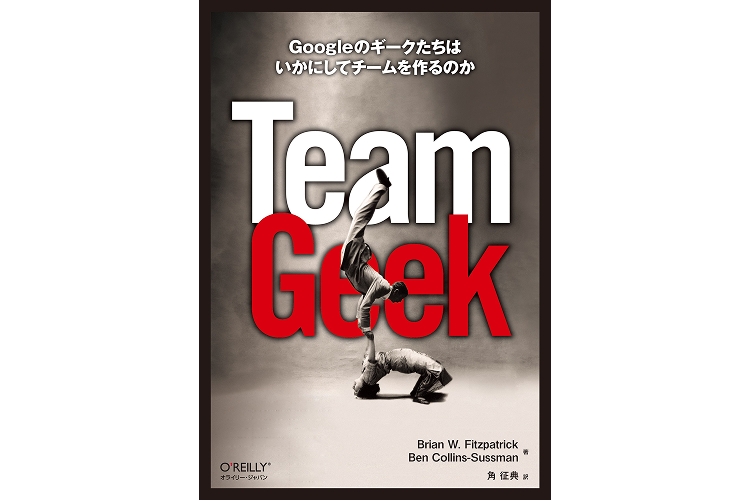
熊谷:日々のチームとの関わりにおいては、本書が提唱するHRT(Humility:謙虚、Respect:尊敬、Trust:信頼)の三原則を特に意識しています。「多様なメンバーの意思を紡ぎあげる」という営みは、この原則がどれが欠けても成り立ちません。
自分の知識や過去の成功体験に溺れることなく、間違いを素直に認める「謙虚」。技術的な議論で自分と異なる意見が出たときに、相手の考えの背景を深く聞く「尊敬」。そして、重要な仕事を任せた後、マイクロマネジメントに陥らずに結果を信じて待つ「信頼」。こうした日々の具体的な行動の積み重ねの大切さに気づかせてくれました。
『HARD THINGS』(ベン・ホロウィッツ)にも大きな影響を受けました。
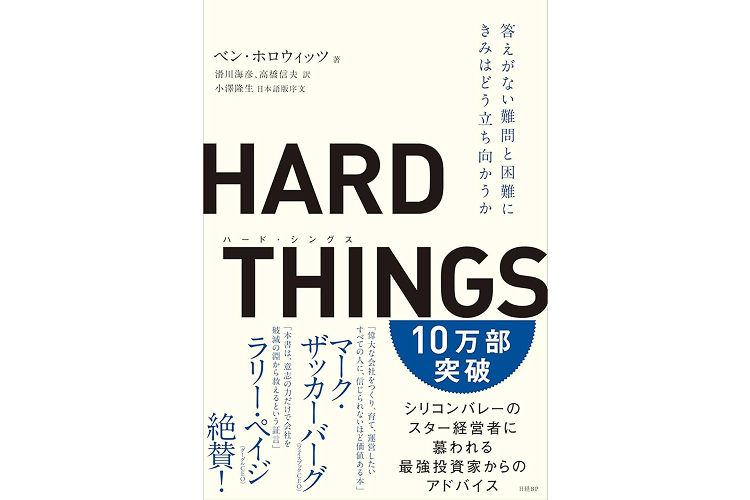
熊谷:マネージャーとして成果を出す過程や企業文化の大切さを、この書籍から学びました。短期的な視点に偏りそうになった時に、長期的・本質的な視点に立ち返らせてくれます。
10年後、20年後、30年後に振り返ったときに個々の取引で勝ったとか負けたとか、どれだけ儲けたとか覚えている人はいない。覚えているのは、ここで働いていたときの気分、我々とビジネスをしたときの気持ちや印象、我々が周囲に与えた影響だ。つまりそれが企業文化であり、誰もここから逃げることはできない。
短期的な数値目標の先には、最後まで残る「感情」がある。本書にあったこの言葉は、折に触れて思い返すようにしています。
最後に紹介したいのが『[現代語抄訳]言志四録』(佐藤一斎)です。
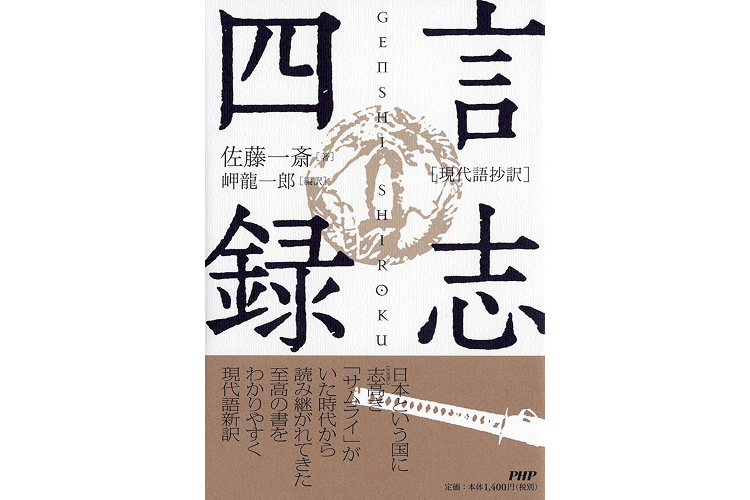
熊谷:いくら知識や経験を積んでも、現実はそう綺麗にいくことはまず無く、泥臭さの連続です。マネージャーとしてある程度経験を重ねた今でも、不確実さの中で判断に迷い、困難に直面することは多々あります。そのたびに自分の力不足や不甲斐なさを痛感し、心が折れそうになる。そんな私を何度も支えてくれたのが、佐藤一斎のこの言葉でした。
一燈を提げて暗夜を行く。暗夜を憂うること勿れ。只だ一燈を頼め。
この「一燈」は、何も崇高なものである必要はないのだと思います。初めて自分が作ったものが誰かに喜ばれた瞬間。困難なプロジェクトを共に乗り越えた仲間。これまで自分を支えてくれた人々。エンジニアを目指した頃の初心。尊敬するリーダーや憧れの人、あるいは、学生時代に心を揺さぶられた原体験。もちろん、家族の存在。
自分にとって大切なものに気づき、見失わず、常に自分の中心に据えておくこと。それこそが、役割の変化に伴う喪失感を乗り越える力となり、新たな可能性を育んでくれるのだと、私は信じています。
取材・構成・編集:光松瞳
関連記事

誇り高き「マネージャー」を全うするために。“理想のEM”小田中氏を支えた珠玉の5冊

EMの仕事には「5つの再現性」がある。5社でEM/CTOを歴任する中で、再現性に効いた5+1冊

感覚頼りのマネジメントから脱却。事業/技術/組織を全て構造化して、複雑性を解きほぐす思考法
人気記事






