最新記事公開時にプッシュ通知します
コードから離れる不安、評価への戸惑い。「マネジメントの本質を掴むまで」の日々を支えた10冊
2025年8月5日


READYFOR株式会社 VPoE/EM
熊谷 遼平
学生時代の起業を皮切りに、ウェブ・ネイティブアプリケーション開発、インフラ設計構築、全文検索エンジンの導入など、テクノロジー領域での開発経験を積む。プロダクトマネージャーやプロダクトオーナーとしてのチームマネジメント経験の他、事業開発やインサイドセールスチームの立ち上げにも携わる。現在はREADYFORのVPoE/EMとして、エンジニアリングを軸に事業と組織の成長を推進すべく、日々奮闘中。
エンジニアがマネジメントに踏み出すとき、今まで向き合ってきた「技術やシステム」と、マネージャーとして向き合うべき「組織や人」の特性の違いや、役割の変化に戸惑う人も少なくありません。
この連載では、業界で活躍する多くのマネージャーたちに、今までどんな困難にぶつかってきたのか、また、そのときどんな本が助けになったのかを紹介していただきます。
今回ご登場いただくのは、READYFOR株式会社でVPoE・EMを務める熊谷遼平さん。SNSで多くの書籍を紹介している読書家でもある彼は、学生起業時代からマネージャーと現場を行き来してきたそう。マネージャーとしての意思決定の不確実性やプレッシャー、コードから離れる不安といった数々の壁と向き合う上では、常に書籍から学びを得てきたといいます。
本稿では、その道のりで特に大きな助けとなった書籍を厳選。彼がその言葉をどのように読み解き、自身の力へと変えていったのか、思索の軌跡と共に紹介します。
※本取材は前・後編でお届けいたします。後編はこちら
- 「マネージャーとは何か」がわかれば、「自分でやる」を手放せる
- 不確実性とプレッシャーは、ひとりじゃなく「組織」で引き受ける
- マネジメントはセンスではない。実行可能なフレームワークを学ぶ
- 「自分は何をしたいのか」を軸にすることが、実は近道
「マネージャーとは何か」がわかれば、「自分でやる」を手放せる
――プレイヤーからマネージャーという役割の変化が起きた際、成果の定義や求められる動きが大きく変わって戸惑う人が多くいます。熊谷さんはこの変化を、どう感じていますか?
熊谷:マネージャーになって直面するのは、「自分で完結できていた世界」とのギャップだと捉えています。いわゆるマネージャー“あるある”の苦悩やアンチパターンを、私も経験していました。
マネージャーになると、コードを書く、リリースするといったアウトプットへの直接的な関与が減ることで、短期的な達成感を得にくくなります。自分で対応すれば数分で終わったような修正も、誰かに作業を依頼し、説明し、確認するという煩雑なプロセスを踏まなければならない。それがスムーズに進まないと「ああもう、自分でやってしまいたい」「でも僕はマネージャーだから、任せなくちゃ」と葛藤する。このような経験は多くの方がしていると思います。
――「自分でやる」という選択肢は、そう簡単に手放せるものではありませんよね。そんな葛藤からどうやって抜け出したのでしょうか。
熊谷:こうした葛藤は「マネージャー」という役割そのものを捉え直さない限り、なかなか解消されませんでした。その助けとなるのは、この3冊の書籍です。
1冊目は『エンジニアリングマネージャーのしごと』 (James Stanier)。
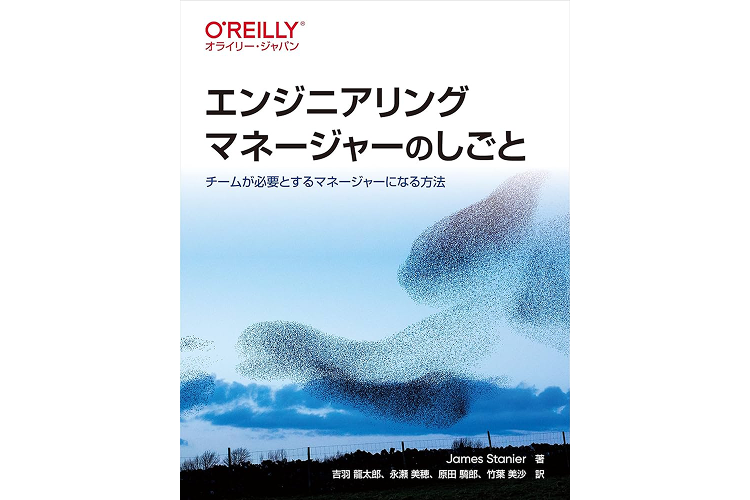
熊谷:今となってはエンジニアリングマネージャーの必読書ともいえるくらい知られているこの本は、「マネージャーの役割は、機能するチームを作ること」だと、とてもシンプルに定義してくれています。また、「マネージャーが満足感を見つけるのが難しい理由」や「マネジメントの4つの活動」など、マネージャーになりたてのころに苦悩しがちなトピックも簡潔明瞭に提示してくれています。
この本のおかげで「自分の成果が見えにくいのも、自分が手を動かすべきでないのも当然だ」と受け入れられるようになり、その中でどうやって達成感を見出していくか、という新たな問いを与えてくれました。
2冊目は『エレガントパズル』(ウィル・ラーソン)。これも名著ですね。
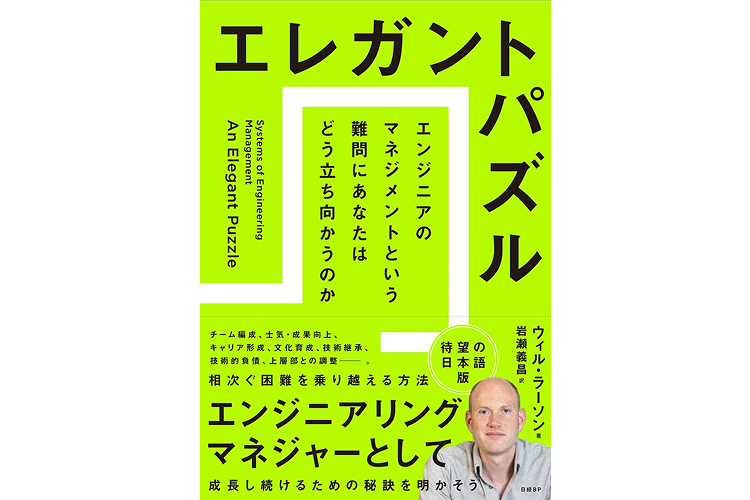
熊谷:本の中の「プロセスよりも人が大事」「マネジメントの本質は倫理的であること」といった言葉が、強く印象に残っています。
自分の仕事の重心が「技術的な正しさの追求」から、「人や文化」といった複雑で曖昧なものへとシフトしたことや、その重要性を認識するきっかけになりました。
「マネージャーが解くべき課題は、明確な答えがないからこそ、挑む価値のある難問(パズル)なのだ」と、視点を変えることができたのです。
3冊目は『冒険する組織のつくりかた』(安斎勇樹)。
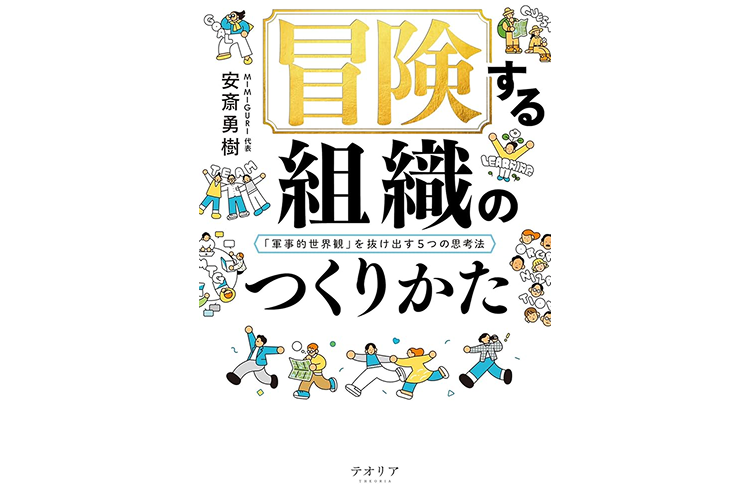
熊谷:この書籍は、マネージャーが直面するしんどさの正体を「アイデンティティ・クライシス」だと指摘しています。青年期に「エンジニア」という専門性を確立した人が、再び『自分は何者か』と問われる“人生で2度目の危機”なのだと。この構造的な解説によって、自分の苦しみは決して個人的な問題ではなく、誰もが通る普遍的な課題なのだと客観視でき、「これまで漠然と感じていたモヤモヤの正体はこれだったのか」と、スッと腑に落ちました。
アイデンティティは固定的なものではなく、自分や環境に応じて自然と変わり続けるものである。そう受け入れることができたおかげで、変化を悲観せず、むしろ探求し続けるプロセスとして楽しんでいきたいと、改めて思えるようになりました。
不確実性とプレッシャーは、ひとりじゃなく「組織」で引き受ける
――マネージャーになると、求められる「意思決定」の種類も変わりますよね。
熊谷:そうですね。プレイヤーのころは「技術的に最善か」という視点で意思決定をしていましたが、マネージャーになると事業の状況も踏まえてトレードオフを考慮する必要が出てきます。成果に至るまでの変数が増えるから不確実性は上がるし、結果がわかるまでに時間がかかるし影響範囲が広いから、プレッシャーも高まります。
――その不確実性やプレッシャーと、どのように向き合っていますか。
熊谷:意思決定の「精度」や「スピード」だけでなく、「不確実性」との向き合い方も大切だと考えています。
完璧な精度を求め続けることは、大きなプレッシャーとなり自分を追い詰め、いずれ疲弊させてしまいます。そもそも「VUCA(※)の時代」と言われる現代において、意思決定に100%の精度を求めること自体が不可能です。また意思決定の結果を左右するのは、マネージャーだけではありません。メンバー一人ひとりが日々下す判断の総和が組織の力になり、成果を形作るものです。
(※)VUCA:Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った言葉で、将来の予測が困難であるという意味合いを持つ
意思決定のスピードも、もちろん重要な要素です。しかし、私は目先の「初速」だけを追い求めることには、慎重な姿勢でいます。拙速な意思決定が、後から大きなサンクスコストを生み、結果的にチーム全体を大きく失速させてしまうケースは、決して少なくないからです。
精度とスピード、このどちらかにこだわってしまうと、良い結果は得られません。精度ばかりを求めれば個人が疲弊し、スピードばかりを重視すればチームが道を誤ってしまう。であれば、2つの両立を丁寧に追求できれば、結果的に組織の「最高速度」を引き出せるはず。
つまり組織全体で「不確実性」を受け入れ、より良い意思決定との「向き合い方」を体得していくことが、より大きな成果を出せる「強いチーム」を創るのだと信じています。
――今の考え方に至るまでに、どんな書籍が参考になりましたか。
熊谷:1冊目は『意思決定の教科書』(ハーバード・ビジネス・レビュー編集部)。
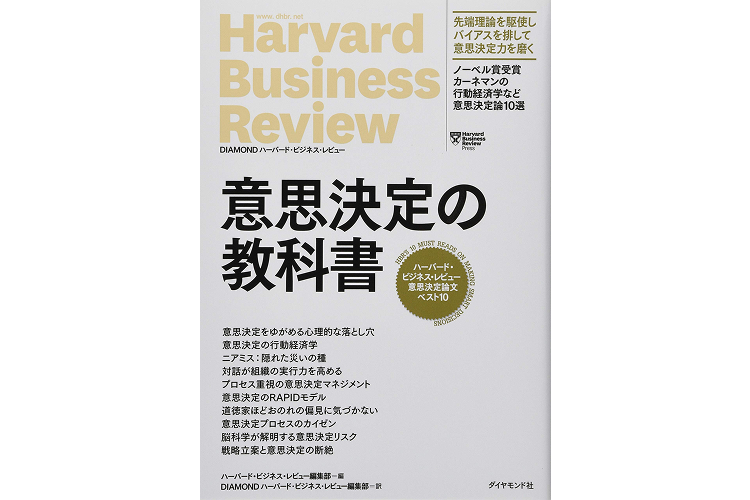
熊谷:まず驚いたのは、人間の意思決定という行為が、アカデミックな領域でこれほど「科学」されているという事実でした。
この本は、その研究の成果をもとに、意思決定の誤りは、多くの場合プロセスではなく「意思決定者の心の中」に潜んでいると教えてくれます。例えば、過去の投資を惜しんで引き返せなくなる「サンクコストの罠」 や、自分の直感を裏付ける情報ばかりを集めてしまう「確証バイアスの罠」 など。私自身が過去の失敗で陥った数々の「思考の罠」に、はっきりと名前が与えられていました。
この本を読んだことで、自分の失敗を客観的に振り返り、そこから具体的な教訓を得ることができました 。完璧な判断は不可能でも、こうした思考の罠を「自覚」すること。それこそが、より良い判断を下すための最も確実な一歩なのだと学びました。
2冊目は『[新版]競争戦略論I』(マイケル・E・ポーター)。
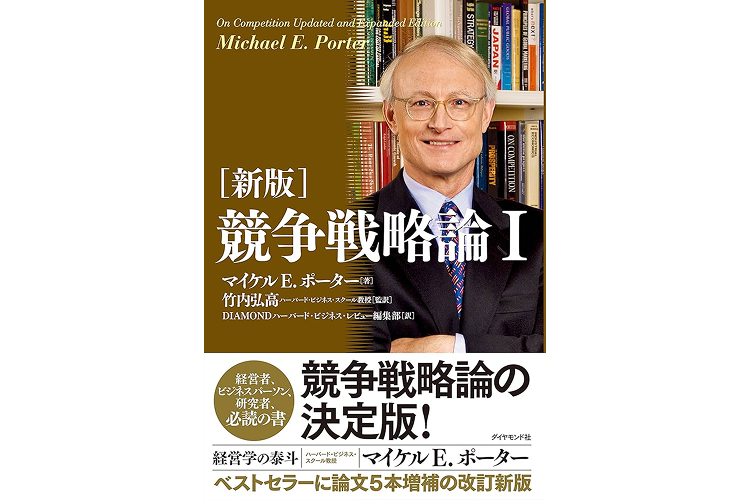
熊谷:この本の内容は、後発の多くの戦略論の書籍で引用されています。正直なところ内容は非常に難解です。ただ、その後生まれた多くの思考の源流である原書に触れると、大きな学びが得られるものだと感じています。
特に、本書が提唱する「戦略」と「業務効果」のフレームワークは、今でも私の思考の土台となっています。「この判断は他社に追いつくためのものか」「それともトレードオフを伴う、我々独自の道を選ぶためのものか」。この問いを立てることで、プレッシャーの中でも、判断の拠り所を見出すことができるのです。
読み返すたびに新しい発見があって、いまだに著者の思考の深淵には辿り着けないなあと感じています。
最後に『エッセンシャル思考』(グレッグ・マキューン)です。
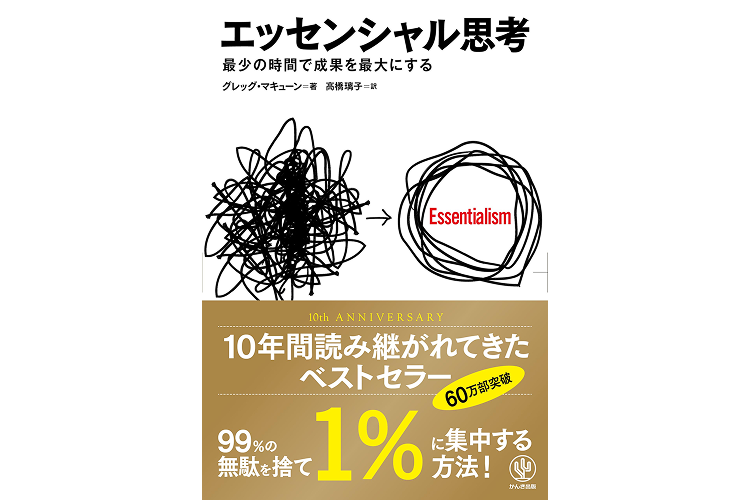
熊谷:プレイヤーだった頃、開発においては「バックログを網羅的に列挙し、優先度を決め、いかに効率的に消化していくか工夫する」という進め方をとることが多いと思います。
しかしマネージャーになると、様々な立場から無数の「やりたいこと」が寄せられます。その全てに応えるのは不可能ですし、闇雲に進めるとチームはあっという間に疲弊してしまう。そんな中で組織に求められる成果を出さなければならない。
こうした状況で重要なのは「本質的な課題はどこにあるのか?」「本当に重要なことは何か?」という問いを立て、数多ある選択肢の中から本質を見極めるという、思考の転換です。本書は、多くのマネージャーが躓きがちな、「成果を出すための思考の切り替え」を、力強く後押ししてくれる一冊です。
マネジメントはセンスではない。実行可能なフレームワークを学ぶ
――評価される際の基準や期待値の変化も、マネージャーになったばかりの人にとって戸惑いを感じる部分かと思います。
熊谷:おっしゃる通り、評価の軸が個人から組織へとシフトする点は、マネージャーにとって大きな挑戦だと思います。基準が大きく変わると、つい目先の評価制度にだけ思考を奪われがちになりますし。組織という大きな変数を含んだ成果を評価されることに、違和感を覚えるときもあるでしょう。
このとき大きな突破口となったのは「そもそも組織における評価とは何か」「自分はマネージャーとして、評価にどう向き合うべきか」という本質的な問いに立ち返り、一段高い視座で捉え直すことでした。
――「評価」を捉え直す中で、特に有用だった書籍は何ですか。
熊谷:2冊あります。
まず1冊目は『人事評価で最高のチームを作る方法』(川内 正直)です。
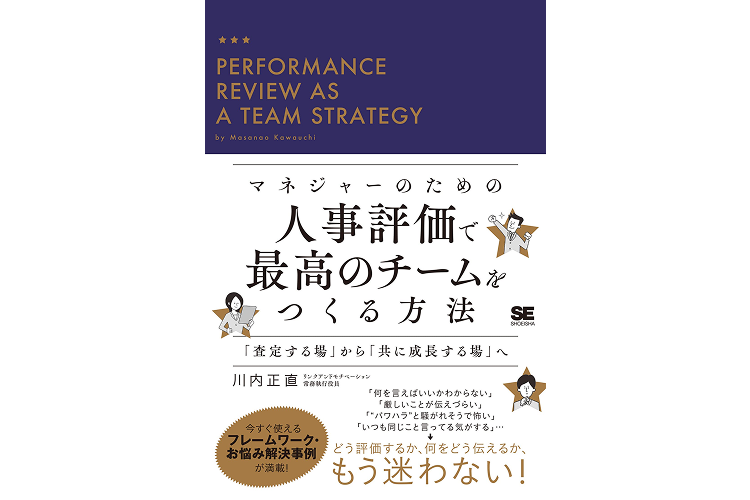
熊谷:評価制度の設計に関する本の中でも、本書は一貫して現場のマネージャーによる「運用」にフォーカスしています。マネージャーになり評価者の立場になって初めて戸惑うことがたくさんある中で、とても参考になると思います。
「人事評価業務は好きじゃない、は当たり前」といった、管理職なら誰もが感じる“評価あるある”から話が始まるので、とても共感できます。そこから「では、なぜやるのか」「どうやるのか」を、現場に寄り添う形で丁寧に伝えてくれています。
読み進めると次第に、評価は「機会を提供するツール」でしかない、有効活用できるかは管理者の向き合い方次第なのだ、という本質に気づかせてくれる一冊です。
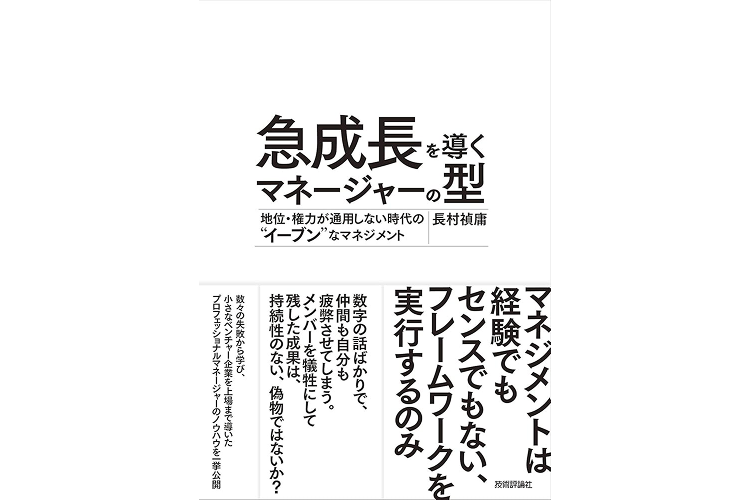
熊谷:本書は、「マネジメントはセンスではなく、実行可能なフレームワークである」と教えてくれました。
チームの目標や戦略を具体的な「型」に沿って設定し実行していく手法が紹介されています。この手法を知ることで、コントロールできないように思えた「組織の成果」も、実はそんなことはなく、道筋を立てて成果に導けるものなのだと気づきました。
本にあった「マネージャーとメンバーは役割の違いでしかない、イーブンな関係だ」という言葉は、今も日々の業務の中でよく意識しています。
「自分は何をしたいのか」を軸にすることが、実は近道
――マネージャーになると、最新技術のキャッチアップに割く時間も、現場で打席に立つ機会もなくなります。すると、十分な実績を積んでいる人も、そうでない人も、手を動かす技術者としての「市場価値」に不安を感じてしまう場合もあると思います。
熊谷:確かにそう感じる人もいると思いますし、私も一時期はそうでした。ただ、今は「市場価値」というものさし自体を追いかけすぎないようにしています。
なぜなら、市場価値は技術トレンドや経済といった外部環境に大きく左右される、非常に不確実なものだからです。それを追い求めすぎると、思考は短期的な利害に縛られ、打算的になってしまう。その結果、自分にとっての本質を見失い、かえって価値を損なうという本末転倒な事態に陥りかねません。
――では、何に軸足を置くべきでしょうか。
熊谷:やはり「自分が何をしたいのか、どうありたいのか」という、自分自身の内なる探求心だと思います。その探求を続ければ自ずと、組織に潜む本質的な課題の発見やその解決へと向かっていくはずです。
このように私の考え方を大きく変えてくれたのは、2冊の書籍でした。
1冊目は「スタッフエンジニアの道 ―優れた技術専門職になるためのガイド」(Tanya Reilly)。
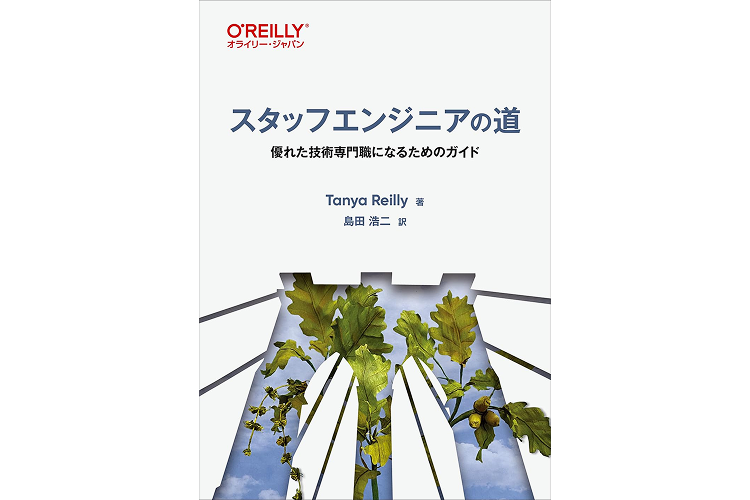
熊谷:この本は、マネージャーもスタッフエンジニアも、本質的な役割は「個別のタスク」から「より大きな課題解決」へとシフトしていくものだ、と明確に言語化してくれました。役割や日々の活動は変わっても、自分自身の価値の源泉である「課題解決」という本質は失われるのではなく、むしろ進化していくのだと。自分のアイデンティティを「コードを書く人」から、より抽象的で強固な「課題を解決する人」へと再定義する手助けをしてくれました。
またこの本には、スタッフエンジニアとエンジニアリングマネージャーに共通する責任として「リスクを特定し、阻害要因を取り除き、問題を解決する責任を負っています」という一節があります。これこそが探求心の行き着く先であり、シニアな専門職に共通する核心だろうと感じています。
もう1冊は、『東大物理学者が教える「考える力」の鍛え方』(上田 正仁)です。
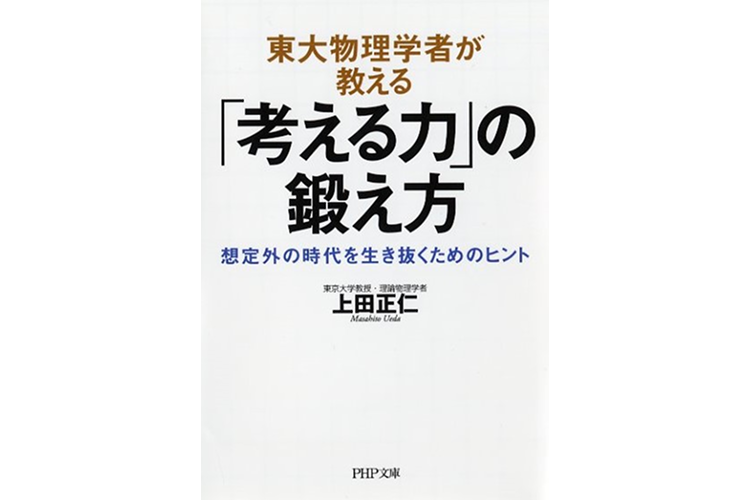
熊谷:「課題解決」という役割を、どのような心構えで探求していくべきか、その指針を与えてくれた一冊です。
思えば20代の頃、私は「エンジニアとして技術力を高める」という1つのゴールを目指す「ゴール・オリエンテッド」な思考に囚われていました。だからこそ、マネージャーになってそのゴールが遠のくと、市場価値への強い不安を感じてしまう。
しかし本書は、一見非効率に見える「キュリオシティ・ドリブン(好奇心主導型)」の大切さを説いています。この考え方に触れ、自分の軸足を「定められたゴールを目指すこと」から「好奇心の赴くままに探求すること」へと意識的に移すことの重要性に気づくことができました。
私自身の経験を振り返っても、「エンジニアリングマネージャー」という肩書きは、目指してたどり着いたものではなく、目の前の課題解決に夢中になっていたら後からついてきた、という感覚です。結局のところ、自分が「どうありたいか」を追求し続けた先に、本質的な価値や役割が自然と与えられる。そう信じて、これからも歩んでいきたいですね。
取材・構成・編集:光松瞳
関連記事

感覚頼りのマネジメントから脱却。事業/技術/組織を全て構造化して、複雑性を解きほぐす思考法

誇り高き「マネージャー」を全うするために。“理想のEM”小田中氏を支えた珠玉の5冊

EMの仕事には「5つの再現性」がある。5社でEM/CTOを歴任する中で、再現性に効いた5+1冊
人気記事






