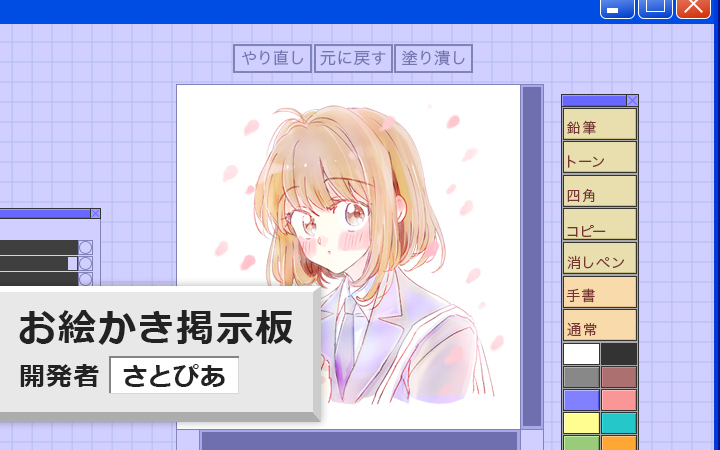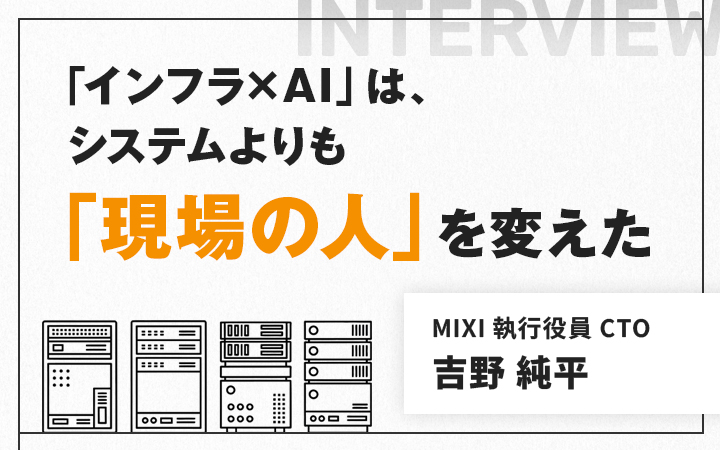最新記事公開時にプッシュ通知します
ワークス同期たちの、今だから話せる「原点」。カミナシCTOとKyash、タイミーVPoEが新卒時代に得たもの、失ったもの
2025年7月4日


株式会社タイミー VPoE
赤澤剛
2009年に株式会社ワークスアプリケーションズに入社、ERPパッケージソフトウェアの開発とプロダクトマネジメントに従事。2015年よりシンガポール及びインドにてR&D組織の強化、海外企業向け機能開発をリード。その後LINE株式会社での新銀行設立プロジェクト、株式会社アルファドライブ及び株式会社ニューズピックスでの法人向けSaaSの開発に携わった後、2021年1月にアルファドライブ執行役員CTO、2023年4月に株式会社NewsPicks for Business取締役に就任。2024年2月よりVPoEとしてタイミーにジョイン。

株式会社カミナシ 取締役CTO
原トリ
大学を卒業後、株式会社ワークスアプリケーションズのR&Dチームにてソフトウェアエンジニアとして設計・開発に従事。クラウドを前提としたSI+MSP企業で設計・開発・運用業務を経験し、2018年Amazon Web Services入社。AWSコンテナサービスを中心とした技術領域における顧客への技術支援や普及活動をリードし、プロダクトチームの一員としてサービスの改良に務めた。2022年4月カミナシ入社、2022年7月よりCTOに就任。

株式会社Kyash 執行役員VPoE
こにふぁー(小西裕介)
ワークスアプリケーションズ、株式会社奇兵隊、Quipper Limited. を経て、2017年Kyash入社。AndroidやiOS開発を経験した後に、2019年からMobileチームのEMを経てサーバーサイド、QAチームのEMも担った。2021年にEMから離れたのち、QAチームのいちメンバーとしてテストの自動化を半年ほど手がけた後に、2022年よりVPoEとしてプロダクト開発チーム全体のマネジメントに従事。
タイミー VPoE・赤澤剛さん、Kyash 執行役員 VPoE・こにふぁーさん、カミナシ 取締役 CTO・原トリさん──注目企業の技術部門を牽引する3人は、もともとERPパッケージベンダーである「ワークスアプリケーションズ(以下、ワークス)」の新卒同期でした。
彼らが過ごした15年以上前の同社には、ハードワークを是とする文化と、たとえ新卒のエンジニアであっても「顧客との交渉、プロダクトの要件決め、設計・開発なんでもやる」という環境がありました。そこで、優秀な仲間たちと切磋琢磨しながら成長を重ねていったといいます。
血気盛んだった当時の経験が、なぜ開発組織を率いるスキルの原点になったのでしょうか。今回はワークス時代のエピソードや、当時の学びや反省を、同期だからこその視点で語ってもらいました。
- とんでもない失敗だって山ほどした「あの頃」
- 打席に立たされ、バットを持たされ「打て!」の日々。「越境精神」が財産に
- 越境が当たり前だったから、他職種への理解と敬意が自然と生まれた
- 「どう解決すればいいかわからん」状態が、一番成長する
とんでもない失敗だって山ほどした「あの頃」
――今、各社をけん引する立場で活躍されているお三方は、新卒で同期だったんですね。今回は当時のことを振り返りつつ、みなさんの成長につながった要素を探していきたいと思います。まず、新卒時代はお互いにどんな印象を持っていましたか?
赤澤:トリさん、こにふぁーの二人は、新卒のときからめちゃくちゃ輝いていました。お世辞じゃなく、ちょっと話して、何を作っているか聞いただけで「この人、すごいぞ!」ってすぐにわかるというか。話しているだけで学びがありました。だから業務で直接関わりがなくても、休憩時間とかにフラッと「会いに行こうかな」って人でしたね。こにふぁーは同じフロアだったから、仕事が一段落したあとによく雑談してました。
こにふぁー:僕は「トリさんは優秀だけど、怖いなー」と思っていました。仲良くなれないだろうなって。
原:えー、そうなの?
赤澤:こにふぁー、僕にもそう言うんですよ。「赤澤とは仲良くなれなそうだなと思ってた」って(笑)。
こにふぁー:その頃、僕は人との関わりがあんまり上手じゃなかったから(笑)。

赤澤:こにふぁーのエピソードで、めちゃくちゃよく覚えてるのがあって。ある日の夜、こにふぁーがトコトコ僕のところに来たんですよ。で、「ちょっと聞いてくれる? 俺、良くないことを言っちゃったかもしれない」って話しかけてきて。
どうしたのか尋ねたら、「ある職種の人たちの業務を効率化するツールを作ってるんだけど、ちゃんと業務を知ろうとして、1週間くらい一緒に作業した」って。その結果、「これは改善し甲斐がある!」ってこにふぁーは考えたらしくて、勢い余って「一緒に作業させてもらって強く感じたんですが、これは人間のやる仕事じゃないですね!」ってメールを打って本人たちに送っちゃったんですよ。
こにふぁー:そしたら、相手からガチなトーンでお叱りの返信が来て。「私たちが普段やっている仕事に、そんな言葉をかけられると傷つきます」って。みなさんが大変な思いをしていると知って、それをめちゃくちゃ改善できると伝えたかったんですが、完全に言葉足らずでした…。もう本当に申し訳なくて、すぐに直接謝罪しました。
赤澤:こにふぁーから「そういう意味で書いたわけじゃないんだけれど、やっぱり良くなかったかな……」って相談されて、「うん、絶対に良くない!」って返した記憶がある(笑)。
こにふぁー:今は絶対にやらないですね。
赤澤:今でこそ、ソフトスキルの高さで有名なこにふぁーにも、そういう時期があったんですよ。でも、こういう経験を積み重ねてして、今のこにふぁーが形作られているんだなって。
打席に立たされ、バットを持たされ「打て!」の日々。「越境精神」が財産に
――当時、ワークスのエンジニアたちはどんな環境で働いていたんですか?
こにふぁー:必要なことは全部やりなさいって感じでしたね。仕様を決めるのも、事業開発も、システムの設計・実装も、顧客への提案も、ぜんぶ自分でやれっていう。
赤澤:打席に立つ回数はめちゃくちゃ多かったよね。戦略的に方法を考えるというより、毎日打席に立たされて、バットを渡されて、「はい、球が来るぞ!打て!」って。
原:エンジニアが客先に出るのが当たり前というか、むしろ推奨されていましたね。
――その環境の中で、ご自身が成長できたと感じられる点はありますか?
原:エンジニアが顧客を理解して、ドメイン知識を持っていたから、「何をなぜ作るべきか」の解像度が高かったですね。顧客と対話するのが当たり前だったから、その感覚が自然と染みついたというか。新卒のうちにそれができたのは、今振り返ると貴重な体験でした。
こにふぁー:仕事の中で「○○を作ってください」とあまり言われなかったんですが、むしろそれが良かったですね。エンジニアに求められていたのは、あくまで顧客の課題を解決することだけ。必ずしも、プロダクトや機能を作ることだけが解決策とは限らないというか。たとえば「運用でカバーできないから機能開発が必要かも」という話があっても、「そもそも、なぜ運用を変えられないのか?変えるべきではないのか?」といった具合に、前提を疑う文化があった気がします。
赤澤:それから、「仕様やスケジュールは決して絶対的なものじゃない。もし変えることで事業やプロダクトが良くなるなら、エンジニアが干渉して積極的に変えてもいい」ってことも理解しました。

赤澤:たとえば、あまり良くない設計の機能があって、「本当は再設計したいけれど、すでに何十社と実務で使ってくださっていて、それらの会社に影響が出るから変更は厳しい」という状況があるとするじゃないですか。それなら、「自分たちがその数十社のお客さますべてに説明して、業務フローや利用方法を変えてもらう」という方法もあるわけですよね。実際、ワークス時代はそういうこともよくやっていました。
原:めちゃくちゃやってたね。スケジュールも機能も顧客の声も、プロダクト開発の“変数”のひとつなので、動かせない要素じゃない。だから、顧客のためになるのなら、その変数を動かしてもいいという。「開発だけじゃなくて、(他の領域に)どんどんしみ出そうぜ」ってノリは、ワークスで学んだ気がします。職種の枠に収まるな。ちゃんとビジネスにも入り込もう、みたいな。
越境が当たり前だったから、他職種への理解と敬意が自然と生まれた
――職種の壁を超えた当事者意識は、なかなか持てるものではないですよね。それを新卒の頃に経験していると、マインドもスタンスも変わりそうです。
赤澤:とはいえ、もちろんマイナスだった部分もたくさんあって、いわゆるプロダクト開発のベストプラクティスは学べなかったですね。良くも悪くも「課題を解決できればいい」というスタンスだったので、スマートな解決策じゃないものも、いくつもやっていました。転職してから「本当はこういうやり方をすべきだったんだ」って後追いで学んだことが多かったです。
あと、ワークスでは「プロダクトマネージャーっぽい仕事」もやっていたんですが、転職後に本職の方と会って、レベルの高さにビビりました。「僕のやってたこと、全然プロダクトマネージャーじゃなかったじゃん」って。衝撃だったし、他の職種の人たちをめちゃくちゃ尊敬するようになりましたね。ワークス在職中は「プロダクトマネジャー的な動きもやっています、できます」と話していましたが、転職してから二度と言わなくなりました(笑)。
原:車輪の再発明もしまくってたよね。たとえばHTTP通信のライブラリとか、既にあるのにゼロからスクラッチで作ったりしていました。ExcelっぽいUIを実現するライブラリとか、たぶん社内には無数に存在していたと思う。
赤澤:そういったライブラリを自作できる経験は、個人のスキルアップにはつながるけれど、開発組織全体としては無駄が多くなっちゃうからね。
原:あの開発スタイルを、よく許容してくれていたよね。
赤澤:プロダクト開発に限らず、プロジェクト管理や組織運営などでも、うまいやり方を知らないからアンチパターンを片っ端から全部やってしまったんですよ。後になってから本を読んで「僕のやってきたこと、全部書いてあるじゃん!」と気づいて、世の中の体系化されたプラクティスをちゃんと学ぶことの重要性を痛感しました。
当時の経験は自分自身の学びにはなりましたけど、働き方は持続可能なものではなかったので、読者のみなさんに真似をしてほしいものではないですね。
こにふぁー:どうしても、僕らが語る内容は生存者バイアスがかかっていると思います。あの頃のスタイルは今はマッチしないと思いますし、再現性のある美談でもないと思います。

「どう解決すればいいかわからん」状態が、一番成長する
――振り返ってみて、新卒の頃に今みたいになるって想像していましたか?
こにふぁー:新卒時代は将来どうなりたいとか考えてなかったですね。
赤澤:それは間違いないね。
原:同じく、考えてなかった。
真面目な話をすると、新卒の頃って、そもそも自分にどんな強みがあるのかわからないと思うんですよね。仮に「自分はここが強い」と考えていたとしても、それが社内外の他の人と比べて相対的に価値があるのか、新卒時代には判断する力がない。だから、「将来、良い会社の良いポジションに就くにはどうすればいいだろう」と悩むより、打順が回ってきたら全部打つ、みたいな気持ちで仕事に取り組んだほうが、結果的に自分の強みを発見できるっていうのはありますよね。
たぶん、そのスタンスだから自分はCTOという肩書きで働けているのはある。カミナシに入るまで、マネジメントも経営もしたことなかったですからね。「経験がないので、CTOなんて無理です」って言ってたら、こんな機会も回ってこなかったはずです。これまで転職のたびに、未経験の領域をイチから学ぶことをくり返してきたけれど、苦じゃなかったですね。

赤澤:自分がマネージャーの立場でメンバーと向き合うときは「相手のできること、やりたいことをやらせるのが、いつだって正解なわけじゃない」という考えを持ってます。
ワークス時代の僕らって、個人のWill以上に、組織やプロダクトの状況で業務のアサインとかチーム配置が決まっていたこともよくありました。でも、全力でやってみたら、それが後から振り返って間違いなく自身の強みやキャリアになったんですよね。
自分がこれまで所属したエンジニアリング組織でもたまに「○○さんはこの領域が未経験なので、他の方のアサインの方が適しているかも」みたいな声をもらうことがあったんですけど、当然考慮すべき事項ではありつつ、そういうときは「人間なんて、いつだって未経験の塊だから、大丈夫だよ!」という考えもベースに持っています。
極端な例ですが、自分が赤ちゃんだった頃、立ち上がる前に「ハイハイしかしたことないから、無理だな」なんてならなかったですよね。みんな、がむしゃらに取り組んだら、ある日突然できるようになった。だから、「未経験=できない」ってネガティブに捉えすぎないほうがいいよねって話を、みんなにもよくしています。
こにふぁー:これは余談なんですけど、ワークスのインターンをしてた時代に、(わからないことがあっても)隣のインターン生と相談するなって言われていたんですよ。今思えば、自分で課題を解決する力を伸ばすっていう方針だったのかもしれないですね。
赤澤:新しく組織に入ってくださった方に「この仕事、簡単じゃん」って感じさせちゃうのが一番まずいと思ってるんですよ。「かなり頑張らないとキツいな」というチャレンジングな仕事を、適切に与えるのが重要です。もちろん、相手の状況を把握、フォローし、そして当然ながら法律や会社のルールをきちんと守ったうえでのハードさで、です。「任せるかどうか迷ったときは、任せる」っていうのが、自分の中では人を育てる原則ですね。
原:「どう解決すればいいかわからん」って状態のときが、一番成長するものですからね。
――やはり、打席に立ち続けて難易度の高い課題を解くことが、成長につながるのですね。
原:将来のキャリア像についてビジョンを描けているのは、それはそれで素晴らしいですけど、描けてないからといって悲観する必要はないですよね。職場選びについてアドバイスするなら、「打席に立たせてもらえる会社に行こう」っていう感じかもしれない。
こにふぁー:きっとどの会社でも、誰も手をつけていない課題が絶対にあるんですよ。そういう仕事を拾っていくだけでも、打席には立てるはずです。ただ、そういう動きをしたときに「それは、あなたの仕事じゃないから」って言われると、しんどいですよね。だから、エンジニアの挑戦を歓迎してくれる会社で働くのがいいんじゃないかなと思います。

取材:中薗昴、光松瞳
執筆:中薗昴
編集:光松瞳
撮影:山辺恵美子
人気記事