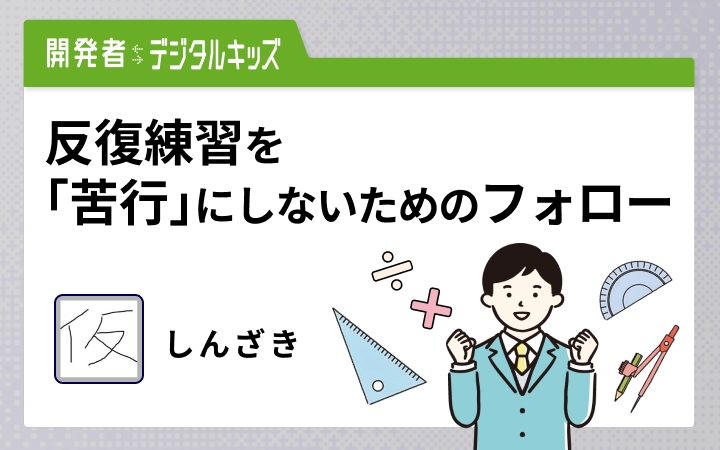最新記事公開時にプッシュ通知します
評価へのモヤモヤはなぜ生まれる? 広木大地氏に聞く「アピール」の本質
2025年2月25日

一般社団法人 日本CTO協会 理事 / 株式会社レクター 代表
広木 大地
2008年に株式会社ミクシィに入社。同社メディア開発部長、開発部部長、サービス本部長執行役員を務めた後、2015年退社。株式会社レクターを創業。技術経営アドバイザリー。著書『エンジニアリング組織論への招待』がブクログ・ビジネス書大賞、翔泳社技術書大賞受賞。一般社団法人日本CTO協会理事。
適切な評価を受けるためには、自分自身の成果をきちんと評価者に伝えなくてはなりません。しかしそうした「アピール」には、相応の労力を伴います。その労力を払わないが故に、実力に見合った評価を受けていないエンジニアを見たことがある人は多いのではないでしょうか。「普段の動きを見ていれば、一人ひとりの実力はわかるはずなのに」と、組織の評価に対してモヤモヤを感じることもあるでしょう。
評価される側として、評価制度に対してどのようなスタンスで向き合うべきなのか。また、そもそも「アピール」とは何を指す言葉で、それにはどんな目的があるのか? 「評価」や「アピール」との向き合い方について、開発組織の運営に詳しい広木大地さんに聞きました。
- 「正しい評価」は存在しないし、「見ていればわかる」は前時代的
- 評価されるための「アピール」は、「自分を良く見せるためのもの」じゃない
- 正しい「アピール」ができるようになると、評価へのモヤモヤは晴れていくはず
「正しい評価」は存在しないし、「見ていればわかる」は前時代的
——開発現場で活躍しているにもかかわらず、会社から適切な評価を受けていない人がよくいると聞きます。
広木:確かにそういう人はいますし、そういう人を「ちゃんと評価してほしい」と、周りのエンジニアがモヤモヤする気持ちもわかります。
ただ私としては、そのモヤモヤは「評価制度に対する過度な期待」から生まれているのではないかと思います。
——過度な期待…?
広木:「評価制度や評価者は非常に優れた神様のようなものであって、何も言わずとも常に社員の成果を正しく認識してくれるもの。だからその制度を通せば、必ず適正な給料が出てくるはず」といった期待ですね。評価者の立場を経験したことがない人は、得てしてこうした期待感を持ちやすい部分もあると思います。
ただ、「評価する側」を経験した人はよくわかると思いますが、実際にはそもそも、そのような完璧な評価制度をつくることはできません。ドラゴンボールでいうスカウターのように、その人の能力値をスキャンするようなものではないですよね。
なので、評価される立場の人は誰しも、自分の能力や成果を言語化し、上長の期待ときちんと擦り合わせなくてはなりません。現代の、成果に基づく評価制度の中では、このスキルも「仕事ができる人」に求められるもの。どれだけ実務ができても、その成果が組織にとって望ましいものであるとコミュニケーションできなくては、評価されることはないのです。
——自分の実績や成果を積極的に伝えるのが苦手だ、という人もいませんか。
広木:そうですね。個人の資質や価値観はそれぞれですし、特に日本では、自分の正当性や貢献を強調することは美徳に反する、と思われがちですから。単純に、普段自分がやっていることを改めて言語化するのが面倒に感じる部分もあるでしょうし。
しかし現代のほとんどの会社では、「従業員同士、そして従業員と会社はフェアな関係性にある。会社は従業員を、等級制度が定めるルーブリックの期待に対してどの程度成果を出したかを軸に評価する、という契約に則っている」という考えのもとで人事制度が運営されています。上司が部下を評価するためには、部下からの「こういう成果を出しました」「この成果は組織が求める期待に合ってます」という説明が必要です。それがないなら、評価したくても評価できないのです。
視点を変えて、経営者の立場に立ってみましょう。報酬として従業員に支払える原資は限られています。その原資を、「どんな成果を上げているのかよくわからないし、現在の待遇に満足しているように見える人」に対して多めに振り分ける理由はありませんよね。それよりも「事業貢献につながる成果を出しているとわかり、かつ報酬をアップさせることでモチベーションが上がる人」を優先するという判断は、極めて合理的です。
——たしかにそのとおりです。ただ、優秀なエンジニアがそれに見合う評価を受けられていない姿を見るのは、何とも歯がゆいものだと思います。
広木:評価者ももちろん、「この人はそういうのが苦手なんだな」とわかっているので、ある程度汲んで評価することもあります。
ただそのように、過剰に察するようになると「従業員同士はフェアである」という原則に反してきませんか? こうした特定の配慮はすなわち、上司が自分の権限にのっとって、特定の部下を高く評価している、ということになります。それに、上司にとって複数人いる部下の中で、その部下だけを特別にみているというわけですから、いわゆる「ひいき」ともとれます。
この場合、上司とその部下の間には明確な主従関係がありますよね。「上司がある特定の部下に目をかけ、評価を引き上げようとする」のは、日本の伝統的な年功序列的、家父長制的な価値観に近い、といえるのではないでしょうか。
現在、多くのエンジニアは、例えば社員を強制的に転勤させたりしないなど、従業員に対して会社の力が強すぎない会社で働きたいと思っているはず。今私たちが働いている多くの企業はそのような、北米に近い価値観で運営されています。
そうした会社で働きながらも、評価において「察してもらいたい、便宜を図ってもらいたい」と望むのは、前時代的とされる年功序列的な価値観と、現代的とされる北米の価値観のいいとこどりをしようとしているといえます。部下にとって都合のいい制度を望めば、中間管理職として間に立つマネージャーが板挟みになる。これでは組織に歪みが生じてしまいます。
もっとも、その「評価されていない優秀な人」が、「評価されたいわけじゃないから評価のための行動はしないし、結果にも納得している」となれば、それはある種フェアだといえるかもしれませんけれどね。
評価されるための「アピール」は、「自分を良く見せるためのもの」じゃない
——身近に「もっと評価されてほしいと思うエンジニア」がいるときに、できることはありますか?
広木:短期的には自分がその人の代わりに、その人の成果を言語化して評価者に伝えればいいと思います。
中長期的には、自分がマネージャー(=その人の能力をいかして成果を出せるポジション)になれば、その人と一緒に成果を出して、それをさらなる上位の役職者に認めてもらうこともできるようになるでしょう。
しかしこれらを実行するためには、まずは自分自身が「どんな成果を出したのか」「その成果は組織の求めることとどう結びつくのか」を言語化して伝えるスキルを身につける必要がありますね。
——自分の成果を上位者に伝えるスキルを身につけ、それを誰かのために使うのですね。
広木:そうだと思います。成果を言語化して、それと組織が求めることの一致点を見つけて伝えるのは、言ってしまえば「アピール」です。
ただ、勘違いして欲しくないのは、アピールという言葉は「実際以上に良く見せること」ではなく、「組織内の透明性を確保する行動である」ということです。
近年の組織作りでは「透明性」がキーワードになっています。「上の意思決定がどのようになされたのかを、下に対してオープンにする」といった、「上から下」の透明性に言及されることが多いです。
しかし、組織の透明性を担保するためには、「下から上」も必要です。現場で働いているメンバーが、自分たちの取り組みが事業の目的にどう貢献したのかをきちんと言語化することが、組織の透明性を高め、一つひとつの業務を事業や組織に沿ったものにしていくのです。
この透明性を担保する能力の高い人はもちろん評価されるでしょうし、周囲のエンジニアが適切な評価を得られるように働きかけることもできると思います。
——こうしたアピールには、具体的にどのようなスキルが求められるのでしょうか?
広木:自分の成果がどのように事業の目的に貢献したかを言語化する力、そして相手にとってわかりやすい形でアサーティブに伝える力が必要です。
私は能力のあるエンジニアにとって、こうしたソフトスキルは技術力と同じくらい重要で、身につけやすいものだと思います。なぜなら「明確な言語化」とはプログラミングそのものだからです。自分がしたこととその目的を明確かつ論理的に説明する能力は、言い換えれば、目的を的確に設定し、そのための手段を論理的に結びつけていくことであり、これは要件定義や、コードや設計の質に通じますよね。
——それらのスキルを鍛えるためには、できるだけ多くの経験を積む必要がありそうです。
広木:そうですね。ただ、自己の成果の言語化の経験を積める機会は、定期的な評価面談のときのみに限られてしまっている場合がほとんどです。
多くの会社では、評価面談して目標管理して…といった昇給に関する一連のサイクルが、社員にとって負担の大きいものになってしまっています。よく定期昇給のための面談を年に2回など定期的に行っている会社がありますが、私はあまり良くないんじゃないかと思いますね。年度や半期といったスパンで数%ずつ給料が上がるのを繰り返すのは年功序列的ですし。それに半年に1回の頻度では、半年分の「やったこと」を改めて言葉にしないといけないわけですから、綿密な準備が必要です。ものすごく準備して面接に臨んだところで数%しか昇給しないのなら「なんのためにやっているの?」という気持ちになってしまうのも無理はありません。
こうした大掛かりな面談を年に1~2回だけするよりも、期待と成果をすり合わせる活動をこまめに行うようにすることで、評価する方も評価される方もハッピーになれるのではないでしょうか。
具体的には、「期待と成果のすり合わせ」のタイミングを、給与に関わるときと、そうでないときに分けるのです。給与に関わらないすり合わせは、普段の1on1などの際に行います。給与が関わっていなければ、かしこまった準備は必要ありませんから、頻度を高くしても負担が大きくなりすぎません。この繰り返しの中で、ソフトスキルを磨いていく。
逆に給与が上がる際、例えば等級の上昇など、次の役割ができるようになったタイミングでのアセスメントでは、期待と成果の一致を言語化しアピールすることで、転職活動に近い形で伝えて、その結果としてプロモーション(昇格)するのです。これが、普段磨いてきたソフトスキルを試すタイミングとなります。
エンジニアは転職した方が給料が上がるとはよく言いますが、転職でよくある3~4年スパンで見れば、社内で役割が変わったり等級が上がったりする中での昇給幅は、転職した場合と同じくらいといえる可能性はあると思っていて。こうした等級や役割の大きな変化は、多くて年1回あるかないかです。その際に、転職活動時には当然行うアピールが必要になる、といった考え方をすれば、その準備にかかる労力もある程度は受け入れられるのではないでしょうか。
正しい「アピール」ができるようになると、評価へのモヤモヤは晴れていくはず
——アピールのスキルが身につくと、ただ表面を取り繕うだけの「悪いアピール」と、透明性を担保するための「良いアピール」の区別がつくようになりそうです。
広木:そうかもしれませんね。「悪いアピール」と言われるのは、例えば個人の利益のために情報を隠したり、あまりにも我田引水と見られる行為をすることだと思います。
悪いアピールをする一部の人は、むしろアピールのスキルが足りないといえます。多くの人はそもそも、透明性の担保を目的とした、適切な言語化やコミュニケーションをするためのトレーニングを受けていません。そのため、本来の意味でのアピールと、悪いアピール、すなわち嘘をついたり、自分を嘘で塗り固めてよく見せようとする行為の区別がつかないのです。ですから、組織全体でアピールのスキルが上がると「悪いアピール」は消えていくはずです。
ただ、悪いアピールの代表格とされがちな、いわゆる「社内政治」は、必ずしも悪いアピールではありません。
例えば、ある企画を通したいときに、その企画の可否を議論する前に、関係部署の人と擦り合わせたり、人間関係をつくるために飲みに行ったりした人がいたとします。その結果企画が通ると、周囲の人は「あの人はずるい」と感じるかもしれません。でもその人がやったことは、単なるステークホルダーとの合意形成にすぎません。こうした「悪いアピールと誤解されがちなこと」に対する見方も、アピールのスキルが上がるにつれて、次第に変わっていくはずです。
——確かに、一見本質的ではない取り組みで評価されているように見える人も、実は組織にとって重要な働きをしていたのかもしれませんね。
広木:自分の業務が事業にどのように貢献しているのかを言語化できるようになれば、他の人の業務についても、やるべきことかどうかが見えるようになってきます。
それに伴い、組織の中での立ち位置も自然と変わってくるものです。仕事をチームの目的に沿って考える力がある人は、多様なステークホルダーの状況を見極めて行動することができるので、いろいろな仕事を任されるようになるでしょう。
言語化スキルが高まると視野が広がり、その結果、組織の中でのチャンスも広がるということですね。
——視野を広げるために、普段から心がけておくべきことはありますか。
広木:人間には「わからないもの=悪」とみなしてしまう思考の癖が備わっていることは、知っておいた方がいいと思います。
先ほどの「悪いアピール」の話もそうですが、例えばあるメンバーが他部署の人と飲み会に行って、その後案件の話が進んでいることがわかったとき、どうして一部の人は「ずるい」と感じてしまうのでしょうか? それは自分自身がそうした人間関係の形成が苦手であるが故に、そこで行われていることの意味がよくわからないからではないでしょうか。
これは「ハンロンの剃刀(かみそり)」という考え方にも通じるものです。「何か良くないことが発生した場合に、その原因は関わった人の無能にあるのであって、悪意にあるのではない」という意味です。私たちは何か良くないことが起きた時に、その背後には誰かの悪意が働いているのではないかと考えてしまいがちです。しかし実際は、そんなことはないことがほとんどなのです。
大切なのは「人は不完全である」という前提に立つこと。誰も神様のように人の能力をスキャンすることはできないことを認識した上で、適切なアピールを行っていく姿勢が、被評価者には求められているのではないでしょうか。
取材・構成・編集:光松瞳
執筆:一本麻衣
関連記事

エンジニアにとっての成果とは「いいコードを書くこと」——エムスリーVPoEに聞く、エンジニア組織のパフォーマンスを最大化する「評価」のあり方

「サッと助けてくれるエンジニア」は、試行錯誤の質が高い。 nrs氏に聞く「経験の積み方」

給与は自分で決める?!話題の職位ガイドラインを作ったCEOがエンジニアの評価システムを完全公開。その真意とは?
人気記事