最新記事公開時にプッシュ通知します
EMの仕事には「5つの再現性」がある。5社でEM/CTOを歴任する中で、再現性に効いた5+1冊
2025年2月13日

エンジニアがマネジメントに踏み出すとき、今まで向き合ってきた「技術やシステム」と、マネージャーとして向き合うべき「組織や人」の特性の違いに戸惑う人も少なくありません。この連載では、業界で活躍する多くのマネージャーたちに、今に至るまでにどんな本が助けになったのかを紹介していただきます。
第2回に登場いただいたのは、これまで5社でEMやCTOを歴任し、HRBrain社にEMとして入社、現在はVPoEを務める田村祐樹さん。
EMの仕事はチームや会社によって大きく異なるため、「他のチームのEMになったときにも生きるスキルが身についているのか」と悩む人もいます。そんな中で田村さんは、2023年12月のブログでCTOやVPoEと違いEMには再現性があると解説しています。
今回はこの「EMの再現性」とは何かを、EMの役割から分解しながら改めて整理します。
そして、5つの再現性の獲得に役立った書籍や、1冊で網羅できる書籍を紹介してもらいました。
- どの組織でも役立つ「5つの再現性」と「EMがやるべきこと」
- 「5つの再現性」それぞれの習得に役立った5冊
- 網羅性のある1冊は「エレガントパズル」 初心者にも経験者にも役立つ
- 「5つ」の中には、EMになる前から身についていくものもある
- どの会社でも「EMのやるべきこと」は変わらない
どの組織でも役立つ「5つの再現性」と「EMがやるべきこと」
――ブログにあった「EMの再現性」とは何か、改めて教えてください。
田村:今までの経験から「EMとしてのポータブルスキル」を改めて言語化し、5つにまとめたものです。
・先読みして有事に備える
・適切に判断し、Noと言う
・評価を勝ち取る
・開発者体験(Developer Experience)を高める
これらのスキルはEMとしての役割を果たす中で、どの組織でも共通して役立っています。
――EMの役割を果たすためには、具体的に何をやるべきでしょうか。
田村:EMの役割は「CTOやVPoEが定めた組織の方向と、チームの方向を合わせ、チームのアウトプットを最大化すること」です。
これを果たすためにやるべきことは、主に4つのステップに分けられます。
ステップ1:「組織のシステム」をアーキテクチャとして理解する
マネージャー職に就くと、それまでより膨大な情報に触れることになります。CTOやCEOなどステークホルダーと接する機会も増え、会社の売上やプロダクトの状況などに、より深く触れるようになるからです。
この膨大な情報を整理して、自身やチームのやるべきことを明確にしていくために、まずは「組織のシステム」を理解する必要があります。自分たちの組織やプロダクト、売上がどのように計画され、何を達成しようとしているか。コミュニケーションの仕組みはどうなっていて、決裁者は誰で、どういう提案をすると通りやすいか。この構造が理解できていることが、EMの役割を果たす基礎となります。
ステップ2:「組織が目指す方向」を理解し、「チームが目指す方向」を定める
ステップ1で整理した「組織のシステム」をもとに、膨大な情報から「組織が目指す方向」や「組織からチームへの期待」を掴みます。組織は何を達成したくて、そのために自分のチームはどういう役割を担っていて、何を達成するべきかを、明確に理解するのです。
組織の期待と現在のチームの状態のギャップが大きく、期待されている時間軸で期待通りの成果を出せる見込みが薄い場合は、CTOやVPoEに、現実的な期待感を持ってもらうようコミュニケーションをとります。
ここまでのステップを適切に踏めているかが、以降のステップでの取り組みが実るかどうかを左右します。
ステップ3:ステップ2までで決まった方向に向かって、チームのアウトプットを最大化する
チーム全体の方向性を合わせながら、各メンバーの成長を促してできることを拡張したり、生産性やパフォーマンスを上げたりと支援していきます。成果を出す過程にある障害物を取り除くこともあります。
ステップ4:チームが出した成果に対して、組織から適切な評価を得る
チーム全体でつくりあげた成果を、組織に適切に評価してもらえるように働きかけます。これはEM自身の評価とも直結しているだけでなく、チームのモチベーションやエンゲージメントを維持・向上するために非常に重要です。
――このステップの中で、「EMの5つの再現性」はどのように発揮されるのでしょうか。
田村:主にステップ2以降で役に立ちます。
再現性1:チームの状態を正しく把握する
ステップ2で「組織からチームへの期待」を掴んだら、それは今のチームで実現できるのかどうかを判断することになります。その際にこのスキルが必要です。
今のチームに本当に人が足りないのか、メンバーのスキルが足りないのか、うまく動ける状態か、そうでないか。その原因は、やろうとしていることが多すぎるのか、それとも間違っているのか。これを正しく把握することで、期待値調整の必要があるかどうか、チームが成果を出すためにどんな取り組みが必要かを判断できるようになります。
再現性2:先読みして有事に備える
このスキルはステップ2~3において必要です。チームの状態は流動的で、主に、退職、上層部の意思決定などの内的要因や、事業や市場の変化などの外的要因によって変化します。組織の期待とチームの状態のギャップをつくらず、組織が求めることを果たせるチームをつくっていくためには、これらの変化を予測し先回りして、判断したり備えたりする必要があります。
再現性3:適切に判断し、Noと言う
ステップ3で、組織がチームに求める成果を着実に生み出していくためには、チーム内外に対して「No」と言う必要があります。「やらないこと」を決められるのは、チームにおける意思決定者、すなわちEMです。チームが間違ったことに取り組もうとしているなら止めなければいけませんし、チーム外からの脅威にさらされるべきでもありません。チームがやるべきことに集中してアウトプットを出せるようになるために、「No」を伝え納得してもらうスキルが必要です。
再現性4:評価を勝ち取る
このスキルはステップ4のために必要になるスキルです。組織が求める成果をチームに設定するのがEMである以上、その成果を達成した際に評価を勝ち取るのもEMの役割です。チームのやっていることの重要性や必要性を正しく組織に伝播させ、評価を得なくてはなりません。
再現性5:開発者体験(Developer Experience)を高める
ステップ1~4を繰り返し、チームがある程度機能する状態になったら、そのアウトプットを最大化するために、開発者体験の向上に取り組む必要があります。
開発者体験の向上は、チームメンバーの生産性が高まるだけでなく、モチベーションアップ、離職率の低下、仕事に対する満足感の向上に直結しています。ツール、プロセス、ポリシー、アーキテクチャ、ドキュメント、文化など、開発者の体験を構成する要素は無数にあります。これらの中から、チームに与えるインパクトが大きい施策を適宜実践していくのです。
「5つの再現性」それぞれの習得に役立った5冊
――5つの再現性を身につけるために、それぞれおすすめの書籍はありますか。
田村:読んでよかった書籍はたくさんありますが、それぞれ1冊に絞って紹介しますね。
「チームの状態を正しく把握する」に関しては、「世界はシステムで動く ―― いま起きていることの本質をつかむ考え方」をおすすめしたいです。
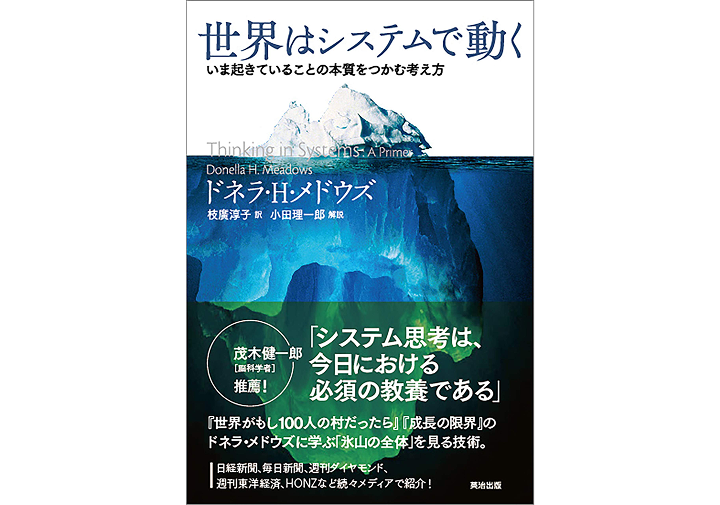
田村:この本は「システム思考」という、物事を大局的に捉える方法を教えてくれます。
チームではいろんな出来事が起きる。その出来事の裏側にある「構造」をシステムとして捉えると、「チーム」も「組織」も「システム」で動いていると理解できるようになります。この考え方を身につけることで、チームの状態をフラットに正しく把握できるようになっていきました。
「先読みして有事に備える」には「デッドライン」という、プロジェクトマネジメントにおける様々な法則を教えてくれる本が役立ちました。

田村:プロジェクトは常に問題を抱えており、過去うまくいったことでさえ、タイミングや状況によっては問題になってしまいます。つまり、プロジェクトに関わるすべてのことが問題になりえる。だからこそ、その機序を普遍的な法則から学んでおくと、先読みもできるようになるのです。
「適切に判断し、Noと言う」ためには「エッセンシャル思考」が役立ちました。
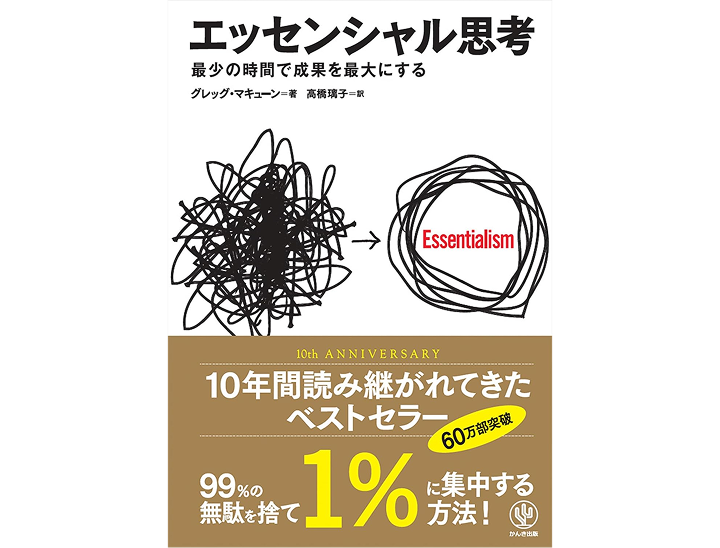
田村:この本は「物事の大多数は不要である」という考え方のうえで、どれが「必要」なのかを判断する方法を解説しています。
EMとして有限の時間と有限のリソースを扱う上では、意思決定の基本である「選択と集中」を身につける必要があります。大事なことは極限まで絞り、大事なこと以外には「No」と言うべきだと、この本に教わりました。
「評価を勝ち取る」スキルを得るには、「HIGH OUTPUT MANAGEMENT」から多くを学びました。
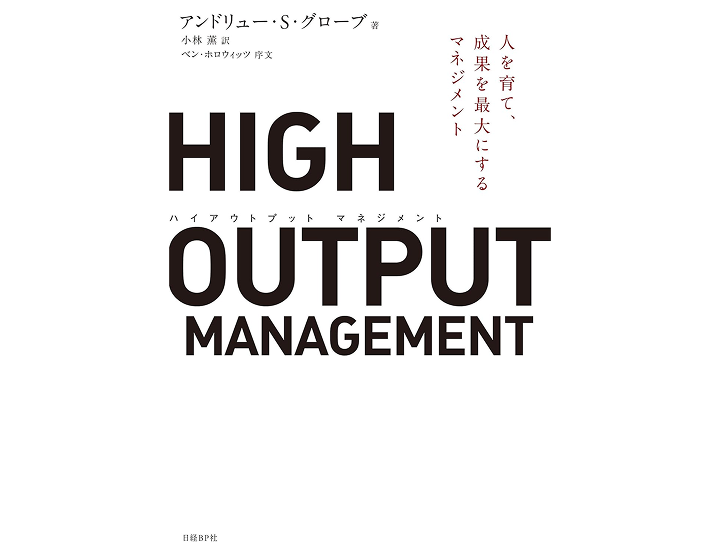
田村:これは「アウトプットとは何か?」について深く考えさせられる本です。
チームが評価を得ようとした時、エビデンスとなるアウトプット、アウトカムが必要になります。「アウトプットとは何か」を理解することで、チームやメンバーへの期待や成果の定義が明確になり、適切な評価を得られるようになっていきます。
「開発者体験(Developer Experience)を高める」には、「LeanとDevOpsの科学[Accelerate]」が非常に参考になりました。
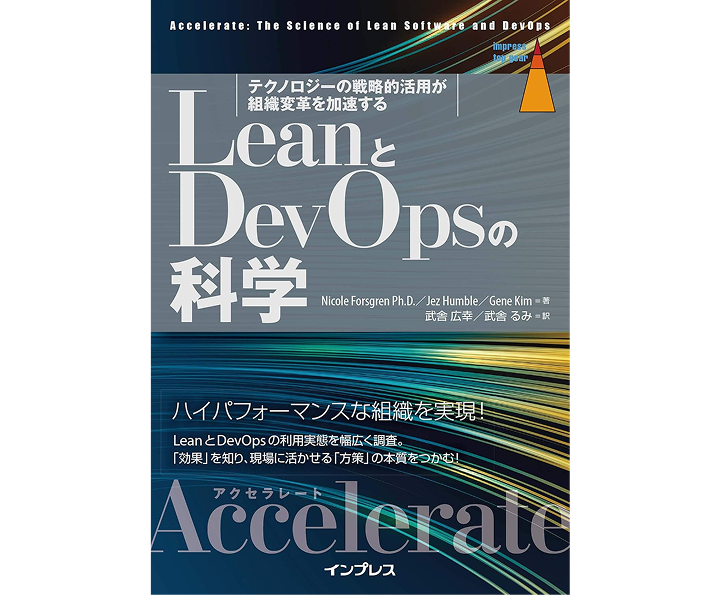
田村:開発者体験を測る指標は様々で、この本で紹介されているDORA (DevOps Research and Assessments)指標値がすべてだとは思いません。ただ、DORA指標値は多くの組織で利用されているため、まずはこの本を読むことから始めるとよいと思います。真っ当な開発環境で真っ当なことをやれている組織やチームは強いからです。この「真っ当」を知るにも良い書籍です。
さらに先に進めたい場合はLaura TachoのWhat Dashboards Don’t Tell Youを観てみてください。
網羅性のある1冊は「エレガントパズル」 初心者にも経験者にも役立つ
――ほかに、田村さんがこれまで出会った中で、特に役立った書籍があれば教えてください。
田村:初めてEMになった人にも、そうでない人にも「とりあえずこの1冊」とおすすめしたい書籍があります。それは「エレガントパズル エンジニアのマネジメントという難問にあなたはどう立ち向かうのか」です。著者のWill Larsonが、Digg、Uber、Stripeでの具体的な経験を、体系立った内容として記しています。
これからEMになる方にとっては「エレガントパズル」の示してくれる具体的な行動は試すに値するものと考えています。私が挙げた「再現性」を持つためのスキルの獲得にも広く役立つ実用的な本です。また、EMを複数回経験した私にとっても、これまでマネジメントに関連する本を多数読んで実践しながら得てきた感覚値を、体系だった知識に落とし込むきっかけとなった本でした。
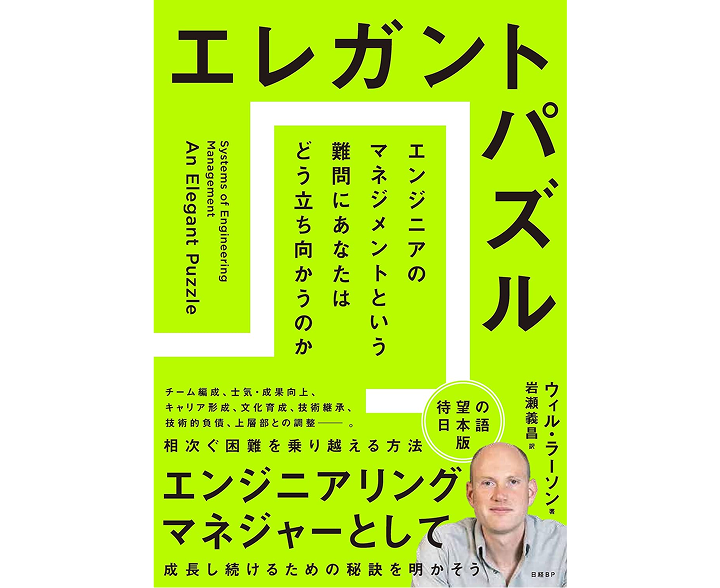
田村:業務の中で特に役立った箇所は「チームへの向き合い方」です。この本では、チームを4段階に分け、「遅延」「現状維持」「負債返済中」「革新」と名付けています。
この定義があることで、採用などチーム組成の際に、どんな人が必要かをフラットに検討できます。また、複数のチームの状況を把握して手を打つべきときにも、各チームの状況をシンプルに整理して打ち手を考えられるようになりました。
「エンジニアリングマネージャーが行き詰まりを感じない方法」も有益です。うまくいかなくなるのはどんな時なのか、そうならないようにどうするべきかを学べます。「燃え尽き症候群にならないためのアドバイス」は、EMとして戦い抜くためにもっと早く知っておきたかったですね。
ちなみに著者のブログである「Irrational Exuberance」も非常に示唆に富んだ内容になっています。
EMが数歩先に進みたいとき、もしくは突然VPoEやCTOに任命されてしまった時の1冊
まだ邦訳が出ていませんが、「エレガントパズル」と同じ Will Larson の「The Engineering Executive’s Primer: Impactful Technical Leadership」がおすすめです。
これはEMの一歩先である「Engineering Executive」に関する本ですが、EMとしてCTOやVPoEの責務を理解し能力を伸ばしていくのにも非常に有用でした。
「5つ」の中には、EMになる前から身についていくものもある
――5つの再現性のあるスキルを、田村さんはどんな順番で身につけてきたのですか。
田村:最初に挙げた順番で、1つずつ身についてきたように思います。
「チームの状態を正しく把握する」が最も早く身につきました。これは、テックリードをやっていた時とも通じるスキルです。マネジメントの経験がなくても、複数のチームに所属したことがあれば習得は難しくないはずです。
「先読みして有事に備える」も、マネジメントレイヤーでなくても、ある程度は身につけられます。同じ会社で数年働いていれば、チームのメンバーが辞める、上層部が方針を変える、市場に大きな変化がある、などは経験してきているはず。「先読み」は少しずつできるようになるでしょう。マネージャーとしてこれらを気にする必要が出てくると、より正確な「先読み」「備え」のスキルがついていきます。
次に「適切に判断し、Noと言う」スキルが身につきやすいと感じてます。
テックリードやリーダーをやったことがある人は、「それはできません」「こうすればできると思います」といったコミュニケーションの経験はあるはずですから。ただ、マネージャーになると、チーム単位ではなく全体最適を考えて、Noと言うべきポイントを考えなければいけないので、少し時間がかかりました。
「評価を勝ち取る」には、一定の時間がかかりましたね。「評価がどう決まるのか」を理解するには、複数回の評価会議で様々なパターンを経験する必要があります。評価の観点や決まり方は一定ではなく、少しずつ変化しますから。
例えば、会社の状況が上向いていれば良い評価を得るのは容易になり、芳しくなければ評価を得るのは難しくなる、というような「状況変化」があります。また、評価の最終決定者が持っているバイアスに、最終評価が左右され、見極めや交渉が必要になるケースもしばしばあります。
「開発者体験(Developer Experience)を高める」の獲得は最も難しいです。そもそも正しい答えがない分野ですから。
近年はDORAやSPACE指標値が注目されていますが、個人に落とし込んでみると「やりたいことがやれているか」「チームや組織に尊敬できる人がいるか」「自己効力感を高められているか」など、数値化しづらい項目も多いです。だからこそ、マネジメントを担う上では、どんな立場になってもこのスキルを磨き続ける必要があると感じています。
どの会社でも「EMのやるべきこと」は変わらない
――最後に、今までの経験の中で、田村さんが「EM」をはじめとしたマネジメントレイヤーを務めることをどう捉えてきたのか、教えてください。
田村:私が最初にマネジメントに接したのはgumi社で技術開発部長になった2011年、31歳の時でした。これはCTOの直下で、実質的に開発組織を動かすポジションです。
組織が5年で80名から800名に拡大していく中でテックリードやEMを任命したり、採用したりしなくてはなりませんでした。マネジメントに取り組むのは初めてで、たくさん失敗しました。EMに何を求めるべきかもわからなかったですし、権限委譲もうまくできなかったので。
試行錯誤を続ける中でCTOが退任し、自分がCTOとなったのがきっかけで「EMとは何をする人か?」をより深く考え始めることになりました。
ディライトワークスに転職しCTOになった際も、マネージャーのいない小さなチームから、5年で40名→400名への組織拡大を経験しました。gumiに引き続き「急速に成長する組織での組織マネジメントとは?」という課題に向き合う中で、ピープルマネジメントの考え方や委譲のしかたが次第に固まっていきました。
組織が急拡大する中で権限委譲は必須で、できなければメンバーの挑戦の機会を奪うことにもなりかねない。適切なメンバーに適切な挑戦を委譲し、手法ではなく考え方や方向性を伝えて、答えを自分で出してもらえるように努めました。また、成長する組織というのは「強い個」によって為されるのではなく、「強いチーム」の連なりが組織を形成して為されるものだと強く感じました。
次に勤めたスマートニュースでは当初からEMとして参画し、チームの強化を行いました。グローバル環境で、複数チームにまたがる6名のマネジメントから始まり、2年後には国籍の違う様々なメンバー23名のマネジメントを行いました。
話す言語が日本語から英語になり、それぞれ違うカルチャーを持つメンバーと接する中で、「環境が変わっても、EMがやるべきことは変わらない」と気づき、うまく整理できたタイミングでもありました。
gumi、ディライトワークス、スマートニュースとそれぞれの会社が掲げるビジョンは異なります。しかしEMの役割はいつも「組織とチームの方向性をそろえた上でアウトプットを出す」ことでした。これは、その後のキャリアであるMFS、estie、現在所属するHRBrainでも変わらないと感じています。
これまでたくさんの本を読み、実践し、失敗と試行錯誤を繰り返して今があります。「日本を変えられるようなインパクトのある仕事をしたい」というモチベーションとともに、ここまで歩んできました。HRBrainで働くことに決めたのは「働く人が正しく評価され、働く時間が最小化しながらも成果は最大化し、自己効力感の高い働き方ができる世界」が実現できると思ったからです。マネージャーとして良いチームをつくることで、日本全体を変えていけたらうれしいですね。
取材・構成・編集:光松瞳
関連記事

誇り高き「マネージャー」を全うするために。“理想のEM”小田中氏を支えた珠玉の5冊
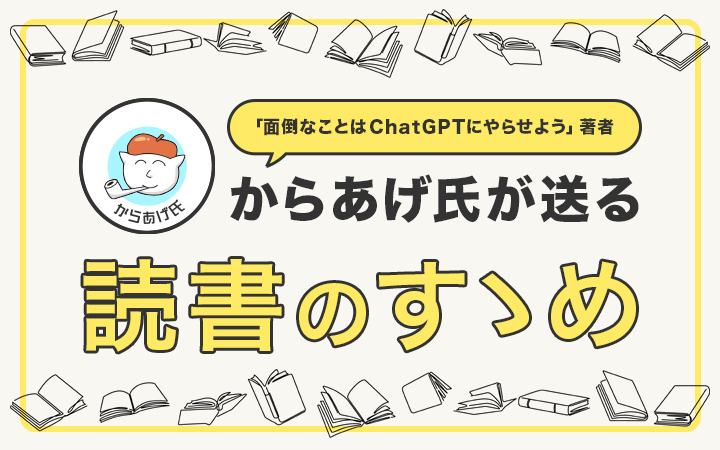
圧倒的な読書量を誇るからあげ氏が実践・読書との向き合い方
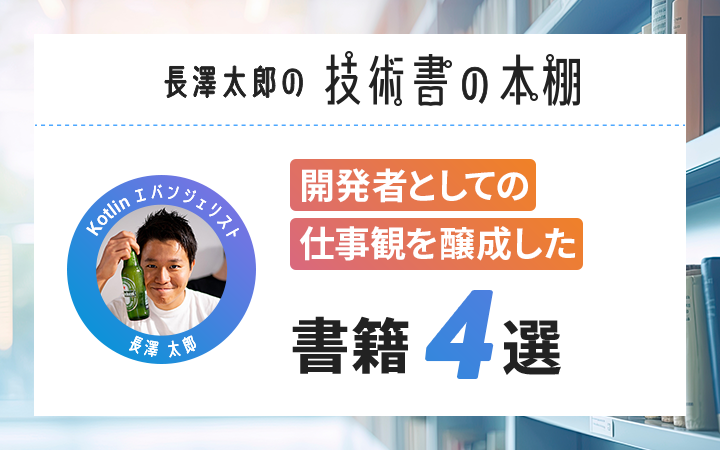
行動の選択肢を広げる。Kotlinエバンジェリスト・長澤太郎氏が選ぶ、キャリアを切り開いた書籍4選
人気記事







