最新記事公開時にプッシュ通知します
誇り高き「マネージャー」を全うするために。“理想のEM”小田中氏を支えた珠玉の5冊
2024年6月20日


株式会社カケハシ EM
小田中 育生
筑波大学大学院修了後、外資系半導体企業を経て、2009年に株式会社ナビタイムジャパンに入社。2019年からはVPoEを務める。2023年10月に、EMとして株式会社カケハシに入社。薬局DXを支えるVertical SaaS「Musubi」をコアプロダクトに位置づけ、「しなやかな医療体験」を実現するべく新規事業のプロダクト開発にコミットしている。著書に『いちばんやさしいアジャイル開発の教本 人気講師が教えるDXを支える開発手法』(2020年、インプレス、共著)がある。
X
note
エンジニアがマネジメントに踏み出すとき、今まで向き合ってきた「技術やシステム」と、マネージャーとして向き合うべき「組織や人」の特性の違いに戸惑う人も少なくありません。
エンジニアとしてキャリアをスタートし、今はエンジニアリングマネージャー(以下EM)、VPoEなどマネージャーとして活躍されている方々も、これまでマネジメントにおける様々な「うまくいかない!」に直面し、それらを突破してきました。
この連載では、業界で活躍する多くのマネージャーたちに、今までどんな困難にぶつかってきたのか、また、そのときどんな本が助けになったのかを紹介していただきます。
第1回に登場いただいたのは、株式会社カケハシでEMを務める小田中育生さん。同僚からも「理想のマネージャー」と称される彼も、今までにたくさんの困難を乗り越えてきたそう。マネージャーとしてのこれまでのキャリアを、書籍と一緒に振り返ります。
- 『ピープルウェア第2版』マネージャーという仕事の“手ごたえのなさ”と向き合う
- 『「影響言語」で人を動かす』コミュニケーションを諦めず、感情と向き合う
- 『GTD 実践編』『コンフリクト・マネジメントの教科書』ステークホルダーの「板挟み」に立ち向かう
- 『恐れのない組織』組織と向き合うために、現状維持バイアスと闘う
『ピープルウェア第2版』マネージャーという仕事の“手ごたえのなさ”と向き合う
——今日はよろしくお願いします。まず最初に、初めて「マネジメント」という仕事に触れたときのことについて教えてください。
小田中:キャリアの中で初めて「マネージャー」になったのは、2013年4月、働き始めて7年目の頃でした。担当していたのは、当時所属していた企業のコア技術を扱うチーム。複数の事業からの要望に応えて新機能を開発したり、顧客の声に耳を傾けながら地道な品質改善活動を行ったりするチームです。マネージャーになったのは、創業期から積み上げてきたシステムのフルリプレイスにも着手し始めたタイミングでした。
ステークホルダーマネジメント、プロジェクトマネジメント、そしてピープルマネジメントが同時に求められる状況でしたね。
——初めてのマネジメントなのに、かなり骨のあるシチュエーションだったんですね。
小田中:そうでしたね。ただ当時は、マネージャーとしての自分の仕事に手ごたえを感じられなかったことが、何よりつらかったです。
エンジニアとして手を動かしていたときは、ビルドが通り、テストが通り、プログラムが期待通りに動作することから、自分の仕事への手応えを即座に感じることができていました。しかし、マネージャーに期待されている仕事からは、そういった直接的な手応えを得ることはなかなか難しかったんです。
タスクの優先順位を決めたり、チームの構成を変更したりして、様々な試行錯誤をしていましたが、これらの取り組みの結果を知るのは、長い時の試練を経た先のこと。自分が一生懸命やったことが「最良の選択であったかどうか」はその場ではわかりません。良かれと思ってやっているけど、「この取り組みはただの自己満足なのではないか?」という所在なさを日々感じていました。
——その困難を突破するきっかけとなった書籍は何でしょうか。
小田中:『ピープルウェア第2版』です。
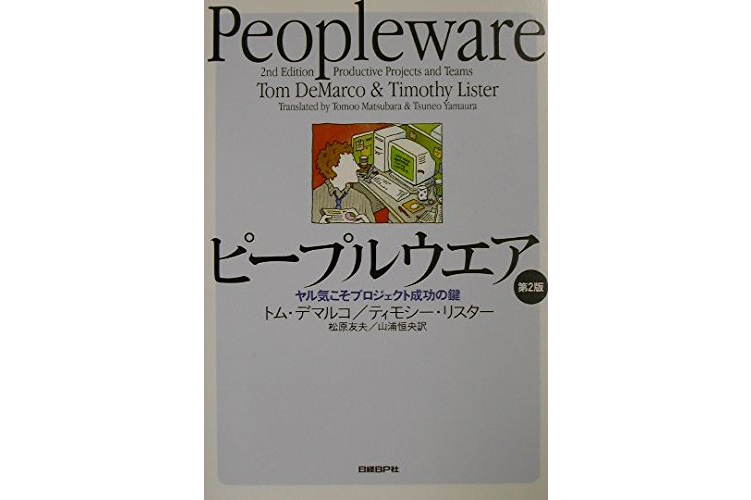
小田中:この本を読んで、私は自分がマネージャーとしてのメインミッションを捉え違えていたことに気づきました。
私はマネージャーとなった当初、開発者体験の向上にフォーカスすること、プロジェクトの工程に転がる障壁を取り除くことを、自分のミッションだと捉えていました。もちろんこれらも大事ですが、結局は「人」なんです。
——「人」、といいますと?
小田中:ビジネスとしての開発はチーム戦ですから、特定のメンバーだけがパフォーマンスを発揮しているような状況は好ましくありません。マネージャーがメンバー全員のパフォーマンスを引き出し、チームとしてまとめていく必要があります。
でも、モチベーションの源泉は千差万別です。とにかく機能をつくることを楽しむ人もいれば、きっちりと品質をつくり込むことにやりがいを見出す人もいます。そうした異なる人々が、皆いきいきと働けるようにすることこそがマネージャーの仕事だと、この本に教えてもらいました。
そのおかげで「いかに開発をスムーズに進めるか」にばかりフォーカスするのではなく、メンバー一人ひとりにモチベーションを感じてもらえるよう、マネージャーとしていかに働きかけるべきかを大切にするようになりました。
——先ほどの「手ごたえが感じられない問題」については、どんな変化がありましたか?
小田中:「人」に目を向けられたおかげで、メンバーたちが活発に対話をしている様子など、「人の状態の変化」から手応えを感じられるようになりました。
マネージャーの仕事は、メンバーのパフォーマンスを最大限引き出し、組織が求める成果につなげていくこと。チームにいる一人ひとりが自己実現を果たしながら、それが組織の成長につながり、世界をよりよいものにしていくことです。この本がそう教えてくれたから、関わる人全てにポジティブな作用をもたらしうるこの仕事は、とても誇らしいものだと感じられました。
『「影響言語」で人を動かす』コミュニケーションを諦めず、感情と向き合う
——マネージャーとして働く中で、「人の感情に向き合うこと」に困難を感じる人も多いです。小田中さんはどうでしたか。
小田中:私もマネージャー職になる前からずっとそう感じていました。
人の気持ちは目に見えない。でも何かあったときはすぐに対処しないといけません。時間が経過するとともに、適切な対処をすることがどんどん難しくなっていきます。そのうえ、対処が適切だったのかは、その場でわかるわけではありません。他人の気持ちとの対峙は、なかなか手ごわいものですね。
——「人の感情」について、小田中さんはどんな困難に直面しましたか。
小田中:複数の人間が協働するなら、ちょっとしたコンフリクトはつきものですが、それにどう対処したら「適切」なのかについて戸惑っていました。
実体験をお話しますと、当時自分がマネージャーを務めていたチームのリードエンジニアと若手エンジニアの間でコンフリクトが発生していました。パフォーマンスが出ない若手に対して、リードエンジニアは「やる気があるならわからないことは聞いてくるはずだ」と不満をもっていました。一方、若手エンジニアからすると、「リードエンジニアは日々忙しい。質問したら“こんなこともわからないのか”と怒られてしまうんじゃないか」という不安から、彼に質問できず、仕事の遅れにつながっていました。
リードエンジニアは自分で困難を切り拓いてきたからこそ「質問するのをためらう」という若手の気持ちがわからない。一方で若手は「困ってるのになぜ助けてくれず、怒るんだろう」とつらく思ってしまう。マネージャーである私としては正直、「聞いてねって言ってるのになんで質問しないの?」って思っちゃうリードエンジニアの気持ちも、できる先輩に質問することをためらってしまう若手エンジニアの気持ちも痛いほどわかる。だからこそどう対処するべきか‥と思い悩んでいました。
——この時に助けになった本は何でしたか?
小田中:『「影響言語」で人を動かす』です。
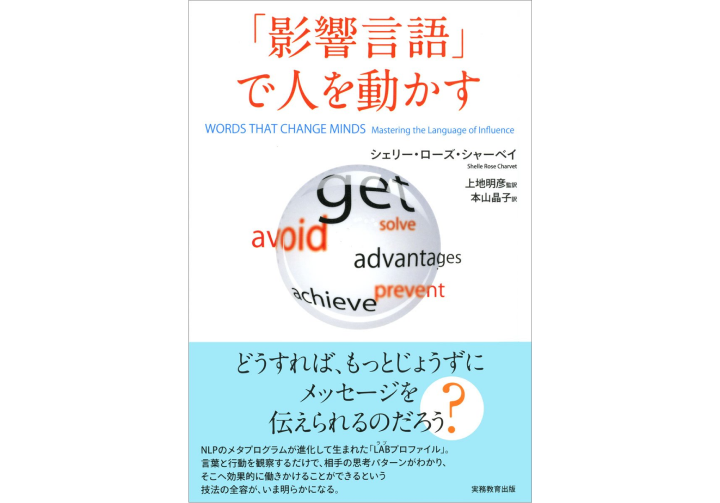
小田中:この本は「人には様々な志向性があること」「志向性によって、響く言葉は違うこと」を教えてくれました。
それまでは、人それぞれ考え方は違うんだと意識しながらも、自分のなかで「こうあるべきだ」と固執した考えを持っていて、それと異なる部分には寄り添いきれず、かける言葉が見つからないことがありました。でもこの本を読んで、異なる考え方を持つ人に寄り添うための言葉を見つけられた気がします。
先ほどのコンフリクトについても、当時はコミュニケーションによる解決がうまくいかず、組織改編のタイミングでそれぞれ違うチームにアサインしました。対処が遅れたら双方のメンタルが悪化するなど、もっと大きな問題になっていたかもしれませんから、これは当時できる最善解だと思っています。
でも、この本を読んでから振り返ると、もっとやれることはあったはずだと思います。ふりかえりの場で相互に話し合ってもらったり、私との1on1を通して自分と違う考え方をコーチングしたり、コミュニケーションによって相互に理解し合うことを目指せたはずでした。こうした対処法が思い浮かび、同じようなことがあったときに相互理解を促せるようになったことも、この本に助けられたからこそです。
——コミュニケーションの柔軟性が上がったことで、うまくいったことはありましたか?
小田中:たくさんありますよ。1つ分かりやすい例を挙げるなら、エンジニアばかりのチームに、営業畑のメンバーがジョインしたときのことです。
営業畑のメンバーはことあるごとに「絶対いけるよ」「これで目標達成できるよ!がんばろう!」と発破をかけますが、エンジニアたちはいまいちそれにノッていけませんでした。これはまさに「響く言葉」が掛け違っていたからです。
当時ちょうど「影響言語」について知ったタイミングだったので、その営業畑のメンバーに「エンジニアは『絶対』っていう言葉を好まないし、目標達成とモチベが密接しない人もいますよ」と伝えました。彼はものすごく驚いていましたね。その後、彼自身が「エンジニアに響くコミュニケーション」を模索していったことで信頼関係が生まれていき、チームとしてまとまっていったんです。異なるバックグラウンドの人同士でも、適切な言葉でコミュニケーションができれば、いいチームになれるんだという手応えを感じました。
『GTD 実践編』『コンフリクト・マネジメントの教科書』ステークホルダーの「板挟み」に立ち向かう
——利害関係の異なるステークホルダー同士の合意形成や説得のシーンも、マネージャーならではの難しさです。小田中さんはいつ頃この問題に直面しましたか?
小田中:マネージャーになったばかりの頃からずっと向き合い続けています。組織に通底する暗黙のコンテキストなど、ざっくりいうと「政治的」な難しさを実感するようにもなっていきましたね。
ステークホルダーの主張は往々にしてお互いに食い違いますが、対話を重ねるうちに、事業の成果を最大化するという観点では、それぞれ正しいことを主張しているんだとわかってきます。その中で取捨選択をし、自分の判断について全てのステークホルダーに理解してもらい、協力してもらうことこそ、ステークホルダーマネジメントの難しさだと感じています。
——具体的にどのような難しさがあるのでしょうか。
小田中:取捨選択のときは、関わるステークホルダーの想いや会社としての戦略など様々なことを考慮に入れて意思決定します。でも、その意思決定のために得られる情報は断片的ですし、ステークホルダーたちが持っている情報の粒度や範囲もそれぞれ異なります。そのため、私の決断が誰から見ても正しいとは言い切れないのです。
その意思決定をあらゆるステークホルダーに納得してもらうために、自分が普段意識していない観点について学んだうえで説明し、理解してもらう必要があります。たとえば、ビジネスに直結する価値創出と比べて、開発生産性向上など後から効いてくるタイプのアクションは、どうしても後手に回りがちです。そうならないために、開発生産性指標について理解し、収益構造とどうつながっているか説明し理解してもらわなくてはいけません。そのためには、ステークホルダーが関わるビジネス領域に関する基礎知識や、利害関係者たちがもつ収益構造など、今まで自分の土俵になかった知識を、広く深く理解しておく必要があるのです。
また、ステークホルダーが自身のレポートライン上にいる場合「その人の意見を聞かないと評価に不利ではないか」という気持ちが働いてしまう点も、無視できない難しさですね。
——ステークホルダーマネジメントの困難を乗り越えるために、読んでよかった書籍は何ですか。
小田中:『GTD 実践編』と『コンフリクト・マネジメントの教科書』の2冊です。
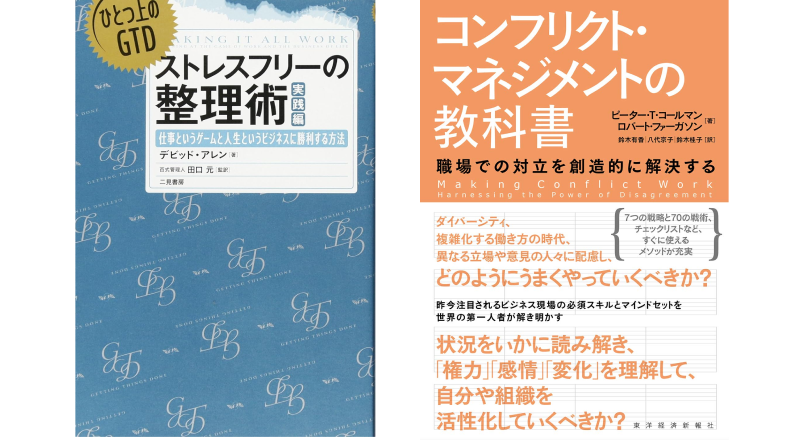
小田中:1冊目の『GTD 実践編』は、大きな困難も、1つ1つ取り組めば必ず乗り越えられることを教えてくれました。ステークホルダーの間でうまく立ち回らないといけないという「板挟み」という状況と真っ向から向き合うときも、仕事を小さく分解してひとつずつ片付けていけば、ちゃんと前に進んでいける。ステークホルダーの顔を立てるために全部の仕事を並行して進めるのではなく、勇気を持ってタスクに優先順位をつけると、結果的にはスピードが出るのです。
2冊目の『コンフリクト・マネジメントの教科書』からは、コンフリクトとは「あってはならないもの」ではない、と学びました。それまでは、コンフリクトは不和や不完全さから生まれた、あまり健全じゃないものだと思っていました。でもこの本には、「コンフリクトは異なる視点、価値観、期待から生まれるもので、健全なコンフリクトは場に多様性を生み出すポジティブなもの」とあり、そういう捉え方もあるのか!と目から鱗が落ちたようでした。それ以降はちょっとしたコンフリクトがあっても「うっ」とならず、ポジティブに捉えられるようになりましたね。
また、この本には、話を聞くことの大切さも丁寧に記されています。相手と向き合って、ニーズを汲み取り、なぜそれをやってほしいのか、なぜ今なのかを聞いて、読み解いていく。この営みによってこそ、コンフリクトを良い機会に転換することができるのです。
『恐れのない組織』組織と向き合うために、現状維持バイアスと闘う
——小田中さんは今、EMとして組織を率いていますが、「組織」という「人の集合体」のマネジメントには、どんな困難がありますか。
小田中:より良い組織をつくるために変化を起こし続けることは、やっぱりとても難しいものですね。
組織には往々にして、現状の姿を維持しようとするバイアスが働きます。新しい提案が出てきたとき「うちには合わないかな」「今、別に困ってないから」といった、変化に否定的な意見が出てきたり。変化を起こそうとする人は、もちろんその変化によって良いことが起こると信じているからやりたい。けれどもそれ以外の人にとっては、前提知識が足りない中で、良いことが起きるかどうかはわからない。するとその不安が言葉を通して、変化を起こそうとする人にも伝わって、組織全体が現状維持モードになってしまうのです。
加えて、特に成熟した組織では、個が主流から外れた発言をしづらくなるメカニズムも同時に働きます。新しい提案は、既存のあり方への批判とも捉えられます。「こうしたらもっといいはず」というアイデアがあったとしても、提案することで抵抗に遭ったり、ともすると関係性の悪化につながってしまったりもする。そう思うとマネージャーとしても、いいアイデアを持っている人の背中を手放しに「いいじゃん!やってみなよ!」と押すわけにはいきません。
さらに厄介なのは、組織を現状維持に向かわせるバイアスは組織にいる全員にかかりうることで、それに気づかずにいる人も多いです。自分にかかっているバイアスは、「こういうバイアスがかかっているんだ」と自覚することで、ある程度向き合えるでしょう。一方、他者のバイアスは、本人が無自覚だからと「あなたバイアスかかってますよ」と指摘してしまうと、こじれてしまうだけです。丁寧にその人の考え方と向き合っていく必要があります。
——より良い状態に向かっていきたいけれども、変化はときにハレーションを生む。ままならないものですが、この困難に立ち向かうヒントは、どんな本から得ていますか。
小田中:『恐れのない組織』です。
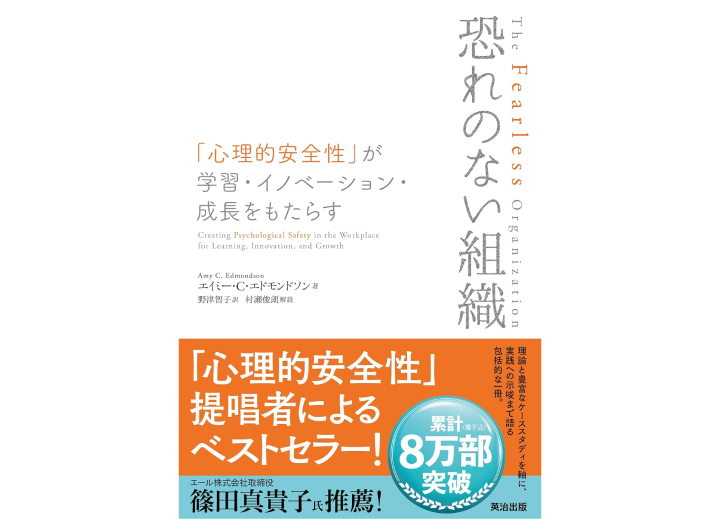
小田中:この本は、いわゆる心理的安全性について書かれたものです。心理的安全性のない組織とある組織の違いや、そこにあるメカニズムを理解し、自分がどのようにアプローチしていくべきか考えるきっかけになりました。
私たちを現状維持の重力に縛り付けるのは、「こんなことを言ったら罰せられるのではないか、笑われるのではないか」といった恐怖です。現状維持バイアスに負けず、より良い組織を追求し続けるには「変化を起こそうとした人が罰せられない・バカにされない」という安心感、つまり心理的安全性が必要不可欠なのです。
当初、心理的安全性という言葉の響きからは「嫌な思いをさせない」という生ぬるさを感じており、あまり好んでいませんでした。しかし、この本を読んで、本来の意味での心理的安全性を理解し、それ以降は重要なファクターだと考えています。
——最後に、10年間マネージャーとして働いてきた中で得た、最も大きな収穫について教えてください。
小田中:この10年間、マネージャーとして数え切れない失敗を繰り返しながら進んできました。その中でも、記憶に残るような成果をいくつか世に出せたこと、そしてそれを共につくり上げたチームメンバーたちと一緒に成長できたことが、何よりの収穫です。
マネージャーとして人を成長させるスキルを身につけられたという自負と、ともに働いてきた人たちが今もいきいきと働いているという喜びが、マネジメントという仕事への私の情熱の源になっています。こうしてもらった情熱を、今いる組織やメンバーに届けられるよう、これからもますます努力していきたいですね。
取材・構成:光松 瞳
編集:王 雨舟
関連記事
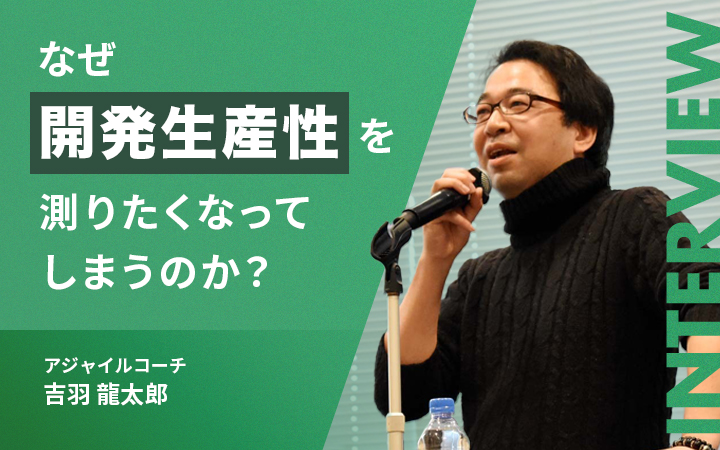
実は相性が悪い「開発生産性」と「アジャイル」。うまくいかない開発を好転させるためにPMがやるべきこととは【ryuzee|吉羽龍太郎】

うまくいっていても、組織にはスクラップアンドビルドが必要。タイミーが「短期的な非合理」を選び続ける理由【kameike×赤澤】

「いらない機能はさっさと消したい」負債解消の初手「消す」を組織全員で実践する方法【Sansan西場正浩】
人気記事






