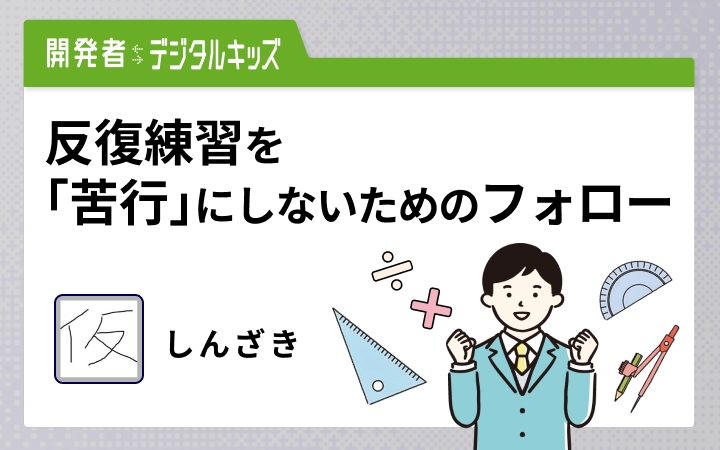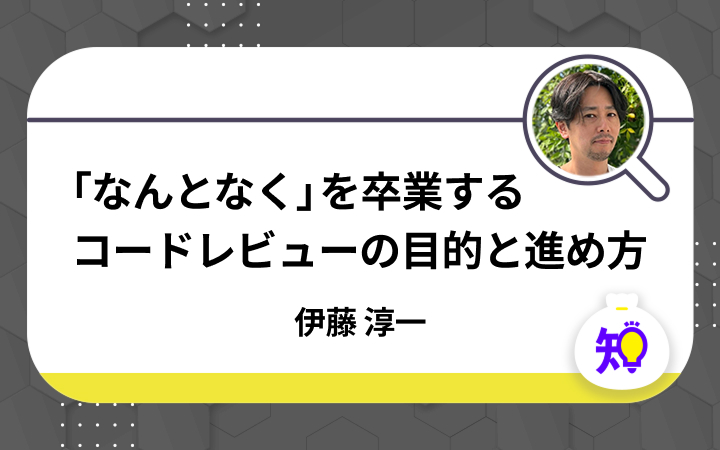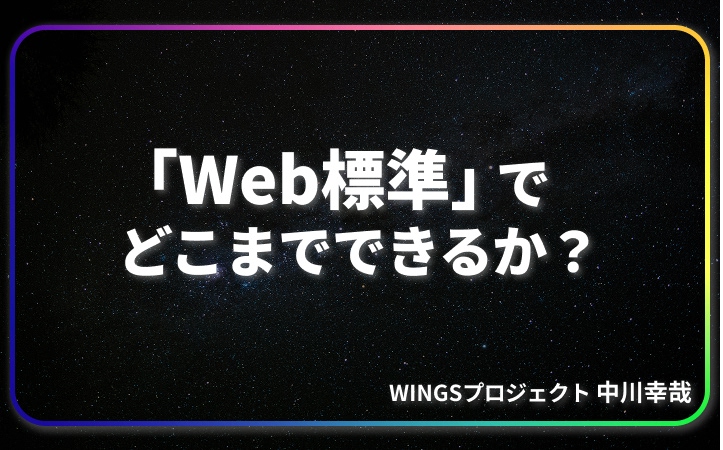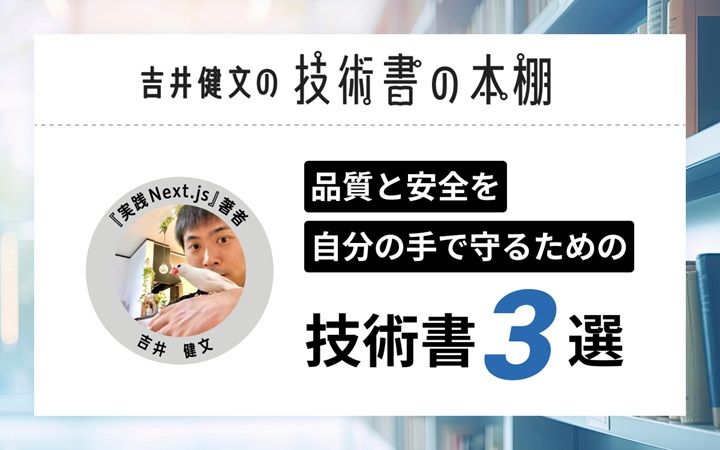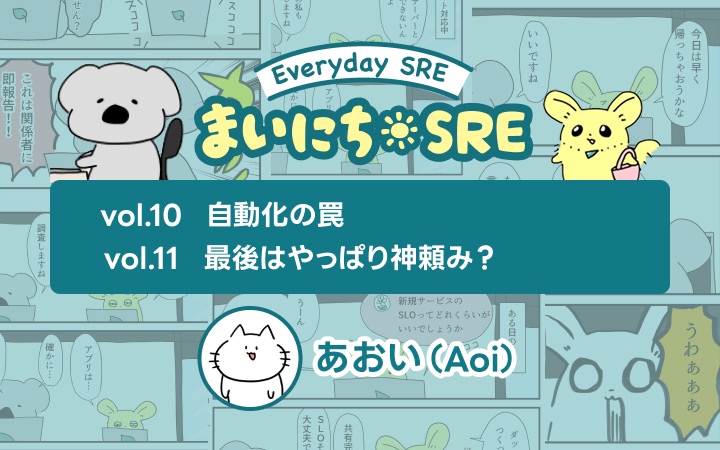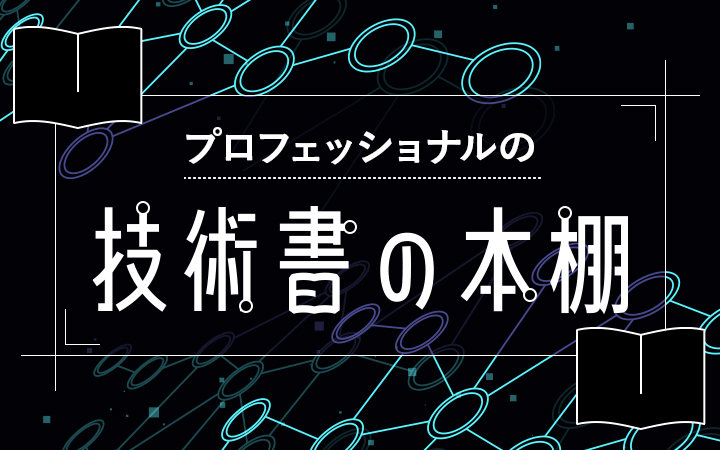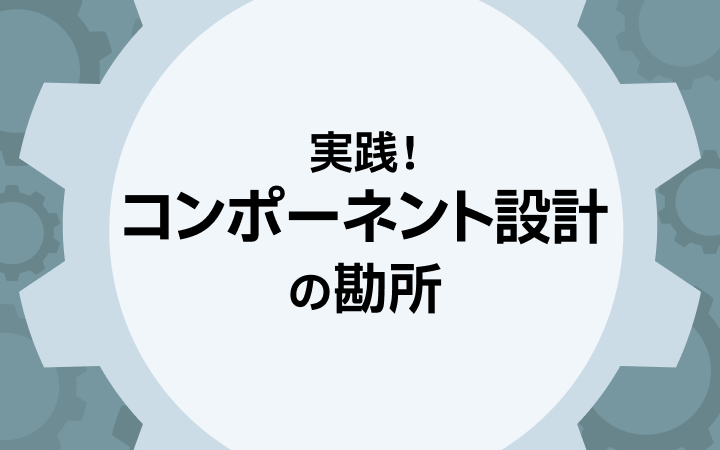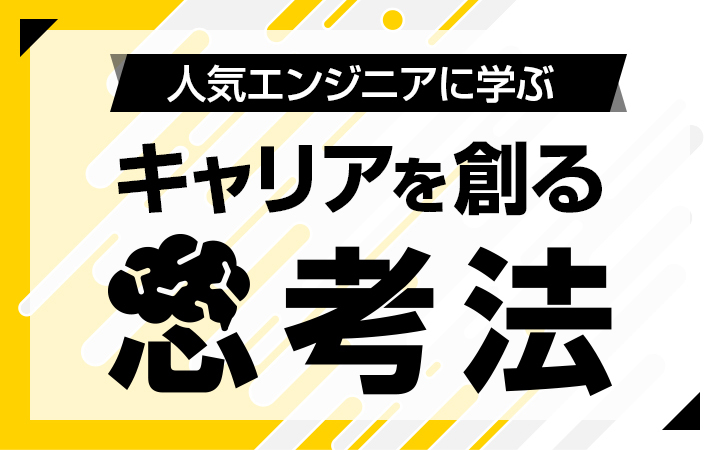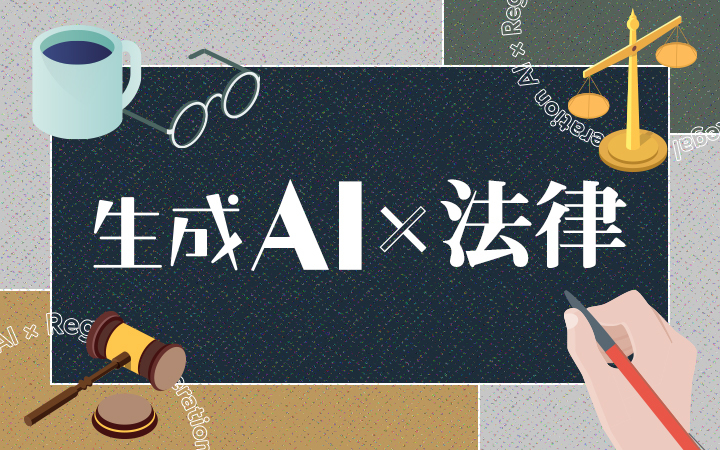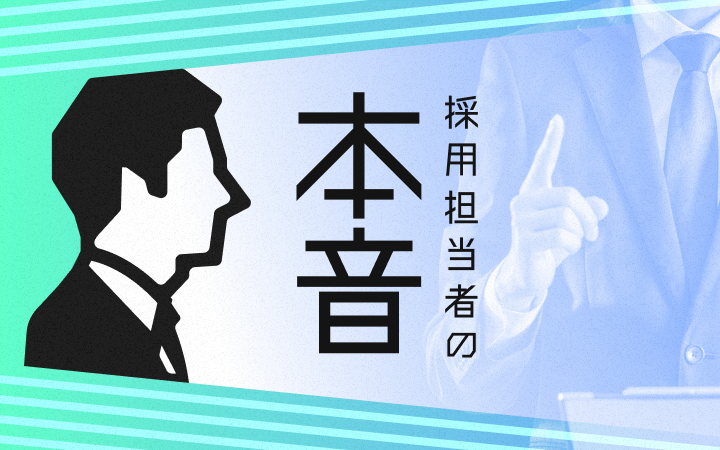【3/26(木)オンライン開催!】Rust いまのアーキテクチャにどこから入れる? ~ yukiさん、kenkooooさんが部分導入の“最適解”を語る夜 ~
本イベントは、yukiさん・kenkooooさんから、既存システムにRustを「部分導入」する実践ノウハウをお話しいただきます。アーキテクチャのどこにRustを組み込み、AIツールをどう移行に活用するか。「全面刷新は無理だけど、Rustでプロダクトを強くしたい」エンジニアの方は必見です。ぜひご参加ください!
2026年2月24日
AIエージェント
プログラミング言語
プロダクト開発