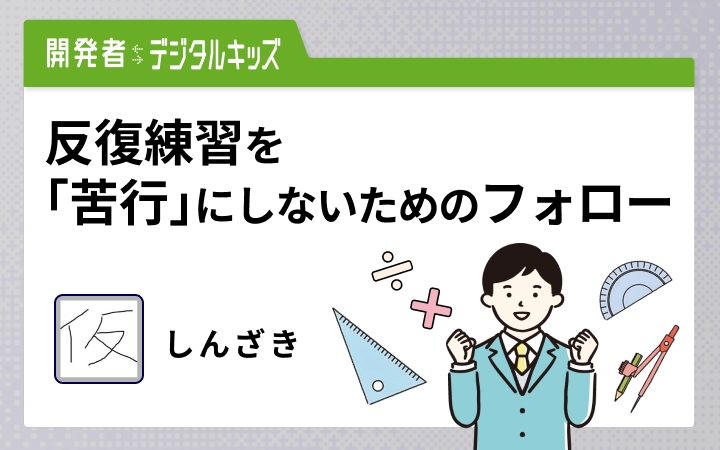最新記事公開時にプッシュ通知します
初代プレステで「神」になろうとした男。機械学習で生命創造を試みた『がんばれ森川君2号』『アストロノーカ』開発者の苦悩と野望【フォーカス】
2025年4月22日


モリカトロン株式会社代表取締役
森川幸人
1959年生まれ。CGクリエイターとして『アインシュタイン』『ウゴウゴ・ルーガ』等のテレビ番組に携わった後、1995年に有限会社ムームーを設立してゲーム制作の道へ進む。AIとゲームシステムが融合したタイトルを多数手がけており、代表作に『がんばれ森川君2号』『アストロノーカ』等がある。2004年に『くまうた』で文化庁メディア芸術祭審査員推薦賞を、2011年に著書『ヌカカの結婚』でダ・ヴィンチ電子書籍大賞を受賞。2017年にモリカトロン株式会社を設立し、現在はエンターテイメントへのAI導入を支援している。
初代プレイステーションの時代に、機械学習をゲームに取り入れたクリエイターがいます。
1997年の『がんばれ森川君2号』ではニューラルネットワークを、1998年の『アストロノーカ』では遺伝的アルゴリズムを用い、現在も例が少ない「ゲーム中に学習・進化するキャラクターAI」を開発した森川幸人さんです。
メインメモリわずか2MBという制約の中でAIに自律思考をさせる斬新な挑戦は、「世間からまったく理解されなかった」と悲しい顔を見せる森川さん。それでもゲーム×AIの領域から離れられない理由は、機械学習で成長するキャラクターを初めて生み出した際に感じた「自分が神様になったような衝撃」だったと言います。
本質的にはゲームをつくりたいわけでも、誰かを感動させたいわけでもなく、「生命を創造したい」という個人的な動機からゲーム業界への貢献を続けてきた森川さんは、現在の生成AIブームの先に何を見据えているのでしょうか?取材しました。
- 『がんばれ森川君2号』:「自分で考えてウンチを殴るAI」に感じた生命らしさ
- 『アストロノーカ』:人生で一度も「ゲームをつくりたい」と思ったことはない
- 機械学習はゲームと根本的に相性が悪い?
- 「このまま忘れられることを覚悟した」時代を先取りしすぎた苦悩
- もしも新作をつくるなら「生態系」を表現したい
- 自分でも「乗っかれよ、時代に!」と思っているけれど……
『がんばれ森川君2号』:「自分で考えてウンチを殴るAI」に感じた生命らしさ
――まずは、森川さんが初代プレイステーションの時代にどのようなAI技術を活用していたのか教えてください。
森川:最初につくったのは『がんばれ森川君2号』というニューラルネットワークを用いた育成ゲームです。AIを搭載したロボットを育ててプレイヤーの代わりにステージをクリアさせるという、機械学習が根幹にあるタイトルでした。
発売年が1997年なので、もう30年近く昔の話になりますか。きっかけは、販売元であるソニー・コンピュータ・エンタティンメント(以後SCE)の方に「ゲームをつくってみませんか」と誘っていただいたことでした。当時の私はCGデザイナーで、“なんだか変なアイデアを持っていそうな奴”ということで声がかかったんですね。
AIのアルゴリズムには当時最先端だった「バックプロパゲーション」(※1)を使いました。簡単にいえば、ニューラルネットワークの各層が誤差にどれだけ影響したかを出力結果から逆算して、層ごとの重みを調整する手法です。当時はフレームワークなんてなかったので、私が一から関数を書いてプログラマーに渡していました。
ニューラルネットワークのような機械学習は、一般的なソフトウェア開発でもほとんど使われていなかった時代です。それをゲームに取り入れたことで人工知能学会からも先進性を注目され、素人ながら私も論文を執筆しました。
(※1)バックプロパゲーション(誤差逆伝播法):ニューラルネットワークの学習に用いられる基本アルゴリズム。出力結果から誤差を逆算し、各層の重みを調整することでAIの予測精度を効率的に高める手法。1990年代当時は最先端技術であり、現在もディープラーニングの基礎として広く応用されている。

――初代プレイステーションでニューラルネットワークが動くものなんですね。
森川:それがね、最初はぜんぜん動かなかった(笑)。バックプロパゲーションは、今となってはディープラーニングの基盤として使われるような基本的な技術ですが、プレイステーションのR3000というCPU、2MBのメモリでは計算の負荷が高すぎたんですよ。
もちろん結果的に動かしたのですが、ゲーム全体のメモリ使用量をフルチューニングして、かなり無理やり詰め込みました。ニューラルネットワークの層ごとのノード数、脳でいうところの脳細胞の数も可能な限り減らしています。最終的には300……が無理で、270ノードに落ち着いたんだったかな。
最新の画像認識や自然言語処理には数万~数億ノードが用いられていますから、規模がぜんぜん違いますよね。実際にゲーム内で育てることになるロボットのAIは、決して覚えが良いとはいえない性能でした。
――私が育てたロボットは道に落ちてるウンチを執拗に殴り続けていました。
森川:そういうおバカなところも含めて面白がってくれた人もいれば、「やってらんないよ」という人も当然いて。SCEさんが宣伝してくれたおかげで40万本ほど売れましたが、世間の評価は賛否両論でした。
ただ、私自身はすっかりAIの魅力にはまってしまって。

森川:機械学習で自律思考するキャラクターを初めて見た時に、ものすごく感動したんです。人間が指示を出さずとも、過去の経験から最適な行動を推理してステージを攻略したり、良かれと思ってウンチを叩いたりする。これはもう生き物じゃないかと。
間違えるところも含めてとにかくかわいかったですし、自分が神様になったような全能感もありました。あるいは、脳みそが入ったカプセルを並べて喜ぶマッドサイエンティストになったような気分ですね。『がんばれ森川君2号』の開発が終わる前から、もう次のAIをいじりたい気持ちで頭がいっぱいで、2作目である『アストロノーカ』のアイデアを練っていた記憶があります。
『アストロノーカ』:人生で一度も「ゲームをつくりたい」と思ったことはない
――『アストロノーカ』は農業シミュレーションゲームであり、『がんばれ森川君2号』のようにAIが主役というわけではありませんよね。どのようにAIを活用したのでしょうか。

森川:ニューラルネットワークを用いた遊びがゲームの大部分を占めていた『がんばれ森川君2号』とは異なり、『アストロノーカ』は敵キャラクターの成長と進化という一部分にAIを活用しました。
このゲームでは、毎日「バブー」と呼ばれる害獣が野菜を狙って畑にやってきます。プレイヤーは畑への道中に様々なトラップを仕掛けて害獣を撃退できるのですが、時間が経って世代交代していくと、害獣はしだいにトラップの回避方法を学習し、さらにトラップそのものが効かない個体が現れます。
たとえば、プレイヤーが「落とし穴」ばかり使っていると、ジャンプで穴を飛び越えることを学習し、時間が経つと「羽の生えたバブー」が誕生するようなイメージです。
――ジャンプ台でバブーを川に放り込んで遊んでいたら、ある日めちゃくちゃ重い個体がやってきて全てを粉砕された記憶があります。どのような仕組みでバブーは進化するのでしょうか?
森川:生物の進化のメカニズムを応用した「遺伝的アルゴリズム」(※2)という手法を利用しました。
「身体能力」「トラップに対する戦略」「トラップへの耐性」という3つのパラメータを遺伝子に見立て、交配や突然変異といった操作をAIに繰り返させることで、トラップに強い個体の遺伝子が次世代に引き継がれていきます。
開発側でパラメータを設定したのは第一世代の20体だけで、それ以降に登場する害獣の能力はユーザーのプレイスタイルに応じて幅広く変化します。また、害獣にとっては野菜を食べることが報酬になりますから、「あえてトラップを配置せずに野菜を与えることで進化のスピードを緩やかにする」といった戦略も選べるようになっています。
こうしたアイデアはゴミ埋立地の公害問題から思いつきました。東京の江東区にある「夢の島」は、いまでこそキレイな公園になっていますが、昔はゴミがむき出しの状態だったから夏になるとハエが大量発生したんです。
ハエを駆除するために殺虫剤をまくんですが、なかには耐性がある個体もいて、次の世代でワーッと増えるんですよ。で、そいつらにも効果がある強力な殺虫剤を使うと、さらに強い耐性を持ったハエが生まれてきます。人間がハエを駆除し続ける限り、いたちごっこは止まらないという。
(※2)遺伝的アルゴリズム:生物の進化を模倣した最適化手法。初期設定された個体群に対し、選択・交叉・突然変異といったプロセスを繰り返して適応度の高い解を導き出す。
――なるほど。『アストロノーカ』では「人間と動物の共生」までAIで表現しているのですね。
森川:本音を言っちゃうと「ゲームをつくりたい」と思ったことって人生で一度もないんです。まずはAIの活用法に関するアイデアがあって、そこからゲームのガワを考えていく。
ゲーム業界に足を突っ込んだ当時の私は……というか今もですけど、ビデオゲームをあまり遊んだことがなかったんですよね。さすがにマリオ、ドラクエくらいは遊んだことがありましたけど、ゲームオーバーになるたびに「誰か代わりにクリアしてくれないかな」と考えていました。
それで、「ゲームを代わりにクリアしてくれるAI」をつくりたい気持ちで『がんばれ森川君2号』の企画書を提出したんです。
ただ、実は最初にソニーさんに提出した企画は、少し違うものでした。具体的には「AIがパズルを生成するパズルゲーム」という、もっと遊びの要素が強いゲームだったんですよ。でも、当時の私は何も分からない素人だったので、まず「AIについて勉強させてください」とお願いして、関係者をひたすら待たせている時期が半年くらい続きました。その後、やっと準備が整ったタイミングで「勉強していくうちにニューラルネットワークが面白くなったので、企画を根本から変えます」と宣言して、ちゃぶ台をひっくり返してしまったんですね。よく許してくれたなと思います。
ぜんぜん私が言えた話ではないんですが、なんというか、めちゃくちゃな時代でした。とにかく誰もやっていない新しいことを面白がる空気があって。「成功事例はあるのか?」「採算は取れるのか?」みたいにブレーキをかける人があまりいなかった。右も左も変なゲームばっかりで、仲の良いクリエイター同士で「よくもまあワケの分からない物をつくったな!」と笑いあってましたね。
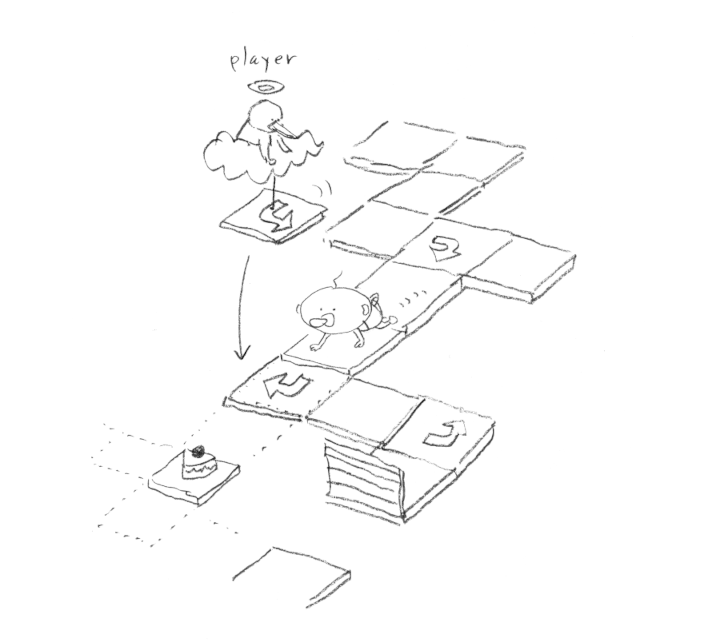
機械学習はゲームと根本的に相性が悪い?
――最新のゲームハードは『がんばれ森川君2号』『アストロノーカ』の頃とは比較にならない計算量を処理できるようになりましたが、それでも「キャラクターがゲーム中に学習する」形で機械学習を使用しているゲームは珍しいように思います。なぜでしょうか。
森川:おっしゃる通り、たとえばプレイステーション5のスペックがあれば、単純なニューラルネットワークはもちろん、多層構造のディープラーニングまでゲームに組み込むことが可能でしょう。
それでもゲームAIの主流がビヘイビアツリー(※3)のようなルールベースに留まっているのは、一般的なゲームと機械学習の相性が良くないからだと思っています。
というのも「ゲームを遊ぶ側」も「ゲームをつくる側」も、大多数の人は自分自身の手でゲームをコントロールしたいと考えている。アンコントローラブルな機械学習はゲームにとって邪魔者なんです。
(※3)ビヘイビアツリー: ゲームAIでよく使われる手法の一つで、キャラクターの行動を「もし~なら、こうする」という条件やルールの組み合わせで制御するもの。「敵が近くにいたら攻撃する」「体力が減ったら逃げる」といった行動をツリー状に整理して設計する。
――「ゲームをコントロールしたい」とはどういうことでしょうか。
森川:プレイヤーからすれば、操作できることが少なく、AIが勝手にゲームをクリアするところを見ていても面白くもなんともないんですね。自分の手でキャラクターを動かす爽快感とか、自分で考えた攻略法がバチっとはまる達成感といったプレイヤーがゲームに期待する楽しさをAIが奪ってはいけない。
そしてゲームをつくる側、特にゲームバランスを調整するプランナーからすれば、不確定要素が増える機械学習は非常に扱いにくい技術といえます。プランナーの仕事は、設計通りの面白さをプレイヤーに届けるために細部のパラメータにまでこだわり抜く、いわば職人技のようなものです。それは、機械学習の「何が起こるかわからない面白さ」とは正反対のアプローチなんですよ。
実際の所、AAAタイトルでもキャラクターAIに機械学習を導入しようという動きは存在するのですが、現状は行動判断のごく一部に利用されるのみに留まりがちです。あるあるなんです。スタート時点ではキャラクター全体をAIが制御する計画だったけど、だんだんと邪魔になって隅へ隅へと追いやられていくという流れは。
まとめると、機械学習をゲームに取り入れるためには、「AIの斬新な活用法とゲームとして押さえるべき“定番のツボ”を融合させる」「AIの不確定要素まで考慮してバランスを調整する」という特異な技術が求められます。そのためには機械学習に関する深い知識が必要不可欠ですから、わざわざ勉強してまでゲームに実装したいと考えるクリエイターは、まあ、少ないですね。
というか、この点については、私自身が『がんばれ森川君2号』で失敗していまして……。「機械学習で動くキャラクター」という斬新な要素をつくった時点で満足してしまって、遊びとしての完成度にまで考えが回っていませんでした。
――『がんばれ森川君2号』はまさにプレイヤーがAIを眺めるゲームですからね。
森川:ただ、私も『がんばれ森川君2号』への世間の評価を大いに反省して、次作の『アストロノーカ』は「AIを取り入れた面白いゲームをつくるにはどうすればよいのか?」という課題と本気で向き合いました。

――具体的にどうやって解決したのですか。
森川:『アストロノーカ』では、プレイヤーの利益を最大化する手段は、プレイヤー自身でコントロールできるようにしました。
AIは敵キャラクターのみに使用して、プレイヤー側の行動、つまり「どのトラップをどの場所に設置するか」には一切関与させなかったんです。技術的にはトラップの設置まで自動化することもできたのですが、それはプレイヤーの楽しみを奪っちゃうだろうと。
――ゲームのバランス調整についてはいかがでしょうか?
森川:アルゴリズムの調整は最大限行ったうえで、それでも残る不確定要素に関しては「AIのリスクを、AIと無関係の部分で低減する」という形で対処しています。
『アストロノーカ』は敵キャラの成長をAI制御しているので、「敵が強くなりすぎてプレイヤーが太刀打ちできない」という形でバランスが崩れるリスクを抱えていました。
そこで、バトルに負けても「まあいいか」と思えるように、ペナルティを低減できる手段をゲーム全体でいろいろと用意したんです。たとえば、“おとり”の畑を用意すれば本命の野菜が食べられる可能性を下げられますし、あえて安い野菜を先に食べさせることで大事な野菜を食べられないようにするような戦略も存在します。しかも、先ほどお話した通り、トラップを仕掛けず害獣と共生していると少しずつ能力が退化していくんですね。
この辺りは「ゲームの面白さとAIの面白さがかっちり噛み合ったぞ」という手ごたえがありました。
「このまま忘れられることを覚悟した」時代を先取りしすぎた苦悩
――実際に当時のゲームメディアでも、ゲームとしての面白さを高く評価されていたのですよね。
森川:たしかにゲーム部分はけっこう褒められたのですが、代わりに肝心のAIに関してはまったく触れてもらえなかったんです。インタビューでもがんばって遺伝的アルゴリズムについて話したのですが、毎回カットされてしまって。「こんなつもりで面白くしたわけじゃないのに」とふてくされていました。
……ただ、それは今では笑い話なんです。
本気でショックだったのは売上本数ですね。8万本しか売れなかったんですよ。RPGのような売れ線のジャンルじゃないことを差し引いても、当時の基準で明らかに少なかった。世間に見放されたような感覚がありました。

――今でこそ「知る人ぞ知る名作」としてたびたび話題になりますが、当時はSNSどころか匿名掲示板すら物珍しい時代でしたからね。
森川:悔しかったです。『アストロノーカ』が発売される前は自信満々だったので。開発チームも「これが売れたら漁業と林業だ!一次産業をコンプリートするぞ!」なんて浮かれていたから、反動が大きかった。
ここまで「ゲームで機械学習が流行らないのは相性が悪いから」なんて話してきましたが、仮に『アストロノーカ』が100万本売れていたら、もっといろんなAIゲームが生まれていたと思うんです。成功事例を作れなかったことに対して、ちょっと責任を感じています。
アストロノーカの後もいくつか新作をつくりましたが、2010年頃になると「AI」という言葉の鮮烈さすら失われてしまって。僕はもうこのまんま忘れられていくんだろうな……と覚悟を決めていました。
もしも新作をつくるなら「生態系」を表現したい
――森川さんは2017年にモリカトロン株式会社を立ち上げ、エンタメ業界でAIの活用支援を行っています。悲観的な状況からどのように事業を軌道に乗せたのでしょうか?
森川:転機はディープラーニングの流行でした。
2015年頃がピークだったと思うのですが、画像認識や自然言語処理への活用が進んだことで、ゲーム業界でも「これからは機械学習を勉強しなきゃいけない」という機運が高まったんです。その結果、「なんか森川って奴がAIのゲームをつくってたな」と各所から声をかけられるようになりまして。
どうせなら自分のAIゲームをつくるだけじゃなく、業界全体にAIを普及させるような会社をつくるのもいいのかもしれないと思いました。今はQA・デバッグ用のAIですとか、アニメーション制作用のAIですとか、ゲーム会社から相談を受けてAIの導入を支援しています。
ありがたいことに「AIで開発コストをカットしよう」という動きがゲーム業界全体で高まっていて、自分でゲームを企画していたころよりもぜんぜん需要がありますね。
――何かご自身でつくりたいゲームAIのアイデアはないのでしょうか?
森川:『アストロノーカ』の頃から変わらず、生態系とか生存戦略、そういう自然界に存在するメカニズムの美しさを目の当たりにすると、「これをAIで表現したら面白いだろうなあ」と感じますね。「神様になりたい」という初期衝動が何年経っても忘れられなくて。
たとえば、新型コロナウイルス感染症が流行したときに、不謹慎かもしれませんが、私はコロナウイルスに生物としてのしたたかさを感じました。最初は感染力を高めて重症化する傾向の変異が目立っていましたが、やがて弱毒化する傾向の変異が優勢になり、今ではマスクを着けて生活する人はほとんどいなくなりましたよね。
一見すると人間がウイルスを抑え込んで勝利したように見えますが、共存戦略という意味ではウイルスも人間に勝利していると思うんです。現状では、人間がコロナを完全に根絶しようとする動きはほぼ見られなくなっていますからね。
このウイルスの働きをAIで再現し、独自の世界観を考えたら、なんだかゲームになる気がしませんか?
――安直ですが「ファンタジー世界で人類とモンスターの争いを調停するゲーム」が思い浮かびました。
森川:いいですね。そのテーマで何ができるか考えてみましょうか。
この場合、キャラクターAI同士のコミュニケーションで「ナッシュ均衡(※4)」に辿り着けるアルゴリズムを作り出せれば、技術的にはゲームとして成立させられるかもしれません。
ナッシュ均衡とは「お互いの生存戦略が安定した状態」のことです。先ほどの話でいえば、「ウイルスは人間に被害を出しすぎると根絶されてしまうから弱毒化する」「人間は費用対効果を鑑みてウイルスの根絶を諦める」という形で互いの戦略に折り合いがついている現状がまさにナッシュ均衡になります。
(※4)ナッシュ均衡:ゲーム理論における基本概念。複数の主体が互いに最適な戦略を選んだ結果、誰も一方的に戦略を変更する動機がない均衡状態を指す。現実の経済や生態系の分析に用いられ、AIによる戦略最適化の目標として応用される。有名なナッシュ均衡の例に「囚人のジレンマ」がある。

――ということは「人類とモンスターのAIがナッシュ均衡にたどり着く=和平が成立した状態」になると。
森川:その通りです。両陣営のキャラクターAIには、それぞれ互いの利益が最大になるように行動させます。すると、プレイヤーが何もしなくてもいずれはAI間で折り合いがついてナッシュ均衡が生まれるのですが、それではタイムリミットに間に合わなかったり、ハッピーエンドにたどり着けなかったりする。
そこで、プレイヤーは様々な方法で両陣営に介入し、できるだけ早く最良の結果にたどり着けるよう働きかけるわけですね。
――負けている陣営に武器を与えて武力のバランスを取るとか、モンスターをかわいらしく進化させてペットとして生き残らせるとか、いろいろと想像が膨らみますね。短時間のプレイを何度も繰り返すローグライクゲームに向いていそうです。
森川:なんらかの形で自然界のエコシステムをゲームに落とし込む、より大きく出れば世界を一から生み出す挑戦はぜひやってみたいと思っていて、技術的にもいろいろとアイデアはあるんですが……今のところ誰も乗ってきてくれません。
自分でも「乗っかれよ、時代に!」と思っているけれど……
――先述の「機械学習とゲームの相性の悪さ」があるからでしょうか?
森川:それもありますが、やはり世間的なトレンドは生成AIなんです。もはや「生成AI以外はAIにあらず」みたいな空気を感じています。経営者としては、AIへの関心が高まっていてありがたい限りなのですが、なんというか、まあ、個人的には……
――あまり面白味がないですか?
森川:非常につまらないです。
――非常につまらない。
森川:もちろん生成AIの技術そのものは素晴らしいですし、非常に可能性がある分野だと思っています。これから先はさらにパーソナルな方向に進化して、ますます人間の隣人のような存在になっていくのではないでしょうか。
ただ、漠然と「生成AIで何か斬新なゲームを作りたいんです!」と相談されると少し困ってしまいますね。生成AIを使っただけで話題になるような時期はもう過ぎ去っていて、面白いゲームをつくるためには、クリエイティブを牽引する人の知識とアイデア、それらを生み出すための熱意が求められる段階になってきていると感じています。
私たちも2023年に『RedRam』という「ストーリーから殺害ロジック、背景、キャラのイラストまで全部生成AIでつくられるマーダーミステリーゲーム」を公開したのですが、あくまで技術デモとして作成したコンテンツでして、そこから商品として完成させるためには結構なコストが必要だと思いました。

森川:あとは経験上、企業が生成AIをゲームに活用しようとしても、諸般の事情で途中でストップがかかることが多いんです。というのも、現状はクリエイティブな領域で生成AIを使用することに対して否定的な意見も根強くて……。そうなると、法的に問題がなくても渋い顔をせざるを得ない部署があるわけです。いつも心の中で「斬新なゲームをつくりたいなら、面白くてゲーム向きのアルゴリズムは生成AI以外にもたくさんありますよ!」と叫んでいます。
生成AIに限らない話ですが、そういう意味でAIと相性が良いのは、技術選定のフットワークが軽く、個人の情熱でどこまでも走っていける小規模開発のインディーゲームでしょうね。ゲームシステムに組み込む以外に、開発リソースの不足を補ってくれる「貧者のツール」としてもAIは活用する価値があります。
先ほどの『RedRam』もインディー開発者のヒントになればと思って開発したタイトルです。ソースコードも全て公開しています。私も歳をとったからなのか、時間をかけて自分のアイデアを形にするよりも、短いスパンで様々な技術を普及させることで、若くて情熱のあるクリエイターにアイデアのを伝承していきたいと考えるようになりました。
というわけで、最近は社員にも「自分はポスト生成AIでいくから」と伝えています。半分は冗談ですが。
――でも、もう半分は本気なんですよね。
森川:私はAIという技術全体の可能性を信じているので、一部の使い方だけにスポットライトが当たっている状態は、長い目で見るともったいないと感じてしまいます。
そんなことを言っていると「世間に理解されたくて凹んでいたくせに何がポスト生成AIだ!」「乗っかれよ、時代に!」と叱られそうですが、幸いなことに、当時と違ってAIに可能性を感じている仲間が社内外にたくさん増えました。
ろくなスキルチェックもされずに企画が通ったイケイケの90年代もある意味では良い時代だったと思いますが、それでも今の方が、孤独は感じなくなりました。ずっと私につきまとっていた「忘れられるんじゃないか」という心配は、どうやら杞憂だったみたいです。

取材・執筆:戸部マミヤ
編集:光松瞳
撮影:曽川 拓哉
©1997 Sony Computer Entertainment Inc.
©MuuMuu Co., Ltd.、SYSTEM SACOM corp.、ENIX 1998
©Drecom Co., Ltd.
関連記事

『メタルギア』『ZOE』の開発者がレトロゲームエンジン「Pyxel」を作った理由【フォーカス】

『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』に学ぶ、スキル習得の難易度コントロール

AIがマイクラ上に“暮らす”「Project Sid」を解剖し、 ハルシネーション抑制のカギを探る
人気記事