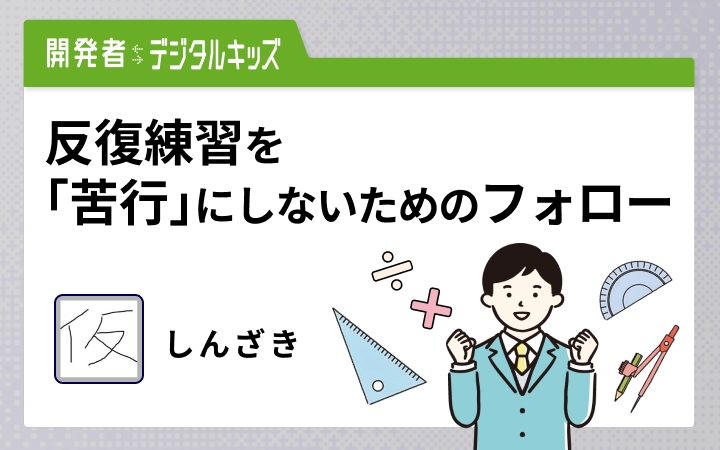最新記事公開時にプッシュ通知します
5指駆動「サイボーグ義手」が実現した理由。“実用化だけ”を見据えた研究者たち【フォーカス】
2024年11月25日


東京理科大学 工学部 電気工学科 助教
山野井 佑介
筋電義手研究者。2016年に電気通信大学情報理工学研究科修士課程、2019年に横浜国立大学大学院工学府博士課程(工学)修了。電気通信大学時代の師・横井浩史教授をはじめとして、横浜国立大学や国立成育医療研究センターなど様々な団体と共同研究で筋電義手開発・社会実装に取り組む。2023年より現職。ニューラルネットワークによる姿勢制御やソケット部品の開発など、筋電義手に関してソフトウェアからハードウェアまで幅広い知見を持つ。
プロフィール(東京理科大学公式サイト内)
Google Scholar
reserchmap
筋肉が発する微弱な電位をもとに、着用者がどう動かしたいのか意図を読み取って動作する「筋電義手」。中でも、5本の指がそれぞれ独立して動作できる「5指駆動筋電義手」は、長年、実用化が困難でした。人が身につけられる大きさや軽さを保ちながら、腕の動きを機械的に再現することは、現代の技術水準ではほぼ不可能なためです。
そんな5指駆動筋電義手の実用化が2022年、電気通信大学の研究者らによって実現されました。「BITハンド」との名称で製品化までされ、補助金を受けての購入が可能になったのです。研究チームを主導したのは、筋電義手研究者の山野井佑介さん。現在は東京理科大学に所属を移して助教を務めつつ、電気通信大学などと共同で義手の研究を続けています。
一体、どうやって実現したのでしょうか。そこには、「人体の再現という研究者の夢」も、「革新的な技術開発による学術的な名声」も望まず、本当に必要な要素は何かを見極め「実用性だけ」を徹底的に追い求めた研究者たちの努力がありました。
半世紀近く実用化困難だった「5指駆動筋電義手」
――本日はよろしくお願いいたします。SF作品にはしばしば、本物の腕の動きを完璧に再現できる電動義手が登場しますが、実際のところ、山野井さんらが取り組んでいる最新の筋電義手は、どのような性能を実現できるのでしょうか。
山野井:片手を欠損された方が我々の筋電義手を使うと、日常生活に必要な把持(しっかりと手に持つこと)の85%をカバーできます。具体的には、5本の指が独立して動くことにより、大まかに3種類の動きを実現可能です。5本指で握る「握力把持」と、親指の腹と人差し指で何かをつまむ「精密把持」、カードや鍵といった厚みの薄い物を持つ「側面把持」です。
▲山野井さんが取材に対応しながら筋電義手の動作実演を行っている様子を撮影した映像。筋電義手で物をつまむには、実行前に指の動きを途中で一時停止し、まずは物体の形状や大きさに合わせる「プリシェイピング」動作が必要であることなどが解説されている。映像内の動作には、握力把持と精密把持を含む
山野井:握力を目安でいうと、数kgほど。500mlのペットボトル程度なら、しっかりと握って持つことができます。ただ、大きな力を出すことはできていませんし、自由自在にピアノを弾くといった細かい動作を義手だけで実現することは現段階では不可能です。
――さすがに、手の動きを完全再現するようなことは難しいのですね。
山野井:はい。そもそも、人体の完全再現を目指す以前に、5本指が動く義手を実用化すること自体が最近まで長らく困難でした。
筋電義手が普及しはじめたのは1960年代にまで遡り、5指がそれぞれ駆動する義手も、研究の実験レベルでは1980年代には登場しています。しかし、海外メーカーも含めて、政府が定める「完成用部品」(※1)のリストに5指独立駆動型の筋電義手が登録されたのは、2022年になってようやくのことでした。
それまで、実用化されている義手では、親指とそれ以外の4本の指がまとめて同時に動いて、「握る」「開く」という単純な動作だけできるものがほとんどだったのです。
(※1)「完成用部品」:厚生労働省から認可を受けた義肢装具の部品のこと。義肢をつくる時は、義肢装具士がさまざまなメーカーの部品を選び、患者の体に合わせて制作を行う。完成用部品として指定を受けている部品ならば、患者は公的な補助を受けて購入でき、負担が大幅に減る。

――実用的な5指駆動筋電義手の登場まで、半世紀近く時間がかかったのはなぜでしょうか?
山野井:5指駆動を実現する高度なメカニズムと、日常生活で使えるまでの小型軽量化を両立させることが極めて困難だったからです。
ここ10~15年で、国内外で5指が独立して動く実用的な筋電義手が実現したのは、やはりハードウェア・ソフトウェア面の技術的進化が大きいです。ただ、我々の場合、「人間の完全再現をしようとする方針」を見直したことが、実用化に辿り着いた最大の要因かもしれません。
筋電義手研究は、そもそものアプローチにおいて、大幅な遠回りを長年してしまっていたんです。
「完璧ハイスペック義手」をあえて諦める
――「人間の完全再現をしようとする方針」を見直したとは、どういうことでしょうか?
山野井:現在の技術水準では、筋電義手の開発において人体の再現を目指そうとすればするほど、実用化から遠ざかるのです。研究開発自体が困難ですし、何よりも、義手使用者の方々が着用して日常的に使えるような重さをはるかに超えてしまうからです。
人間の動きを完璧に再現しようとすると、極めて複雑な制御技術の実現が必要になって、義手に搭載するコンピュータを大型化させざるを得ませんし、大きな力を発揮できるモータを何十個も搭載する必要も出てきます。すると、義手の重さは数kg以上にまで増大します。
義手は、体の一部ではなく、あくまで欠損のある腕の先に装着して使うものです。それはダンベルを腕の先に吊り下げるようなものなので、数kgであろうと、すさまじい負荷が義手使用者にかかることになります。数分以上も使い続けることは困難です。なので、実用化を目指すなら、本体重量を数百gレベルに留めるべきなんですよ。

――義手の重さは、想像以上の負担になるのですね。
山野井:はい。しかし、研究者はしばしば、人間の動きを完全に再現できる技術の実現を目指すのです。その方針が、多くの場合において実用化を遠ざけるボトルネックとなります。
僕は電気通信大学情報理工学部時代に出会った同大教授・横井浩史先生と筋電義手の研究を続けています。2013年に僕が配属された段階では、横井先生の研究室は人体の動きの再現性向上を重視した研究を進めており、一定の研究成果も上げていました。
同時に横井先生は、世の役に立つ義手を実現したいという強い信念を持つ人でもあるので、上肢切断者の方々にご協力いただき、研究段階の義手を実際に試用してもらうことも多くありました。しかし、結局のところ、人体の完全再現を目指した義手の実用化は、極めて難しい。
研究成果と社会実装をつなげるためには、どうすればいいのか。強い課題意識を抱いていた横井先生と我々は、ある時立ち止まって「義手使用者にとって、本当に必要なものはなにか」を考え、使用者のヒアリングや先行研究のリサーチに注力しました。そこで、日常生活における人の手の全把持のうち、握力把持が35%、精密把持が30%、側面把持が20%で、3つの動作が計85%を占める…という海外の研究に着目しました。
――それが、大きな転機だったのでしょうか?
山野井:はい。完全再現は現状、非現実的なアイデアでしかない。なので、まずは「日常生活で必要な動作を実現すること」に焦点を絞り込んだ。義手使用者が、大抵のものを持つことができる義手をつくり、ペットボトルのフタを開けたり、スマートフォンを操作したりする、といった細かい動きは、もう片方の、残っている手で行ってもらえばいいと考えたんです。
こうして、2015年ごろから、実用化を明確な目標とした義手開発に軸足を移し始めました。
すると、何をするべきかが自然と見えてきました。3つの動作を確実に実行できる、必要最低限のセンサとモータを搭載。また、耐久性をあえて犠牲にし、ボディには重い金属ではなく3Dプリンタで製作可能な樹脂素材を採用。「壊れない義手」をつくるのではなく、「壊れたら交換すればいい」という設計思想のもと、軽量化と汎用性を重視したのです。
さらに、病院と提携し、数十名の、上肢欠損を抱えた被験者に義手を使っていただき、「使いにくいところはありませんか?」と従来よりも大量のフィードバックを細かく受けながら研究開発を進めました。
その結果、実用性を担保しつつ、海外製の義手よりも制作コストは半分に抑えた、5指独立駆動の義手を実現することができました。重量も、ソケット(切断部位と義手を接続する部品)を含めて、約600gに抑えています。

――とはいえ、5指の制御技術を実現することは困難だったのではないでしょうか。
山野井:ええ。まずなにより、「着用者の意図を理解する」仕組みの実現に、大きな課題がありました。筋電位の信号の大きさというのは、乾電池が発する電圧の約10万分の1というレベルで、極めて微弱なんですよ。計測しようとすると、部屋の蛍光灯から発される電磁波の影響すら受けるほどに、ノイズが混じりやすい。単純に「手を握る・開く」だけならともかく、5指分の筋電位をそれぞれ計測し、義手使用者がどの指を動かしたがっているのか分析するのは難しいことでした。
この課題については、機械学習を用いた信号処理技術を開発し、解消しました。義手使用者から得られる筋電位の周波数分布を個別にAIに学習させることで、5本指それぞれへの細かい命令を識別することができるようになったのです。
特に、この技術は、後天的に手を失ったのではなく生まれつき欠損を抱える方にとって大きなメリットがあります。従来の筋電義手が使えない方にも、対応可能だからです。
というのも、先天的な欠損を有する方は、実際に手を動かす感覚を知りません。つまり、仮に「手を握るつもりで、筋肉に力を入れてください」と言われても、どこの筋肉を動かせばいいかわからないため、通常とは異なる筋電位信号が生じます。なので、一般的な筋配置を前提とした筋電義手を使うと、義手は全く意図しない動きをしてしまうのです。
一方、我々の技術では、機械学習によって個別最適化が可能です。例えば「手を握るつもりで力を入れて」といわれた時に発される信号が、一般的な筋活動とは異なっても、「この人は手を握ろうとすると、こういう特徴の筋電位を発するんだ」と分析し、意図する動作と、その方独自の周波数分布をどんどん関連づけて学習していくのです。こうして個人個人に最適化された制御が可能になるため、生まれつき欠損のある方でも、意図通りに義手を動かせます。
――機械学習技術の進歩も、実用化において大きな要素だったのですね。
山野井:その通りです。
ただ、意外なところで苦労したのは、実験の効率化です。
筋電義手の実験では、1回の実験で被験者に実際に装着してもらい、意図する動作とその際発される筋電位の関係を分析する作業を何度も行います。ところが、計測データを分析にかけるにあたって、5年前までは実験時に毎回パソコンと筋電義手のコンピュータを有線接続し、計測結果を転送して処理にかける必要があったのです。
すると、被験者の体がケーブルに引っかからないよう注意しながら実験する必要があるため、医療機器が多く転倒リスクのある病院内での実験や、何かと動き回りがちな小さなお子さんを対象とした実験は困難でした。
そこで僕は、Bluetooth通信機能を用いたデータ送受信のミドルウェアを開発しました。これによって、義手とパソコンの無線接続により、リアルタイムで筋電位データを取得・解析できるようになり、被験者には体を自由に動かしてもらいつつ、場所を選ばず気軽に実験が可能となりました。
同時に、モータを付け替えたときなどに義手の動作確認を素早くできるようにするため、スマートフォンやタブレット端末などから義手を動かせるソフトウェアもつくっています。細かい部分ですが、こうした積み重ねによりさまざまな制御アルゴリズム研究や動作検証がしやすくなり、研究開発スピードが上がっていきました。

筋電義手は「アカデミアとビジネスの狭間」に取り残されていた
――「とにかく最低限の機能を搭載し、実用性を追い求める」アプローチによって、サイボーグ義手の社会実装が実現したのですね。横井教授や山野井さんが取り組むまで、国内でこうした動きがなかったのはなぜなのでしょうか?
山野井:義手研究は、学術界と産業界のどちらでも研究が進みづらい特殊な事情を抱えているからかもしれません。
まず、学術界では、一般的に論文発表が研究者の主要な業績指標となります。論文では新規性や独創性が重視されるため、「0から1」を生み出す研究は高く評価されます。
ところが、5指が独立して動く筋電義手自体は、1980年代に既に構想があり、研究レベルでは存在していました。それを「実用的に使えるようにする」というのは、既存の研究成果に対する改良、すなわち「1から10」の研究です。これを推し進めても、研究者として高い評価を受けられるとは限りません。
さて、「1から10」の研究は、産業界の得意分野です。既存の研究にビジネスの可能性を見出した企業が大規模な投資を行い、商品として利益を生み出せるレベルまで改良し、実用化する動きはよくあります。
しかし筋電義手の場合、顧客は上肢欠損者ということになり、市場としての規模は極めて小さい。すると利益が見込めないので、残念ながら研究開発投資からは敬遠されがちなのです。
学術界では新規性に欠けるとされ、産業界では採算が見込めない。5指筋電義手の実用化は社会全体で見れば誰かが担うべき重要な研究開発であるにも関わらず、このような構造的な問題によって、長らく停滞を余儀なくされてきたのです。
その点で、「困っている方の助けになれば」と、何よりも実用化を最優先に据える信念を持った横井先生の研究室は、稀有な存在だったと思います。

――そもそも山野井さんは、なぜ横井教授らと筋電義手の研究を行うようになったのですか?
山野井:最初から筋電義手に興味があったのではなく、高校時代の僕は、脳波などで機械を動かすアイデア「ブレイン・マシン・インタフェース(BMI)」に憧れていました。SF作品のように、念じただけで動くロボットがあれば、人々の生活が便利になるだろうなと思って。
それで電気通信大学に入ったのですが、授業などを通してBMIは想像よりはるかに実用化が困難な技術だと知りました。脳波というのは、筋電位の比でないほどにノイズが混ざりやすく、純粋な運動意図を読み解くのは至難の業なのです。
一方で、筋電義手自体は、BMIと同じく生体信号を利用する技術でありながら、すでに実用化はされている。考えただけで機械を動かすような世界をまさに実現できる分野だと考えて、当時から義手分野で著名な横井先生の講義を受けるようになり、そのまま研究室にも入りました。
――山野井さん自身も、実用的なものをつくりたいとの思いは、もともと強かったのですね。
山野井:そうですね。ただ、筋電義手の研究を通して「本当に人々の生活に役立つものとは何か」への考え方も少し変わったかもしれません。
実験で出会った、欠損を抱える被験者は、義手を通して「物が持てた」「キャッチボールができた」という、健常な体の人にとってはごく当たり前な動作ができるだけで、僕の想像する以上にものすごく感動して喜んでくださるんですよ。
僕は本来、BMIを使ったSFのような技術を実現して暮らしを豊かにすることに興味があったわけですが、最低限の機能性を備えた義手で笑顔になる方々を見ていると、「本当に役に立つものとは、単に技術的に優れていることではなく、実際に困りごとを抱えている人に寄り添うことで生まれるのかもしれない」と思いました。

――利用者の視点に立つことが、より多くの人の役に立つ技術を生み出す原動力になるのですね。こうして2022年、5指駆動の筋電義手が実用化されましたが、現在の普及状況はいかがでしょうか?
山野井:そこは明白な課題でして、国内における普及率は極めて低いです。正確な統計データは存在しませんが、一般的には、義手を必要とする方のわずか2%しか筋電義手を使っていないのではないか、といわれています。
理由はいくつか考えられますが、昔よりも便利で、しかも低コストになったことが、全く知られていないというのが大きいと思います。
我々の筋電義手の場合、身体障害者手帳をお持ちの方は市町村の補助を受けて1割負担で購入できる場合(※2)もあり、このケースなら実費は18万円程度で済みます。重量も600g程度で、昔の義手に比べて、かなりお役に立ちやすいのではないかと考えています。
2000年代ごろは、5本指の動く筋電義手は極めて重いうえに、特注という形になり、装着するのに専門医師やエンジニアチームによるサポートが必要で、数千万~数億円かかるといわれていました。また、「握る・開く」しかできないシンプルな筋電義手は100万円程度で購入可能ながら、やはり数kgすることはざらにありました。
サイズの問題もあるでしょう。従来品の筋電義手は本物の腕と比べて、見た目が異様に大きいものも多く、心理的にも忌避されやすかったのです。なので上肢の欠損を抱える人は、機械的な機能を有しなくとも、安価かつ軽量で、見た目の違和感を無くすことに重きを置いた「装飾用義手」を選ぶ人が大半でした。この、「筋電義手は高価で重い」とのイメージが、今も残っているのではないかと推測しています。
(※2):補助の条件は自治体や収入によって異なり、所得制限によって全額負担となるケースもある。
――せっかく研究開発を行ったのに、今度は認知度に関する課題が?
山野井:そうなんです。5指の筋電義手という選択肢があるということを周知する活動に力を入れていかなくてはいけないと痛感しております。
とはいえ、義手としてもこれで完成形だとは思っていません。日常生活の約85%をカバーできるとはいっても、まだまだ改善の余地があることも事実です。さらに細かく筋電位を分析できる技術を確立しつつ、より細かい動きができるようなモータの組み合わせを模索していきたいと考えています。
目下の目標は、何かを手に持つだけでなく、軽量のまま細かな操作までできる義手を実現することです。そして、いつの日か、すべての義手使用者さんが自分に合った義手を選べるような未来を実現できるように研究開発に尽力していきます。

取材・執筆:田村 今人
編集:王 雨舟
撮影:赤松 洋太
関連記事

“アニサキス殺し”パルスパワーは「器用貧乏」な技術だった 「電気エネルギー界のドラえもん」が拓く未来【フォーカス】

その変形バイクにはトランスフォーマーの遺伝子が宿る。開発者が追い求めた、ロマンと実用性を融合させる道【フォーカス】

Preferred Networksをやめ“フリーランス”を選んだ、ある研究者の独白【フォーカス】
人気記事