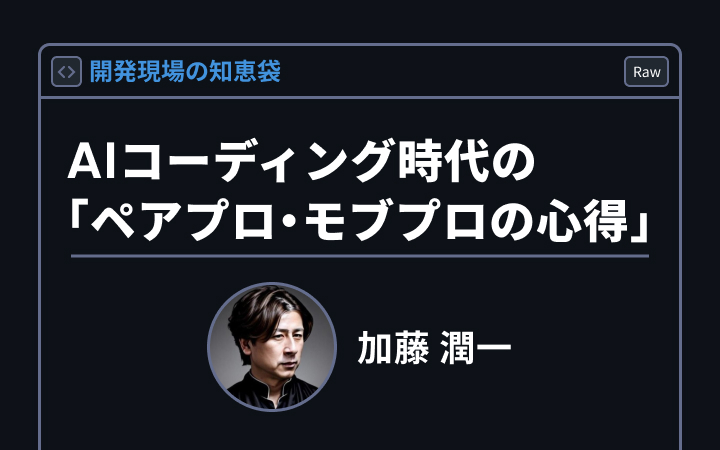最新記事公開時にプッシュ通知します
QRコード誕生30周年、生みの親は「まだ進化させたい」 いまも現場に立つ原昌宏氏が注いだ情熱と“遊び心”【フォーカス】
2024年6月24日


株式会社デンソーウェーブ 主席技師
原 昌宏
1957年生まれ。東京都杉並区出身。1980年、法政大学工学部電気工学科(現:理工学部電気電子工学科)卒業。同80年、トヨタグループの部品サプライヤーである株式会社デンソーに入社。バーコードリーダーや関連システムの開発に携わる。1994年にQRコードを提唱・開発。2001年より、組織改編によりデンソーウェーブに所属。2014年、QRコードの開発チームとともに欧州発明家賞を受賞。2023年には日本学士院賞・恩賜賞を受賞。
デンソーウェーブ公式サイト
QRコードドットコム
いまや街を歩いていて目にしない日はないと言っていいほど、世界的プロダクトになった「QRコード」。その生みの親であるデンソーウェーブ社・原昌宏さんは、66歳になったいまでもQRコードの開発に携わっており、主席技師として現場に立ち続けています。
誕生から30周年となったいま、原さんは取材に対し、まだまだQRコードを進化させるアイデアがたくさんあると語ります。そのうちのひとつは、二次元コードだけで画像データも持ち運べるようにするというアイデアです。
変わることのないその情熱の源泉は、一体どこにあるのでしょうか。「やはり楽しくなければ、仕事は長続きしませんから」と語る原さんに、30年間QRコードに携わるとの開発の面白さと、現場に立ち続けるモチベーションについて詳しく聞きました。
- 「苦し紛れ」だったオープン化。アイデアは向こうからやってくる
- 「オフラインの世界」を支えるため、QRコードをさらに進化させたい
- 青い技術志向から「現場主義」へ
- 「楽しくなきゃ仕事じゃない」の時代だから
「苦し紛れ」だったオープン化。アイデアは向こうからやってくる
━━今年で30周年を迎えたQRコードは世界中で使われ、生活や産業になくてはならないものとなっています。その生みの親として、これまでを振り返って率直なお気持ちをお聞かせください。
原:正直、一般の方までが日常的に使うようなプロダクトになるとは、想像していませんでした。
たしかに、QRコードを開発した1994年当時、「我ながらいいものができたなあ」とは思っていました。ただ、デンソーはあくまで自動車部品製造を主業とするBtoBの会社です。QRコードも当初は、製造現場における部品の生産管理用に開発されたものです。
ここまで広く使われるようになったのは、最初から特許は取得するものの、仕様をオープン化し、規格化されたQRコードを活用したあらゆる物からは特許使用料を徴収しないように決めたことが大きかったと思います。

━━オープンソース化は、思い切った決断ですよね。当時の日本にはあまりない、先進的な考え方だったのでは?
原:よくそういうふうに言っていただくのですが、われわれとしてはある意味、「苦し紛れ」の戦略でもあったんですよ。当時はそもそも部品管理以外の用途や、QRコードを活用した新たなビジネスについて、模索をしてみても特に良いアイデアが浮かばなかったんです。この時、社内にはマーケティングや商品企画を担う部署すらなかったものですから。
ただ、我々はものづくりの会社で、これまでもずっとバーコードリーダーの開発に携わってきて、「読み取り技術」に大きな自信があったんです。
なので、QRコードをオープンソースにすることで、他の企業にお好きに自分たちのサービスに使っていただき、普及を図る。そして、「我々はQRコードの読み取り装置をつくって売ることで稼いでいこう」というのが、当時描いていた青写真だったのです。
━━普及につれて、様々な派生規格も生まれたんですよね。
原:はい。いろいろと手がけてきました。
━━中でもとくに思い入れのあるものはどれですか?
原:一番思い入れがあるのは、「SQRC®」(2007年開発)でしょうか。
当時は、高精度なカメラを備えた携帯電話が大きく普及しつつあったころで、専用のリーダーがなくても、誰もがお手軽にQRコードを読み取れるようになっていました。すると、機密情報や個人情報をQRコードを用いて扱いたい企業さんからは「機密性の高いコードが欲しい」という要望が多く寄せられたんです。こうした要望を受けてつくったのが、1つのコードに「公開領域」と「非公開領域」の二層構造を有している「SQRC®」です。
公開領域は通常のQRコード同様、スマホを使って誰でも読み取りできますが、非公開領域は、あらかじめ設定した特定のリーダーでしか読み取りできません。同じコードでありながらも、読み取り端末によって異なる情報が表示されるのです。
面白いのが、SQRC®の見た目は通常のQRコードとほぼ同じということです。なので皆さんに気づかれていないだけで、身の回りには、一見普通のQRコードに見えて、実は隠し情報を内包したSQRC®なのが結構ありますよ。
たとえば、商品のパッケージにSQRC®を使う施策では、店頭にて一般の消費者がスマホで読み込むと、商品の使い方ページや企業のPRサイトが表示されますが、専用のリーダーで読み込むと細かな品質情報や生産者情報が表示される、というものがあります。

━━ほかにも印象的な派生製品がありますか?
原:鉄道のホームドアの開閉制御用に開発された「tQR®」も印象深い製品です。こちらは2019年に東京都交通局様と共同で開発したもので、車両のドアに専用のQRコードを貼り、ホーム側上部に設置したカメラでその動きを読み取ると、連動してホームドアが開閉するという仕組みです。このアイデアも交通局の職員の方から持ち込まれたものでした。
tQR®の開発で一番むずかしかったのは、やはり鉄道のホームドアが設置された屋外環境で、影ができたり、雨に濡れたりしても、一瞬で正確に読み取れるようにすることですね。
もともとQRコードは製造現場でのニーズを汲み取っていたので、機械油などで面積の30%が汚れても読み取れるようにしてあります。ただ電車となると、屋外を走る路線だと影・日向の影響、時間帯による日差しの変化、雨風による汚損で可読性が変わりやすいので、確実に読み取れるよう、50%まで欠損しても読み取り可能にしてあります。

「オフラインの世界」を支えるため、QRコードをさらに進化させたい
━━今後、QRコードを通してやっていきたいことはなんですか?
原:QRコードをさらに進化させます。一定容量の画像データをコードに埋め込める派生規格をつくる、という構想があります。
現行のQRコードだと、バイナリデータとしてせいぜい約3KBぐらいの情報しか記録できません。「漢字・かな」テキストなら1817文字分です。
この容量そのものを数MB分に増やし、ある程度大きな画像でもオフラインで持ち運んで伝達ができる、そんなQRコードを設計したいのです。
━━実現可能性はどうですか?
原:技術的には実現可能と考えています。現在思い描いているアイデアのひとつは、現行のコードで177セル×177セルのマトリクスと定めているところを、1000セル×1000セルにまで拡張する方法があります。また、コードを構成する新たな要素として「色」を加える構想もあります。こうすることで、埋め込める情報量が飛躍的に増えます。
「より多くの情報を格納できるQRコード」をつくること自体は、1994年当時でも可能だったんですよ。ですが、ハードウェア側のセンサ―の性能水準により、一般的な機器で確実に読める大きさの限界が「177×177」だったんです。でも昨今では、高精度なカメラを搭載したスマホをみんなが持つようになったので、機は熟したという所感です。
━━なぜ画像データも持ち運べるQRコード規格をつくりたいと考えたのですか。
原:背景には東日本大震災、そして2024年1月の能登半島の地震の影響が大きいです。

━━どういうことですか?
原:最初は東日本大震災の直後。東北地方の病院の先生方から、被災地で診察を行うと、患者の持病やアレルギー情報を即座に把握できず、緊急時には特に災害関連死の発生リスクが高まってしまう――という悩みの声が寄せられていました。
そこで、PDFデータやレントゲン写真、エコー写真といった画像データも、QRコード形式にして患者が持ち運べるようになったら便利そうだな、と僕は考えました。ただ、当時はいまほど画素数の多いカメラを備えたスマホの普及率はまだまだ低かったので、このアイデアは実現を見送りました。
でも、今回の能登地震でも、ネット回線が物理的な被害を受け、被災地域では広範な通信障害が起きたと連日報じられましたよね。改めて、ここまで情報技術が進歩しても、「オンラインの世界」にはある日突然つながらなくなるリスクがあると痛感しました。
今後、クラウドベースでの「電子カルテ」がさらに普及したとしても、オフラインでアクセスできる手段がない限り、また大地震があったときに、医療情報の取得が困難になるリスクが依然として高いと思ったんです。
スマホという読み取り機も浸透したいま、いよいよ、より大きな容量を格納できるQRコード規格を現実化させたいという思いが強くなっています。誰もがネットにつながることを前提とした情報化の時代だからこそ、いざという時のバックアップとして、「オフラインの世界」の設備を整えていきたいのです。
青い技術志向から「現場主義」へ
━━QRコードが工場での使用を想定していたのもそうですし、秘匿性のニーズに応じてつくられたSQRCも、東京都交通局の要請に応じて生まれたtQRも、そして画像を搭載できるようにするという構想も、こうしたアイデアの多くは、さまざまな業界における現場の課題から生まれたものなのですね。
原:はい。トヨタグループの「現場を大切にする姿勢」はよく知られていますし、デンソーやデンソーウェーブもまたそういう会社なのです。あらゆるお仕事の「現場」には、必ず課題がある。なんとかして課題を特定し、それを解決できないか、というのを日ごろ強く意識しているんです。
それが自社課題ならば当然、社の改善につながりますし、外部の課題ならばビジネスにもできます。僕自身もそういう考え方を仕事のなかで習い、取り組んできました。現場の課題を知ることは、世の役に立つものをつくるチャンスなのです。
━━どうやって現場の課題をキャッチしているのですか?
原:近ごろは社内外を問わず、現場の方からご相談をいただくことが多いです。ただこうなるまでは、課題をキャッチするために、デモ用の読み取り機を持ち、営業担当と共に現場に行って、「何か課題はないか?」と、お客さまと具体的な意見交換を積極的にしていました。さらに、製品を納めた後も、バグや不具合の対応のために、お客さまのところまで積極的に出向いて頭を下げに行っていました。
プライドや手間を厭わずに、誠意をもって対応することで、お客さまからの信頼を得られます。すると自然に、「こんなことで困っているんだけど、解決できない?」という相談が、取引先や関係者から来るようになる。こうした信頼関係ができて初めて、本当の困りごとを教えてもらえるようになるのです。

━━原さんは最初から厭わずそれができたのでしょうか?
原:最初は「嫌」でした(笑)。入社当初の僕は、技術への志向ばかり強い人間でしたから。「つくったものが技術として優れてさえいれば、必ずビジネスとしても成立する!」と、そんな青い考えを持っていたんです。
転機があったのは、入社して5年が経っていた1985年ごろのこと。POSレジやコンピュータとセットでバーコードリーダーを販売したいSIerの要求に応じて、OEM生産をするため、言われた通りの仕様で読み取りシステムや機器をつくる仕事をしていました。
で、ある時、仕事の一環で、とある会社の製造の現場を見学する機会がありました。なんとそこはたまたま、僕が開発に携わった製品が納められていた工場だったんですよ。
僕はそこで、自分のつくったバーコードリーダーと関連機器が一式、埃をかぶっているのを目撃しました。「ええ!?」って思って、思わず作業員の方に話を聞いてみたら、「こんなに使いづらいもの、誰が使うんだ?」と直接言われてしまったんです(笑)。
どうやら、つくったプロダクトの仕様が現場のニーズにぜんぜん、合っていなかったようでした。当時はまだ「技術が優れているものさえつくれればいい」との思いは強かったのですが、使ってもらうために開発したものが触られもしなかったのを目の当たりにして、「なんのためにつくっているのか…」という気持ちになりましたね。
そこから大きく、意識が変わりました。僕と現場との間に、さまざまな関係者が入ってしまうと、「フィルター」がかかってしまい、本当に必要なものが何かを教えてくれる「現場の声」が届いてこないと気付いたんです。
直にユーザーの声を聞きたい…そう思ったことで、僕はすっかりと現場主義になったというわけです。現在も、自社の技術営業には僕が主席技師としてお客さまのところまで同席し、ニーズを拾い、改善策を提案しています。

「楽しくなきゃ仕事じゃない」の時代だから
━━発明から30年が経った今も、原さんのQRコードに懸ける情熱は失われていないと感じます。その源泉はどこにあるのでしょうか?
原:それはもう、楽しいからですよ。
まず、お客さまからの感謝の言葉をいただけるのが何より嬉しいですよね。お客さまの相談や要望を聞いて、その課題を解決すると、ものすごく喜んでもらえます。
僕にとっては、その課題を解決できる武器が、QRコードやその関連技術なわけです。だから現場に立ち続けて、日々あらゆる人々の悩みを聞いてまわり、解決できる課題がないか探し続けています。
それに、QRコードぐらい社会に大きく根付いたプロダクトに触れていると、日常ではできないような面白い経験もたくさん、させてもらえるんですよ。たとえば、「tQR®」の実装にあたっては、鉄道路線での実証実験が必要になります。東京都だと、電車が止まるのは終電から始発までの3〜4時間だけです。普通では入れない時刻に、駅のホームからその裏側まで入っていくという経験ができたのは、純粋に面白かったです。

原:あと、SQRC®にも実はちょっとしたトリックがあります。先ほど、公開領域と非公開領域の2層構造になっていると言いましたが、厳密にいうと、これ、実は4層構造まで拡張できるんです。現状2層しか使われていないのですが、読み取り機の設定次第で、4フィールドの情報を仕込むことが将来的にはできます。
━━え?一般公開されていない仕様があるということですか?
原:そういうことです。テック企業のソフトウェアエンジニアがプロダクトを開発する際、要件となる仕様以外にも隠し機能をつくることがあるとの話をたまに聞きますが、それに近いと思います。
━━いわゆる「イースターエッグ」でしょうか。原さんは、なぜ隠された仕様を手がけたのですか?
原:だって、こうやって用意しておけば、それを使ってくれる人が現れるかもしれないじゃないですか(笑)。もっと遊んでほしいんですよ、QRコードで。4層を使い切れるアイデアを持った人がいつか現れるのが、開発者として実は楽しみだったりもするんです。
たとえば街の夜空にドローンアートで巨大なQRコードを表示させて、人々がスマホでカメラを向けてみると、機種ごとに異なるサイトが出てくるとか、そういったイベントや広告施策もできるかもしれません。
このように、僕自身は「面白い、楽しいから」という理由でここまでやってきたのですが、若いころは「仕事に楽しさや遊びを持ち込むなんてことはありえない」と説教をされた世代です。
それがいまはどうでしょう。「楽しまなきゃ仕事ではない」なんてこともよく言われるようになっているじゃないですか。
だからいまこそ、「やっぱり仕事は楽しくないと」と僕も言いたいです。そうでないとなかなか、長続きなんてしませんから。

取材・執筆:鈴木陸夫
編集:田村今人・王雨舟
撮影:赤松洋太
関連記事

「情報 I・II」を学んだ高校生の技術レベルってどのくらい? 元エンジニア校長にホントのところを聞きました【フォーカス】

NFTで儲けたい人が見落としたもの 新しい技術を使いこなす正しい姿勢をブロックチェーン研究者が語る【フォーカス】

“アニサキス殺し”パルスパワーは「器用貧乏」な技術だった 「電気エネルギー界のドラえもん」が拓く未来【フォーカス】
人気記事