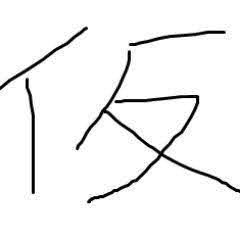最新記事公開時にプッシュ通知します
ゲーセンの『ダライアス外伝』で学んだPDCAの回し方
2025年9月22日
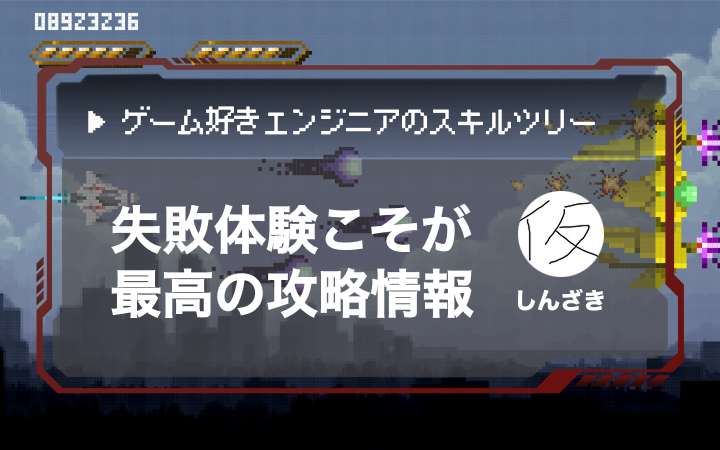
こんにちは、しんざきです。
この記事で書きたいことは、大体以下のような内容です。
・スコア狙いプレイをする上で、失敗するとつい「捨てゲー」をしてしまう、いわば失敗体験を受け入れられないことが課題でした
・これは、仕事で言うと「成果物のハードルを上げ過ぎてしまい、トライ&エラーができなくなる」という状態に近いです
・「成功目標」ではなく「失敗目標」をつくって、その失敗を言語化することをルールとして心がけるようになりました
・上手くいかなかったとしても、試行回数を重ね、「失敗」から何かを学ぶことができると実力は伸びます
・そのために、失敗体験を受け入れる心の余裕を持つことが重要です
・自分の「失敗」に向き合い、失敗体験から経験を得るノウハウを身につけておくと、役に立つことが多い気がします
よろしくお願いします。
さて、書きたいことは最初に全部書いてしまったので、後はざっくばらんにいきましょう。
- しんざきのシューティングゲーム偏愛について
- スコア狙いプレイで立ちはだかった全国の高い壁
- 理想と現実のギャップに向き合えず「捨てゲー」気味に
- 「失敗ノート」がもたらした、たった1度の栄冠
- 仕事でも活きた「失敗体験」との向き合い方
しんざきのシューティングゲーム偏愛について
ちょっと、ゲームの話から始めさせてください。
しんざきは幼児の頃からのゲーム好きなのですが、特にシューティングゲーム(以下、STG)が大好きです。
近所の駄菓子屋においてあった『ゼビウス』というゲームに魅せられて以降、「敵が弾を撃ってきて、それを避けて、自分も弾をばしばし撃って敵を倒す」というSTG特有の面白さが、すっかり脳に刻み込まれてしまいました。
STGと一言でいっても色々あるのですが、私が偏愛しているのは『グラディウス』や『R-TYPE』『コットン』『ファンタジーゾーン』のような、いわゆる「横スクロールSTG」といわれるジャンルです。
そんな中でも『ダライアス外伝』(通称:ダラ外)というゲームについては、人生でもトップレベルにやり込みました。あれだけ濃密な時間はもう二度と過ごせないかもな、と思うくらい、誇張なしで「一日中」ダラ外を遊んでいました。今でいう廃人です。
『ダライアス外伝』というのは、1994年にタイトーから発売されたSTGでして、魚の形をモチーフにした巨大戦艦がボスである『ダライアス』シリーズの3作目です。
何かの冗談のようにかっこいいBGMと、どんどんパワーアップしていく自機「シルバーホーク」で敵を蹴散らす爽快感、そして魔法でもかかっているかのように印象的な各ステージ・ボスの演出に、私は完全に魅入られてしまったわけです。
例えば、最終ゾーンの1つである「Yゾーン」。このゲームのBGMは、どの曲ももの凄く印象的なのですが、最終ゾーンだけは「無音」で始まります。今までと打って変わって静かな空間、Yゾーンの場合は生命力の粋であるはずのジャングルのような地形で、静かにスクロールするゲーム画面、けれど敵の攻撃だけは普段とまるで変わらず激しいまま。その激しい攻撃をひたすら凌いでいると、やがてゆっくりと流れ出す、静かな、あまりにも静かな最終面BGM「SELF」。
STGの最終面としてはあまりに独創的な、もの悲しささえあるメロディを聴いている内に、やがてジャングルに虹がかかり、その虹を突き破るかのように現れる最終ボス、マンボウをモチーフにした偉容「オーディアストライデント」。
人生の中でも、これだけ衝撃を受けたゲーム体験は滅多になく、上記の光景は今でも脳にはっきりと刻みこまれています。まあ、今久々にプレイしてみると、当時やり込んだ頃のプレイが全然再現できなくて絶望するんですけど。
スコア狙いプレイで立ちはだかった全国の高い壁
さて。
皆さんご存知かもしれないですが、STGには「スコア狙い」という遊び方があります。主に敵を倒すと上がっていく得点を、可能な限り稼いでいくプレイ。当時は、一部のアーケードゲーム雑誌で、毎月ハイスコアの集計をしていて、ゲーセンからスコアを応募するとそのスコアを雑誌に載せてくれたりしていたんですよ。
「スコア」というのは、要は「自分がどれだけそのゲームをやり込んだか」ということを示す指標です。どのステージで、どんな動きをすれば得点が上がるのか。どこまで自分のプレイを突き詰められるのか。それが、「スコア」という数値で、とても分かりやすく可視化されます。
私は、ダラ外が好き過ぎて、本気で全国スコアを狙いにいこうとしました。自分が一番好きなタイトルで、並み居るSTG強者の中に割り込みたい。そう思いました。
当時、インターネットはまだ一般的ではなく、当然攻略サイトも動画サービスもありませんでした。情報源にできるのは 『ゲーメスト』のようなゲーム攻略誌と、「Nifty」や「東京BBS」のようなパソコン通信、あとはあちこちのゲームセンターを回って、他のプレイヤーのプレイを盗み見ることくらいでした。
といっても、プレイの盗み見は「スパる(スパイする)」と言われていて、店舗によっては嫌がられたり、スパイ防止のために段ボールで目隠しをされたりしていました。この時の経験もあって、私は今でも「人のプレイ動画を見て学習する」という行為に罪悪感があります。
バイトの資金や可処分時間など、生活のほぼ全リソースをつぎ込んだおかげで、私の腕前も少しずつ向上して、近所のゲーセンではほぼ1位から落ちないくらいの腕前にはなったのですが、まだまだ全国スコアまでの道は遥か遠いままでした。この時になって初めて、私は自分のプレイスタイルについて悩み始めました。
理想と現実のギャップに向き合えず「捨てゲー」気味に
今だからはっきり認識できるのですが、当時の私は、1つ大きな課題を抱えていました。
それは、自分の「失敗体験」をうまく言語化・活用できていない、という課題です。
ダラ外のスコアアタックにおいて、「銀勲章(得点が入るボーナスアイテム)」のランダム得点による大きな運要素以外は、基本的に「腕前」だけの世界になります(厳密にはランダム要素もあるのですが、脇道なので一旦おいておきます)。例えば上手い人のプレイを参考に、「こう動けば高い得点が出せるはずだ」という動きを想定した後は、ひたすらその動きに自分を近づけていくために練習します。
STGが上手い人というのは、この「最適な動き方」というのを理屈ではなく直感的に見出して、しかもそれを突き詰めていくことができるのですが、私はそうではありませんでした。本来、今でいうPDCAを繰り返して、愚直にプレイを最適化していかなくてはいけませんでした。
いわゆる「シューター」の方なら覚えがあるかと思うのですが、STGには「捨てゲー」という概念があります。例えばノーミスクリアが目標なら、ミスしてしまった時点でそのプレイは捨てて、さっさと次のプレイにいく、という概念ですね。
私は、大して上手くもないくせに、プレイが上手くいかないと捨てゲー気味になってしまっていました。自分の中でなんとなくの理想像はあるのに、そこに近づけようとしてミスをしてしまうと、「ちくしょう!」という悔しさのあまりやる気がなくなって、その後のプレイがおざなりになってしまうし、「今なんで失敗したんだろう?」ということを考え抜くこともできていなかったのです。
要は、自分の「失敗」にちゃんと向き合えていなかったし、失敗から学ぶこともできていませんでした。
ゲームセンターですから、背後で見ているギャラリーに対する見栄やプレッシャー、という面もあったと思います。何かしら失敗したら恥ずかしいし、それ以上みっともないプレイを見せたくない。だから、「はい次、次」という感じで、そのプレイを締めてしまいたくなる。
ただ、今から考えると当たり前のことなのですが、「既に腕前が完成してる人」が時間を節約するために捨てゲーをするならともかく、「まだまだ発展途上の人」が捨てゲーをしても、何一ついいことはないんですよね。失敗したその先の展開を学習することもできないし、正しいプレイを試行することもできず、結果何度も同じことを繰り返すだけ。ゲーセンでプレイごとに50円必要なのでお金ももったいない。
本当は、「自分が何故失敗したのか」「今のプレイはどこが悪かったのか」「どうすればそれを回避できたのか」って滅茶苦茶重要な情報で、つきつめれば自分にとっての最高の攻略情報になり得ます。失敗すればする程、自分にとってのノウハウが増えていくのです。
「失敗ノート」がもたらした、たった1度の栄冠
さっき、「スパる」、つまり他人のプレイをのぞき見る行為について触れました。実を言うと、私が「スパった」中で一番重要だったのは、名古屋のとあるゲーセンで、ダラ外をプレイしていた人が、ミスをした後「そのミスの内容」「ミスの原因」をノートに書き付けている姿を見たことでした。
その人を真似して、私は「失敗ノート」をつくり、「失敗目標」を決めました。つまり、「今日は1日最低何回は失敗する」ということを決めて、その「失敗」の情報を集積することを、1つの目標にすることにしました。
これの何が良かったかというと、まず「失敗」に対する心理的障壁がなくなったんですね。もちろん失敗のないプレイを目指しはするけれど、失敗自体は発生して当然、むしろ目的の1つだし、ノートの記載が増えるので悪いことは何もない。そういう風に頭を切り替えることができた。
ノートに書くために、1回1回の失敗をちゃんと言語化するようになった、というのも大きかったと思います。失敗の言語化というのは、要は原因分析であり、「どうすればよかったのか」を模索する作業でもあります。それが重なれば重なるほど、自分にとってのテクニックは蓄積されていきます。
ここで蓄積した「テクニック」は本当に色々とあるのですが、例えば「Jゾーン」というステージのスコア稼ぎ。このステージ、上手くいく時といかない時で何十万点もスコアに差が出るステージでして、これは「ボスの直前のシーンで可能な限り素早く敵を倒さないと、高得点の敵が出現しないで消えてしまう」ということが原因なのですが、スコアが出なかった時の動きを言語化することで、自分なりのパターン構築につなげたのが、失敗ノートの効果の1つでした。
こういった成果の結実として、私はとあるゾーンで1度だけ、全国1位のスコアを出すことができました。そのゲーセンのスコアボードに自分の名前が載り、それを雑誌にも応募してもらえました。全国1位を示す「星」がついた時には、ゲーセンで「おっしゃぁぁぁ!」と叫びました。
まだ、全国で「どういうプレイがハイスコアに繋がるか」ということ自体模索されていた、いわばどさくさ紛れの話です。当時の全国スコアはどんどん更新されていき、私が出したスコアは次号ではあっさり他の人に置いていかれ、以降は全く届かなくなってしまいました。やがて、ダラ外には自機が無敵になるバグが発見され、スコア集計自体取りやめになってしまいました。確か、スコア集計が始まって半年ちょっとくらいのことだったと思います。
それでも、この「1度きりの全国スコア」は私の勲章になりましたし、あのスコアを見た瞬間の喜びは、今でも昨日のことのように思い出せます。あそこまでゲーム攻略を突き詰めることは、今ではなかなかできないですが、それでも「失敗」に対するスタンスは、あの経験を経て明確に変わったと思っています。
以上が、私にとっての『ダライアス外伝』と、「失敗体験」についてのエピソードです。
仕事でも活きた「失敗体験」との向き合い方
上記のような話は、ゲーム以外、それこそ趣味でも、仕事の上でも、あらゆる場面で発生することです。
私は、モチベーションを育てるのは成功体験、テクニックを育てるのは失敗体験だと思っています。
プレゼンの資料作成でも、モデル設計でも、アーキテクチャ設計でも、「正解」がすぐ見えることなど、実際のところほとんどありません。あーだこーだと色々つくっては、「ここがダメじゃん」「これ抜けてるじゃん」ということに気付き、あるいは他者からフィードバックを受けて、時には盛大なバグを出してシステムを止めながら、少しずつ自分のノウハウを溜めていきます。
けれど、自分の「失敗」と向き合うのは、どんな人にとってもキツいことです。誰だって叱られたくはないし、ダメ出しをされたくはない。結果、トライ&エラーの回数自体が減ってしまうし、成果物が小さく小さくまとまってしまうのです。
だから、「失敗体験を受け入れる心の余裕をどうつくるか」というのは、どんな人にとっても重要なノウハウです。仕事によっても、環境によっても、周囲の人によっても適したやり方は変わるので、何が正解というのは言い難いところではあるのですが、「失敗」を積む心理的下地が強固であるほど、その人の実力は伸びやすいということについては、一般的に言ってしまっていいと思います。
私自身が『ダライアス外伝』の攻略過程から学んで、そして仕事でもちょくちょく使っているやり方は、「失敗を逆に目標にしてしまう」ということです。失敗の数自体を、いわばKPI(数値目標)にしてしまって、それをチーム内の共通認識にしてしまうわけです。特に、失敗を怖がる傾向のある新人さんの指導に有用なやり方です。
例えばコーディングで、「3つ以上失敗してみましょう」と伝えてみたり。あるいは週次の報告で、「失敗したこと」を報告事項にしてみたり。実際に「失敗した」と思ったことを言語化して、リストにしておいてもらう。そうすれば、「これだけ失敗しましたよ」ということを成果にできる。自分が言語化した失敗を、他人にも共有できる。失敗が成果の一部になることで、「失敗すること」の心理的な負担が大幅に軽減する。
重要なことは、「失敗」というものの価値をチーム全員で共有して、「失敗すること」を許容どころか推奨する、そういう空気をつくることじゃないかなあ、と思います。
そのためにも、自分の「失敗」に向き合い、失敗体験から経験を得られるノウハウを身につけておくと、役に立つことが多いのではないか、と。
そういう話だったわけです。
最後に少しだけ余談になるのですが、最近「アーシオン」というゲームが発売されました。ゲームBGM界のレジェンド・古代祐三さんが手がけた新作横シューで、かつてのメガドライブの雰囲気を如実にたたえ(実際にMD互換らしいのですが)、演出もすごければ爽快感も素晴らしく、一方「何度も遊ぶことで自機の強化が蓄積されていく」という、初心者が遊びやすい要素もあります。
全国の横シューターが「俺はこれが遊びたかったんだ!!」と叫ぶような傑作なので、皆さんも是非遊んでみていただけないでしょうか。面白さは保証します。
今日書きたいことはそれくらいです。
関連記事
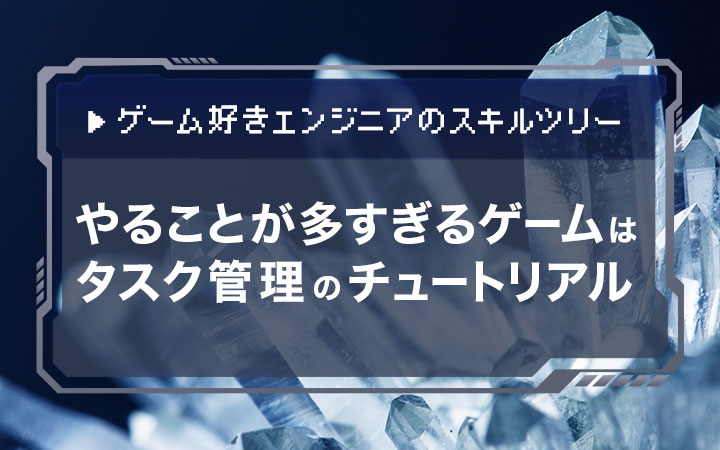
『FF14』でタスク管理のノウハウを学んだ話|しんざき
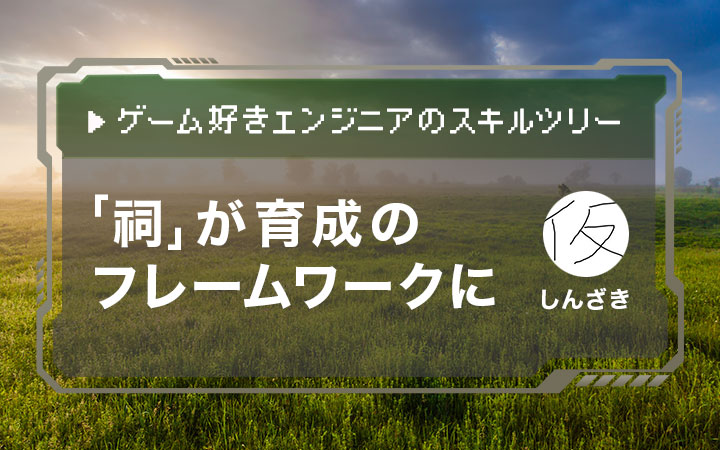
『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』に学ぶ、スキル習得の難易度コントロール
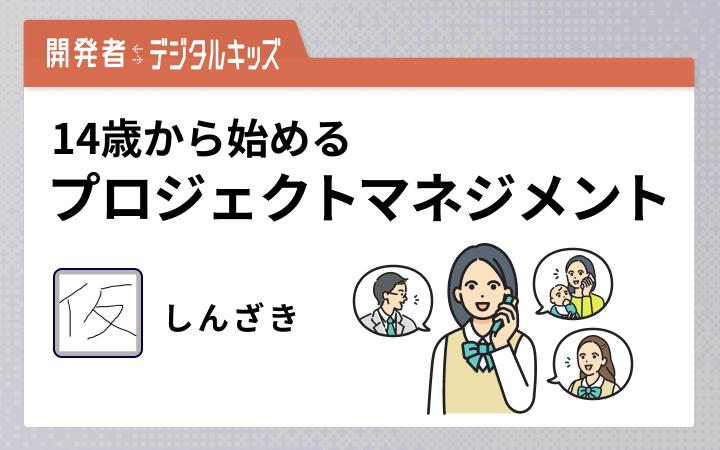
「中学生だけのカラオケ会」開催失敗から長女と学んだ「事前調整」の大切さ
人気記事