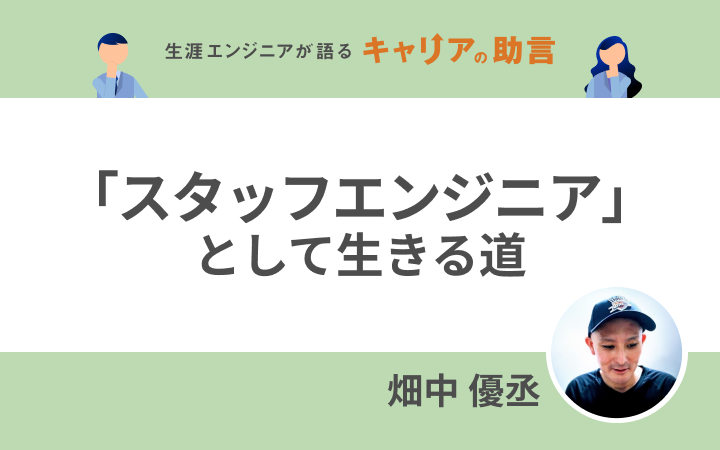最新記事公開時にプッシュ通知します
「市場価値」への不安に押しつぶされそうだった10年前。現状認識から始め、キャリアの「軸」を見つけるまで
2025年8月21日
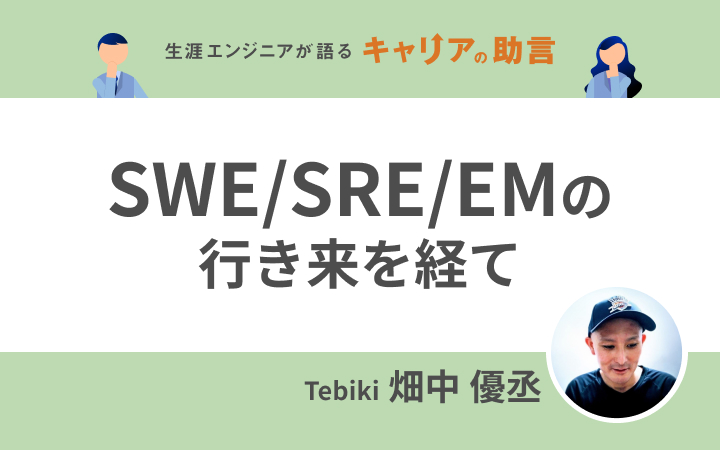
私はこれまでにソフトウェアエンジニア(以下、SWE)、SRE、エンジニアリングマネージャー(以下、EM)を行き来しました。1つ言えるのは、様々な経験をすることは、私にとっては良かったということです。マネージャー職から再びSWEに戻れるのかどうか不安である、といった感情も生まれませんでした。ただ、このキャリアを人にすすめられるのかは、わかりません。
なぜなら、今見える景色から何かを感じ取り、現状を認識し、進みたい方向へ足を伸ばしてきたに過ぎないからです。自分に嘘を付かず、自分の感情に素直に従って来たということです。それでも後悔をしたことはありません。
この記事では、私がこれまでに繰り返してきたキャリアの選択について、そのきっかけや、どのように現状認識してきたのかをできるだけ具体的に書き、なるべく思考プロセスを感じていただけるよう努めました。ご自身のキャリアに対する考え方と照らし合わせるきっかけとなれば幸いです。
- 35歳、プレイングマネージャーとして抱いた漠然とした不安感
- 技術的なチャレンジを求め、いちプレイヤーとして転職
- 再びEMに。中間管理職となり、大局観を得る
- 40歳、スタッフエンジニアへの道
- まとめ:キャリアの選択とは
35歳、プレイングマネージャーとして抱いた漠然とした不安感
およそ10年ほど前、私はとあるC向けWebサービス開発会社で、EMとして働いていました。私にとってこれが最初のEM経験であり、書籍やブログを参考にしたり、勉強会などでお会いする他社のEMの方に話を聞くなどしながら、試行錯誤を重ねていました。働く時間の半分ほどは開発も行っており、いわゆるプレーイングマネージャーとして、3年ほど働きました。当時私を精神的に支えていたのは、技術で組織をリードすることに対する、自信と実績でした。
一方で、「自分は市場で高く評価されるような技術を有するエンジニアではないのではないか」という不安に押しつぶされそうになっていました。
なぜここまでの不安を抱えてしまったのでしょうか?
振り返ってみると、1つはSNSの流行があったように思います。2010年代当時は、AWSを代表とするパブリッククラウドによる運用事例が増え、Docker によるコンテナ技術の普及、それからGo言語によるアプリケーション開発など、現在に繋がる技術の潮流がテックブログやTwitterなどのSNS上に現れ始めた頃でした。私は、これらの技術のメリット・デメリットへの理解や、活用実績を積むことが、今後も技術者を続ける上で必要になると感じていました。
しかし、現在では主選択となり得るこれらの技術も、当時は採用するために組織的な体力を必要としました。そのため、当時から少しずつ導入や検証を進めていたものの、日々、凄腕エンジニアの足跡を目で追い、劣等感を養うといった結果になっていました。
もう1つは、当時35歳になった自分にとって、市場と比較したときの収入に差があると感じていたことでした。
この漠然とした不安感の正体を自分なりに認識できたことで次のキャリア選択の基準が定まりました。つまり、「収入が市場水準にある」「生活拠点の関西で働ける」、そしてさらに技術者として自分のスキルを高められるように「理想から考え技術を選択できる器量があり、技術的なチャレンジが文化として根ざしている組織」でキャリアを歩むと決めました。ここまで現状を認識すれば、後は面談の中で欲しい情報を引き出し、自分に合う組織なのかどうかを考えることができました。
技術的なチャレンジを求め、いちプレイヤーとして転職
チャレンジは成功し、とあるB向けWebサービス開発会社で働くチャンスを得ることができました。ここで私は、SWEからSRE、そして再びEMというキャリアを歩みました。
入社して最初の1年半ほどは、スクラムチームの一員として、SWEとしてプロダクト開発に携わりました。そのチームは誰のために、何のためにソフトウェアを開発しているのかということに、強くフォーカスできるチームでした。「チームファーストで、目の前のことを一生懸命やる」ということの価値が深く刻まれた体験だったと思います。これは、今でも大切にしている価値観です。
この期間で、自分がこれまで積み重ねてきた技術や働き方がここで通用するという自信を付けることができました。これは、チームのサポート無しにはあり得なかったことです。当時のチームメンバーには本当に感謝したいです。
メンバーとしてSREチームへ
ある日、SRE職へのチャレンジを打診されました。携わっていたプロダクトのインフラ実装を主導したことがきっかけだったと記憶しています。私にとっては、「できないことができるようになるチャンス」であり、有り難くチャレンジさせていただきました。
スクラムチームで働くなかで、「自分ができないと思うことは、ほとんどの場合、単にやったことがないだけである」という気付きがありました。技術に発明、実装、利用があるとすれば、ほとんどの場合、私は技術の利用者です。発明と実装が難しくても、利用することは技術的に可能です。
一方で、これには、少し「嘘」も含まれています。技術を使いこなすためには、対象の技術領域に対する構造的な理解が必要なのは言うまでもありません。例えば、Linux OS でアプリケーションを動かすのであれば、メモリやプロセスに対する理解が必要です。TCPで通信をするのであれば、プロトコルへの理解が必要です。アプリケーションを実装するなら、対象の言語ランタイムに対する理解が必要です。なぜそうなのか、構造的に理解することが「利用する」上で近道になりますし、積み重ねた知識からしか得難い知識も存在しています。
これは技術に限ったことではありません。プロダクトや組織、採用に至るまで、様々な領域に対する知識と経験の積み重ね、そこから得られる構造的な理解は、戦略的に物事を進めるために重要だと考えています。
さて、当時のSREチームは、個々人でテーマを持って開発しつつ、全サービスのインフラ保守運用を行うようなチームであり、スクラムチームの働き方とはまったく違っていました。最初は戸惑ったものの、技術にも働き方にも少しずつ慣れていきました。
再びEMに。中間管理職となり、大局観を得る
再びEMになることを決意したのは、SREチームに移って1年ほど経ったときのことです。35歳当時に抱えていた、技術や市場価値への漠然とした不安は既に無く、「チームファーストで、目の前のことを一生懸命やる」という基準が強く残っていました。そこで私は、拡大するSRE組織を支えるために、EMがもう1人必要だと考えるに至り、それを自ら志望しました。これが次の転機となりました。
SREチームのEMとしては2年半ほど働きました。当時、私がEMとして重視していたことは、中長期的なSRE組織全体の組織構想を議論できるようにすること、社内でチームのプレゼンスを高めること、それからメンバーの評価キャリブレーションを行うことでした。そして、これらの取り組みを通じて、EMとして組織全体のテーマを理解することと、チームのテーマを考える必要性に気付くことができました。
社内でチームのプレゼンスを高める
EM時代の後半1年ほどは、プロダクトチームが自律的にサービスを運用することができる仕組みを開発する、プラットフォームチームのEMとして活動していました。我々が開発するプラットフォームの利用者は社内のエンジニアであることから、社内でチームのプレゼンスを高めることは非常に重要でした。我々が何をどのような意図で作っているのかを認識してもらい、実際に使ってもらうため、毎月全社にチームの取り組みを発信し、特に改善の成果を数字で出すことにこだわりました。
メンバーの評価キャリブレーション
メンバーの評価キャリブレーションとは、私とメンバー、および私の上司との間で、人事評価が確定するタイミングより前に評価に合意している状態を作ることを目的とした施策です。人事評価に驚きは必要ありません。それを実行に移すためには、組織全体のテーマを理解し、チームのテーマを言語化し、それらをベースにメンバーごとのテーマを議論し、合意し、進捗を確認し、フィードバックをする必要がありました。
当時は中間管理職であり、評価を最終決定できる立場にはありませんでしたが、私がどれだけメンバーの成果を上流にアピールできるかが、人事評価における重要なインサイトとなることは理解していました。私がメンバーの成果を説明できない場合は、何かが足りていないというサインです。これを言語化し、代替を提案し、粘り強く寄り添うことは、非常にタフな経験となりました。
このように大規模な組織でのEM、中間管理職として働き、自らテーマを作り上げる過程で、新しい価値観を発見することができました。
それは「プロダクトビジョンが組織と技術、全ての礎となる」という価値観です。
通常、組織全体のテーマに、実現のためのプロセスが示されることはありません。プロセスは、個々のチームの仮説によって決定されるのが一般的でありますし、スケーラビリティの観点から、それが現実解でもあると思います。これらの仮説は、一定期間を経て検証され、その結果は次の仮説へと利用されます。
全ての意思決定には、仮説検証のサイクルがあるべきだと考えています。組織全体が効率的に向かいたいところへ向かうには、組織全体の仮説、すなわちテーマが検証されねばなりません。私は、このテーマがプロダクトビジョンだと気付いたのです。なぜなら、顧客を成功へと導くことが我々の使命であり、その具体的なソリューションがプロダクトだからです。
そのような大局を見るようになったからこそ、EMとして組織開発にウェイトを置く活動と、プロダクトビジョンの実現のために顧客課題に向き合う活動との間で葛藤が生まれました。顧客課題への仮説検証を繰り返す開発サイクルにこそが価値であるという考えのなか、その手応えを実感することができずにいました。これが次の転機となりました。
40歳、スタッフエンジニアへの道
このまま現職でいるというよりは、様々な可能性について考えてみたくなりました。
私にとってコミットすべきプロダクトビジョンとは、壮大な仮説であり、程よく実現可能性を帯び、顧客が儲かる仕組みを含んでいるものだと考えています。また、主にエンタープライズ製造業向けプロダクトであることも重視しました。欧米と比較して、日本のエンタープライズ製造業のDXは遅れを取っているように感じ、非常に解決の難しいチャレンジングな領域に思えたからです。そして、私は現職の Tebiki のプロダクトビジョンに共感しました。
このようなプロダクトビジョンそのものの納得度に加え、既に組織で働いている人々が、プロダクトビジョンに対して熱狂的かという観点も重要でした。多くの人が熱狂的になれるビジョンにこそ価値があると考えていたからです。社員がプロダクトビジョンに熱狂的かどうかは、社員にプロダクトビジョンを語ってもらうのが一番だと思います。特に、EMや役員といったプロダクトビジョンへの解像度が高いであろう人よりも、一緒に働くチームメンバーに面談の機会を頂き、直接プロダクトビジョンについてどう思うかを聞いてみるのが良いと思います。
反対に、どのような技術を使っているか、現在の組織体系や評価制度、どんなエンジニアが働いているのかなどは興味の対象になりませんでした。これらは、組織の拡大に応じて変化することも、コントロールできることも、順応することも可能です。しかし、プロダクトビジョンはそうではありません。全てのベースとなるプロダクトビジョンへの価値観の違いは、許容できないと思っています。これらの要素を踏まえて、私は、Tebikiのプリンシパルスペシャリストという肩書で入社しました。
役割としては、一般的にはスタッフエンジニアと呼ばれるポジションに近いと考えています。テックリードと呼んでいる組織もあるかもしれません。ここでは、スタッフエンジニアと呼称することにします。
Tebiki のスタッフエンジニアを一言で表わすと、ピープルマネジメントよりもテックマネジメントに軸足を置いたリーダーということになります。とはいえ、スタッフエンジニアにも、ピープルマネジメントの領域は明確に存在しています。例えば、次のスタッフエンジニアを見出すといったことが該当します。また、全てのリーダーに通じる素養として、組織の信頼を獲得することが求められます。これらは、エンジニアリング能力だけで成すことはできず、経験の厚みが活きる部分であると考えています。このことは、EMを経験すべきかという質問の1つの答えになると思います。私は、チャンスがあるなら経験するべきだという考えです。
信頼とは、私の意思決定に対する信頼と言い換えることができます。どのようなリーダーのどのような意思決定なら信頼することができるでしょうか?次回、私が Tebiki のスタッフエンジニアとして何を考えているのかについて書きたいと思います。
まとめ:キャリアの選択とは
本記事では、私のこれまでの転機、そのきっかけとなる現状認識を振り返りました。
プレイングマネージャー時代に抱いた漠然とした不安感は「市場で通用するのかが不安」というものでした。転職後、チームでの成功体験を積み上げることで、その不安はなくなり、「チームファーストで、目の前のことを一生懸命やる」という大切な価値観を持つに至りました。まず漠然とした不安感を払拭できたからこそ、この価値観へ至ったのだと思います。なぜなら、目の前のことを一生懸命やることが重要だと思うためには、市場での価値が認められたエンジニアなのだという自負が必要だったように思うからです。
そして2度目のEM経験で、「プロダクトビジョン」がキャリアの軸になると気付きました。壮大な仮説であり、程よく実現可能性を帯びた、顧客が儲かるプロダクトビジョンを求めてTebikiに転職しました。これが、私のキャリア選択の全貌です。
では、私にとっての「キャリア選択」とは何なのでしょうか。
それは、無限の可能性と現状の両面を認識することから始まるものです。キャリアの選択は、制限された選択肢の中からいくつかを選ぶことのように感じているかもしれません。そう感じるのは、世の中には無数の選択肢がある中で、職種、分野、年収、労働環境などをはじめとし、選択肢を無意識のうちに自らの基準で制限しているからです。キャリアの選択を司る基準は、人それぞれに存在しています。まずは現状と向き合うことで、その「制限」に気付くことが次のステップにつながります。
そもそも、キャリアとはゴールの存在しない「道」のようなものと捉えています。
キャリアを選択し進むことは、ゴールに近づくことではありません。今見える景色から、行きたいところへ向かうことが、キャリアを前進するということです。行きたいところが無くても構いませんし、とても辿り着けそうになくても構いません。しかし、目の前にはただ自分の道があり、それを歩き続けます。同じ日は二度と訪れませんし、キャリアを戻る道も存在しません。やり直すことはできず、全ては前進となります。
そのため、例えばこれまでのキャリアをもう一度選び直せるとして、再び同じ選択をするかどうかは本当にわかりません。そのときに何を感じるのかによるからです。その時に何を思うかわからない以上、今考えても意味が無いと思っています。言い方を変えるなら、「今」の方が、より重要です。
とはいえ、私は、情熱に突き動かされたとてつもない行動力の持ち主ではありません。キャリアの道を歩む中では、迷うこともあります。何かを成し遂げようとしている人には圧倒されます。自分には無い情熱や行動力を目の当たりにし、我が身を振り返ります。才気に溢れた人々を横目に、自分はこのままで良いのだろうかと不安になります。しかしそれでも、目の前には自分の道が存在するだけです。
これが、キャリアに対する私の基本的な考え方です。
おそらく方法には個人差がありますが、最後に私のメソッドを紹介して終わりにしたいと思います。四六時中内省し、キャリアの考察を深めているわけではありません。現状認識は、自分と対話を繰り返すことと言い換えることができます。
私の場合は、朝の散歩です。ごく一般的な習慣であり、共感できる方も多くいらっしゃるかもしれません。週に2〜3日、多いときには毎日、時間にして80分ほど、外を歩いたり走ったりします。コースは変えないことにしています。80分の1on1は、思った以上に効果があるようです。最初の数日は、景色が珍しかったり、ポッドキャストが面白かったり、歩いていること自体が新鮮で自分との対話に時間が割けません。
しかし、続けていると、次第に外の景色など珍しくもなんともなく、ポッドキャストはなんとなく流れ、自然と頭の中で引っかかっていることについて考え出すようになりました。昨日の件は腹が立ったなとか、あのときはなんと言えば良かっただろうとか、今日のミーティングはどのように進めるかとか。日ごとに自然と湧いてきます。些細なことでも記憶に残り、感情が動き、脳のリソースを消費していることに気が付きます。このとき、なぜそうなのか自問自答を繰り返し、構造を理解しようと努めるのが好きです。答えを見つけるのではなく、仮説を立てるのです。全てはこの朝に、自分で整理します。私の場合は、この習慣が現状認識に繋がっているようです。
関連記事
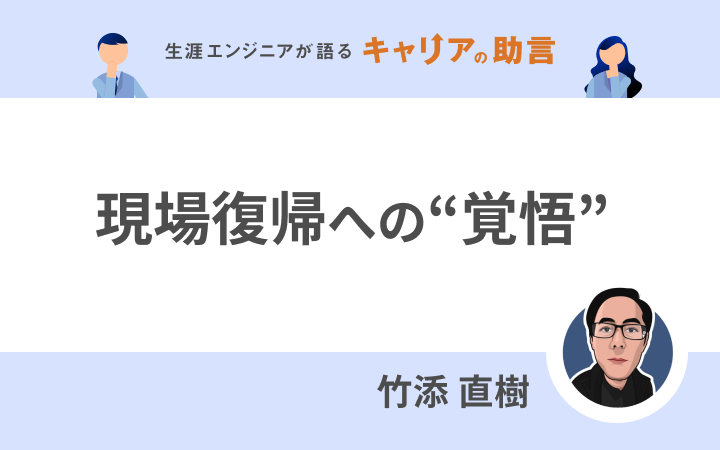
「もう一度、現場へ」40代プリンシパルエンジニアが開発の第一線にこだわる理由
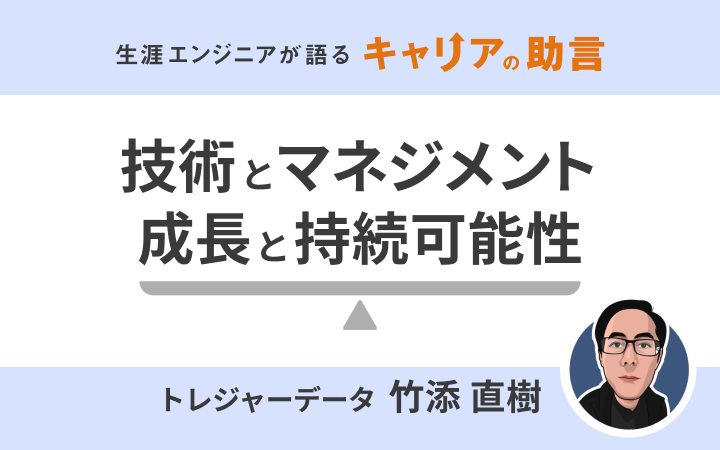
40代シニアソフトウェアエンジニアが見つけた「燃え尽きない」ための“バランス”
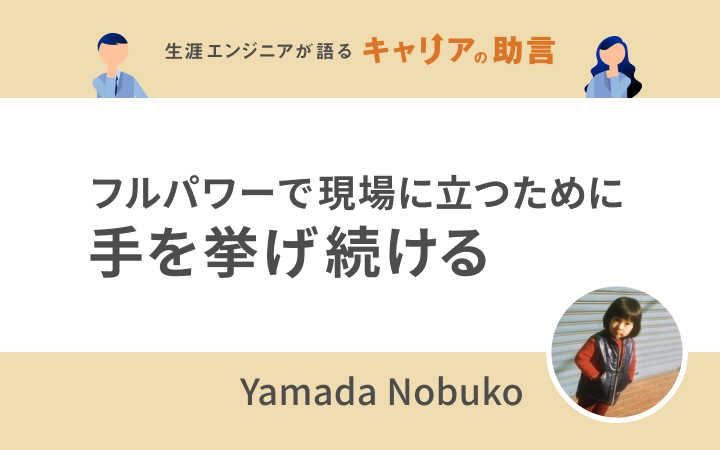
【新連載】「生涯、エンジニア」を目指す私が勤続20年で身に付けたキャリアの築き方
人気記事