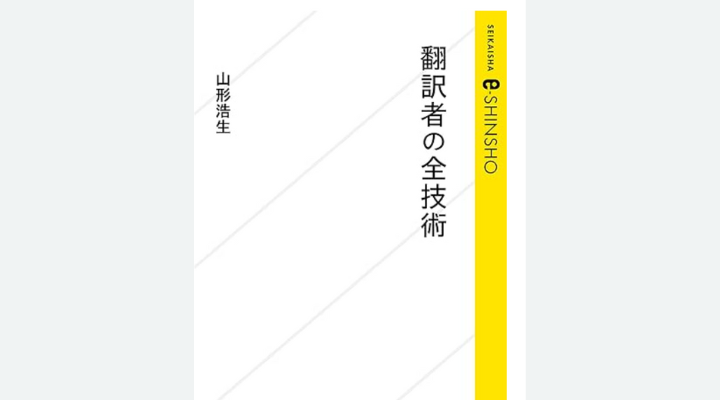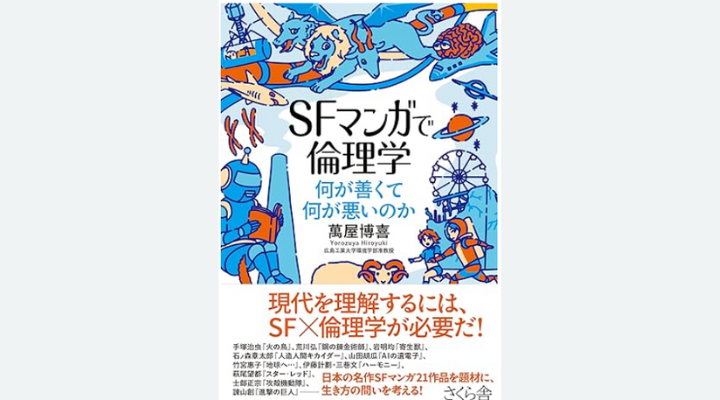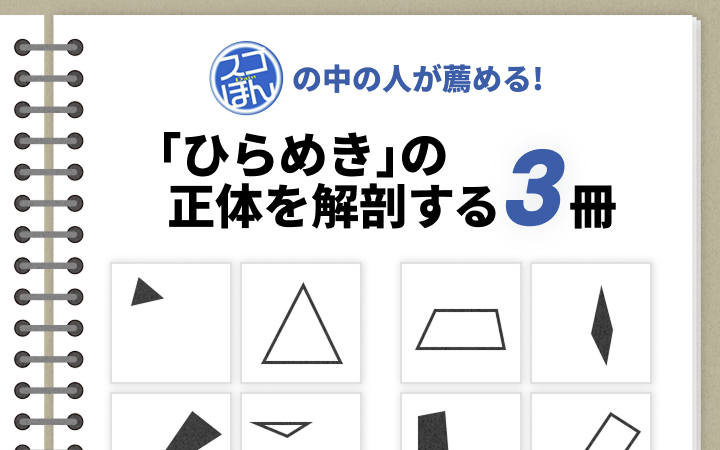最新記事公開時にプッシュ通知します
【スゴ本】雑多なインプットで「センス」を増やす5冊
2025年7月24日


古今東西のスゴ本(すごい本)を探しまくり、読みまくる書評ブログ「わたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいる」の中の人。自分のアンテナだけを頼りにした閉鎖的な読書から、本を介して人とつながるスタイルへの変化と発見を、ブログに書き続けて10年以上。書評家の傍ら、エンジニア・PMとしても活動している。
わたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいる
- はじめに
- 未知の分野を開拓し、“中間地点”を探す
- “SF×倫理学”。好奇心のアンテナを掛け合わせる
- 論文=好奇心を呼び覚ます、科学のカタログ
- 「人」からたどる知のネットワーク
- アンテナの受信感度を高めるトレーニング
- おわりに
はじめに
センスとは何か。
ひとことで言えば、「世界から感じ取る能力」になる。大事なのは、「感度」だけではなく、「受信アンテナの数」や「接続するチャンネル数」でもあることだ。つまり、ある事物に対して「良い」と感じられるかどうかは、その人の中にそれを感じ取るアンテナやチャンネルがあるかどうかにもよる。
例えば、あるウィスキーを飲んだときがこれだった。強烈な風味に驚いたのだが、一緒にいた友人に「これ、正露丸の味でしょ?」と言われて、口の中で起きている経験と正露丸の記憶がつながった。
私がハマったこの香り、麦芽を乾燥させる際に燃やすピート(泥炭)から生まれているんだそうな。私にとってラフロイグの10年モノなんて気軽に飲める代物ではないので、ウィスキーを飲むたびに正露丸の香りを探すようにしている。ウィスキーを楽しむチャンネルが増えたと言える。
そう考えると、センスとは世界から何かを感じ取り、それを「美味しい」「面白い」「楽しい」と認識できる能力だといえる。
だから、センスは「磨く」というよりも、「増やす」ことが重要なのだ。
では、どうやってアンテナやチャンネルを増やすのか?
答えはシンプルで、「自分とは異なるアンテナを持っている人・モノ・分野に接触する」になる。面白い問題に取り組んでいる人を見つけたり、自分が使わない思考ツールを試したり、よく知らないジャンルの事例を調べたりする。
自分が慣れ親しんだ世界とは別の領域へ「越境」することで、それまで持っていなかった視点を得たり、自分の中に蓄えられていた経験と外界との別のつながりかたを見出すのだ。
ここでは、そうしたアンテナやチャンネルを増やすことに役立つ書籍を5冊、紹介する。知らない世界へ「越境」する手がかりとしたり、記憶と経験を結びつけるチャネルを増強する手立てとしてほしい。
- 1. 『翻訳者の全技術』山形浩生 著
- 2. 『SFマンガで倫理学』萬屋博喜 著
- 3. 『すごい科学論文』池谷裕二 著
- 4. 『宇宙・動物・資本主義』稲葉振一郎 著
- 5. 『センスの哲学』千葉雅也 著
未知の分野を開拓し、“中間地点”を探す
実践的なやつは山形浩生『翻訳者の全技術』にある。
これ、タイトルに「翻訳者」とあるので翻訳の話かと思いきや、ぜんぜん違う。Linuxのようなオープンソースの古典『伽藍とバザール』、ピケティ『21世紀の資本』、囚人実験の先駆け『服従の心理』、Netflixでドラマになってる『エレクトリック・ステイト』の原作などの翻訳を手がけてきたため、タイトルに「翻訳者」と入れたいのは分かる。
けれどもこれは、本の読み方とか積読の是非、どうやって知的領域を広げるかといった、いわば山形浩生の知的心得帖ともいえる一冊なんだ。なので、どこを掘ってもお役立ち情報だらけだが、ここでは、読書と発想の技術の章から、「好奇心の広げ方」を紹介する。
手っ取り早い方法として、「全然知らない分野の雑誌を見つけて読め」という。野次馬的な興味で『月刊住職』に手を出したり、10代向けファッション雑誌『CUTiE』とか『KEROUAC(KERA /ケラ!)』を読んでいたという。
もしあなたが KindleUnlimited に加入しているなら、普段読まないような雑誌にも気軽に手を出せるのでおすすめ。あるいは、図書館に行けば、最新の雑誌を館内で読み放題だ。
「知らない雑誌を読む」という提案は一つのやり方で、何でもいいと思う。知らない世界に触れることで、惰性で生きてきた日常に少し揺さぶりをかける。昔だと『ぴあ』とか『ダカーポ』を眺めることで「わたしが知らない(でも面白そうな)情報」に触れていたが、これを意図的にやるわけだ。
ときどき私がやっているのは、「ログアウトしてYouTubeを見る」になる。馴染みのないネタが並んでいるのが目新しい。アマプラやネトフリを新しいプロフィールで見るというのもいいかも。
こういう世界があるんだという驚きが、また何か別の分野を開拓するときの心理的ハードルを下げてくれる。
ネットで決め打ちで買うのではなく、書店に足を運ぶのもいいかも。私は、放っておくとどんどん慣れている方を選んでしまう。同じジャンルの似たような作品ばかり読みふけって、井の中のカエルになりがち。だから、知らない分野の棚を(物理的に)探索することで、好奇心を広げるのだ。
そこで知った新しい(でも面白そうな)分野をどうやって攻略するか?山形がすごいのはここからで、「複数分野の中間地点を狙え」と説く。
物理学のようにすでに完成された世界なら、今から究めるのは難しいし、アマチュアは研究者に勝てるわけない。けれども、別の分野を掛け合わせることによって、新しいものを生み出すという方針なら話は違ってくる。
自分の好奇心を広げて、まったく関係のない別々の分野を眺めていて、その間にある面白そうな所をしゃかりきに勉強すれば、世界のトップにだって立てるという(期間限定だけど)。
例えば、フリーソフト。コンピュータのプログラムと経済学の重なり合いでできたテーマだ。そしてインターネットが広がった時も、そこから生まれるプライバシーや規制の話も含め、ネットと法学が重なるような分野が登場した。今や当たり前のように馴染んでいるローレンス・レッシグ(※)の世界だが、これを25年前に紹介したのは、山形だ。
※ローレンス・レッシグ…アメリカの法学者・政治活動家で、非営利団体Creative Commons(クリエイティブ・コモンズ)の創設者。
好奇心のアンテナを増やし、面白さが重なった中間地点で頑張れば、「1週間だけ世界ナンバーワン」になれる。そして、そういうナンバーワンの積み重ねが人生を変えることもあるのだ。
私のブログでの紹介は[見切る読書で積読を解毒する『翻訳者の全技術』] 。
“SF×倫理学”。好奇心のアンテナを掛け合わせる
好奇心のアンテナは、掛け合わせることによって増やすことができる。先ほどの「複数分野の中間地点を狙う」例として、萬屋博喜『SFマンガで倫理学』を紹介したい。
何が善くて、何が悪いのか?こうした問いに、真正面から取り組むのが、倫理学だ。倫理学の歴史は古く、それこそ人類が「考える」ことを始めたときから誕生したといっていい。
一方で、SFマンガには、科学技術が発展したユートピアやディストピアがテーマとして描かれたものがある。マンガという臨場感あふれるステージで、倫理学で扱われてきた問いが目の前の問題として突き付けられる。
問1:かけがえのない自然を守るため、人を減らすのは悪か?
問2:合成獣(キメラ)の生成と命の再生は「命を弄ぶ」観点からどんな違いがあるのか?
問3:みんなの健康のためなら「何をしても」許されるのか?
著者は現役の倫理学者で、義務論、功利主義、徳倫理学、倫理的相対主義といった思考ツールを用い、それぞれの問題の論点をクリアにし、現時点でどこまで議論が詰められているかを解説する。
例えば問1。人の頭に寄生して神経を支配し、人を捕食する寄生生物を描いた『寄生獣』を例に、「なぜ自然を守らなければならないのか?」という問いを深掘りする。
まず、「生態系が破壊され、人間が暮らしづらくなってしまうから、自然を守るべき」という立場だ。この場合、その『自然』とは、人間が暮らしていくために利用する、人間のための道具としての存在だろう(人間中心主義)。
一方で、人間という一つの種の繫栄よりも、生物全体を考える立場もある。「万物の霊長」と名乗るからには、人間のためだけでは正義は成り立たない。人間を中心に考えるのではなく、生物全体のバランスや生態系そのものに価値があると考え、これを尊重するアプローチがある(エコセントリズム)。
『寄生獣』のタイトル回収話である第55話で、寄生獣の定義を、「人を捕食する」から「自然を蝕む」ことへ逆転させる。
つまり、地球資源を蝕む人間こそが、寄生獣だというロジックだ。立場が違えば「自然」の定義すら変わってしまう。本書ではさらに、人間中心主義 vs. エコセントリズムの対立だけに着目すると、見落とすものが出てくるという。
それは、自然という概念そのものが持つ多様性だ。
一口に「自然」といっても、様々な種類がある。
例えば、人の手によって部分的に管理され、特有の生物多様性が保たれている半自然がある。日本の里山、イギリスならコモンズ、アルプス地方のアルムが有名で、風防や治水の役割も果たしている。あるいは、野生動物保護区や自然公園といった、一定の目的の下、コントロールされた自然環境も存在する。自然とは、人の手の入り具合によって、ある程度のグラデーションを持った存在なのだ。
「自然」環境の破壊を悪と見なすなら、史上最大の環境破壊である「農耕」こそが悪になる。では人類は農耕を捨てるべきか?そうはならない。善と悪がはっきりしていれば白黒つけやすいが、そうは問屋が卸さない(人間=善、寄生獣=悪という構図になっていない点に似てて面白い)。
環境保護、人のクローン、人生の意味、人工知能など、物語の形で埋め込まれた現代の問題を、倫理学のアプローチから考える。SFと倫理学を掛け合わせることで、好奇心のアンテナを増やすことができるのだ。
私のブログでの紹介は[寄生獣、鋼錬、攻殻、進撃、火の鳥…SF×倫理学で現代を理解する『SFマンガで倫理学』]。
論文=好奇心を呼び覚ます、科学のカタログ
好奇心のアンテナの「数」を増やしたいなら、科学論文に当たるのがいい。
世の中には、面白いテーマを追いかけている科学者がごまんといる。その成果は論文という形で発表されているが、数は膨大だ。玉石混交のなかから、輝くダイヤモンドをどう見つけるか?
まずは、一流と呼ばれる科学雑誌の論文を当たってみよう。それだけでも凄まじい数になるし、英語という壁にぶつかることも多いだろう。そんなときは、雑誌『ニュートン』や『ナショナル・ジオグラフィック』が助けになる。特集記事だけでなく、毎月のコラムで「いま話題の科学論文・学説」を紹介している。そこから探せばいい。
さらに効率よく、そうした「面白そうな科学論文」をピックアップして紹介しているような都合の良い本はないだろうか?
実はある。池谷裕二『すごい科学論文』がそれだ。
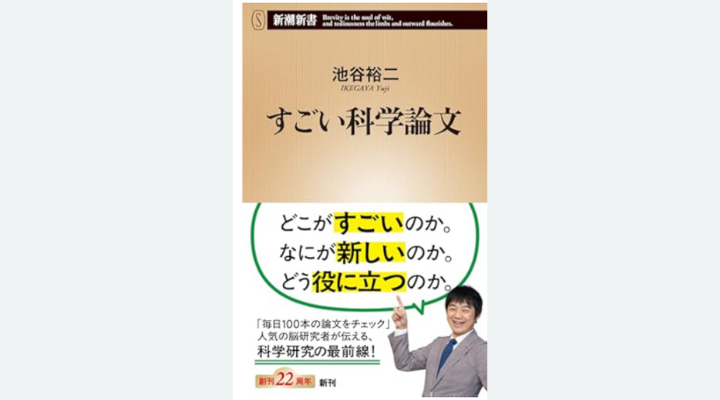
著者の日課は、科学論文を読み漁ること。「ネイチャー」や「サイエンス」など世界的な学術誌から最低でも1日に100本(多いと500本)、年間だと5万本の論文に接しているという(全読は無理にせよ、アブストラクトだけでもすごい!)。
そんな中から、特に面白いもの、今までの常識や定説を覆すもの、インパクトのあるものを選んだのが本書になる。著者が「これはすごい!」と感じたのが判断基準なので、さまざまな分野の論文が俎上に上る。
ある意味「ごった煮」となっているカオス感が楽しい。専門が薬学で、脳科学についても詳しいのでそっち系が多い。例えばこんな感じ。
- ・鶏肉は洗うな(洗うと雑菌が飛び散るので不衛生)
- ・生物と無生物を分ける新しい定義「寄生される」
- ・クジラとフクロウの収斂進化に学ぶ失明治療のヒント
- ・乳腺は汗腺が発達した器官という観点からのおっぱい成分分析レポート
- ・DNA配列をAIに学習させたら、「天然」よりも高性能なDNA配列を編み出した
- ・Chat-GPTの価値観は欧米圏(主な学習ソースが欧米圏だから)
注が豊富で、巻末に論文タイトルが挙げられているので、気になるものは自分でチェックすると、さらに楽しい。
遊び方は、本書を読んで、好奇心を引っ張るものがあったら、そのタイトルを検索する。すると、概要や内容の一部を紹介しているサイト(たぶん英語)がヒットするだろう。そのURLをChat-GPTなどに食わせた後、好き勝手に質問すればいい。
単純に翻訳してもらうだけでなく、論点を整理してもらったり、似たような論文が無いかを調べてもらうのもアリだ。ただし、GPTのハルシネーションで嘘を掴まされるのがイヤなら、Connected Papersが便利だ。
論文のタイトルを入れると、それを中心とした関連のある論文をグラフィカルに生成してくれる。単に被引用・引用というツリーだけでなく、内容として似ている論文も含めたネットワーク図を提供してくれる。
好奇心のアンテナを、論文の関連性の中で可視化することができる。知識を増やすというよりも、むしろ、その知を誰がどう研究してきたか(しているか)という人を探すツールとして使うんだ。
私のブログでの紹介は[「鶏肉を洗うな」は本当か?―――『すごい科学論文』に学ぶ現物に当たる重要性] 。
「人」からたどる知のネットワーク
アンテナを増やすには、自分と似た好奇心を持っている人を探す。それも「名前も知らないけれど、興味が近い面白い人」を見つけるのだ。
これは、本の探し方を応用するといい。
世の中には、星の数ほど本がある。話題の本や有名な作品なら、事前情報で「面白そうかどうか」について、ある程度判断できる。もちろん、実際に読んでみるまでは分からないが、少なくとも「探し方」はある。
けれど、本当に出会いたいのは、「タイトルも著者も知らないけれど、自分にとってものすごく面白い本」だ。これは厄介で、そもそも「知らない」ものは検索のしようがないし、話題になっていても、自分がその話題の輪にいなければ届いてこない。
そんな時、私がするのは「本ではなく、人を探す」ことだ。
たとえば、自分が好きな作品や著者について語っている人を検索してみる。その人がどんな本を推薦しているかを見ると、自分が知らなかったけれど面白そうな作品に出会える確率が高い。
この方法は、本探しにとどまらない。「知らないけれど、自分と似た興味を持っている人」を見つけるのにも応用できる。
具体的には、自分の興味と重なる著者や評論家がいれば、その人が対談している相手や、引用している人物をたどっていく。そうして出会った人たちは、まだ自分が知らないけれど、きっと刺激をくれる「面白い人」なのだ。
この「人」を探すのにうってつけのやつが、稲葉振一郎『宇宙・動物・資本主義』というタイトルの対談集だ。
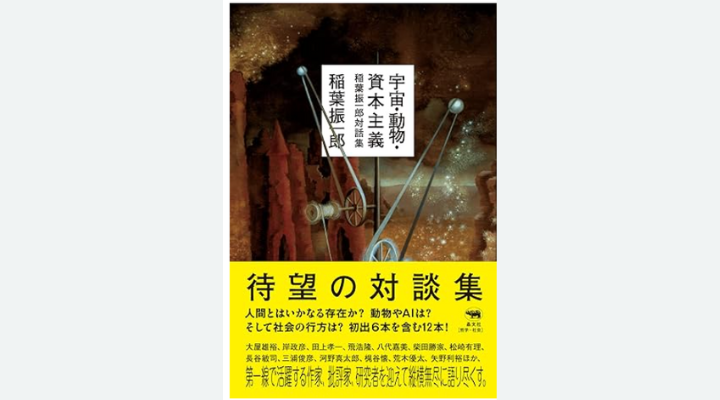
中身は奇妙なタイトルが物語っている通りだ。哲学、倫理学、社会学、経済学、宇宙開発、ロボット工学、文芸批評、SF、ファンタジー、コミック、アニメなど、ジャンルも射程も広くて深い。
対談・鼎談相手も様々で、大屋雄裕、吉川浩満、岸政彦、田上孝一、飛浩隆、八代嘉美、小山田和仁、大澤博隆、柴田勝家、松崎有理、長谷敏司、三浦俊彦、河野真太郎、金子良事、梶谷懐、荒木優太、矢野利裕と、作家、批評家、研究者を迎えて縦横無尽に語り尽くしている。
語られているテーマも膨大なので、そこから面白そうなトピックを拾い読みするだけでも楽しい。特に私の目を引いたのはこちら。
- ・物理学が存在する宇宙だけだったり、物理学が成立するローカルな環境だけを研究していることが、物理学の正体
- ・twitterのbotなど、人間ではないものによって政治的な傾向が偏向し、民主政治のセキュリティホールになる
- ・古典的自由主義と区別したいのは分かるけど、新自由主義って何十年もずっと「新」って言い続けてるね
- ・ピンカー『暴力の人類史』は過去の暴力を過大に見積もりすぎ
- ・ナウシカ「風の谷」と未来少年コナン「ハイハーバー」とシン・エヴァ「第3村」を比較すると何が見えてくるのか
重要なのは、こうした面白そうなトピックから、それを語っている「人」を探すんだ。物理学の正体については、第8章「思想は宇宙を目指せるか」における三浦俊彦氏の発言なのだが、こうある。
私がかねてから興味を持って追いかけている「人間原理」は、理論物理学は物理学が存在する宇宙だけを研究している、あるいは物理学が発生するようなローカルな環境を研究するのが物理学の正体である、という実態を暴いたことに重要さがありました。
(p.329 第8章「思想は宇宙を目指せるか」より)
「人間原理」の本質的な面白さは、物理学が普遍的な真理を探究している(はず?)なのに、実際には「物理学が成立可能な宇宙」に限定された真理だけしか扱ってないのでは?というツッコミにある。
笑っている間もなく、人間原理の話から地球外生命体の探索ネタ、ネオ・ダーヴィニズム、フランク・ティプラーの仮説、シンギュラリティ、神の恩寵説、系外惑星の発見が人間主義をリライトする可能性へと、次々と繰り出してくる。
さらに、探査機を飛ばすのではなく、宇宙へ人間を送り込むためには人間自体を改変していく必要性の議論、さらにはレム『ソラリス』やストルガツキー『ストーカー』を引きながら、「異質な知性体」のテーマに斬り込む。
どちらも持ちネタが大量にあり、かつ、話している時間も限られているので、すごい勢いで話が過ぎ去っていく。
私は本書のおかげで三浦俊彦のブログにたどり着けた。gooブログなので2025/11にサービス終了するけれど、[モンスター映画]の一言メモは読んでおきたい。
こんな感じで、この一冊を「人」のカタログとしてみなして、人のアンテナを増やしていくのだ。
私のブログでの紹介は[問題領域の重なる人を探す『宇宙・動物・資本主義──稲葉振一郎対話集』]。
アンテナの受信感度を高めるトレーニング
ここまで、アンテナやチャンネルというメタファーを使って、センスを「増やす」方向で説明してきた。ここでは、そうして増やしたセンスを良くする(=増えたアンテナの感度を良くする)やり方について、おすすめ本を紹介する。これだ。
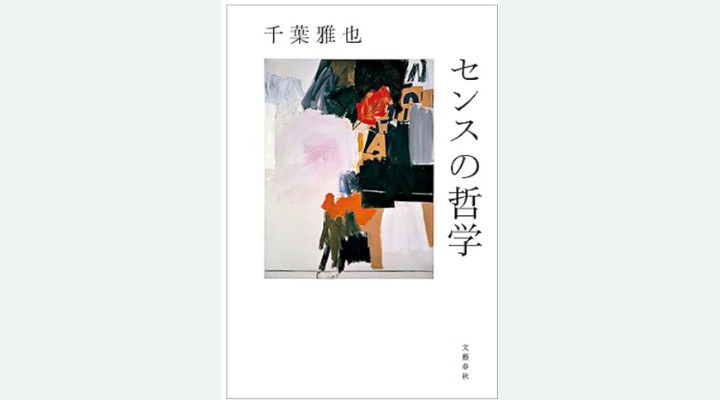
千葉雅也『センスの哲学』は、「センスを良くする」にはどうすればよいかを、哲学や芸術論のアプローチから解き明かす。
「音楽のセンスが良い」とか「着る服のセンスが良い」というけれど、この「センス」とは何ぞや?から始まり、小説や絵画、映画の具体例を挙げつつ、芸術作品との向き合い方を生活レベルで語り明かす。
本書の切り口はフォーマリズムだ。形式や構造に焦点を当てることで、作品が持つモチーフやテーマが示す意味や目的からいったん離れ、メタな視点から、対象をリズムやうねりとして「脱意味的」に楽しむ。
例えば、ポークソテーのマスタードソース。
脂の旨味の上にピリッとした粒マスタードが効いてて、噛みしめるごとに旨みと酸みがテンポよくやってくる。柔らかいロースにマスタード粒のプチプチした食感がアクセントになって口中を刺激する。クレソンの苦味が加わると、さらに複雑な味わいが奏でられる―――要するに、「食べる」という行為に自覚的になるのだ。すると、味や舌触り、見た目、噛む音にも感覚を研ぎ澄ませると、味のリズムが感じ取れるようになる。
ただ食べて漫然と「おいしい」と感じるだけでなく、「おいしい」がどのような構造で、どんなリズムで自分に押しよせているものが何かに着目して味わう。そうすると、この料理のどこが気に入っているのかが、「自分にとって」分かってくる(←ここ重要)。
これを全芸術で考えたのが本書になる。ただ眺め、読んで漫然と「おもしろい」と感じるだけでなく、「おもしろい」がどのような構造を持っているのかに着目する。
ゴダールやセザンヌ、カフカ、ラウシェンバーグなどの作品を引きつつ、形から受ける印象や、(自分の)目の動きから引き出される反応を、「リズム」や「引っかかり」という表現で捕まえる。芸術とは、ある並び、すなわちリズムを作り出し、それを鑑賞する振る舞いだと喝破する。
自分が受け取るリズムとのズレや違和感があれば、それに意識的になる。おそらくそのズレこそが、(自分にとっての)作品の面白いところだろうし、センスの感度が上がるポイントだ。
料理ではなく小説で例えてみる。ある小説を読み進めていって、予想される展開や描写と、実際の作品の差異にズレが生じるとき、「お?」と興味が出てくる。もちろん能動的に「予測」を立てているとは限らないが、「こうなるかも」と無意識に思っていたものが裏切られると、そこに快楽が生じる。
ただし、この裏切りはこれまでのベースを踏襲し、読み手の期待に応えつつ、意外な形にする必要がある。ミステリなら「意外な犯人」だろうし、恋愛モノなら「ハッピーエンド」なんだけど、「意外な犯人と思っていたら被害者だった」とか「実は血がつながっていた」など、予想外の展開に持っていく。
本書では、さらにこの予測誤差をメタ化して、「予測が外れても振り回されないようにする」「予測外れに楽観性を持つ」ところから、楽観性をシミュレートすることに、遊びの本質を見出す。作品を通じて自分のアンテナの感度を意識するだけでも、「センスが良くなる」だろう。
私のブログでの紹介は[センスが良くなるだけでなく、新しい目を得る一冊『センスの哲学』]。
おわりに
漠然とした「センスを磨く」ではなく、具体的にセンスが磨かれている状態を想定するならば、それは自分を含めた世界からの情報チャンネル数を増やしたり、感覚を受信するアンテナを増やすことになる。そうすることで、同じソースから、より数多く、多様なものを得ることができる。
具体的には、好奇心のアンテナを広げる。知らない分野の雑誌や動画を意識的に眺め、自分の興味の持っている分野とのAND(共通点や接点)があるなら、それは何かを考える。知らないところに飛びこむという心理的ハードルを下げるという点でも、『翻訳者の全技術』は、あなたの背中を後押ししてくれるだろう。
『SFマンガで倫理学』は、ANDの掛け合わせの好例だ。自分の好き(SFマンガ)と自分の得意(倫理学)を掛け合わせるとどういう考察ができるかを追いかけるのにちょうどいい。あなたの中の好き×得意の組み合わせは自由にやっていいんだという気にさせてくれるだろう。
「好き」のアンテナを増やしたいなら、『すごい科学論文』で紹介されている論文に当たると良い。数打ちゃ当たるというのはまさにそれで、好奇心のカタログブックのように使えばいい。興味を惹かれた論文は現物に当たることで、違った姿を見せるかもしれない。翻訳や概要のピックアップ、質疑応答はChat-GPTに任せよう。
『宇宙・動物・資本主義』は、「人」のカタログだと思えばいい。流し読みしながら、面白そうなことを語っている人を探すのだ。そして、そういう人は面白そうな問題に取り組んでおり、ネットのどこかで物議を醸している。フォローするだけでアンテナが増えていくだろう。
アンテナの感度そのものを上げるには、『センスの哲学』をすすめる。現実と自分とのズレに意図的になり言語化することで、その差異を楽しめるようになる。いきなり現実に取り組むのではなく、映画や小説など、作品を通じて「お約束が破られる」ことそのものを楽しむのだ。
「人生を豊かにする」という言い回しには、財やステータスのような雰囲気を感じる人もいるかもしれない。だが、この記事を読んだ方なら、「人生を豊かにする」とは、楽しめるチャンネル数を増やし、アンテナ感度を上げることだと気づくだろう。
よいセンスで、よい人生を。
関連記事

【「スゴ本」中の人が薦める】技術書は教えてくれなかった。悩めるエンジニアに新たな考え方をもたらす6冊

【スゴ本】世界がこうなるなら私はどうする?ITエンジニア必読のサイエンス・フィクション6冊
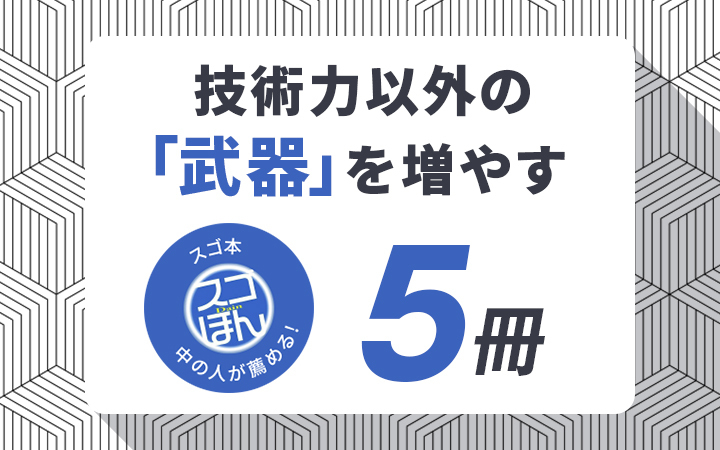
【スゴ本】ITエンジニアの「武器」を増やす5冊
人気記事