最新記事公開時にプッシュ通知します
プログラマー高橋征義が選ぶ、開発者として“生きる”と向き合うための「お守り本」6冊
2025年2月14日
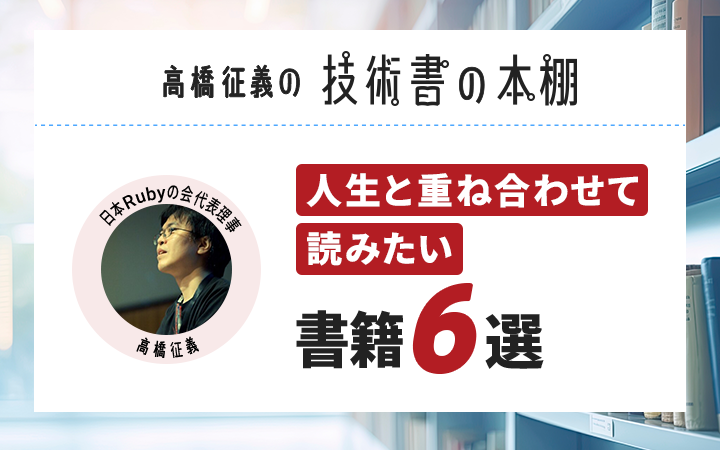

日本Rubyの会代表理事
株式会社達人出版会代表取締役、一般社団法人日本Rubyの会代表理事。20世紀末よりWeb制作会社にてプログラマーとして勤務する傍ら、任意団体として日本Rubyの会を設立。後に法人化し、現在まで代表理事を務める。2010年よりITエンジニア向けの電子書籍の制作と販売を行う達人出版会を創業、現在まで代表取締役。ほか、RubyKaigiや技術書典の運営にも関わる。著書に『たのしいRuby』(共著)など。好きな作家は新井素子。
X:@takahashim
- はじめに
- 極限状態で「生きる意味」を考える
- 社会と文明の構造を少女マンガとして描く
- 50年経っても色褪せない短編SF
- 「書いたコードは自分のものになる」という前提を疑う
- 自己啓発本に惑わされないために
- 「物語る」意味を考える
- おわりに
はじめに
誰かにとってはゴミになるようなものだとしても
私の世界の全てで
(トゲナシトゲアリ『黎明を穿つ』より引用)
前回とは異なり、今回紹介するのはソフトウェア開発から離れた書籍になります。テーマは人生観に影響を与えた「お守り本」です。
最初に断っておきます。計算機科学はその名前の通り計算機のためのものですが、広く一般にも応用できそうな知見も含まれます。その1つとして、式などの計算対象を評価する(eval)際にはその環境(environment)によって評価値が異なること、つまり同じようにみえる事象が起きたとしてもその事象を取り巻く環境によって得られる結果が異なるということが、科学的(再現可能・説明可能)な形で理解できることが挙げられます。同じコードが実行時の環境によって異なる結果を生むように、私たちの行動や思索から受ける影響も環境次第で大きく変化します。
上記をふまえると、今回紹介する本は私にとってはかけがえのない大切な本なのですが、読者の皆さんにとっても大切な本になる確率は相当低いかもしれません。そのため、単純におすすめ書籍のタイトルとその内容を紹介するというよりは、強い影響を受けた本とそこから受けた印象を書くことで、こういう風に本を読んできたプログラマの人もいるんだなくらいに思ってもらえれば幸いです。
なお、私が深く影響を受けた本というとどうしても10年以上前に読んだ本が多くなってしまいます。2025年1月現在で入手困難な本は除くようにしました。できれば紙でも電子でも入手できる本にしたかったのですが、電子化されていない作品も含んでいます。ご了承ください。
では、はじめます。
- 1. 『ひとめあなたに…』新井素子 著
- 2. 「Die Energie 5.2☆11.8」『三原順傑作選’80s』所収、三原順 著
- 3. 「ビームしておくれ、ふるさとへ」『故郷から10000光年』所収、ジェイムズ・ティプトリー・ジュニア 著、伊藤典夫 訳
- 4. 『私的所有論[第2版]』 立岩真也 著
- 5. 『日常に侵入する自己啓発』牧野智和 著
- 6. 『当事者は嘘をつく』小松原織香 著
極限状態で「生きる意味」を考える
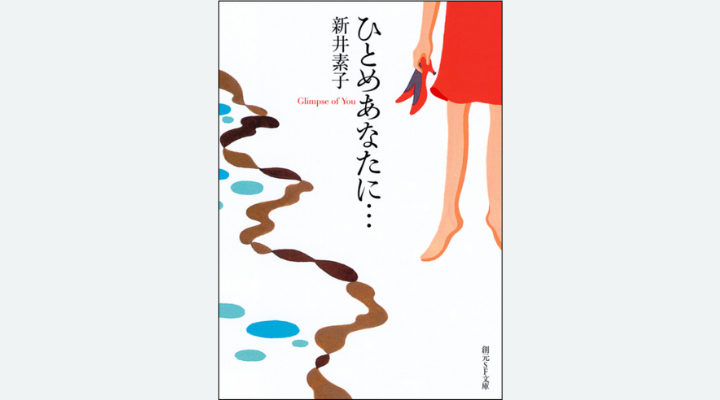
▲『ひとめあなたに…』新井素子 著、東京創元社
のっけからフィクション、しかもSF小説です。でも「お守り本」というテーマからすると、高校受験の際にも本書のサイン本をお守り代わりに持っていった私にとって、何よりも本書がお守り本であることには間違いありません。とても思い入れのある作品です。
本書の「あと一週間で隕石が地球に落ちて人類が滅びる」という設定は、SFの中でも「破滅SF」と呼ばれるジャンルに属するものです。が、それはどんな隕石なのか、被害規模の想定はどうなっているのか、それに対して国内外の政府や研究機関、企業は何をやっているのか、……といった話はまったく出てきません(ちなみに公共交通機関は止まってるようです)。隕石の軌道を計算する科学も、隕石の落下を防ぐ工学も本書では描かれません。本書の設定は「普段はなんとなくやりすごしたり誤魔化してきたものが、極限状態によって誤魔化しきれずあらわになる」という舞台装置として(のみ)機能しています。
主人公の圭子は、練馬から恋人のいる鎌倉まで歩いていくことを決意します。その道中にて、狂気と正気の狭間にいる人たちに出会います。そうした出会いを踏まえて圭子が考えるのは、「人間はなぜ生きるのか」「人間にとって幸せとはなにか」「人生の意味は本当にあるのか」というストレートな問いです。そんな究極的な問いを一人称のエンターテインメントとして描き、多くの人が楽しめる物語に仕上げる。その巧みさには、初めて読んだ中学生の頃も、今読み返しても、同じように感銘を覚えます。
本作品の中で一番好きな登場人物は「真理ーー走る少女」の章に出てくる坂本真理です。世界が終わろうとする中で、高校3年生である彼女は決して行われるはずのない大学入試のために世界史の暗記を黙々と続けます。そして、「あたしは、しあわせなの」と笑みを浮かべます。そこに込められた絶望と希望は、まだ20歳だった著者がその時にしか書き得なかったきらめきを感じます。
社会と文明の構造を少女マンガとして描く
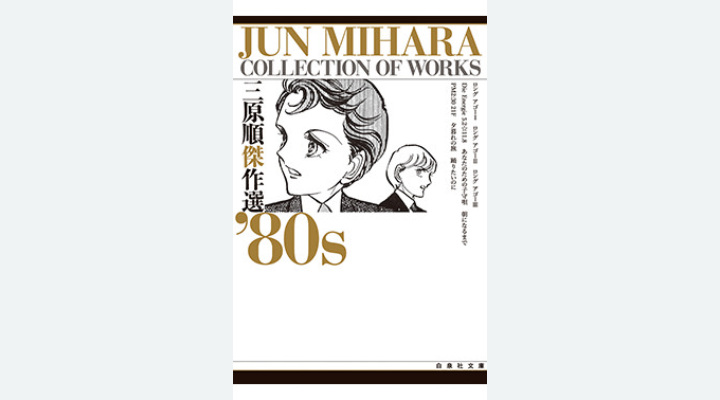
▲「Die Energie 5.2☆11.8」『三原順傑作選’80s』所収、三原順 著、白泉社
続きまして短編マンガです。
三原順は札幌出身の少女マンガ家で、代表作に『はみだしっ子』シリーズがあります。『はみだしっ子』は熱狂的なファンも多い作品なのですが、ちょっと長い上に絵柄のクセが強いかもしれません(それでも読んで損はない作品です)。そういえば本短編集に収録された「ロング・アゴー」は『はみだしっ子』シリーズの番外編でした。彼女は惜しくも1995年に42歳の若さで亡くなってしまうのですが、没後再評価が進み現在は電子で主だった作品が読めます。
本作品はうってかわって、原子力発電所を抱える電力会社を舞台にした作品で、低濃縮ウランの盗難をめぐるサスペンスがメインのストーリーです。主人公は電力会社に勤める会社員で、事件に関係があったりなかったりすることで翻弄されます。今なら「お仕事マンガ」にも分類されそうですが、20世紀には変わった少女マンガとして読まれていたかと思います。
もっとも、盗難事件はあくまで話を進めるためのもので、その背景には文明と社会に対する批判意識があります。
消費者は送られてくる電気を憎みはしないが いかなる種類の発電所でもそれを憎む人々は必ずいる
それは食卓に並んだ料理は好んでも 屠殺場は好まない人々が多いのにどこか似ているそして…けれど現在 発電所は自然を破壊し人々に害をなすことに
ゆるしを与えてくれる宗教を持っていない
(「Die Energie5.2☆11.8」より引用)
本作品は東日本大震災よりも、そもそもチェルノブイリ原子力発電所事故よりも前に書かれた作品です。そのはずなのに、まるで現代にもそのまま当てはまるように読めてしまうのは、本書が今も昔も変わらない社会の構造を描いているからなのでしょう。そしてラスト近く、「オレは加害者でいい! ただの加害者でいい」という重い一言が深く印象に残ります。
なお彼女の別の作品である『ムーン・ライティング』は、プログラマーが主人公のファンタジー作品になっています。1985年に発表された、今から40年前の作品でも「40歳を過ぎてしまったプログラマーってみんな何になるのかしら? 自分で会社をつくれなかった人達は…」というセリフがあるのに驚きます。
50年経っても色褪せない短編SF
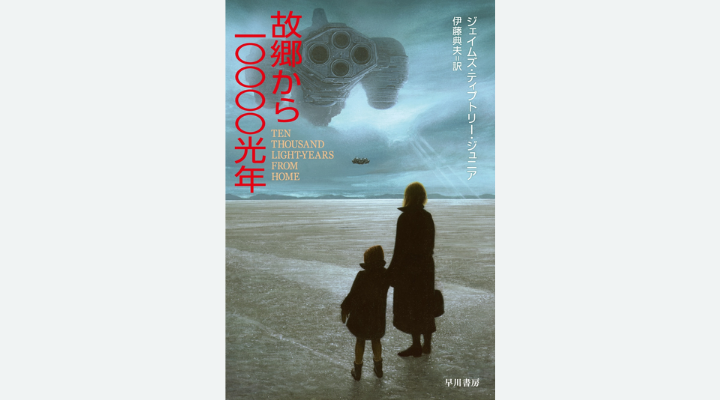
▲「ビームしておくれ、ふるさとへ」『故郷から10000光年』所収、ジェイムズ・ティプトリー・ジュニア 著、伊藤典夫 訳、早川書房
今度は短編SF小説です。若竹七海の初期の長編青春ミステリ『心のなかの冷たい何か』と本作品のどちらかを紹介しようかと迷っていたのですが、調べてみたところ『心のなかの〜』は現状入手困難なのでこちらにしてみました。もっとも本書自体も電子化されておらず、いつまで入手可能なのか心配です。よろしければ早めに入手して読んでいただきたいです。
ティプトリーの経歴はどこまで書いていいか悩ましいのですが、少しだけ触れておきます(本書カバーの著者紹介に書かれていますが、本書を読み終えた後で読むと驚かれるかもしれません)。カレッジを出た後、軍隊に入隊したりCIAに所属したりしてから大学に戻り、実験心理学のPh.D.を取ろうとしていた頃にSF作家としてデビューします。最初に出版された書籍は本作品が収録されている『故郷から10000光年』ですが、出版された頃にはもう50代後半になっていました。かなり遅めのデビューだと言えます。
もっとも作品自体の評価からいうと、本作品よりも同じ書籍に収録されている「そして目覚めると、わたしはこの肌寒い丘にいた」とか「故郷へ歩いた男」といった作品の方が出来がよいかもしれません。しかし、それらとは異なる、独特な手触りと読後感を残すのが本作品なのです。
ストーリーは比較的シンプルで、そこそこ優秀だけれど謎めいた主人公が空軍に入り宇宙飛行士に志願したものの、その計画は中断したため戦場に放り込まれて、最期の時を迎えるのでは…?というタイミングで意外な告白をする…というものです。本書の解説でも本作品は「ティプトリーがもっとも率直に自己の心情を明かした小説」と書かれていますが、読む人が読むと「スター・トレック」の二次創作みたいな作品であることが分かります。そのまんますぎてびっくりです。そしてティプトリーが作品中に残したのは、この現実世界の否認と、存在しないかもしれない”本当の”世界へ帰りたいという望郷の念でした。
“ここは私のいるべき場所じゃない。ここにいる私は本当の私じゃない”__。そんな中二病っぽい心情を赤裸々に叩きつけた挙げ句、読者を置き去りにしたまま“ビーム”されてどこかへと去ってしまう……正直呆然としてしまう幕切れですが、そんな作品を後に「接続された女」「ヒューストン、ヒューストン、聞こえるか?」といった冷徹な作品を残すことになる作家が書いていたということに、深く感じ入るものがあります。
「書いたコードは自分のものになる」という前提を疑う
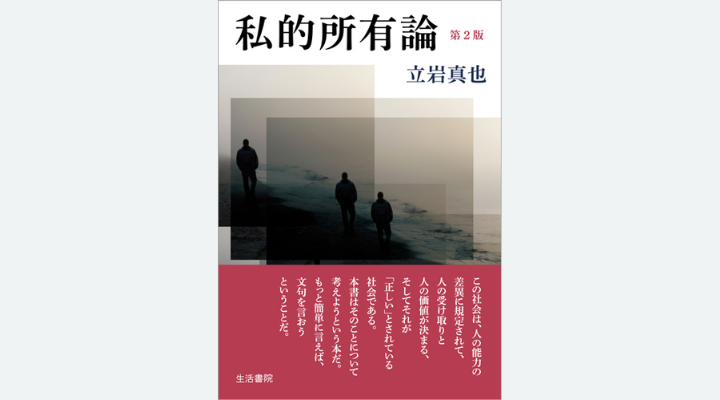
▲『私的所有論[第2版]』立岩真也著、生活書院
フィクションばかり紹介するのもどうかという気がしてきたので、ここからはノンフィクションを紹介します。
現在プログラマーとして活動している人であれば、オープンソースソフトウェア、あるいは自由なソフトウェア(フリーソフトウェア)に触れずに開発を行うことは難しいでしょう。そうすると、「コピーレフト」という、言ってみればトンチのようなロジックで誰にも独占されないコードを生み出すしくみを知ることになるはずです。個人的にはそのしくみへの興味から、「所有」ってなんなんだろうな……という関心を持ち、少し話題になっていた本書を手に取ったような記憶があります。
もっとも本書のもくろみはそんな所有に関する一般論を論じたいということではなく、いわゆる生命倫理とか自己決定とか障害者運動といった関心から派生したようです。本書はそんな関心のために私的所有に関する至極一般的な見解ーーある人がつくったものはある人が所有できる、というロジックーーに反論するべく議論を尽くします。このあたりは、自分の書いたコードは自分が所有できるという、著作権に基づくソフトウェアの通常の理念とは厳しく対立するものです。でも、その一方で、コードを好きにハックしたいがために独特なライセンスやGNU・FSFのような組織までつくり上げてしまうOSS・自由なソフトウェアのスタンスにも通じるところがありそうな気もします。介護の手がないと生きてすらいけない障害者でもなんとか生き続けられるようにする、それを正当化するための理屈をつくって説得したい。そんな問題意識から、本書やその他の立岩氏の活動が行われていたのでしょう。
ところで本書について紹介したい最重要ポイントは、なんと電子版が存在して10ドルで買えるということです。
サイトには「English Version」とか書いてますがこれは気のせい(?)で、なんと日本語版第2版の全文がおまけについてきます。びっくりですね。さすが立岩氏、やることが尋常ではありません。
そしてフォーマットはただの1ページの巨大なHTML(!)です。EPUBでもPDFでもありません。って、そんなのありなのか……。当然ながらDRMもありません。そもそもいまいちvalidなHTMLになっていないというか、タグが壊れているような気もします。が、本稿を読まれているみなさんなら自力でなんとかできるでしょう。
もっとも、本書は長大かつ特徴的な文体によって気軽に読めるものではなさそうなのが難点ではあります。もうちょっととっつきやすい方がよい、という方には『増補新版 人間の条件 そんなものない』を読まれるとよいでしょう。
自己啓発本に惑わされないために
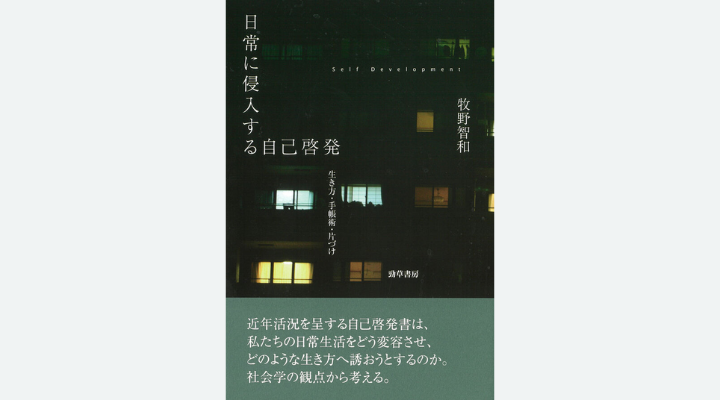
▲『日常に侵入する自己啓発』牧野智和 著、勁草書房
「お守り本」のような テーマですと自己啓発的な本を選ぼうとする意識が働いてしまいます。そんな意識から、逆転の発想で選んでみた本です。が、率直に言って自己啓発書に対する反発、とまではいかなくても根深い懐疑が感じられる選書ですね。好きな方にはすみません。
本書は自己啓発書そのものの分析というよりは、自己啓発書の著者や読者、あるいは編集者といった当事者の分析を足がかりにしたあと、それを取り巻く世界・社会に目を向けます。
なぜ私たちは自己啓発書を読むのか、あるいは読まされてしまうのか、それはどんな社会が要請し、また自己啓発書はどんな世界観の元で書かれ、読まれているのか。
こういった問いに答えるべく、著者は社会学者ブルデューの著名な書籍『ディスタンクシオン』で提唱された枠組みを活用します。ブルデューが明らかにした、文化や生活習慣がどのように社会的階層を形づくり、維持していくのかという視点から、自己啓発書とその背後にある社会構造を掘り下げていきます。
本書のサブタイトル、「生き方・手帳術・片づけ」はちょっと意外な単語が並んでいます。1つ目の「生き方」と比べると残りの2つは妙に生活感、俗っぽさがあるもののように見えます。しかし、自己啓発界における手帳術や片づけは、どちらも単に予定管理を行ったり整理整頓したりする、単なる生活や仕事における技術・ツール的なものでもなく、文字通り人生を変える特別な振る舞いへと変容しています。この一見すると不思議にも感じられる状況について、本書の第4章と第5章では、それぞれ手帳術や片づけ本の歴史を経年的に追いかけていきます。特に片づけに関しては、「掃除」「整理・収納」「捨てる・片づけ」「シンプルライフ」「風水」といった隣接するジャンルが相互に影響しあいながら発展してきた様子が大変興味深いです。
本書を読んでも自己は特に啓発されないというか、成長したり成功に近づいたりときめいたりすることはなさそうです。が、夢や目標を実現するべく自己啓発しないといけない、という不安を抱えている人や、いくら自己啓発書を読んでもしっくり来ないという人にとっては、そういった状況を俯瞰的に見ることで、適度な距離を保てるようになる効果もありそうです。
それとともに、「自己」やその「成功」には強い興味を示しながら、身の回りの日常に手をいれるだけで、それを取り巻き支える「社会」そのもの対しては何もしない、むしろ(どうせ何も変えられない、と切り捨てることで)積極的に遠ざけようとしている世界観への違和も感じ取れるのではないかと思います。
「物語る」意味を考える
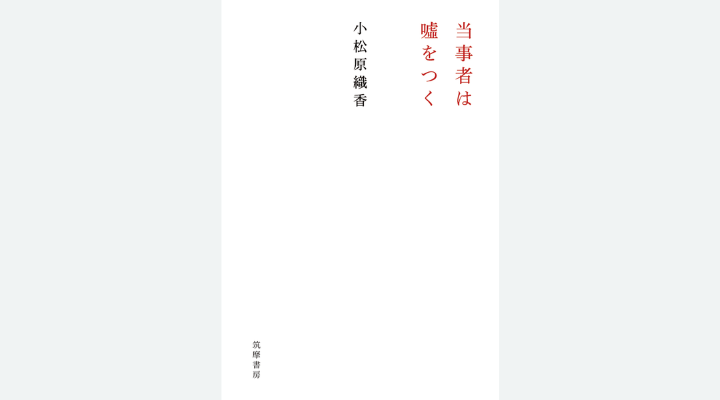
▲『当事者は嘘をつく』、小松原織香 著、筑摩書房
冒頭にも書きましたが、思い入れの深い本を挙げるとどうしても古い本ばかりになりがちです。とはいえ一冊くらいは新しめの本を入れたい、そう思って本書を取り上げることにします。ここ数年で読んだ本の中では、もっとも強い印象を受けた一冊です。
本書は、修復的司法や哲学を研究されている著者が、自身の人生を振り返りながら綴った自叙伝的な作品です。しかし、単なる研究者の自叙伝ではありません。冒頭で著者自身が性暴力の被害を受けた当事者であることを告白します。そしてその事実を伏せて活動することを「嘘をついている」と表現しています。そんな意識を抱え、あがきながらも生き延びてきた、その経験が語られています。
「嘘」という言葉にはネガティブで強い響きがあります。しかし、そのような響きとは異なり、本書では自分自身の語りをどのように構築するのか、自分の経験をどうすれば他者に伝えられるのかという問題が扱われています。別の言葉でいうと「物語」「ストーリー」、あるいは本書のあとがきでも使われている「ナラティブ」という言葉にも通じるものと考えてもいいのかもしれません。
本書では「物語」「物語ること」に関する考察がたびたび登場します。事実というよりも希望に近かった「回復の物語」、自助グループでの「語りの型」、そして博士課程で研究に行き詰まりつつあるなかでケータイ小説を書いてサイトランキングのジャンルで2位までとったエピソード。そして本書の最後でも、「これは、私が描き出した精一杯の当事者の夢である。私(たち)は生きていけるし、研究者になれる。この物語が、少しでも読者の役に立つことを、私は祈っている。」とあります。
「第三章 回復の物語を手に入れる」では「他者の語りを、自己の経験に重ねていく」という表現があります。ここで描かれるのは自助グループでの濃厚な経験でしたが、私たちが日々読書を通じて得られるのはもう少しあいまいでゆるやかな重なり合いでしょう。それでも、読み手の経験を深めていくことがあるのです。
フィクションを含め、これまで紹介してきた作品の多くも、私自身がそのような「物語を自己の経験に重ねながら生きてきた」結果なのかもしれない、と今これを書きながら気づきました。ある種の人は物語を必要とし、物語を生きることと人生を生きることが混ざり合ってしまう、そんな風に生きていくこともあるのです。そういった物語を読む経験の力も本書を読んで気づいたことの一つです。
おわりに
君の旅が
どうか美しくありますように
(赤い公園『pray』より引用)
なんの関連性もない作品を6冊並べてしまったようにも思ったのですが、一通り書いた上であらためて読み返してみると、何かしら似通った題材を感じます。ざっくりとまとめてしまえば、「人間」と「生」と「物語」といったところでしょうか。そしてどこかしら「死」の影がひそんでいるようにも思います。
ソフトウェア開発者としては日々人間ではない機械と向き合っているのですが、考えてみればソフトウェアを利用する者も、また共にソフトウェア開発に携わる者も、そしてソフトウェアを開発する自分も人間です。そのため、仕事としてソフトウェア開発をするにあたっては、人間について向き合うことも避けられないのかもしれません。
そして人間の生の本質はその自由さにあるように感じています。自由と言っても好きな選択肢がいくらでも選びたい放題といったような自由ではないのですが、「このように生きなければならない」といった縛りは本質的なものではないようです。
もっとも、自由な選択を享受するにはリスクを避けることはできません。まかり間違えば取り返しのつかないことになることもあります。仕事の選択や人生の進路においても、さまざまな道を選ぶ自由がある一方で、選んだ結果に伴う責任やリスクは避けられません。リスクがとれない状況にあれば、自由も見せかけのものとしか感じられなくなってしまいそうです。
お守りは、そんなリスクに立ち向かう際に折れそうな心を支えてくれるものなのでしょう。これを読まれているみなさんも、何かをお守りにしながら、難しい選択にも果敢に挑戦されることを願っています。
そして、どうか、生き延びられますように。
関連記事

セキュリティ、DB設計、パフォーマンス分析__。Railsを使ったWebアプリ開発をパワーアップする書籍6冊

Rust.Tokyoオーガナイザーの豊田優貴に聞く、思考の土台をつくった「お守り本」5冊
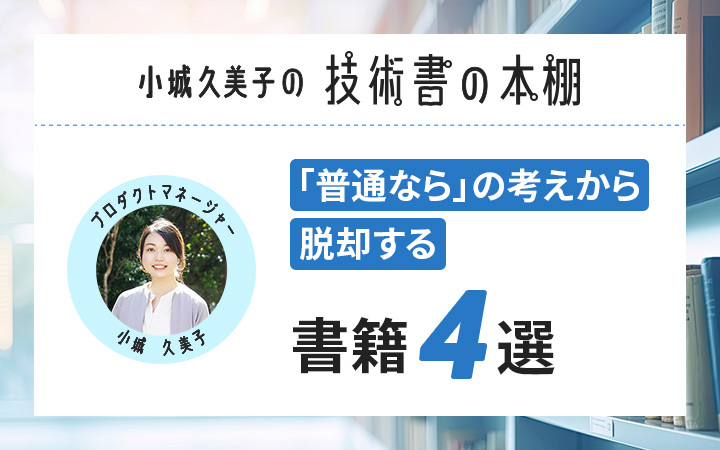
ときにサイコパスのようにクレイジーなアイデアを出し、感情を自分のものにする。小城久美子の「お守り本」4選
人気記事



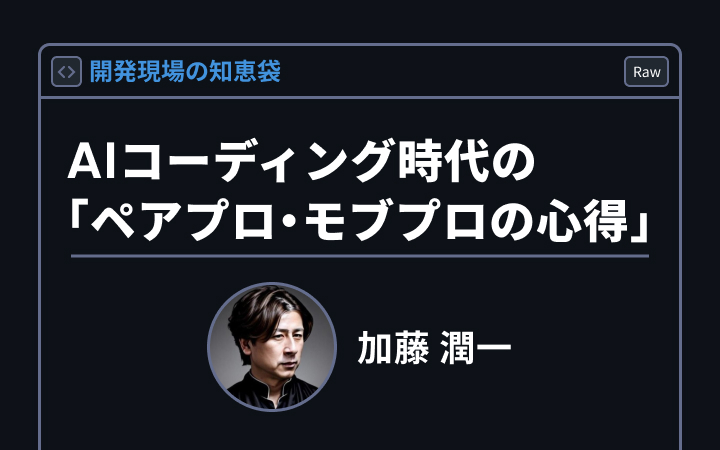


![Next.js on Vercelを使うとなぜ速い?低レイヤ、配信技術、Web高速化の観点から理解する3冊[レバテックLAB]](https://levtech.jp/media/wp-content/uploads/2026/01/260128nextjs.jpg)